INDEX
おすすめ記事
-

税理士事務所の業種とは?求人の探し方も解説
-

働きながら税理士試験に合格するには?無理なく仕事と勉強の両立を実現!
-
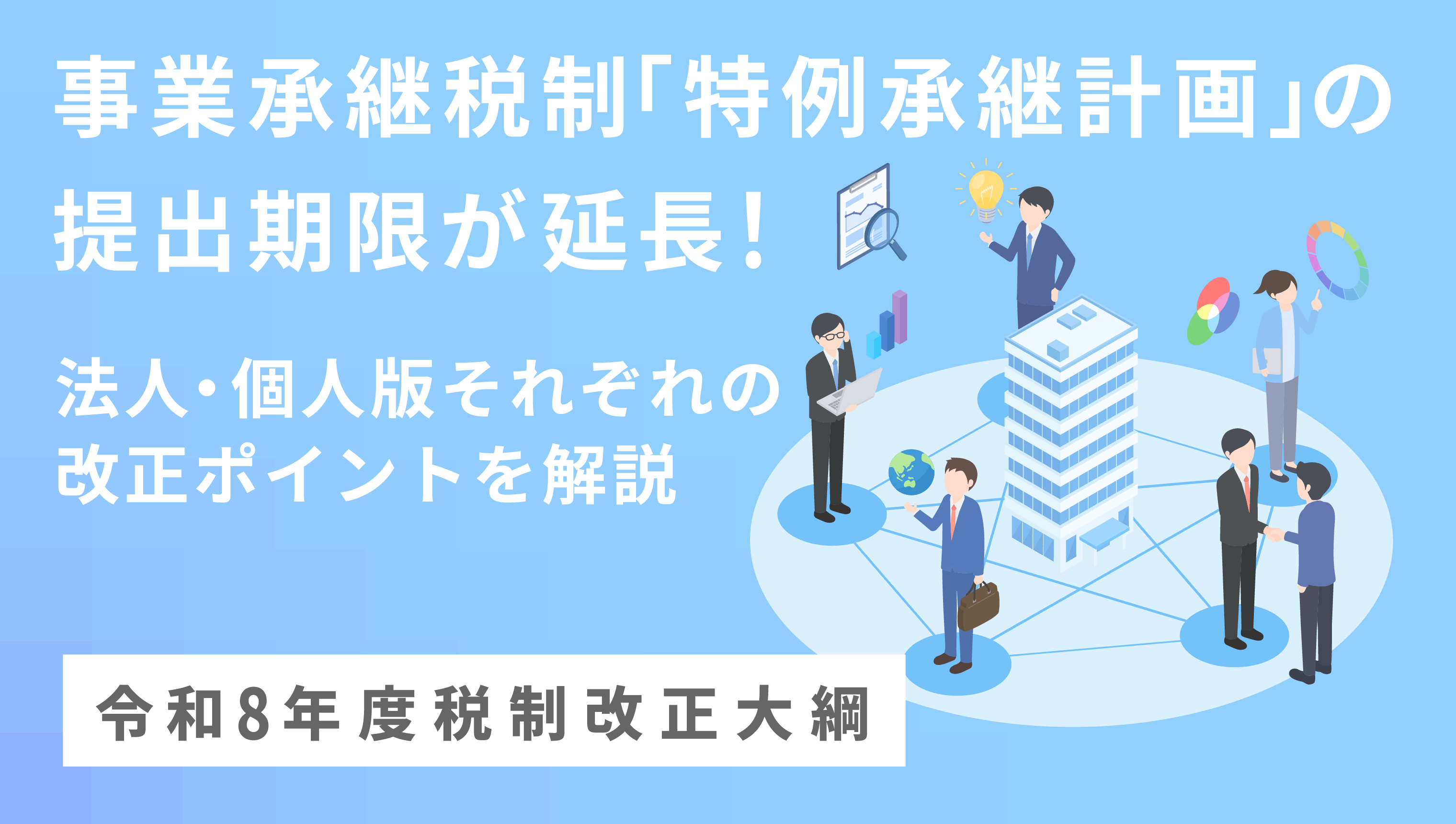
事業承継税制の計画提出期限延長!法人版は2027年9月まで【令和8年度税制改正大綱】
-
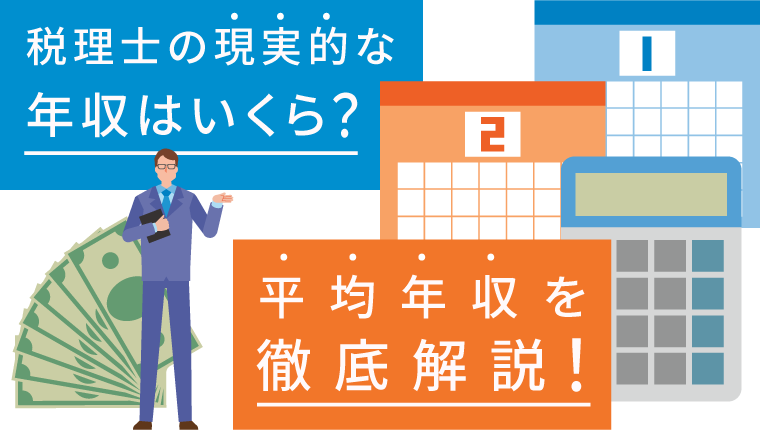
税理士の現実的な年収はいくら?平均年収を徹底解説!
-
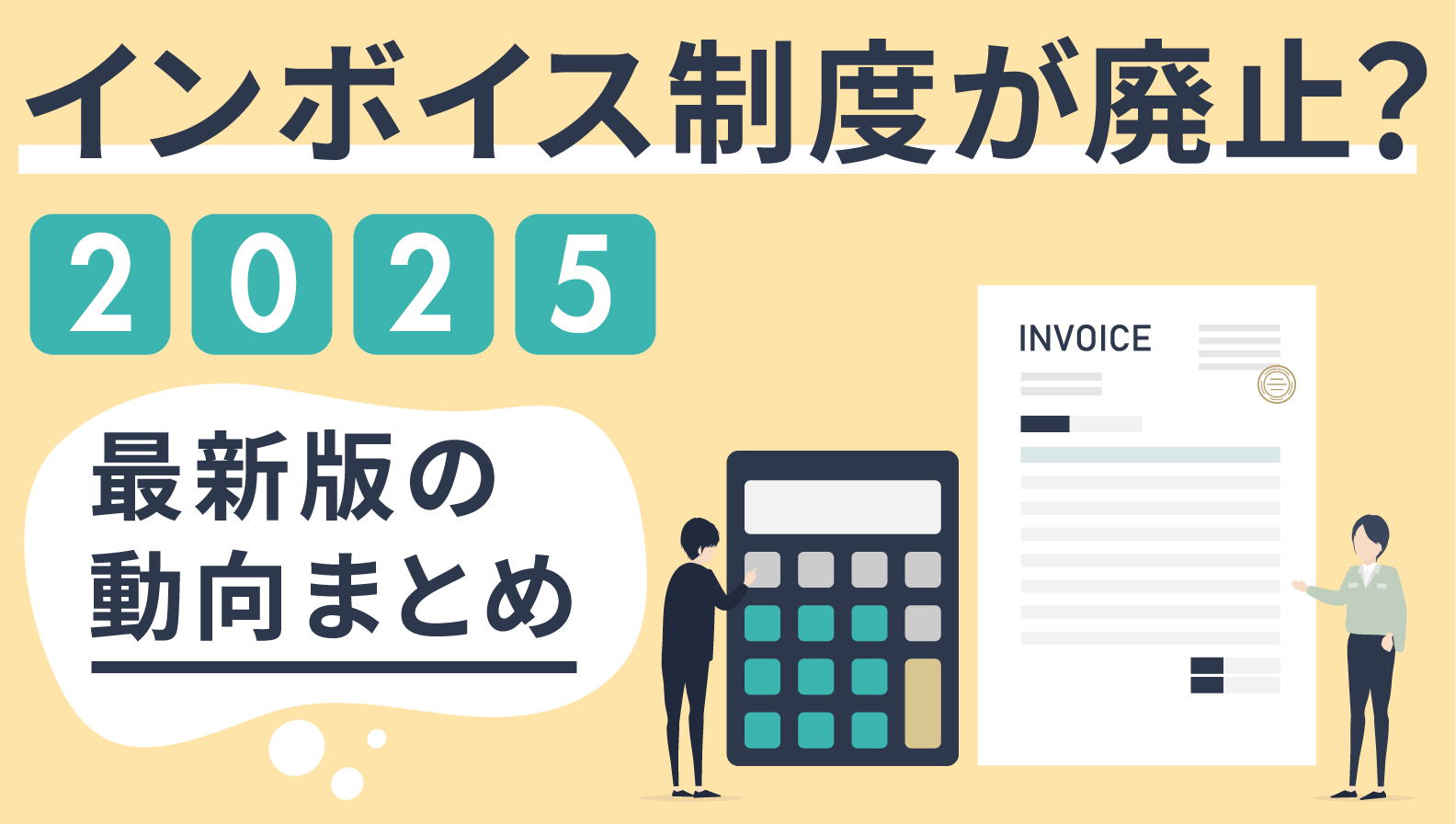
インボイス制度が廃止?2025年最新版の動向まとめ
公開日:2025/05/09
最終更新日:2025/09/06

INDEX
「うちの税理士、正直ちょっと頼りないかも…」
そう思われているかもしれない、なんて考えたことはありますか?
顧問契約の解消や信頼の低下は、派手なトラブルよりも「ちょっとした不満」が積み重なって起こることが大半です。
「返信が遅い」「料金がよく分からない」「節税の話がない」──
どれも税理士側に悪気があるわけではなく、ただ“伝わっていない”だけなのかもしれません。
この記事では、顧問先が税理士に感じがちな不満トップ5とその改善策を徹底解説します。
“変わる勇気”が、信頼を深める一番の近道です。
まずは、あなたの業務をほんの少しだけ客観的に見つめ直すところから始めてみませんか?
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士への不満ランキングTOP5の概要
税理士として長く付き合うためには、顧問先の“ちょっとした不満”にも敏感であることが大切です。
実は、顧問契約の解消や信頼関係の崩壊の多くは、小さな「すれ違い」から始まります。
この記事では、顧客が税理士に対して感じやすい不満トップ5を紹介し、トラブルを未然に防ぐためのヒントをまとめました。
「特別な対応」よりも「基本の徹底」で信頼は築けます。
自分自身の対応を振り返るきっかけとして、ぜひチェックしてみてください。
第1位 コミュニケーションの問題
税理士に対する不満の中で最も多く挙げられるのが「コミュニケーションの不足・ズレ」です。
「質問しても返事が遅い」「説明が専門的すぎて分からない」「報告が来ないから不安」――こうした声は決して珍しくありません。
多くの場合、税理士と顧客の間にあるのは「認識のズレ」です。
よくあるコミュニケーションの誤解
| 税理士側の認識 | 顧客側の期待 |
|---|---|
| 質問があれば連絡してくるはず | 気づいて教えてくれるはず |
| 必要な時だけ対応すればいい | 定期的にフォローしてほしい |
| 伝えたから理解しているだろう | もっと分かりやすく説明してほしい |
このように、「言ったつもり」「分かっているはず」という思い込みがすれ違いを生みます。
改善策 効果的なコミュニケーションの取り方
より信頼される税理士でいるために、以下のような対策が有効です。
1. 初回面談で「連絡のルール」を決めておく
・どの手段で連絡を取るか(電話/メール/チャットなど)
・回答の目安時間や頻度を明確に伝える
2. 情報提供は“定期便”スタイルに
・毎月or四半期ごとに簡易なレポートや一言コメントを送る
・税制改正や注意事項はかみ砕いて一枚にまとめて送付する
3. 専門用語を避け、図や例で伝える工夫
・「一時支出金」ではなく「●●という目的の経費です」など噛み砕いた説明を
・必要に応じて資料にまとめ、あとから見直せるようにする
4. 小さな確認も「先手」で行う
・「こういう書類は来ていますか?」「この件、気になっていませんか?」など、こちらから声がけする
第2位 料金の透明性の欠如
税理士サービスにおいて「料金が分かりにくい」「どこから追加料金がかかるのか不安」といった声も非常に多く聞かれます。
特に初めて税理士に依頼する中小企業や個人事業主にとっては、費用感がつかめないことが大きなストレスになります。
信頼関係を築くうえで、料金の「見える化」は欠かせません。
料金が不明確な理由とは?
以下のような背景から、「料金が不明確だ」と感じられることが多くなっています。
・料金表が存在しない or 公開されていない
→ 相場感が分からず、相談しにくい
・追加報酬が発生するタイミングが曖昧
→ 「それ別料金なんですか?」と後から驚かれる
・月額報酬の根拠が見えにくい
→ 「何に対していくら払っているのか分からない」
顧客側としては「料金が高いかどうか」ではなく、「納得感があるかどうか」が大切なのです。
改善策 料金体系の見直しと明確化
料金に関する不満を防ぐには、以下のようなポイントを意識すると効果的です。
1. ホームページや初回資料で「料金表」を明示
・月額顧問料・決算料・オプション報酬などを一覧化
・業種や売上別の「参考価格」も掲載すると親切
2. 「ここから追加料金がかかります」を明確に
・たとえば「年末調整」「税務調査立会」「節税シミュレーション」などは事前に説明
・「基本サービス範囲」と「オプション」を明確に分ける
3. 月額報酬の中身を“見える化”する
・「月次チェック+会計データ整理+経営アドバイス」など、サービス内容を明文化
・顧客に「その値段に納得できる理由」を届ける
4. 契約時に「報酬規定」を渡す or 確認書に明記する
・契約書に料金に関する条項を盛り込むことで、後からのトラブルを回避
第3位 節税に関する提案不足
「もっと節税できると思っていたのに…」「何もアドバイスをくれなかった」
顧問税理士に対して最も“期待が高い”のが、実はこの「節税の提案」です。
しかしその分、提案がなかったときの落差も大きく、不満や不信感につながりやすい領域でもあります。
節税対策が不十分な理由
税理士側の姿勢や業務スタンスに起因するケースが多く見られます。
・顧客から相談がなければ、深く踏み込まない方針
→ 「言われれば対応する」スタンスが裏目に出る
・法令順守を重視しすぎて、保守的な提案に偏る
→ 攻めの節税を避け、無難な対応にとどまる
・税務申告作業で手一杯になり、提案の時間が取れない
→ 忙しさの中で「考える」「伝える」が後回しに
つまり、「節税=税理士に任せればやってくれる」という顧客の期待と、実務のギャップが原因です。
改善策 節税に強い税理士の選び方
もし顧問先の不満を減らしたい・差別化を図りたいと考えるなら、以下のような工夫が有効です。
1. 年間を通じて「節税のタイミング」を見逃さない
・決算間際だけでなく、四半期ごとの利益予測と対策を提示
・資産購入・人件費見直しなど、期中の節税策も積極的に提案
2. 「顧問先ごとの節税チェックリスト」を作成しておく
・例:個人事業主→青色申告控除、配偶者控除、小規模共済の加入提案
・例:法人→役員報酬設定、福利厚生費、倒産防止共済の活用
3. 事前に「節税方針」や「リスク許容度」を確認する
・顧問先に対して「どこまで攻めた節税を望むか」をヒアリング
・あえて選択肢を出し、「保守型/中立型/攻め型」を提示する
4. 自分自身が「提案型の税理士」であることをアピール
・ホームページや名刺、初回面談で「節税に強い」と伝える
・実績ベースで「こういう提案をしました」と事例を紹介
第4位 相談のしづらさ
「こんなこと聞いてもいいのかな…」「忙しそうで話しかけづらい」
顧問先が悩んでいるのに相談できない──これは、信頼関係において非常に危険な兆候です。
税理士としては「聞いてくれれば答える」と思っていても、相談が来ない=問題が起きていないとは限りません。
実際は“聞けない空気”が、知らぬ間に顧客との距離を広げているのです。
相談しにくいと感じる理由
顧問先が「相談しづらい」と感じる背景には、こんな要素があります:
・専門用語が多く、話すハードルが高い
→ 「相手の土俵で話さなきゃ」と思い込み、萎縮する
・過去に冷たくあしらわれた、または否定された経験がある
→ 一度のやり取りで“心理的ハードル”が急上昇
・連絡手段やタイミングが分かりづらい
→ 「今連絡したら迷惑かも」「返信がなかったら怖い」
税理士の「無意識の圧」が、顧問先の相談意欲を奪っているケースも少なくありません。
改善策 相談しやすい環境作りのポイント
「話しかけやすい税理士」になるための工夫は、意外と小さな配慮の積み重ねです。
1. 「相談していい雰囲気」を明文化する
・初回契約時に「どんな内容でもご相談ください」と伝える
・メールやLINEの署名欄に「お気軽にご連絡ください」と一言添える
2. 相談しやすい“チャネル”を用意する
・電話以外にLINE/Chatwork/フォームなど複数の手段を持つ
・「〇曜日は相談日」など、連絡のタイミングの目安をつくる
3. 小さな相談にも“肯定+フォロー”を返す
・「こんなことを聞いてすみません…」に対して、「いえいえ、大事な視点です!」と安心感を与える
・否定から入らず、まず受け止めてから事実を伝える
4. 定期的にこちらから「声がけ」する
・「最近、気になることはありませんか?」とメールを送る
・年に1~2回は“相談目的の雑談ミーティング”を実施する
第5位 税務知識の不足
「え、そんな制度があったんですか?」「他の税理士さんはもっと教えてくれました」
──こうした言葉は、税理士にとって最も耳が痛いものかもしれません。
税理士に対する信頼は「正確で新しい知識を持っていること」が大前提。
税務の世界は日々変化しており、顧問先は“いつの間にか取り残されている”ことに敏感です。
税理士に求められる最新の税務知識
特に近年は、以下のような分野で知識のアップデートが必須とされています:
・インボイス制度・電子帳簿保存法の改正対応
→ 対応の遅れ=信用低下に直結
・補助金・助成金、税制優遇の活用提案
→ 「教えてもらえなかった」という声が最も出やすい部分
・資産税や相続税など、周辺分野の知識
→ 特定分野に強い税理士が選ばれる傾向
「知らなかった」「説明できなかった」は、顧問先にとっては致命的なミスと感じられます。
改善策 知識向上のための研修と情報収集
忙しい業務の中でも、知識のアップデートは“信頼の原資”と割り切って、意識的に時間を投資しましょう。
1. 定期的に専門誌・メルマガ・税務通信をチェックする
・日経税務・T&A master・週刊税務通信などの媒体を活用
・メールマガジンや速報系LINEグループも活用すると効率的
2. 勉強会や実務研修に定期的に参加する
・税理士会や民間の研修に月1回以上参加する習慣をつける
・特定分野(相続・資産税・法人税の中の一部など)に特化して深掘りする
3. チーム内での情報共有と役割分担
・所内で「分野担当制」を取り入れ、担当者がアップデート情報を共有する
・「誰かが詳しい」体制をつくることで事務所全体の知見が底上げされる
4. 顧問先へのアウトプットを前提としたインプット
・「この情報は次の訪問で話そう」と目的を持って勉強する
・アウトプット前提にすることで、知識の定着と実務への反映が進む
その他の不満点
その他の不満点一覧
| 不満の内容 | 顧問先の本音 |
|---|---|
| 書類の受け渡しが面倒 | 「郵送?FAX?もっと簡単にできないの?」 |
| ITツールに弱く対応が遅い | 「クラウドでやってくれる事務所に変えたい」 |
| 常に忙しそうで相談の優先度が低い | 「うちは大事にされていない気がする」 |
| 節税ばかりで経営の視点がない | 「アドバイスが会計の範囲にとどまっている」 |
| 話が一方的でこちらの状況を理解していない | 「テンプレで対応されてる感じがして残念」 |
改善への一歩 変更を恐れずに
税理士もサービス業。顧問先のニーズや時代の変化にあわせて、自らの業務スタイルや価値提供も「見直し続ける姿勢」が求められます。
1. フィードバックを“怖がらず”に聞く姿勢を持つ
・年1回、匿名アンケートを取る・定期的なヒアリングを行う
2. “昔ながら”のやり方にこだわらない
・紙・ハンコ・FAXなどに依存しすぎない柔軟性
・クラウド会計・チャットツールの導入検討を
3. 「自分の強みと弱み」を見つめ直す
・自分が得意な業種・提案領域に集中することで、他との差別化が可能に
・苦手な分野は信頼できる外部パートナーと連携してカバーする
4. 「変化する=信頼を失う」ではなく「進化する=信頼を積み上げる」
・顧問先は「完璧な人」より「変化を恐れず学ぶ人」に信頼を置きます
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
本記事では、税理士に対する不満トップ5とその背景・対策を以下のとおりご紹介しました:
| ランキング | 不満の内容 | 改善ポイント |
|---|---|---|
| 第1位 | コミュニケーションの問題 | 初回ルール決め/専門用語の回避/定期フォロー |
| 第2位 | 料金の透明性の欠如 | 料金表の明示/追加料金の明確化/サービス内容の見える化 |
| 第3位 | 節税提案の不足 | 年間を通じた提案/リスク許容度の確認/アピールの工夫 |
| 第4位 | 相談のしづらさ | 雰囲気づくり/チャネルの多様化/声かけの習慣 |
| 第5位 | 税務知識の不足 | 情報収集の習慣化/研修参加/事務所内の共有体制 |
さらに、上位に入らなかった「書類対応の手間」「ITリテラシー」「経営視点の欠如」なども、地味ながら見逃せないポイントです。
税理士業務は専門性と信頼の積み重ねで成り立っています。
“変えること”は怖いものですが、“変わらないこと”のほうがリスクになる時代です。
一つひとつの不満を「改善のヒント」として受け止め、自ら進化する姿勢が、長く選ばれる税理士への第一歩になります。
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















