INDEX
おすすめ記事
-
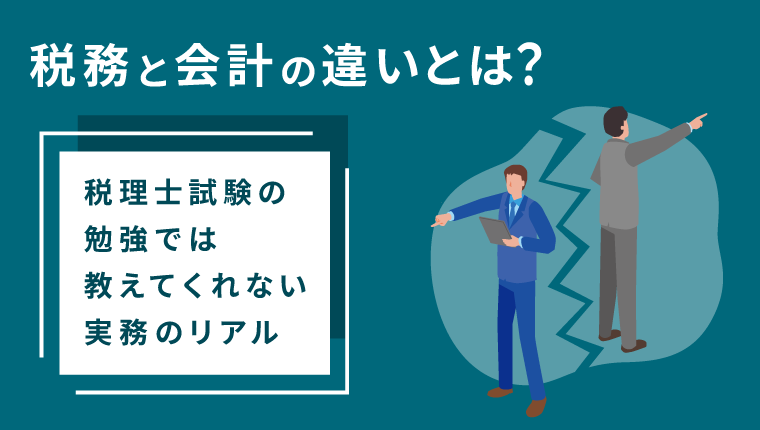
税務と会計の違いとは?税理士試験の勉強では教えてくれない実務のリアル
-
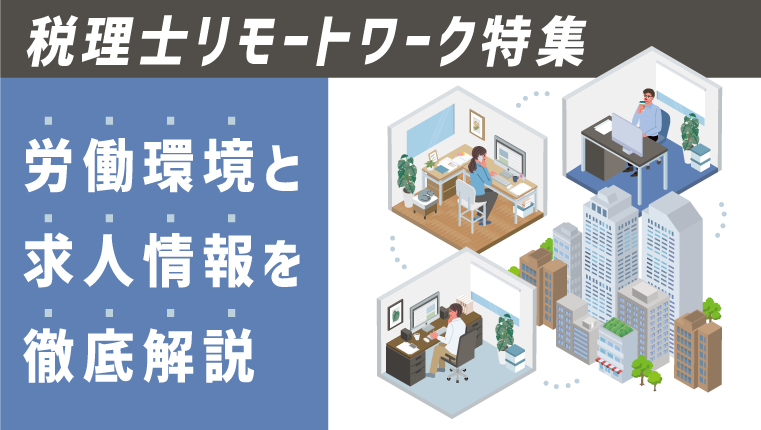
税理士リモートワーク特集|労働環境と求人情報を徹底解説
-
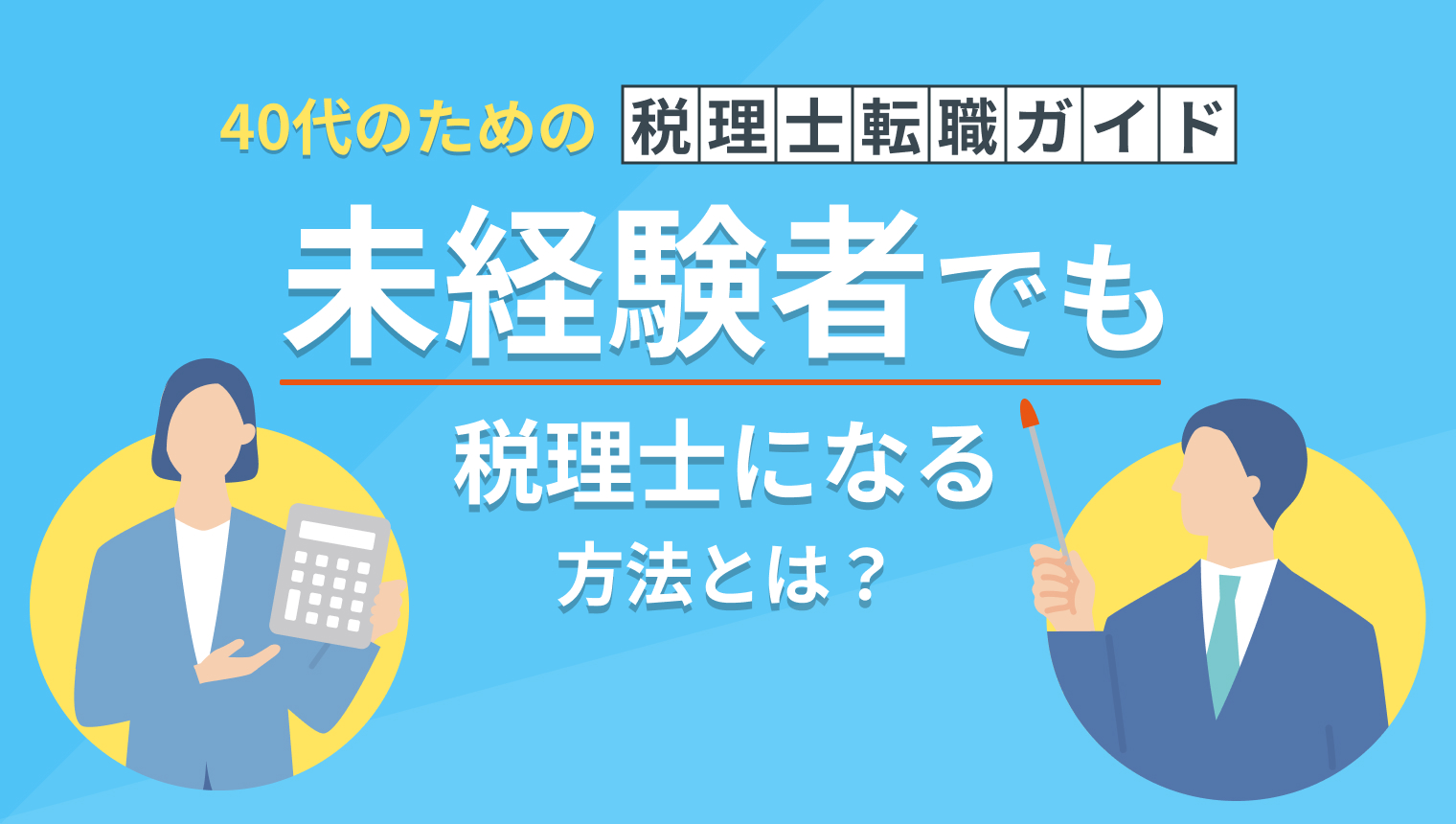
【40代から税理士を目指す!】未経験者でも税理士になる方法とは?
-
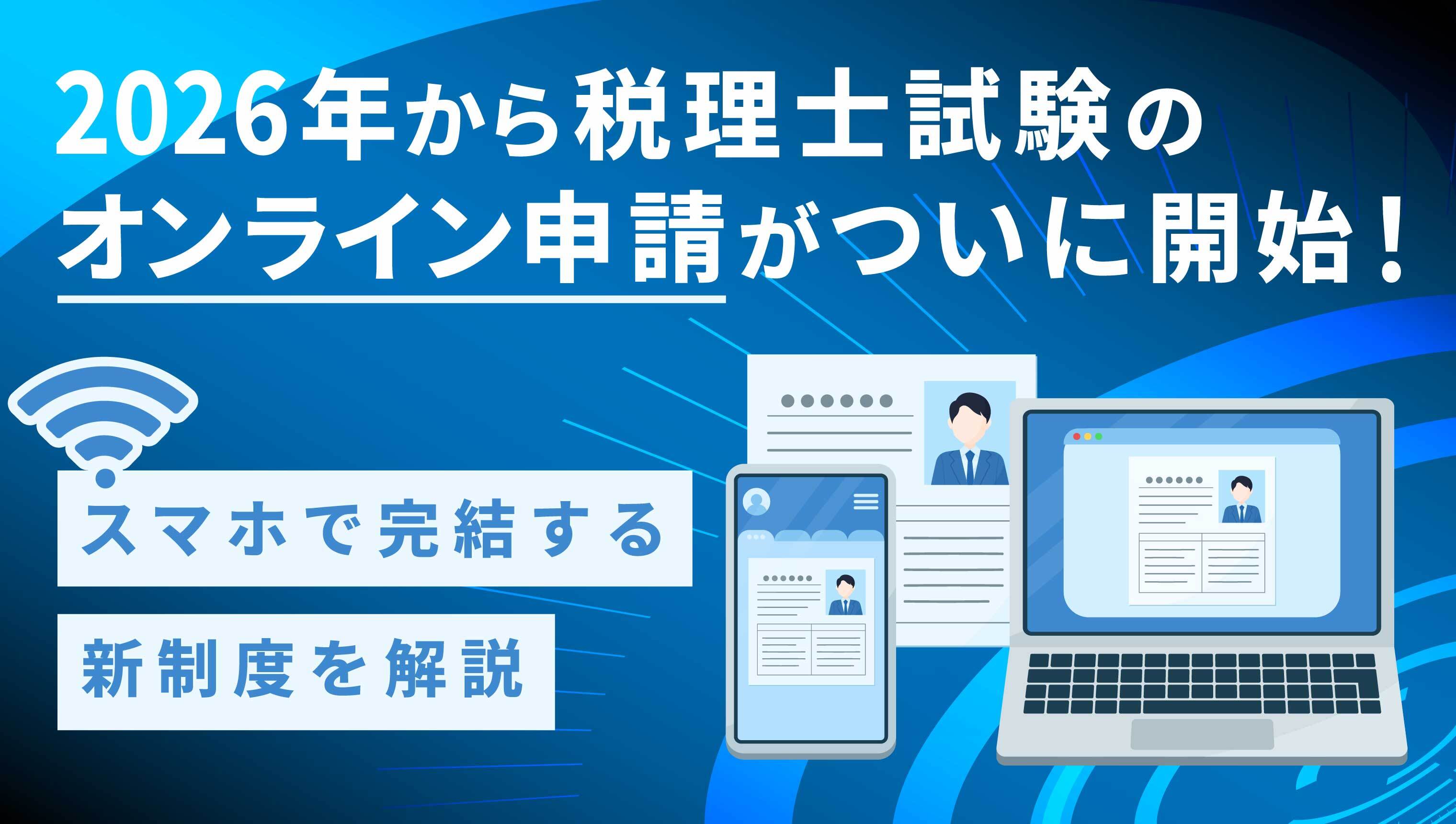
2026年から税理士試験のオンライン申請がついに開始!スマホで完結する新制度を解説
-
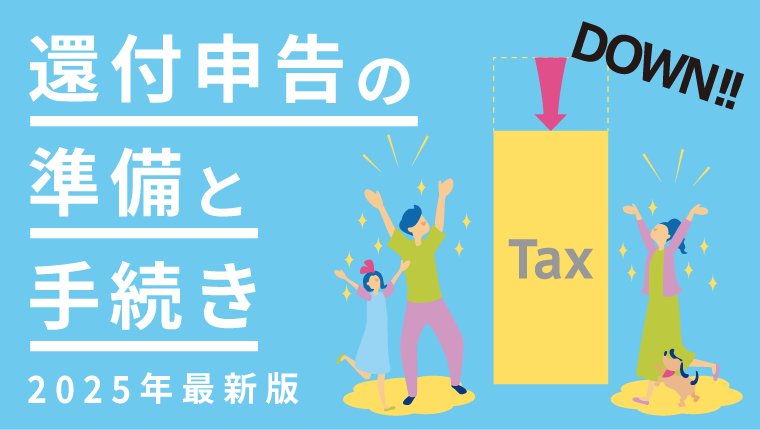
還付申告の準備と手続き【2025年最新版】
公開日:2025/04/10
最終更新日:2025/09/06
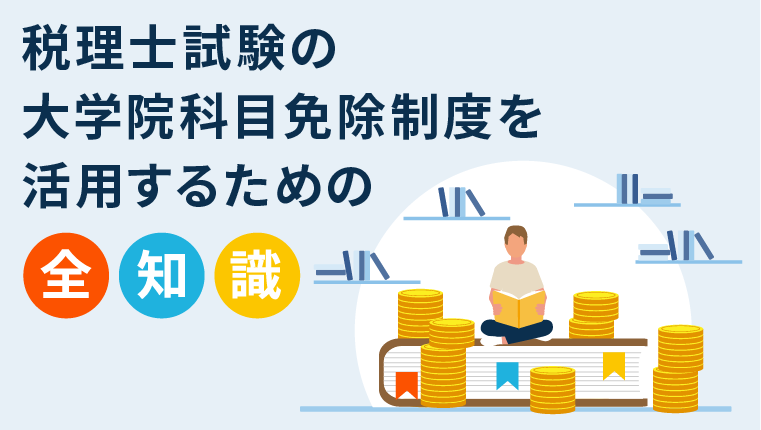
INDEX
税理士試験の科目数に圧倒されていませんか?
「勉強を続けているけれど、5科目合格は遠すぎる…」
そんなあなたに知ってほしいのが、大学院科目免除制度という選択肢です。
この制度を活用すれば、大学院での研究を通じて最大3科目が免除され、合格への道がぐっと近づきます。
でも、それは単なる“裏技”ではありません。
大学院での学びは、試験では得られない本質的な知識と実務に直結する力を身につける貴重な時間。
「税理士になった後も強みになる経験」が、ここにはあります。
この記事では、制度の仕組みから大学院選び、研究テーマの選び方まで、初めての方にも分かりやすく解説します。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士試験における大学院科目免除制度とは
税理士試験における「大学院科目免除制度」とは、特定の大学院(主に修士課程)で税法や会計学に関する研究を行い、所定の要件を満たすことで、税理士試験の一部科目(税法または会計学)を免除できる制度です。
1. 制度の概要
税理士試験の一部科目(最大2科目)を、大学院での研究により免除できる制度です。
税理士試験は原則5科目(会計学2科目+税法3科目)を合格する必要がありますが、この制度を利用すれば、大学院修了によって最大3科目の合格が免除されます。
2. 免除申請の流れ
1.大学院に進学・修士課程を修了
税法または会計学に関する修士論文を作成・提出。
2.国税審議会へ免除申請
修士論文、研究内容、履修内容などを添付して申請。
3.審査を経て、科目免除が認められる
内容が適格と判断された場合、正式に免除されます。
大学院を出ただけでは免除されません。国税審議会による審査と認定が必須です。
3. この制度の意義と特徴
・試験での全科目合格が難しい方にとって、戦略的に税理士を目指す手段となる
・学術的なアプローチから税法・会計学を深く学ぶことができ、実務に強い税理士を目指せる
・修士論文の作成により、論理的思考力・文書作成力・制度理解力が身につく
4. 留意点
・修士論文の質が免除認定の重要な判断材料となる
・大学院選びや指導教員の選定が、研究の成果に大きく影響する
・学費や通学時間など、コストとライフスタイルへの影響も考慮が必要
税理士試験の科目免除制度を活用するメリット
税法に関する深い知識の習得
大学院では、税理士試験のような「正解を当てる勉強」ではなく、税法の制度趣旨や背景、立法過程、判例、学説に至るまで、本質的な理解を深めることができます。
・制度の成り立ちを理解できる
例えば「所得税」や「法人税」がなぜそのような構造になっているのか、理論的・歴史的な視点から学ぶことが可能です。
・判例や学説も学ぶ
実務で問題になりやすい「グレーゾーン」の取扱いについても、判例や学説を用いて多角的に検討する力が養われます。
・応用力がつく
実務で想定外のケースに直面した際にも、表面的な知識にとどまらず、法の根拠や趣旨に立ち返って判断できる力が身につきます。
研究を通じた実践的な理解
大学院では、単なる受動的な学習ではなく、自ら研究テーマを設定し、資料を収集し、論理的に構成する訓練を受けます。
・修士論文の作成を通じた問題解決力の向上
税目ごとの課題(例:相続税の課税公平性、移転価格税制の適用実態など)に対し、自分なりの仮説を立て、調査・分析する中で、実務に即した応用力と文章力が鍛えられます。
・特定分野への専門性が高まる
修士論文のテーマは自由に選べるため、自分のキャリアと関連のある税目を深堀りし、“この分野に強い税理士”としての専門性をアピールできます。
・実務家としての視点が養われる
論文作成においては、理論だけでなく実務との接点や課題解決策を求められることが多く、税務調査や顧問業務にも直結する思考力を培えます。
科目免除を受けるための条件
税理士試験の科目免除(大学院ルート)を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1. 修士課程の修了 | 税法または会計学に関する大学院修士課程を修了していること(博士課程でも可) |
| 2. 該当する研究分野 | 税法免除の場合:税法に関する研究 会計学免除の場合:会計学に関する研究 |
| 3. 修士論文の提出 | 免除申請時に修士論文を添付。テーマや内容が税理士法で求められる水準にあることが必要 |
| 4. 国税審議会の認定 | 大学院修了後、国税審議会に科目免除申請を行い、審査を経て認定を受ける必要がある |
単に大学院を修了するだけでは免除になりません。論文の内容や研究指導の体制も審査対象です。
大学院での研究科目とその重要性
大学院での研究科目(研究テーマや指導科目)は、免除申請において極めて重要です。
・研究テーマが税法と明確に関係している必要があります。
例:
◦所得税における課税の公平性
◦法人税におけるグループ法人税制の研究
◦国際課税とBEPS対策 など
・指導教員が税法の専門家であるかどうか、研究計画書や論文指導体制の記載内容も審査対象になります。
・税理士を目指す場合、「課題設定・理論的な構成・実務的視点」を備えた論文が高評価を得やすいです。
税法科目の選び方
大学院を利用して税法2科目の免除を目指す場合でも、残り1科目は試験合格が必要です(税法3科目中1科目は自力合格が原則)。
よくある選択パターン
| 免除対象 | 試験で受ける科目(例) |
|---|---|
| 所得税法+相続税法(免除) | 法人税法(試験受験) |
| 法人税法+消費税法(免除) | 所得税法(試験受験) |
✅ 科目選びのポイント
・実務で扱いたい税目や将来の専門性に合わせて選ぶのが理想です。
・一般的に試験対策が大変な「法人税法」を免除し、試験では比較的ボリュームの少ない「消費税法」などを選ぶ受験者も多いです。
・大学院側のカリキュラムによっても、どの科目が研究しやすいか変わってきます。
税理士大学院の選び方と注意点
カリキュラムの比較と選択ポイント
大学院によって、科目の構成・研究テーマの自由度・免除実績に差があります。自分の目的に合ったカリキュラムを選ぶことが大切です。
| チェックポイント | 解説 |
|---|---|
| ✅ 免除対象の科目 | 税法免除のみ対応の大学院もあれば、会計学免除にも対応している大学院もあります。どちらを免除したいか明確にしましょう。 |
| ✅ 講義内容の実務寄り/理論寄りのバランス | 実務家による講義があるか、学術的研究に特化しているかを確認。自分がどちらを求めているかで選択。 |
| ✅ 論文テーマの自由度 | 特定の税目(例:法人税中心)に偏っている大学もあれば、幅広く対応している大学もあります。興味のあるテーマで論文を書けるか要確認。 |
| ✅ 社会人向けの配慮 | 夜間・土日開講、オンライン対応など、働きながら通いやすいかどうかも重要。 |
比較例
・A大学院:法人税・所得税に強く、理論重視、修士論文の評価が厳格
・B大学院:消費税・国際税務に強く、実務家教員が多く、通いやすい(平日夜間)
研究施設と教員の質の確認
研究を支える環境と指導者の質は、修士論文の完成度に大きく影響します。
| チェックポイント | 解説 |
|---|---|
| ✅ 指導教員の専門分野 | 自分の研究したいテーマに精通している教員が在籍しているか(例:相続税の専門家がいるかなど) |
| ✅ 修士論文のサポート体制 | 少人数でしっかり論文指導があるか、研究計画書から丁寧に見てくれるか |
| ✅ 過去の修了生の論文テーマや免除実績 | 過去の論文が公式サイト等で公開されている場合、テーマの自由度や指導の傾向がわかります。免除申請が実際に通っているかも確認。 |
| ✅ 図書館やデータベースの整備 | 税法関連の判例・学術資料を利用できる環境が整っているかも重要です。 |
大学院によっては、教員が国税庁出身者や現職の税理士の場合もあり、実務的視点でのフィードバックが得られることもあります。
税理士大学院での研究テーマの選定方法
実務に直結するテーマ選びのコツ
修士論文のテーマは、税理士としての将来の専門性や、実務力の源になる非常に重要な要素です。以下のようなポイントを意識しましょう。
選定のポイント
| 視点 | 解説 |
|---|---|
| ✅ 自分が扱いたい税目から逆算する | 例:将来、相続税に強い税理士になりたい → 相続税に関する論点を選ぶ(納税猶予制度の比較・生前贈与との相違など) |
| ✅ 実務で論点になりやすい領域を選ぶ | 例:交際費・寄附金の損金不算入、インボイス制度、役員報酬の損金算入要件 など |
| ✅ 事例が多く集められるテーマを選ぶ | 実務上の判例・国税不服審判所の裁決・税理士会のレポートなどから、実例を豊富に分析できるテーマは書きやすく、説得力も増します。 |
| ✅ 時事性があるテーマは審査でも好印象 | 例えば「インボイス制度」「電子帳簿保存法」「BEPS2.0」などの最近の法改正テーマは、国税審議会の評価も高い傾向があります。 |
テーマ例(実務寄り)
・「インボイス制度導入による中小事業者の税務対応と課題」
・「事業承継税制の適用実態と制度上の課題」
・「交際費課税における『通常要する費用』の範囲に関する考察」
・「国際取引における移転価格税制と文書化対応の実務上の課題」
法改正への対応力を身につけるための研究
税制は毎年改正されるため、将来的に税理士として活躍するには、「変化に強い」知識構造が必要です。そのためには以下のようなテーマ選び・研究姿勢が重要です。
法改正を踏まえたテーマ選定のコツ
| 方法 | 解説 |
|---|---|
| ✅ 法改正の背景に注目する | 単なる条文の変化だけでなく、「なぜ改正されたのか」「何を解決しようとしたのか」という立法趣旨に踏み込むことで、法の理解が深まります。 |
| ✅ 改正前後の比較研究 | 例:「旧電子帳簿保存法と2022年改正後の制度比較」など、ビフォー・アフターの分析は論理構成がしやすく、実務でも有用です。 |
| ✅ 判例・裁決例との関係を検討する | 法改正が特定の判例・裁決例を契機としていた場合、その前後の解釈の違いを研究することで、思考力・応用力が高まります。 |
テーマ例(法改正重視)
・「インボイス制度の導入と仕入税額控除制度の構造的変化」
・「電子帳簿保存法の改正における実務対応の限界と課題」
・「相続税における小規模宅地特例の改正と課税公平性の検討」
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
税理士試験における「大学院科目免除制度」とは、大学院(主に修士課程)で税法または会計学に関する研究を行い、一定の条件を満たすことで、税理士試験の一部科目(最大2科目)の合格が免除される制度です。この制度を活用することで、通常5科目の合格が必要な税理士試験のうち、大学院での研究を通じて最大2科目を免除することができ、残り3科目の合格で税理士資格を目指すことが可能になります。
この制度の大きなメリットは、試験対策とは異なる視点で、税法や会計学をより深く、体系的に学ぶことができる点です。大学院での学びは、制度の成り立ちや立法趣旨、判例・学説など、理論と実務の双方を踏まえた本質的な理解につながります。さらに、自らテーマを設定し、資料を収集・分析し、論理的に論文を構築する過程を通じて、応用力や文章力、問題解決力といった実務に直結する力も養うことができます。
科目免除を受けるためには、大学院の修士課程を修了しているだけでは不十分であり、国税審議会に免除申請を行い、研究テーマや修士論文の内容が税理士法上の基準を満たしているかどうかの厳格な審査を受ける必要があります。研究テーマが税法や会計学と明確に関係していること、指導体制が整っていること、論文の完成度が高いことなどが、審査通過のカギを握ります。
大学院の選び方も非常に重要です。免除対象科目(税法・会計学)の対応状況、講義内容の実務寄り/理論寄りのバランス、研究テーマの自由度、論文指導の体制、さらには夜間・土日・オンライン対応など、社会人が通いやすい環境が整っているかどうかも、選定の際の重要なポイントとなります。また、教員の専門性や過去の修了生の論文テーマ・免除実績も確認しておくと安心です。
研究テーマの選定においては、自分の将来の専門性を意識し、実務で論点になりやすい課題や、近年の法改正に関わるテーマを選ぶことが望ましいとされています。たとえば、インボイス制度や電子帳簿保存法、事業承継税制など、時事性が高く、かつ実務に直結するテーマは、審査でも高く評価される傾向があります。
このように、大学院科目免除制度は、単に試験を回避するための抜け道ではなく、将来信頼される税理士としての土台を築くための「実力養成の場」として、大きな意味を持っています。研究の過程で得られる知識やスキルは、実務や顧客対応において必ず強みとなるはずです。
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















