INDEX
おすすめ記事
-
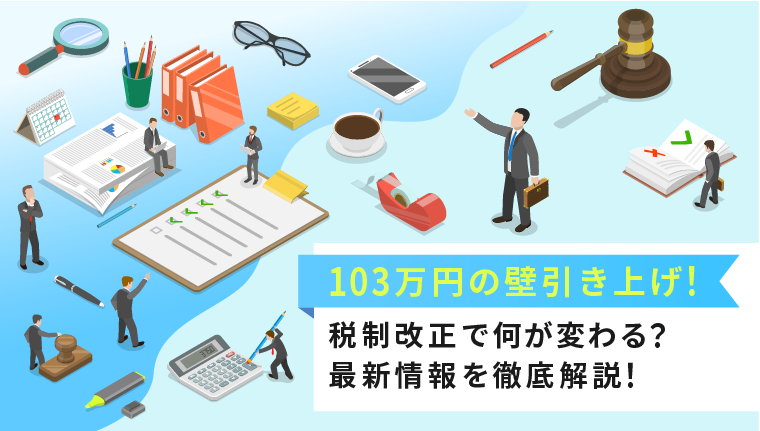
年収の壁引き上げ!2025年税制改正で何が変わる?最新情報を徹底解説!
-
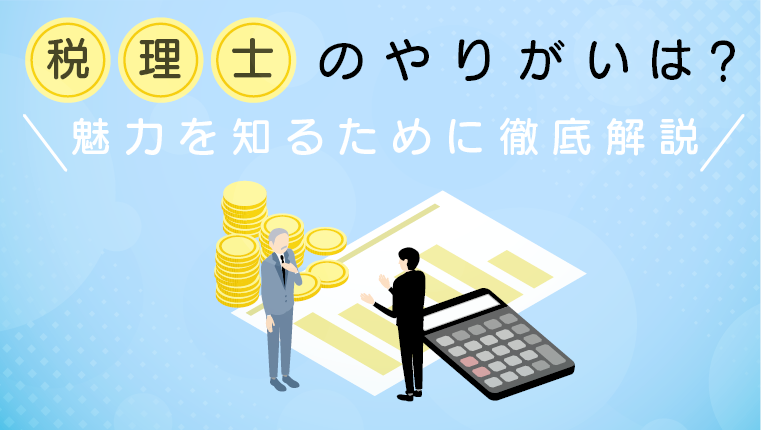
税理士のやりがいは?魅力を知るために徹底解説
-
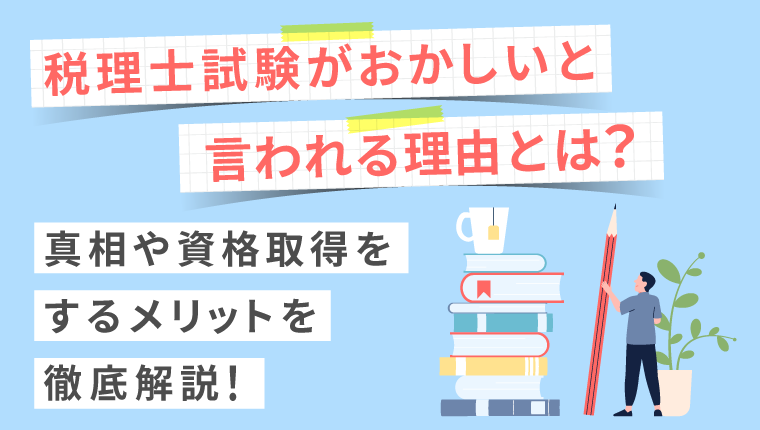
税理士試験がおかしいと言われる理由とは?真相や資格取得をするメリットを徹底解説!
-

IPO支援に強い税理士とは?IPOにおける税理士の役割と実務を徹底解説
-
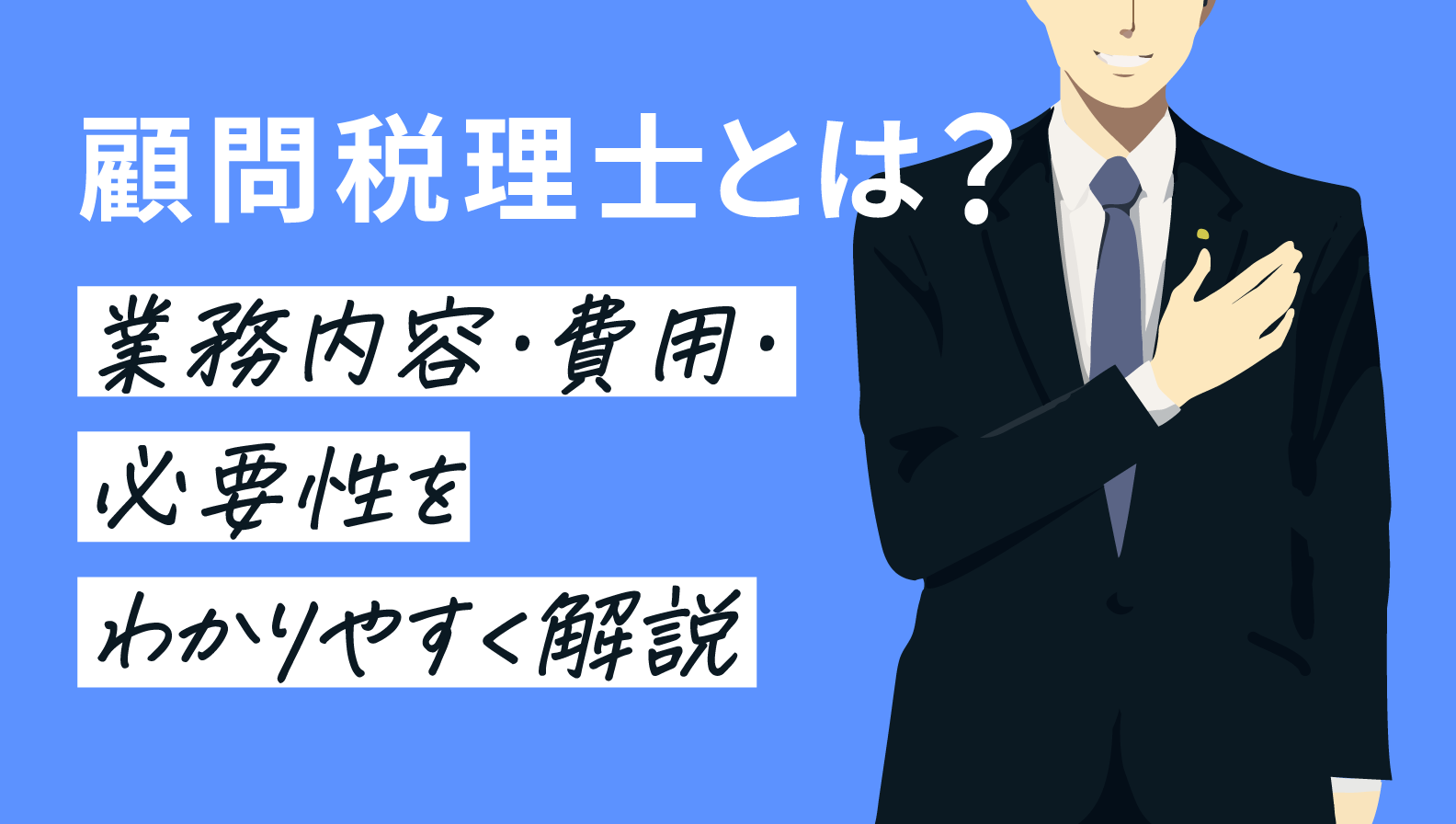
顧問税理士とは?業務内容・費用・必要性をわかりやすく解説
公開日:2025/05/18
最終更新日:2025/09/06

INDEX
税理士試験の住民税。
「地方税だし、簡単そう」なんて思っていませんか?
実は、平日5時間・休日12時間の勉強が必要な、
甘くない戦場です。
しかし、正しい戦い方を知れば、住民税は確実に得点源にできる科目
でもあります。
この記事では、住民税の難易度、出題傾向、そして圧倒的努力を結果につなげる勉強法を徹底解説。
ただがむしゃらに頑張るのではなく、「合格するための努力」に絞り込む方法を紹介します。
「限界までやり切った」と胸を張って試験に向かいたいあなたへ。
今から、住民税攻略のすべてを始めましょう。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士試験における住民税の概要と重要性
税理士試験において「住民税」は、国税と地方税の橋渡しとなる重要科目です。
特に地方自治体に対する税務代理や申告業務を行う上で、住民税の知識は不可欠です。
また、法人税や所得税と密接に関連しているため、これらと併せて理解することで税理士としての実務対応力が格段に向上します。
住民税とは何か?
住民税とは、都道府県や市町村といった地方自治体が課税する税金であり、地域社会の公共サービス(教育・福祉・インフラなど)を支える財源となっています。
・【個人住民税】所得割+均等割の2本立て。
・【法人住民税】資本金等に基づく均等割と、法人税割。
・国税に比べると、地域独自の取り扱いがある点が特徴。
| 税区分 | 主な対象者 | 課税内容 | 課税方式 | 特徴 |
| 個人住民税 | 個人(住民) | ① 所得割 ② 均等割 |
賦課課税方式(申告・特別徴収) | 所得に応じた税+定額負担。 会社員は給与から天引き(特別徴収)。 |
| 法人住民税 | 法人(企業) | ① 均等割 ② 法人税割 |
賦課課税方式 | 資本金や従業員数に応じた均等割+法人税額に連動した法人税割。 |
税理士試験における住民税の位置づけ
住民税は、税理士試験において「地方税法」の一部として扱われます。
地方税法は国税中心の他科目(法人税法・所得税法・相続税法など)とは異なり、地方自治体が課税する税金を対象とする科目です。
住民税はその中核テーマの一つであり、個人・法人両方の住民税について幅広く理解することが求められます。
また、地方税法は税理士試験の中でも選択必須ではないマイナー科目に分類されるため、受験者数は少なめですが、しっかり対策すれば高得点を狙いやすいという特徴もあります。
| 項目 | 内容 |
| 科目分類 | 地方税法(選択科目のひとつ) |
| 住民税の対象 | 個人住民税、法人住民税 |
| 税理士試験での重要度 | 地方税法内で主要テーマのひとつ |
| 出題対象 | 理論問題(制度説明・条文理解) 計算問題(所得割・均等割・法人税割の計算) |
| 難易度 | 中程度(基本を押さえれば高得点可能) |
| 受験者数 | 少なめ(法人税法・所得税法に比べ) |
| 出題傾向 | 改正点+基本問題が中心 |
| 位置づけの特徴 | 地方税の基礎知識と実務理解を問う |
| 実務における重要性 | 企業・個人の税務対応で必須知識 |
住民税の難易度と出題傾向
住民税の難易度レベル
住民税は、他の主要科目(法人税法・所得税法など)と比べると 難易度は中程度 と評価されています。
ただし、単純な「易しい」「難しい」だけでは測れず、以下のような特徴があります。
【1】制度設計が比較的シンプル → 難易度やや低め
・国税(所得税・法人税など)に比べ、制度の複雑さは少ない。
・計算ルールや手続きフローがストレートで覚えやすい。
【2】改正対応が必要 → 難易度やや高め
・住民税は国税の改正に連動して頻繁に細かい改正がある。
・特に「所得割」「法人税割」などに変更があった場合、迅速にキャッチアップが必要。
【3】暗記量が地味に多い → 難易度中程度
・条文ベースで押さえる必要があるため、丸暗記の負担感がある。
・均等割・所得割・特別徴収のルールなど、数字を伴う暗記が多め。
【4】出題範囲が狭い → 得点源になりやすい
・出題範囲が絞られているため、パターン学習が有効。
・効率的に対策すれば高得点が狙える。
難易度比較表
| 科目 | 難易度 | 理由・特徴 |
| 法人税法 | 非常に高い | 制度が複雑、実務性が高く、計算問題も難問多数。 |
| 所得税法 | 高い | 総合課税・分離課税など体系が広く、理論暗記量も膨大。 |
| 相続税法 | 高め | 理論・計算ともに分量が多く、応用問題も多い。 |
| 消費税法 | 中程度 | 範囲が限定されており、計算メインだが改正対応が必須。 |
| 住民税 | 中程度 | 制度はシンプルだが改正対応と暗記量に注意。出題範囲が狭く得点源にしやすい。 |
| 固定資産税 | 低~中程度 | 出題傾向が安定していて、覚えるべきパターンが限られている。 |
過去の出題傾向と分析
住民税は税理士試験の地方税法科目において、毎年安定して出題されています。
特に「理論問題」と「計算問題」の両方でバランスよく問われる傾向があり、基本論点を着実に押さえることが合格の鍵となります。
近年の出題傾向を分析すると、次のような特徴があります。
頻出テーマ
【1】理論問題の傾向
・制度趣旨や徴収方法(特別徴収・普通徴収)について問う問題が多い。
・賦課課税方式の仕組みや、所得割・均等割の趣旨など、条文ベースでの理解を要求される。
・税制改正があった年は、その影響が出やすい(例:均等割額の変更など)。
【2】計算問題の傾向
・個人住民税:所得割・均等割の計算が基本。
・法人住民税:資本金等の規模に応じた均等割額、法人税額に基づく法人税割額の計算が頻出。
・ミスしやすいポイント(課税標準の判定、税率適用、特別控除など)が狙われやすい。
【3】改正対応の傾向
・新設された特例措置、税率変更、控除額改定などは直後2~3年以内に出題されやすい。
・直近では「ふるさと納税制度の影響」や「特別徴収の強化」などが狙われた。
| 年度 | 理論問題テーマ | 計算問題テーマ | 傾向・特徴 |
| 令和6年 (2024年) | 特別徴収義務者の義務と違反措置 | 法人住民税の均等割と法人税割の算定 | 特別徴収関連強化。法人税割の改正対応問われた。 |
| 令和5年 (2023年) | 賦課課税方式の概要と意義 | 個人住民税(所得割・均等割) | 賦課課税の基本趣旨確認問題。計算はオーソドックス。 |
| 令和4年 (2022年) | 均等割額の引き上げと特例措置 | 法人住民税の均等割計算 | 均等割改正点を問う。法人税割は平易。 |
| 令和3年 (2021年) | 普通徴収と特別徴収の比較 | 個人住民税(所得控除適用後の所得割) | 徴収方法の比較整理が必須。所得割計算は標準問題。 |
| 令和2年 (2020年) | 住民税における非課税措置 | 法人住民税の申告・納付期限 | 非課税対象の論点整理。計算は納期限に注意。 |
出題形式の傾向
・計算問題:6割
・理論問題:4割
・実務感覚を問う応用問題が少ないため、基本を確実に押さえるのがカギ。
住民税の効果的な勉強方法
税理士試験は、住民税といえども甘く見ると落ちます。
合格するためには、次の3つの力が必要です。
合格に必要な3力
1.理論暗記力(スピード+正確さ)
2.計算処理力(正確さ+速さ)
3.改正対応力(最新情報への感度)
タイムスケジュール
これらを鍛え抜くために、
平日5時間、休日12時間を最大限有効に使う勉強設計をします。
| 曜日 | 時間帯 | 内容 | 目安時間 |
| 平日 | 朝 | 理論暗記 | 1時間 |
| 昼・隙間時間 | 理論の復習(暗唱) | 30分〜1時間 | |
| 夜 | 計算問題演習+過去問 | 3〜3.5時間 | |
| 休日 | 朝 | 理論暗記+アウトプット | 4時間 |
| 昼 | 計算問題総合演習 | 4時間 | |
| 夜 | 過去問・答練復習+弱点潰し | 4時間 |
▶平日5時間(朝・昼・夜)/休日12時間(朝4h+昼4h+夜4h)の確保が標準ライン。
勉強フェーズ別にやるべきこと
【第1フェーズ(~試験半年前まで)】基礎構築期
やること
・理論テキストを読み込み、キーワードレベルで暗記開始
・計算問題は「基本問題だけを繰り返す」
・改正論点は別ノートで整理していく
ポイント
・「完璧を目指さない」ことが重要(最初は7割理解でOK)
・理論は「読んだ回数=実力」と割り切る
【第2フェーズ(~試験3か月前まで)】応用力強化期
やること
・理論の暗記を「全文再現」レベルに高める
・計算問題は応用問題・実戦形式へ移行
・過去問を本格的に回し始める(5年分×3周以上)
ポイント
・理論の記述練習は必須!(白紙に書き出す)
・計算問題は「手を動かすスピード」を意識
【第3フェーズ(試験3か月前~直前)】仕上げ期
やること
・過去問・答練の間違い問題だけを集中的に潰す
・改正論点・最新情報の復習を徹底
・「理論+計算」通し演習を毎日やる(朝に理論、夜に計算)
ポイント
・「できない問題を潰す」→「得点力の最大化」
・新しい参考書に手を出さない(迷いが命取り)
合格を目指すための戦略とアドバイス
住民税の合格者に共通して見られる勉強法には、いくつかの明確な特徴があります。
以下整理します。
1. 理論暗記は「できるだけ早期に」完了させる
体験談
「最初の2か月は、問題演習は一切やらず、ひたすら理論暗記に集中しました。早めに理論を頭に入れておくと、計算問題に取り組むときも理解が早かったです。」
ポイント
・勉強開始初期は、理論テキストをひたすら素読+暗記。
・暗記といっても、全文暗記よりまずキーワード暗記を優先する。
・キーワードを手がかりに、理論をスラスラ口頭で言えるレベルを目指す。
2. 改正点ノートを自作して毎週アップデート
体験談
「税は地味に改正が多いので、税制改正通達が出たらすぐに自作ノートにまとめていました。これを直前期に見返すと抜群に効果的でした。」
ポイント
・税制改正事項は、公式資料から抜粋→自分の言葉でまとめ直す。
・改正事項だけを集めた「改正特化ノート」を作成。
・週1回、ノートを更新・復習する習慣を持つ。
3. 過去問は「完璧主義に陥らず、復習重視」
体験談
「間違えた問題にしつこくこだわるよりも、復習に重きを置きました。特に同じテーマで違う聞き方をされる問題を探して、横断的に整理しました。」
ポイント
・1問1問に固執しない。「間違いからパターンを拾う」感覚を大事に。
・同じ論点を複数年で出題される場合、問われ方の違いを整理する。
・完璧を目指すより、「似た問題なら対応できる」状態を作る。
4. 法人住民税と個人住民税を「別管理」で徹底整理
体験談
「法人住民税と個人住民税は、問題演習でもノートでも必ず分けて整理しました。一緒にすると税率や課税標準の違いで混乱するので、線引きを意識しました。」
ポイント
・【法人住民税】と【個人住民税】のノートを物理的に別冊に分ける。
・各論点ごとに「法人なら?」「個人なら?」と意識的に考えるクセをつける。
・混同しやすい項目(均等割・税率表など)は特に要注意。
5. 模試・答練の活用法:「練習の場」と割り切る
体験談
「模試や答練で合格点を取れなくても気にしないと決めていました。本番さながらに時間配分と見直し力を鍛える場と割り切ったことで、逆に本試験で落ち着けました。」
ポイント
・模試・答練は結果に一喜一憂しない。
・重要なのは「時間配分ミス」「ケアレスミス」のパターンを把握すること。
・ミスノートを作り、直前期にそれだけを集中的に見直す。
【総まとめ】成功者に共通していること
✅ 理論暗記を早めに仕上げる(キーワード重視→全文化)
✅ 改正点に敏感になり、必ず自作ノート化
✅ 過去問は「理解重視」でパターンをストック
✅ 法人・個人を分けて勉強する(ノートも分ける)
✅ 模試・答練は「本番のための訓練」と割り切る
試験直前の準備と心構え
直前期は「割り切り」が大事です。
満点を狙うのではなく、「落とさない問題を確実に拾う」姿勢を持ちましょう。
直前期の行動リスト
・最低5年分の過去問を回す(ミスった問題だけ重点復習)
・試験1週間前からは新しい問題に手を出さない
・理論のキーワードを5分で言えるレベルに暗記する
・体調管理(睡眠・食事)も優先する
心構え
・「7割できれば合格」のマインドで臨む
・緊張しても手を動かす(手が止まると焦る)
・最後まで諦めずに計算を埋める
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
この記事では住民税の勉強法について解説しました。
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















