INDEX
おすすめ記事
-
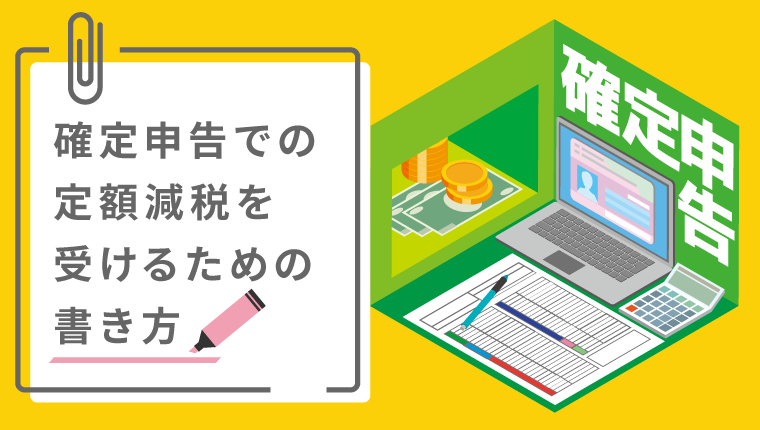
確定申告で定額減税を受けるための書き方|2025年(令和6年分所得)確定申告
-

税理士への不満ランキングTOP5|気を付けるべきポイントと改善策
-
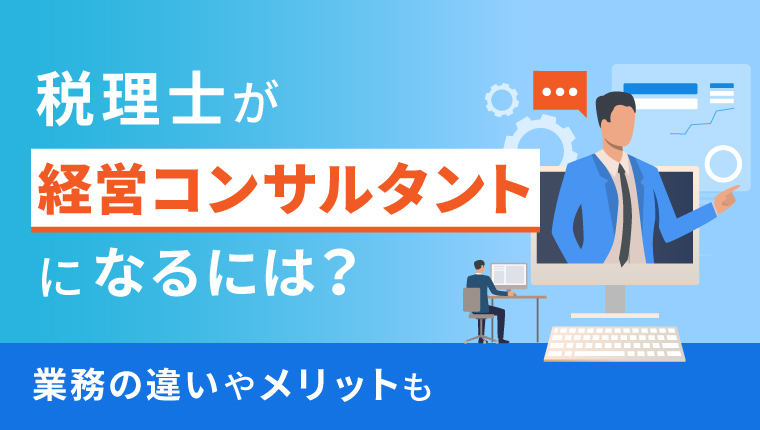
税理士が経営コンサルタントになるには?業務の違いやメリットも
-
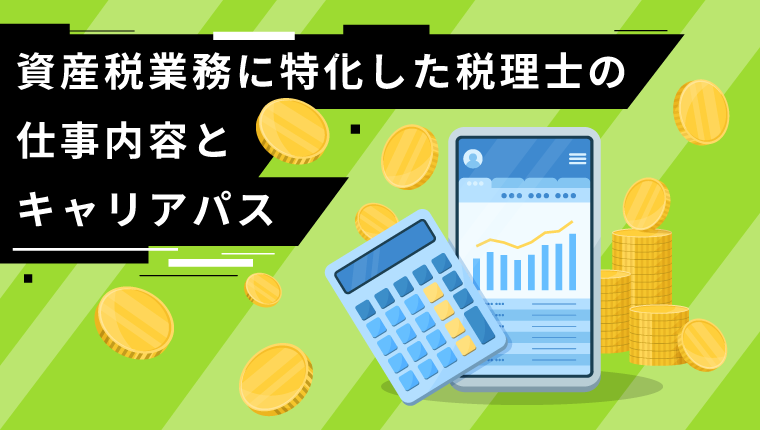
資産税業務に特化した税理士の仕事内容とキャリアパス
-
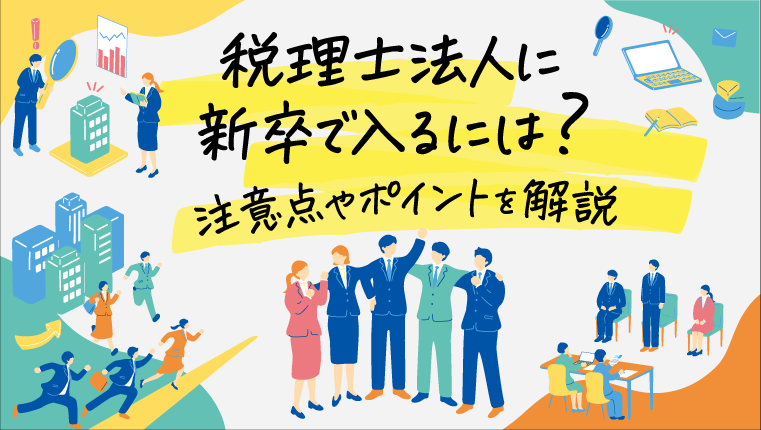
税理士法人に新卒で入るには?注意点やポイントを解説
公開日:2025/05/23
最終更新日:2025/09/06

INDEX
「税理士法人って、結局、儲かるの?」
個人事業よりも組織的で、信用力も高い――そんなイメージはあるけれど、実際に成功するにはそれなりの戦略と覚悟が必要です。
すでに法人化して後悔している人もいれば、法人化して年商1億円を超える事務所も存在します。
違いを分けるのは、“経営”の視点があるかどうか。
この記事では、実際の成功事例をもとに、税理士法人でうまくいった人たちが「何をして」「何を避けたか」をまとめました。
特化か?ブランディングか?共同経営か?
自分の目指すモデルを見つけるためのヒントがここにあります。
法人化を検討しているあなたにこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士法人の設立を考える理由
個人税理士として独立して順調に顧客が増えてくると、業務の幅が広がり、ひとりでは対応が難しくなってきます。そのようなタイミングで「法人化」を考える方が増えます。特に、複数名の税理士で組織的に経営したい場合や、将来的な事業承継を見据える場合に有効です。
主な理由は以下のとおりです:
・顧問先の増加に対応し、分業体制を構築したい
・顧客や金融機関からの信頼性を高めたい
・税理士同士で共同経営を行いたい
・従業員の採用や福利厚生を整え、人材を確保したい
・自分の引退後も、事務所を継続させたい
税理士法人設立のメリット
法人化によって、経営面・税務面・人材管理面での自由度が広がります。単なる「形」ではなく、事務所を組織として成長させるための土台となります。
| メリット | 内容 |
| 組織的な対応が可能 | 職員・他税理士との分業体制が築け、品質の安定や効率化が期待できる。 |
| 所得の分散が可能 | 複数の社員税理士が収益を分け合うことで、税負担の平準化ができる。 |
| 経費処理の柔軟性 | 給与や退職金の支給など、法人ならではの経費処理が可能。 |
| 社会保険の適用 | 法人代表者や職員に対して社会保険(厚生年金など)を適用できる。 |
個人事業との違い
「個人の税理士事務所」と「税理士法人」では、法的な性質や税務の取り扱いが根本的に異なります。どちらが良いかは、事業規模・成長戦略・ライフプランによって異なります。
| 項目 | 個人事業の税理士 | 税理士法人 |
| 経営主体 | 税理士本人 | 社員税理士(2名以上) |
| 法人格 | なし | あり |
| 所得区分 | 事業所得(個人課税) | 法人所得(法人課税) |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 健康保険・厚生年金(法人加入) |
| 業務の継続性 | 本人の死亡・引退で終了 | 法人として継続可能 |
| 節税の工夫 | 限定的(経費処理に限界) | 報酬・退職金などの制度設計が可能 |
| 信用力 | やや低め(個人名義) | 高め(法人格・ブランド性) |
税理士法人設立の基本ステップ
税理士法人を設立するには、「法人化したい」という意思だけではなく、法律上の要件と手続きをきちんと満たす必要があります。特に重要なのが「社員税理士2名以上の確保」です。
税理士法人設立の流れは、以下の3段階です:
1.設立の準備(条件の確認・社員税理士の確保)
2.定款作成・法人登記
3.税理士会での承認・登録
必要な条件と資格
税理士法人は、税理士法に基づく特殊法人です。設立には以下の条件をすべて満たす必要があります。
【法人設立の主な要件】
・社員は税理士のみ(他業種の出資や役員は不可)
・社員税理士が2名以上必要
・代表社員は社員税理士の中から1名を選任
・商号に「税理士法人」という文字を入れる必要あり
・業務内容は税理士業務に限る
※通常の株式会社などと異なり、目的・事業内容に大きな制約があります。
設立手続きの流れ
税理士法人設立は、法人登記だけで完了しません。「税理士会への登録手続き」も必須であり、これが法人として業務を開始するための最終ステップになります。
以下に手続きの流れをまとめます:
【1. 準備フェーズ】
・社員税理士2名以上の確保
・事務所(所在地)の確保
・商号(法人名)の決定
・代表社員の決定
【2. 登記関連の手続き】
・定款の作成(認証不要)
・出資金の払込み
・登記書類一式を作成
・法務局にて法人登記申請(株式会社などと同様)
【3. 税理士会への登録】
・所轄の税理士会に申請書類を提出
・登録審査(数週間〜1か月程度)
・登録完了後、「税理士法人」として業務開始
※ 登録前に業務を行うことはできません。
税理士法人設立にかかる費用
税理士法人の設立には、法人登記のための費用に加えて、税理士会への登録手数料やその他の準備費用が発生します。株式会社のような定款認証(公証人費用)は不要ですが、一定のコストはかかります。
最低でも10万円〜20万円程度は見込んでおくべきです。
登録免許税とその他の費用
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
| 登録免許税(法人設立) | 6万円 | 法務局での法人登記時に支払う国家税 |
| 登録手数料(税理士会) | 約5万円〜7万円程度 | 所属税理士会により異なる |
| 印紙代・書類作成費用 | 数千円〜1万円程度 | 定款印紙代(認証不要だが提出書類に必要なことも) |
| 司法書士等への依頼費用 | 約5万円〜10万円(任意) | 登記や書類作成を専門家に依頼する場合 |
| 事務所設立準備費用 | 家賃・備品など実費 | 机・PC・電話回線など(設立そのものには含まず) |
税理士法人設立のための資金調達方法
税理士法人の設立自体は大きな資本金を必要としませんが、事務所の開設、職員の雇用、設備投資、法人維持費などには一定の資金が必要です。
特に、独立直後でキャッシュが乏しい場合や複数名体制を想定している場合には、創業資金の確保が重要になります。
融資や助成金の活用
1. 自己資金
・最も確実でリスクが少ない方法
・貯蓄や退職金を活用するケースが多い
・信用力アップのためにも一部自己資金を確保しておくのが望ましい
2. 日本政策金融公庫の創業融資
税理士法人でも「新たに事業を開始する法人」として申請可能。
特徴:
・無担保・無保証人でも借入可能(新創業融資制度)
・創業前でも創業計画書を提出すれば申請できる
・金利:年1.5~2.5%程度(変動あり)
・融資額:300万~1000万円程度が一般的
準備が必要な書類:
・創業計画書
・資金繰り予定表
・法人設立関係書類
・個人の確定申告書(開業前の収入証明)
3. 地方自治体の創業支援融資・制度融資
特徴:
・各都道府県や市区町村が、創業者向けに利子補給・信用保証を提供
・例:東京都「創業支援特例制度」、大阪市「スタートアップ支援融資」など
・条件:地域での創業、事業計画の提出、面談 など
4. 助成金・補助金の活用
税理士法人の設立自体に対する補助は限定的ですが、雇用やIT導入など間接的な経費を補助できる制度があります。
活用できる可能性がある制度例:
・キャリアアップ助成金(有期→正社員転換で支給)
・IT導入補助金(会計ソフト・業務管理ツール導入費用の一部補助)
・小規模事業者持続化補助金(広告宣伝費や設備費の補助)
※いずれも法人登記+実際の業務開始が前提になるため、設立後に申請する形となります。
| 資金調達手段 | 特徴 |
| 自己資金 | 自由度が高い、金利なし |
| 日本政策金融公庫 | 無担保融資あり、創業期の定番 |
| 地方自治体の制度融資 | 利子補給や保証料補助が受けられる |
| 助成金・補助金 | 雇用・IT導入など、間接的に活用可能 |
設立後の運営と管理
税理士法人を設立した後は、単に業務を行うだけでなく、組織としての継続的な運営・戦略的な経営・日々の業務管理が求められます。以下に、設立後に重要となる運営・管理のポイントをまとめました。
■ 税理士法人 設立後の運営と管理
設立後は「士業+経営者」という二重の役割を担うことになります。
特に組織として法人を維持していくには、人・金・情報の管理がカギです。
● 主な運営・管理ポイント
・社員税理士の責任分担とガバナンス体制
・職員の採用・教育・評価制度の整備
・会計・給与・税務・社会保険等の内部管理体制
・情報管理(個人情報・マイナンバーなど)の徹底
・業務品質の維持・内部監査的な仕組みの導入
■ 税理士法人の経営戦略
経営戦略のない税理士法人は、価格競争や人材流出に巻き込まれるリスクがあります。法人化したからこそ、中長期的なビジョンと差別化戦略が求められます。
● 経営戦略の主な方向性
・専門特化型:相続・事業承継・国際税務・医療法人など
・業種特化型:建設業・IT・飲食・スタートアップなど
・DX型事務所:クラウド会計・チャット対応・リモート税務顧問
・人材育成戦略:OJT+eラーニングで若手の早期戦力化
・ブランディング戦略:SNS、YouTube、ブログなどでの発信強化
■ 日々の業務の流れと管理方法
税理士法人では、業務を標準化・効率化することが組織運営の生命線になります。
● 一般的な1日の業務の流れ(例)
| 時間帯 | 業務内容 |
| 9:00~9:30 | 朝礼・業務スケジュール確認 |
| 9:30~12:00 | 顧問先対応(記帳・決算・申告準備など) |
| 12:00~13:00 | 昼休憩 |
| 13:00~16:00 | 顧客訪問・税務相談・会議 |
| 16:00~18:00 | レビュー業務・報告書作成・残務処理 |
※繁忙期(3月・5月など)にはスケジュールが変則的になることもあります。
● 業務管理のための仕組み・ツール
・クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)
・タスク管理ツール(Trello、Asana、kintoneなど)
・労務管理システム(勤怠・給与・年末調整の一元化)
・ドキュメント管理(Dropbox、Google Drive)
・業務マニュアル化・ナレッジ共有の仕組み
■ 定期的にやるべきこと
・月次:損益・キャッシュフローのチェック/進捗会議
・四半期:スタッフ評価・業績レビュー/方針の微修正
・年次:事業計画の見直し/社員税理士の報酬調整・採用計画の検討
成功するためのポイントと注意点
税理士法人は「士業+経営」であるため、経営視点が不可欠です。特に下記のポイントを意識することで、成功に近づけます。
● 経営・戦略面
・自社の強み・専門性を明確化(相続、クラウド、外国人対応など)
・顧客ターゲットを絞り、価格や業務フローをパッケージ化
・情報発信(SNS・ブログ・動画)で見込み顧客を獲得
● 組織・人材面
・職員教育・業務マニュアルを整備し、属人化を防止
・キャリアパス・評価制度で若手の定着率を向上
・パートナー間の役割分担・意思決定ルールを明文化
● 業務・運営面
・クラウド会計・RPAなどのITツールを積極導入
・月次レビューや定期ミーティングで業務のPDCAを回す
・トラブル予防のため、契約書・守秘義務・顧問範囲を明確に
● よくある失敗例
・「法人化=自動的に成長」と考えてしまう
・社員税理士同士の意見不一致・関係悪化
・明確な分担や評価制度がなく、人材が離職
・価格競争に巻き込まれ利益率が下がる
・内部統制・業務品質管理が甘く、クレームや法的リスクが増加
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
税理士法人の設立は、単なる組織変更ではなく、経営者としての一歩です。
成功する法人には、「明確な戦略」「役割分担された組織運営」「ITや人材活用による業務効率化」が共通しています。一方で、共同経営の軋轢や、成長を焦った価格競争など、失敗要因も数多く存在します。
本記事では、実際の成功事例をもとに、設立後の経営で重要となるポイントと注意点を整理しました。
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















