INDEX
おすすめ記事
-
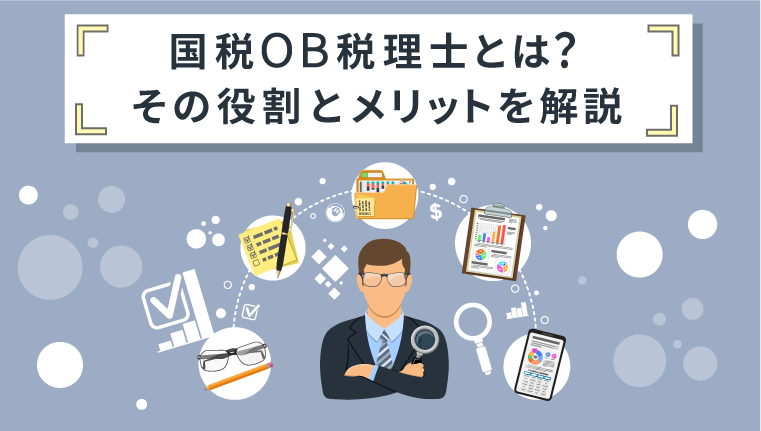
国税OB税理士とは?その役割とメリットを解説
-
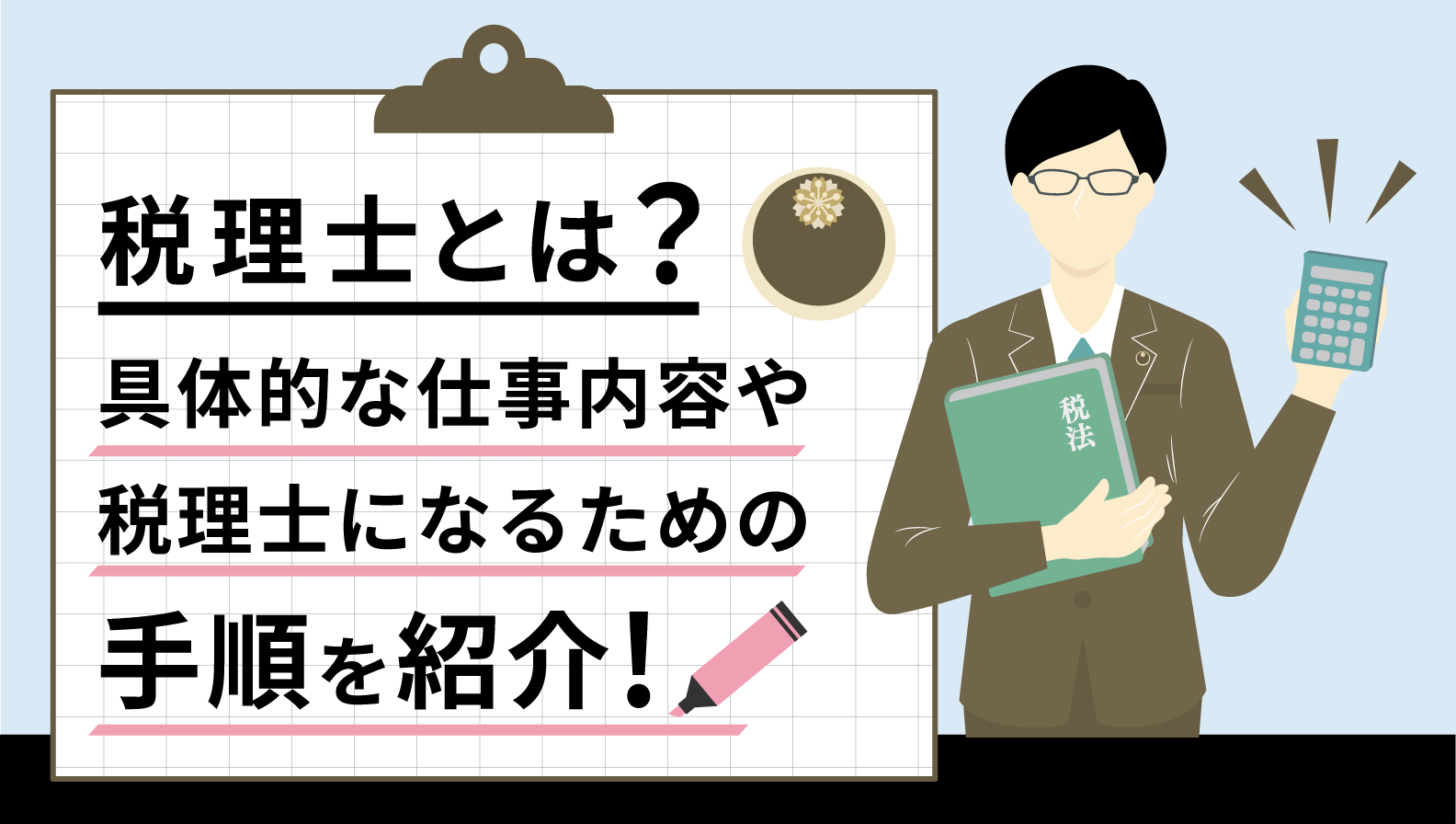
税理士とは?具体的な仕事内容や税理士になるための手順を紹介!
-
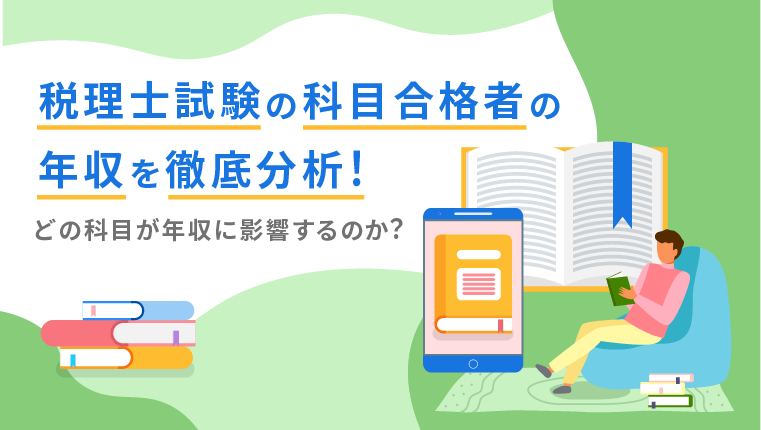
税理士試験の科目合格者の年収を徹底分析!どの科目が年収に影響するのか?
-
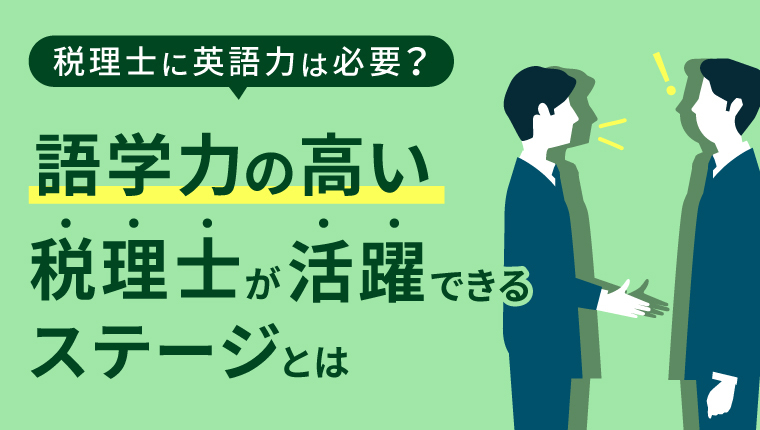
税理士に英語力は必要?語学力の高い税理士が活躍できるステージとは
-
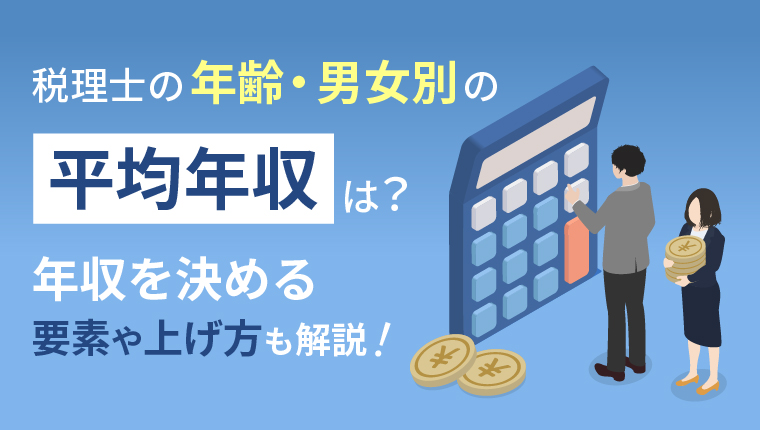
税理士の平均年収はいくら?税理士の年収を決める要素や年収の上げ方を解説!
公開日:2025/11/24
最終更新日:2025/12/04

INDEX
簿記論受験に向けた効果的な対策を行うためには、まず試験について十分な分析をする必要があります。分析対象として様々な要素がありますが、必ずチェックするべき要素の1つが合格率の推移です。
簿記論の合格率の推移を分析すると試験の傾向や優先的に行うべき対策がみえてきます。今回は簿記論の合格率の推移および分析結果からわかること、簿記論の勉強のポイントについて解説します。
適正年収をシミュレーションしてみませんか?
簡単な質問に答えるだけで、一般的な会計事務所ならいくら提示されるのかを即座に算出。「今の適正額」はもちろん、「資格を取得したら年収はどう変わるのか?」など、あなたの現在地と未来の可能性を診断します。
前提|税理士試験 簿記論とその他科目の合格率および2年間の推移【2026年最新版】
簿記論の合格率の推移をみる前に、まずは税理士試験の各科目の合格率を紹介します。
令和7年度(第75回)税理士試験の科目別の合格率は以下の通りでした。
| 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 令和6年度合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 簿記論 | 18,466人 | 2,058人 | 11.1% | 17.4% |
| 財務諸表論 | 15,629人 | 4,980人 | 31.9% | 8.0% |
| 所得税法 | 1,120人 | 146人 | 13.0% | 12.6% |
| 法人税法 | 3,606人 | 488人 | 13.5% | 16.4% |
| 相続税法 | 2,413人 | 333人 | 13.8% | 18.7% |
| 消費税法 | 7,064人 | 712人 | 10.1% | 10.3% |
| 酒税法 | 590人 | 72人 | 12.2% | 12.1% |
| 国税徴収法 | 1,671人 | 231人 | 13.8% | 13.0% |
| 住民税 | 439人 | 78人 | 17.8% | 18.2% |
| 事業税 | 310人 | 38人 | 12.3% | 13.7% |
| 固定資産税 | 928人 | 144人 | 15.5% | 18.0% |
出典:令和7年度(第75回)税理士試験結果表(科目別)
いずれの科目も合格率は10%~20%程度です。合格率の低さから、改めて税理士試験の難易度の高さを窺えます。
簿記論の合格率の推移および受験者数
続いて簿記論に絞った合格率の推移の分析を行います。簿記論の直近10年分の受験者数・合格者数・合格率の推移は以下の通りです。
| 実施年度(回) | 簿記論受験者数 | 簿記論合格者数 | 簿記論合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(第75回) | 18,466人 | 2,058人 | 11.1% |
| 令和6年度(第74回) | 17,711人 | 3,076人 | 17.4% |
| 令和5年度(第73回) | 16,093人 | 2,794人 | 17.4% |
| 令和4年度(第72回) | 12,888人 | 2,965人 | 23.0% |
| 令和3年度(第71回) | 11,166人 | 1,841人 | 16.5% |
| 令和2年度(第70回) | 10,757人 | 2,429人 | 22.6% |
| 令和元年度(第69回) | 11,784人 | 2,052人 | 17.4% |
| 平成30年度(第68回) | 11,941人 | 1,770人 | 14.8% |
| 平成29年度(第67回) | 12,775人 | 1,819人 | 14.2% |
| 平成28年度(第66回) | 13,936人 | 1,753人 | 12.6% |
受験者数・合格者数・合格率の推移から、簿記論について以下の分析ができます。
【令和7年度の衝撃】合格率11.1%への急落
令和7年度(第75回)の簿記論は合格率が11.1%と発表されました。
前年(令和6年度)の17.4%から6ポイント以上、令和4年度の23.0%と比較すると半分以下という数値は、多くの受験生や関係者に衝撃を与えました。
ここ数年(特に令和4~5年)は、合格率が20%前後で推移するなど、簿記論は比較的「受かりやすい科目」とされてきましたが、今回の急激な難化により、来年以降の科目選択のトレンドにも影響があるでしょう。
合格基準点への到達ではなく上位に入ることを目指す必要がある
簿記論に限らず、税理士試験の合格基準は満点の60%です。単純に合格基準への到達を目指すと「全体の60%を解けるようになれば良い」と考えてしまうかもしれません。
しかし、実態は相対評価の側面があると言われており、得点率だけで考えていると足元をすくわれます。
特に、今年度の急激な合格率の低下により、来年度(令和8年度)の簿記論には、今年涙を飲んだ実力のある経験者層が大量に再流入することになります。来年の簿記論は、例年以上にハイレベルな争いになることが予想されます。
以上の理由から、税理士試験において合格基準点は目指すべきゴールにならないといえるでしょう。簿記論に合格するには「上位2~3割にいれば受かる」という感覚は捨て、「上位10%に入らなければ落ちる」という危機感を持ち、合格基準点への到達ではなく、上位に入ることを目指す必要があります。
【参考】令和5年度以降に簿記論の受験者が急増した理由
受験者数の推移をみると、令和4年度と令和5年度で簿記論の受験者数には3,000人以上もの違いがあるとわかります。
令和5年度に受験者数が急増した理由は、受験資格要件の緩和により受験のハードルが下がったためです。
以前は会計学科目を受験するには、学歴要件や資格要件を満たす必要がありました。大学2年生以下が受験するためには厳しい資格要件を満たす必要があり、受験自体のハードルが高かったのです。
しかし、令和4年の税理士法改正により会計学科目の受験資格要件が撤廃されました。令和5年度以降の税理士試験から簿記論と財務諸表論は誰でも受験可能となっています。
以上のように受験のハードルが大幅に下がったために、令和5年度試験から受験者が急増したのです。
その後の年度でも毎年受験者数は増えており、令和7年度では18,466人まで受験者が増えております。
参考:税理士試験の受験資格要件の緩和|日本税理士連合会
簿記論の合格率の推移から分析できる学習のポイント
税理士試験は合格基準の定めがあるものの、受験者数・合格者数・合格率の推移から、実質的には相対評価の試験と判断できます。そのため「合格基準に到達する」ではなく「上位に入る」必要があります。
直近5回分の簿記論の合格率推移から、合格のためには上位10%に入ることを目指すべきと考えられるでしょう。この章では簿記論で上位10%以内に入るために押さえるべきポイントを4つ紹介します。
最優先事項は「基礎固め」
簿記論の受験に向けて最も優先するべき事項は基礎固めです。基礎固めを徹底するべき理由は2つあります。
1つ目は簿記論では基礎的な問題も多く出題されるためです。
簿記論では難易度が高い・ボリュームがある等の理由から解くのが難しい問題も出題されます。一方で、簡単な仕訳や計算問題のような基礎的な問題も多く存在します。特に個別問題の場合、最初は基礎的な内容、小問2問目以降に応用的な内容になることが多いです。
もし全ての基礎問題に正解できれば、それだけで得点を稼げる可能性があります。絶対に解ける問題を増やすためにも、基礎固めを徹底するべきといえます。
もう1つの理由は基礎問題を落としてしまうと上位10%に入れる可能性が低くなるためです。
基礎問題は多くの受験者が解ける可能性があるため配点箇所になりやすいです。基礎問題を落としてしまうと多くの受験者の得点源になる部分で点数をとれず、点差が広がる恐れがあります。
「得点を稼ぐ」「点差が広がるのを防ぐ」この2つの理由から、簿記論の勉強では基礎固めが最優先事項といえます。
頻出論点の対策を優先する
簿記論の勉強では頻出論点の対策を優先しましょう。前節と同様、「得点を稼ぐ」「点差が広がるのを防ぐ」ために必要です。
頻出分野は多くの受験生が優先的に対策する論点のため、正答率も高くなりやすいです。ここで点数を落としてしまうと点差が広がりやすく、挽回が難しくなる恐れがあります。
最低でも過去5年分、可能であればより多くの過去問を分析し、頻出論点の対策を重点的に進めましょう。
苦手や誤りを放置しない
苦手分野や過去に誤った問題は放置せず、確実に解けるようになるまで練習を繰り返すべきです。特に頻出論点に苦手意識がある場合や誤答が続く場合、スムーズに回答できるようになるまで問題演習を徹底する必要があります。
苦手論点やミスしやすい分野など、あなたにとっての「点数がとれない分野」は、ほかの受験生にとっては「差をつけやすい分野」です。苦手な部分で丸々点数を落としてしまえば、その時点で他の受験者との点差が大きく広がる恐れがあります。
ほかの受験者と点差が広がる原因となる要素をなくすために、苦手論点や過去の誤りは本試験までに克服する必要があります。
満点を目指さず優先順位を決める
簿記論で満点を目指そうとする必要はありません。満点を目指すのではなく、優先順位を決めることが大切です。
簿記論は出題量が非常に多く、2時間ですべてを解き切るのは現実的ではありません。その上、難易度が非常に高く必要な計算量も多い「捨て問」と呼ぶべき問題も出題されます。
一問目から順番に解いていくと捨て問に時間を費やしてしまい、後半の問題を解く時間が足りなくなる恐れがあります。簿記論では全ての問題を解こうとはせず、はじめに試験全体を確認し、どの問題を解くべきか優先順位を決めましょう。
簿記論で優先的に解くべき問題の特徴として以下の例が挙げられます。
・頻出論点または基礎的な内容
・自分の得意な論点
・問題文を見ただけで解法をすぐにイメージできる
・大問の最初の方である
(その問題を解かなければ大問1つ丸々落としてしまう)
反対に、以下の問題は優先度が低めと考えて良いでしょう。
・必要な計算量のわりに点数につながりにくい
(1問解くために大量の計算が必要など)
・直近数年分の過去問でみた覚えのない論点であり、解法もすぐには思いつかない
(ほかの受験生も解けない可能性が高い)
簿記論の講座でも、「全部の問題を解く必要はない」と指導されます。満点を目指してすべての問題を解くのではなく、優先度の高い問題を確実に解く方が大切です。
適正年収をシミュレーションしてみませんか?
簡単な質問に答えるだけで、一般的な会計事務所ならいくら提示されるのかを即座に算出。「今の適正額」はもちろん、「資格を取得したら年収はどう変わるのか?」など、あなたの現在地と未来の可能性を診断します。
まとめ|簿記論の合格率の推移からわかること
簿記論の直近10年間の合格率は約11~23%で推移していますが、令和7年度は合格率11.1%とここ10年間で最も合格率が低くなりました。
簿記論合格のためには合格基準の到達ではなく、上位に入ることを目指すべきといえるでしょう。簿記論の合格率の推移から、上位10%以内に入るのが理想と考えます。
以上のように、合格率の推移の分析から様々なことがわかります。簿記論受験に向けて、簿記論の合格率の推移からわかることとして紹介した内容をしっかり押さえましょう。

高梨 茉奈(たかなし まな)
めざせ!TAX MASTER パーソナリティ



















