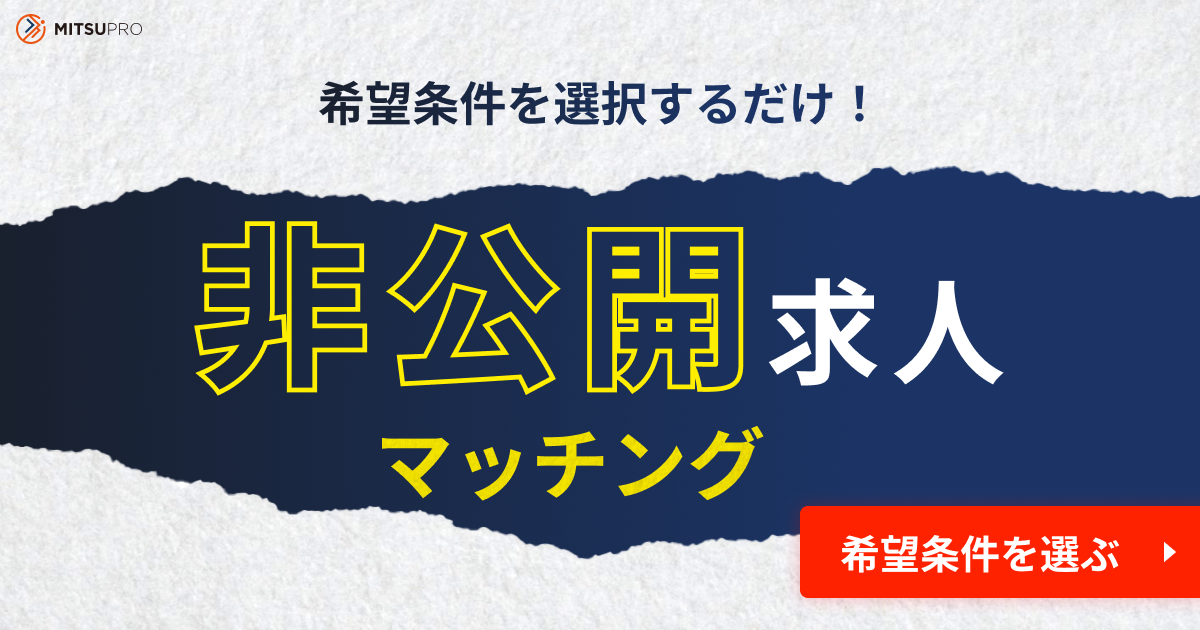INDEX
おすすめ記事
-
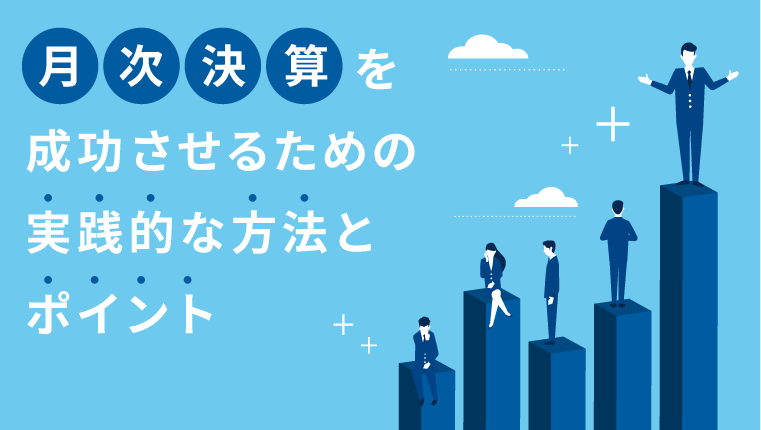
月次決算とは?月次決算を成功させるための実践ポイントを税理士が解説
-
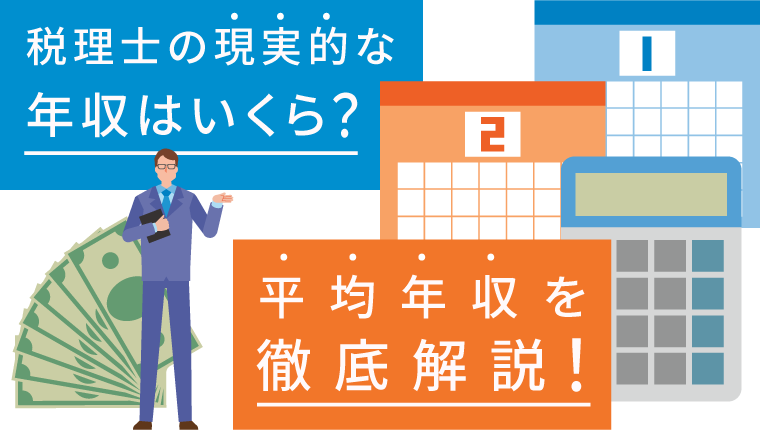
税理士の現実的な年収はいくら?平均年収を徹底解説!
-
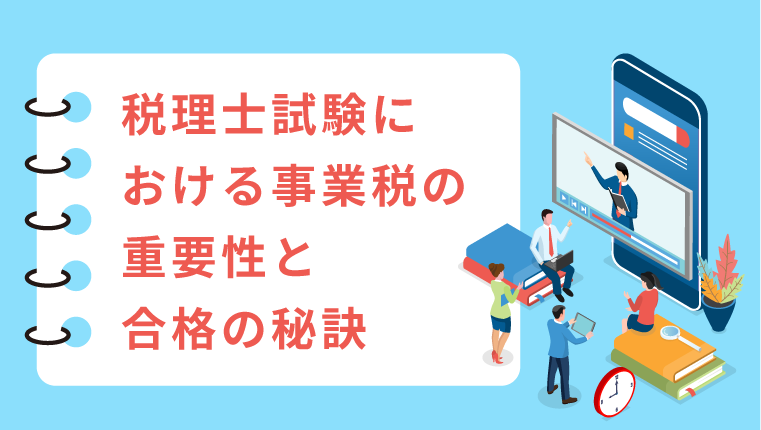
税理士試験における事業税の重要性と合格の秘訣
-

国際税理士ってどんな仕事?国際税理士の仕事内容を徹底解説!
-
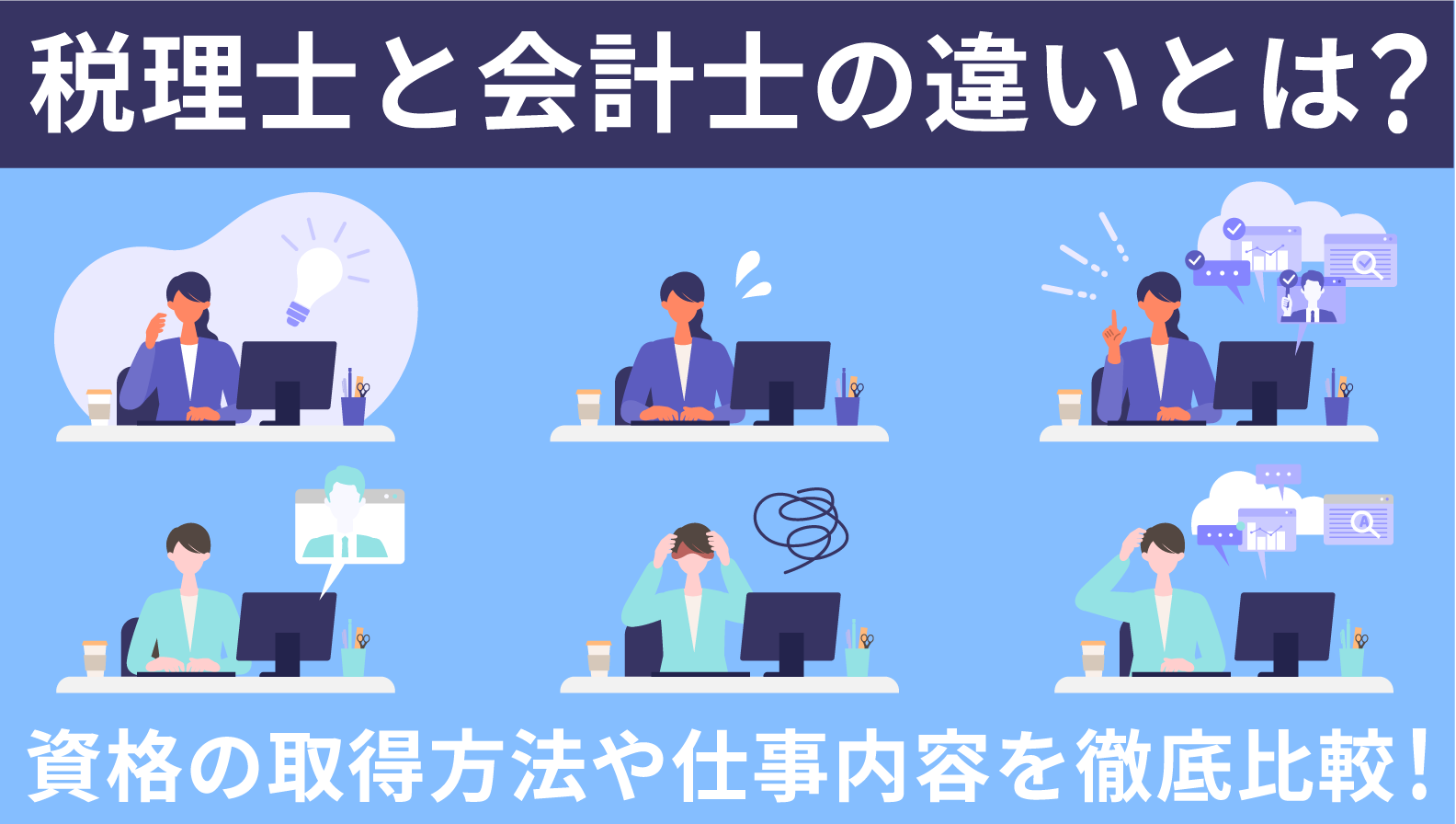
税理士と会計士の違いとは?資格の取得方法や仕事内容を徹底比較!
公開日:2024/09/27
最終更新日:2025/09/08
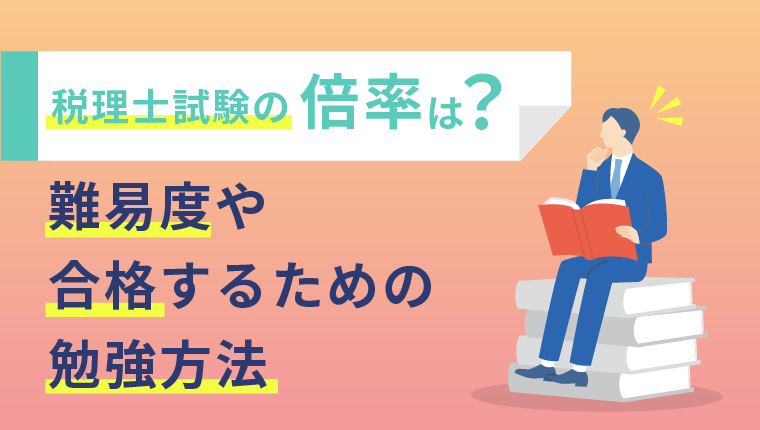
INDEX
税理士試験を受験するにあたり、倍率や合格率は気になるところですよね。
結論から申しますと、合格率は18%前後です。
税理士試験の合格基準は60点と公表されており、例年18%前後の合格者を輩出しています。
平均合格率20%を下回るかなりの難関資格ではありますが、やり方を工夫すれば効率よく科目合格を積み上げていけますよ。
そこで本記事では、税理士試験の難易度や勉強方法等についてまとめました。
これから税理士試験の勉強を始める人は、ぜひ参考にしてください。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士試験の合格率は18%前後
各科目の合格率は18%前後です。100人受験すると82人が不合格になる計算ですね。
税理士試験は11科目中5科目に合格する試験です。5科目の合格を経て税理士試験合格となります。
各科目における合格基準は60点以上です。6割に合格すると科目合格となります。
ただし点数による絶対評価ではなく、相対評価が取り入れられているのではないかとも言われています。その理由は、合格率が上振れしないためです。
毎年問題は変わりますから、年度によって難易度が若干変動し合格者数も変わるはずです。
しかしあまりにも合格率が一定なので、相対評価ではないかと言われているのです。
絶対評価であっても相対評価であっても、合格率は変わりません。
82%以上の受験生よりも高い点数を叩き出し、科目合格を手にしてください。
他の資格試験との合格率比較から見る税理士試験の難易度
ここで、他の難関資格と税理士試験とを比較して、税理士試験の難易度を明らかにしましょう。
司法試験との違い
司法試験の概要
司法試験とは、裁判官や検察官、弁護士になるための試験です。
短答式試験と論文式試験の2種類からなります。
短答式試験の科目は、憲法、民法、刑法の3科目。
論文式試験の科目は憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、商法、行政法、選択科目の合計8科目です。
試験日は例年1回、連続する4日間です。
短答式試験には足切りがあり、点数が低ければ論文式試験の点数が高くても不合格になります。
受験資格や科目合格制の違い
税理士試験との大きな違いは、受験資格と科目合格制の有無でしょう。
司法試験の受験資格は、法科大学院の修了または予備試験の合格です。
法科大学院は最大3年間の受講が必要になります。法科大学院に入学するには入試に合格しなければならず、入学するだけでも大変です。
予備試験は短答式試験、論文式試験、口述試験の3つの試験に合格する必要があります。予備試験は誰でも受験可能ではありますが、その合格率は極めて低く、また順番にすべての試験で合格しないといけません。
そのため司法試験は、試験自体よりも受験資格を得るのが困難な試験とも言われています。
一方の税理士試験は、会計の属する科目は誰でも受験でき、税法に属する科目に関しても、要件を満たす大学の課程修了や日商簿記検定1級の合格等で受験資格を満たします。
司法試験の受験資格を得る方が圧倒的に困難です。
また科目合格制が採用されていないことも大きな違いです。
税理士試験で採用されている科目合格制は、一度合格した一部科目を永久に合格とみなす制度です。そのため合格した科目を何度も受験する必要がなく、科目を絞った勉強が可能になります。
ところが司法試験では科目合格制が採用されていません。
短答式試験と論文式試験に合格しなければ、司法試験合格とはならないのです。
合格率・難易度の違い
司法試験の合格率は20〜30%と言われています。
対する税理士試験の合格率は18%前後です。
合格率だけ比較すると司法試験の方が難易度が低いように感じます。しかし実際は司法試験の方が高難易度です。
まず受験資格を得るための勉強が必要です。法科大学院ルートであっても予備試験ルートであっても、高度で幅広い知識を身につけなければなりません。
次に、科目合格制がなく、まんべんなく多くの科目を勉強し続けなければならないことも難関たらしめている理由に挙げられます。
税理士試験の免除要件の1つに「弁護士となる資格を有するもの」があり、司法試験を突破して弁護士資格を取得した場合、税理士試験を受けることなく税理士になれます。
この事実からも、税理士試験より司法試験の難易度の方が高いことが示されています。
税理士試験よりも合格率が高いのは、受験資格を得る段階で基礎知識が身についているためではないかと推測されます。
公認会計士試験との違い
公認会計士試験の概要
公認会計士試験とは、公認会計士の資格が取得できる試験です。
短答式試験と論文式試験の2種類からなり、短答式試験に合格した人だけが論文式試験に進めます。短答式試験は年2回、論文式試験は年1回です。短答式試験は年2回のうち1回の合格で論文式試験に進めます。
短答式試験の科目は財務会計論、管理会計論、監査論、企業法。
論文式試験の科目は会計学、監査論、企業法、租税法、選択科目を含む5科目です。
短答式試験に合格すると、以後2年間は短答式試験が免除され、論文式試験からスタートできます。
試験方式と合格基準の違い
公認会計士試験は短答式試験と論文式試験の2つからなり、短答式試験の合格者のみ論文式試験を受験できます。そのためまずは短答式試験の突破を目指し、その後論文式試験の勉強を進めます。
税理士試験の試験方式は1つなので、公認会計士試験のように勉強の範囲や仕方が変わることはありません。税理士試験の方が勉強しやすいと言えるでしょう。
次に、合格基準にも着目してみましょう。
公認会計士試験は、短答式試験と論文式試験のそれぞれの総得点比率が合格基準となります。ただし科目ごとに足切りが存在し、絶対評価と相対評価で不合格とされる恐れがあります。つまり、1科目ダメでも他の科目が高得点なら合格できる可能性が残されており、かつすべての科目において最低点は確保しなければならないのです。
一方で、税理士試験は11科目中5科目に合格する試験です。5科目のみ勉強すれば合格できます。各科目について合格点以上を取る必要はありますが、11科目すべてを勉強する必要はありません。
難易度の違い
公認会計士試験の合格率は8%前後です。
税理士試験の18%と比較すると、格段に難しいことが示唆されています。
これほどまでに合格率に差がつくのは、内容の難しさと範囲の広さ、科目合格制がないことに由来すると思われます。
短答式試験合格後は2年間の免除が用意されていますが、2年間で論文式試験に合格できなければ再び短答式試験を受験しなければなりません。税理士試験の科目合格制は一生涯有効なので、どちらが有利かは歴然です。
なお司法試験同様に、公認会計士試験合格者も税理士試験の免除が認められています。
公認会計士試験が税理士試験よりも難関である証明でもあるでしょう。
税理士試験の受験科目の選び方
税理士試験は11科目中5科目に合格することが求められます。
そのため勉強を開始する前に受験する5科目を選ばなければなりません。
本項では受験科目の選び方を2パターン紹介いたします。
勉強時間の少ない科目を選ぶ
税理士試験合格後に実務で使用する科目を選択するのも1つの方法です。
しかし税理士試験合格に焦点を当てるならば、勉強時間が少なくてすむ科目を選ぶという方法も検討しましょう。
| 科目名 | 勉強時間の目安 |
|---|---|
| 簿記論 | 450時間 |
| 財務諸表論 | 450時間 |
| 所得税法 | 800時間 |
| 法人税法 | 800時間 |
| 相続税法 | 500時間 |
| 消費税法 | 300時間 |
| 酒税法 | 150時間 |
| 国税徴収法 | 150時間 |
| 住民税 | 200時間 |
| 事業税 | 200時間 |
| 固定資産税 | 250時間 |
簿記論と財務諸表論は必修科目、所得税法と法人税法は選択必修ですので避けられませんが、その他の選択科目2科目は勉強時間の少ない科目を選びましょう。
おすすめは国税徴収法または酒税法と住民税または事業税です。
ただし、勉強時間が少ないと有利になるため、受験生が集中する恐れも考えられます。
例年の受験者数等を加味したうえで科目を選んでください。
なお上記はあくまでも目安です。経理の知識がほとんどない場合は、記載よりも長時間の勉勉強時間が必要になりますのでご注意ください。
合格率の高い科目を選ぶ
例年の合格率から科目を選択する方法もあります。
平均合格率は18%前後ですが、科目ごとにばらついているのも事実です。
| 科目名 | 合格率(%) |
|---|---|
| 簿記論 | 17.4 |
| 財務諸表論 | 28.1 |
| 所得税法 | 13.8 |
| 法人税法 | 14.0 |
| 相続税法 | 11.8 |
| 消費税法 | 11.9 |
| 酒税法 | 12.7 |
| 国税徴収法 | 13.9 |
| 住民税 | 14.7 |
| 事業税 | 16.4 |
| 固定資産税 | 17.3 |
参考:令和5年度(第73回)税理士試験結果表
上記の合格率から、選択科目において国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税がおすすめです。
所得税法と法人税法は選択必修ですが、例年それほど合格率は変わりませんので、実務に役立つ方または自分が興味のある方を選択しましょう。
税理士試験に合格するための勉強方法
これから税理士試験に挑戦するにあたり、合格のための勉強方法をお伝えいたします。
勉強前に道筋を立てておくことで、合格への期間を短縮できますよ。
スキマ時間を活用する
特に社会人は時間の使い方が重要になります。
通勤時や昼休憩等のスキマ時間を有効に使いましょう。
なお寝る前に暗記すると定着率が良いと言われています。暗記ものは寝る前に覚えると効率的かもしれません。
専門学校や予備校で学ぶ
時間が取れない人や自分を甘やかしてしまう人は、専門学校や予備校に通い、強制的に勉強時間を捻出しましょう。
専門学校等には同じく税理士を目指す同士がたくさん通っていますから、モチベーションの維持にも役立ちます。
勤務先から学校が遠い場合はオンラインを併用しましょう。
大学院進学を検討する
一定の要件を満たす大学院に進学することで科目免除が受けられます。
確実に合格科目を積み上げるための1つの手段として有効です。
ただし大学院に通うための時間と費用を捻出しなければなりません。社会人の場合は勤務先の上司によく相談してください。
社会人が税理士試験に合格するためには
社会人が税理士試験に合格するのは極めて難しいと言えます。
学生であれば1日のすべての時間を勉強に費やせるので、確実に有利なのです。
学生よりも高得点を取得し合格を勝ち取るためのポイントをまとめました。
勉強時間を捻出する
勉強時間の捻出は避けて通れない道です。
上記で紹介したような方法で、勉強時間を作り出してください。
ただし仕事や家庭がおろそかになることは避けましょう。税理士試験が理由でクビになったり家庭が崩壊するといったことは、あってはなりません。
人生における勉強の優先順位は普段から意識しておいてください。
家族に応援してもらう
社会人で扶養家族がいる場合、税理士試験を目指すと宣言すれば家族から反対されるかもしれません。
家族に反対されたまま税理士試験に挑戦すると極めて不利になります。可能な限り家族に納得してもらってから挑みましょう。
家族が不安に感じる大きな理由は、給与が下がることや家族をないがしろにすることです。
これらの点をカバーしたうえで税理士試験に挑戦するのが最善でしょう。
長期間の勉強スケジュールを組む
ざっくりとで構いませんので、合格までのスケジュールを組みましょう。
上記の勉強時間目安から、1年で合格できる科目を割り出し、その科目ごとに勉強を進めます。
1日何時間勉強すれば目安時間に到達できるか分かるので、やみくもに勉強するよりも効率的に進められますよ。
また長期スケジュールを立てることで、ライフイベントとかち合う時期も予測できます。
結婚や出産、住宅購入等の大きなイベントの前後では勉強時間が確保できませんので、その点も考慮に入れてスケジュールを組みましょう。
大学院進学も視野に入れる
大学院進学も検討しましょう。税理士試験科目免除の対象となる大学は全国に存在しますし、夜間大学を選択すれば仕事との両立も可能です。
一旦退職して大学院に通いつつ、税理士試験の勉強を進めることもできます。
長期間の試験勉強の末に不合格となったら、心が折れるかもしれません。しかし大学院進学で免除科目を稼げたならば、1科目不合格になっても持ち直せるでしょう。
時間と費用は必要ですし、仕事との両立には精神力と体力が要求されます。しかし官報合格(5科目を試験でクリア)よりも若干ハードルは下がります。
科目免除だけでなく博士や修士の資格も取得できますので、大変おすすめです。
税理士試験の倍率-まとめ
税理士試験の合格率は18%前後であり、3大難関資格に数えられるほど難しい試験です。1日や2日勉強した程度では合格できません。しかし司法試験や公認会計士試験と比較するとやや取得しやすい資格でもあります。
合格まで平均8年、最低でも2年はかかります。これから税理士試験に挑戦するならば、本記事を参考に事前準備を整えてから、効率的に勉強を進めましょう。

城之内 楊
株式会社ミツカル代表取締役社長