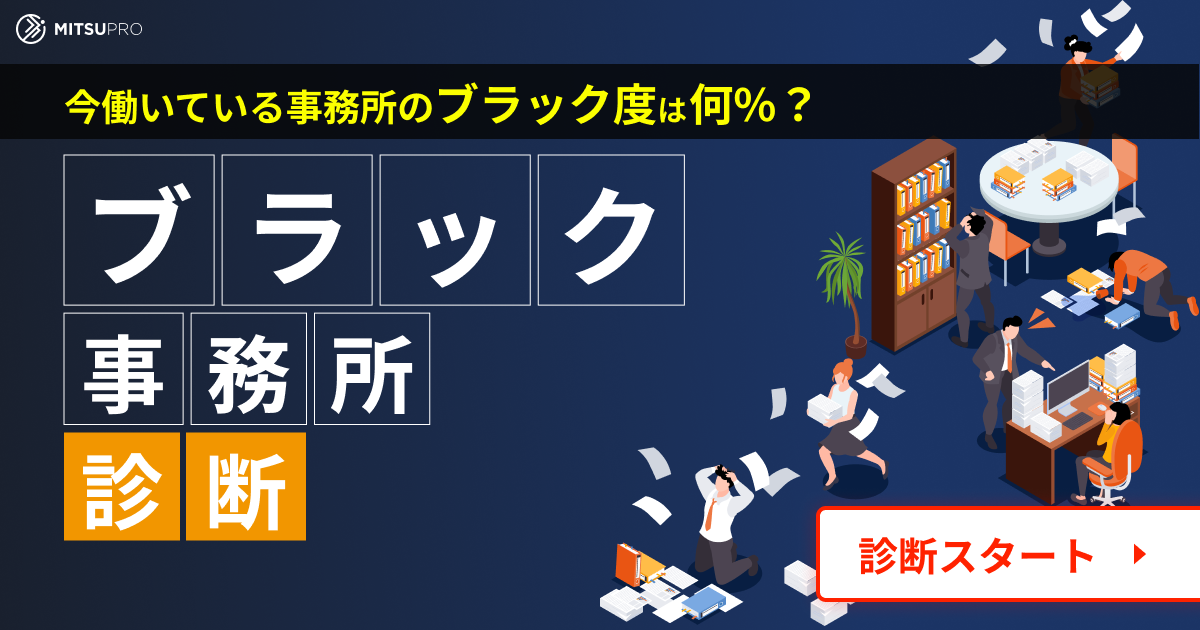INDEX
おすすめ記事
-

税理士向け広告規制の徹底解説【NG事例も紹介します】
-
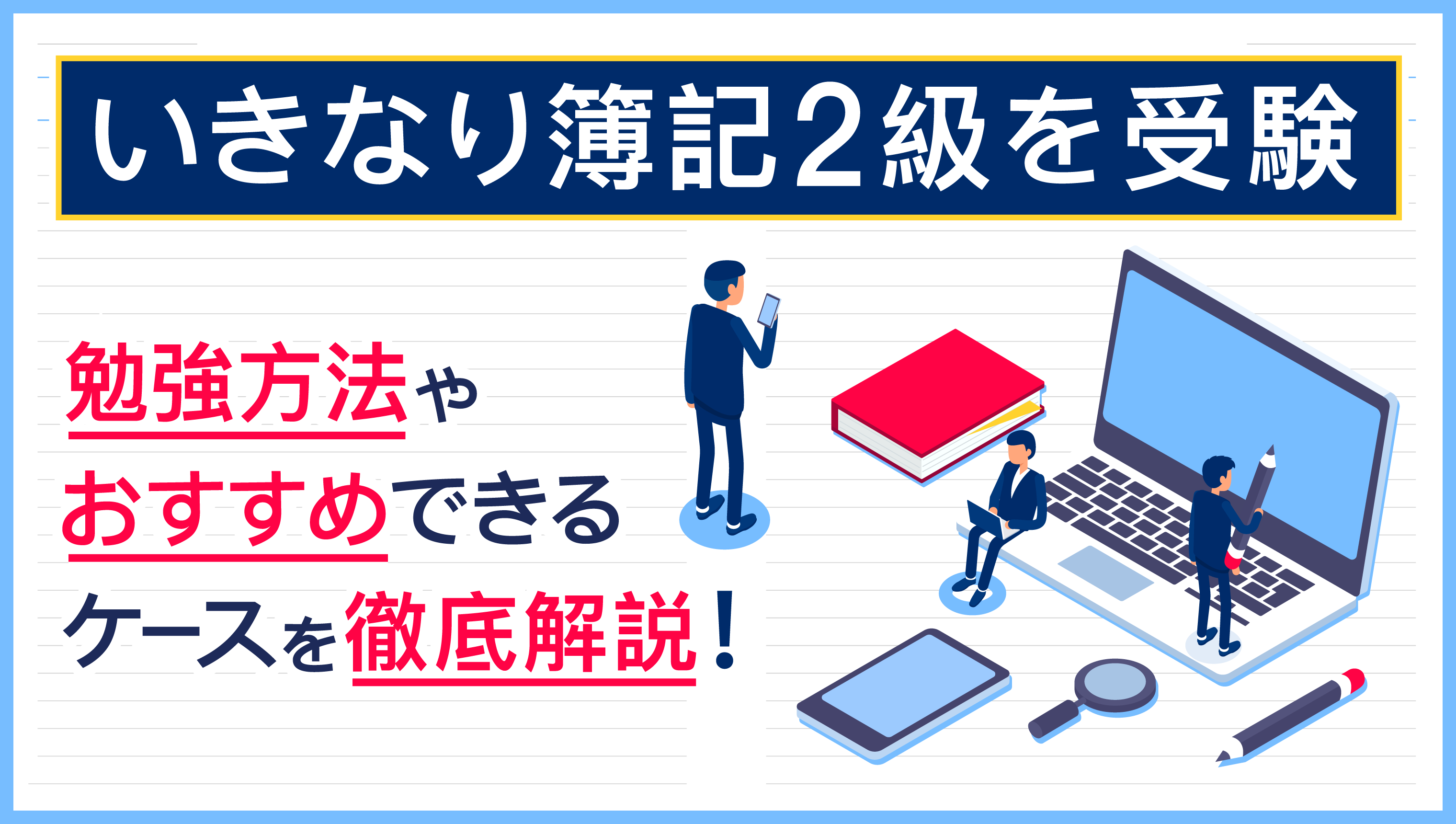
いきなり簿記2級は合格可能?おすすめできるケースや勉強のポイントを徹底解説
-
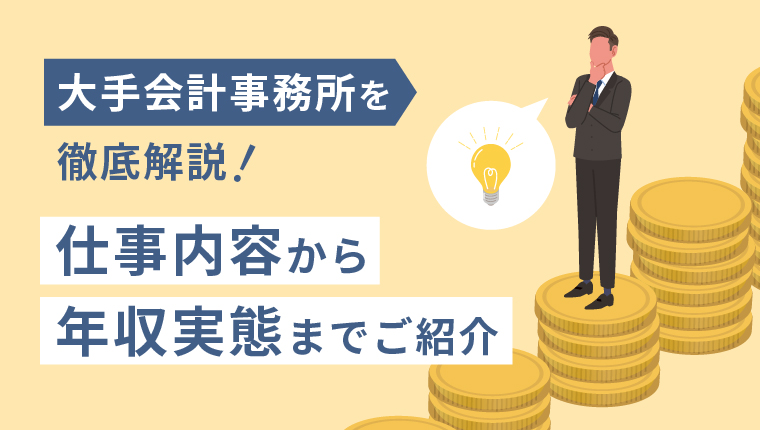
大手会計事務所を徹底解説!仕事内容から年収実態までご紹介
-
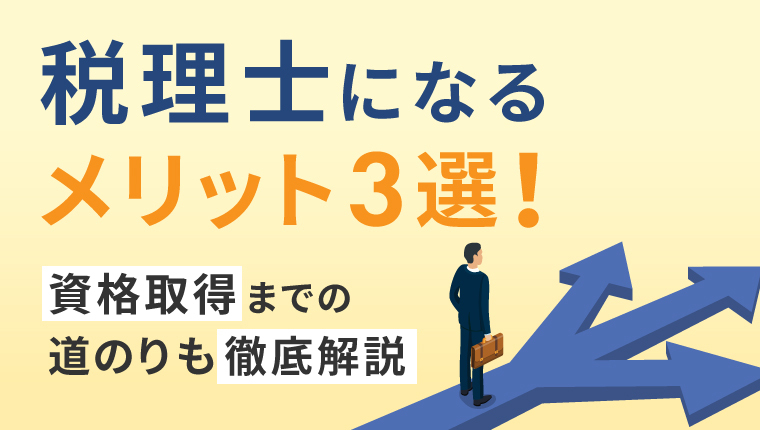
税理士資格を取得するメリット3選!資格取得までの道のりも徹底解説
-
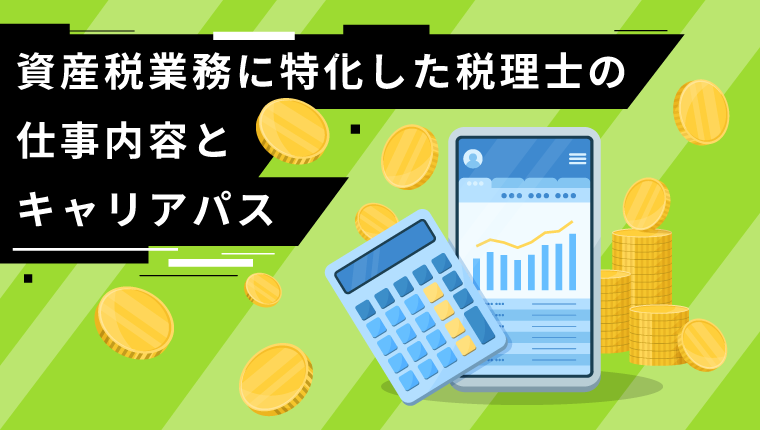
資産税業務に特化した税理士の仕事内容とキャリアパス
公開日:2024/12/05
最終更新日:2025/09/08
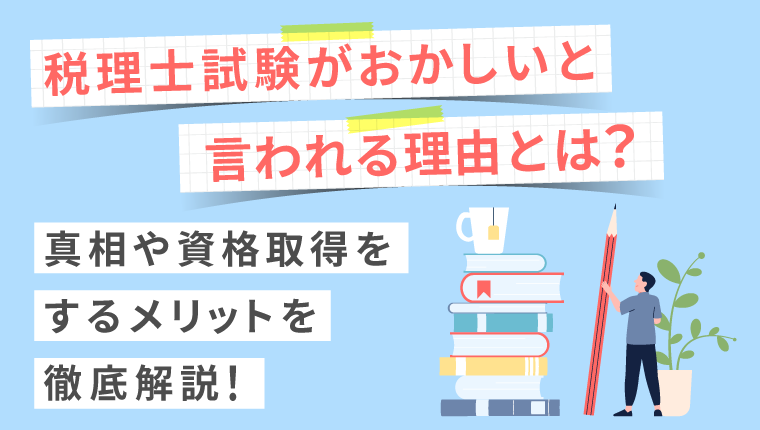
INDEX
「税理士試験って難しいって聞くけど、合格率が低すぎて本当におかしいんじゃないかな…」
「試験の内容が不透明で、どう対策すればいいのか分からない…」
と不安に思っている方も少なくないでしょう。
税理士試験は、その不透明さや試験の仕組みからおかしいと言われることがあります。
この記事では、税理士試験に挑戦しようと考えている方に向けて、税理士試験合格者のAさんにお伺いしつつ解説しています。
- 税理士試験が「おかしい」と言われる理由
- 試験の不透明さや対策の難しさ
- 試験制度の改善点
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士試験について
税理士試験の概要
税理士試験は、税理士資格を取得するための試験です。税理士は、税務に関する専門知識を持ち、企業や個人の税務相談や申告業務を行う職業であり、その資格を得るためには厳しい試験をクリアする必要があります。
税理士試験の難易度と合格率
税理士試験の難易度は非常に高く、毎年多くの受験者が挑戦していますが、合格率は低いのが現状です。試験は全11科目の中から5科目を選択して受験し、合格するためには各科目で一定の基準を満たす必要があります。また、試験は毎年一度しか行われず、合格までに数年かかることも珍しくありません。これが税理士試験の難しさを際立たせています。
ご参考までに2024年の合格率は以下の表のようになっています。
| 科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 簿記論 | 17,711 | 3,076 | 17.4% |
| 財務諸表論 | 13,665 | 1,099 | 8.0% |
| 所得税法 | 1,195 | 150 | 12.6% |
| 法人税法 | 3,585 | 588 | 16.4% |
| 相続税法 | 2,515 | 471 | 18.7% |
| 消費税法 | 7,206 | 740 | 10.3% |
| 酒税法 | 528 | 64 | 12.1% |
| 国税徴収法 | 1,670 | 217 | 13.0% |
| 住民税 | 461 | 84 | 18.2% |
| 事業税 | 249 | 34 | 13.7% |
| 固定資産税 | 893 | 161 | 18.0% |
| 合計(延べ人数) | 49,676 | 6,684 | 13.5% |
税理士試験がおかしいと言われる理由
税理士試験がおかしいと言われる理由には、いくつか税理士試験特有の特徴があります。これらの特徴が、一般的な資格試験と比べて異質であるため、多くの受験者にとって不満や疑問を抱かせる要因となっています。試験制度の複雑さや長期間にわたる試験準備が、受験者にとって大きな負担となることもあります。
以下で詳しく解説していきます。
平均資格取得年数が約8年!?
税理士試験の平均資格取得年数は一説には約8年といわれています。
この長期間にわたる挑戦が必要な理由は、試験の科目数や内容の専門性にあります。税理士試験は、5科目の合格が必要であり、それぞれの科目が独立して難易度の高い内容を含んでいます。
さらに、合格率も非常に低く、毎年約10%前後とされています。これにより、1回の試験で全科目を合格することは難しく、複数年にわたって受験を続ける受験者が多いのが実情です。
また、年によって合格率は変動が大きい傾向があり、例えば2024年で合格率が最も低かった財務諸表論の合格率は8.0%でしたが、前年の合格率は28.1%であり、1年で20%も合格率が低下しています。合格率の低下は様々な要因があるため、合格率が大幅に下がったことが一概におかしいとは言えませんが、受験者によってはおかしいと感じる方も多かったようです。
| ケース | 平均合格年数 | 補足 |
|---|---|---|
| 働きながら受験する場合 | 5〜10年 | 社会人として勤務しながら試験勉強を行う場合、 1年に1〜2科目ずつ合格を目指すのが一般的です。 |
| 専念して受験する場合 | 3〜5年 | 学業に専念できる学生や、仕事を辞めて勉強に集中する方は 比較的短期間での全科目合格を目指すことが可能です。 |
| 全体的な平均 | 8年 | すべての受験者を対象とした平均合格年数として、 この数字が一般的とされています。 |
試験を受けるのに資格が必要
税理士試験を受けるためには、一定の資格が求められることにおかしいと感じる方も少なくありません。日本国内で税理士試験を受験するには、大学で法律学や経済学を専攻しているか、または司法試験などの国家資格を持っていることが必要です。この制度は、受験者の専門知識を確保するために設けられていますが、一般的な試験と比べると非常に厳しい条件です。
直近では、会計学に属する科目(簿記論・財務諸表論)については、受験資格の制限がなくなりましたが、これでも依然として試験を受けるまでのハードルが高く、受験者にとっては大きな負担となることが多いように思えます。
試験日は毎年平日のみ
試験日が毎年平日のみであることも税理士試験の特徴の一つです。この日程は、受験生にとって大きな負担となることが多いです。特に社会人受験生は、仕事を休む必要があり、職場の理解が不可欠です。このため、受験を断念する人も少なくありません。
なお、税理士法人の中には有給とは別に「試験休暇」が設けられている職場もあります。面接の際などに確認することも有効です。
試験日から合格発表までの期間が約4ヵ月
試験日から合格発表までの期間が約4ヵ月もかかる税理士試験は、他の資格試験と比較しても特に長いと感じる人が多いです。この長期間は、受験者にとっては精神的な負担となります。実際に他の試験と比べても期間が長くなっています。
| 試験名 | 試験日 | 合格発表日 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 税理士試験 | 8月上旬 | 12月中旬 | 約4ヶ月 |
| 公認会計士試験 | 8月下旬 | 11月中旬 | 約3ヶ月 |
| 司法試験 | 5月中旬 | 9月上旬 | 約4ヶ月 |
| 行政書士試験 | 11月中旬 | 翌年1月下旬 | 約2ヶ月 |
なぜこれほどまでに時間がかかるのか、その理由にはいくつかの要因があるようです。まず、税理士試験は非常に専門的で、採点に膨大な時間が必要です。また、試験問題の難易度が高く、正確な採点を行うために慎重な確認が求められます。さらに、受験者数が多く、全国規模で行われるため、集計や確認作業に時間がかかるのも一因です。このような事情から、受験者は結果を待つ間、次回の試験に向けた準備を進めることが重要です。
配点不明?!受験後の合否判定が自分で出来ない
配点が明確にされていないことが税理士試験の特徴の一つです。受験者は、試験後にどの科目でどれだけの得点が必要だったのかを知ることができません。これは、合否判定が「自分」で行えない要因の一つです。なお、各予備校より回答案も出されますが、予備校によって回答方針が異なる場合もあります。このような不透明さが、税理士試験がおかしいと言われる理由の一つとされています。
試験に合格するだけでは税理士になれない!
税理士試験に合格した後も、すぐに税理士として活動できるわけではありません。税理士として登録するためには、2年以上の実務経験を積むことが法律で定められており、これが試験に合格するだけでは税理士になれないと言われる理由の一つです。また、実務経験を積むための職場探しも重要なステップとなります。
さらに、税理士会への登録手続きや、研修の受講も必須です。これらのステップを経て初めて、正式に税理士としての業務が可能になります。試験合格だけではなく、現場での経験や研修を通じて、専門的な知識と実践力を身につけることが求められるのです。これにより、税理士としての信頼性と実力を確立することができるのです。
試験を受けなくても税理士になれる!?
試験を受けなくても税理士になる方法として、税務署勤務経験が挙げられます。税理士法では、一定の条件を満たした税務署職員には試験免除の制度が設けられています。この制度により、長期間にわたる税務署での実務経験を持つ職員は、税理士試験を受けずに資格を取得することが可能です。
具体的には、23年以上の勤務経験が必要とされ、これにより税務知識と実務能力が認められる形となっています。制度の背景には、税務署勤務が税理士としての業務に直結するスキルを培う場であるとの認識があります。そのため、試験免除の道は、試験合格とは異なるものの、同等の専門性を持つとされているのです。
また、大学院に通うことによる「院免」という仕組みもあります。
税理士資格を取得するメリット
税理士資格を取得することには多くのメリットがあります。特に、安定した職業選択の幅が広がり、将来的なキャリアの選択肢が増える点で魅力的です。また、税理士として独立開業することで、自分のペースで働くことができ、仕事の自由度も高まります。
以下で詳しく解説していきます。
働き先に困らない
税理士資格を取得することで働き先に困らない理由は、その専門性の高さと需要の安定性にあります。税理士は、個人や企業の税務を担当し、節税対策や税務調査の対応など、専門的な知識が求められる職業です。また、税理士は企業内での経理や財務部門での活躍も期待されており、転職市場でも優位に立てる職種です。
さらに、税理士法人や会計事務所での勤務だけでなく、独立して自分の事務所を構える選択肢もあり、働き方の自由度が高いのも魅力です。このように、税理士資格を持つことで、様々なキャリアパスが開けるため、働き先に困ることは少ないと言えます。
| キャリアパス | 概要 | 推定年収 |
|---|---|---|
| 勤務税理士 | 税理士事務所や会計事務所に雇用され、税務業務を行います。 経験を積むことでキャリアアップが可能です。 |
400万円~800万円 |
| 独立開業税理士 | 自ら税理士事務所を開業し、個人事業主として活動します。 収入は顧客数や業務内容により大きく変動します。 |
500万円~1500万円以上 |
| 企業内税理士 | 一般企業の経理部門や税務部門に所属し、 社内で税務業務を担当します。 |
500万円~1000万円 |
| コンサルティングファームや金融機関勤務 | 税務の専門知識を活かし、 コンサルティング業務や金融関連業務に従事します。 |
600万円~1200万円 |
独立開業ができる
税理士資格を取得すると、独立開業が可能になるため、多くの人々にとって魅力的です。税理士は、顧客の税務申告や経営相談などを行うプロフェッショナルであり、自分のペースで働けることが大きなメリットです。特に、税理士試験に合格すれば、独立して自分の事務所を持つことができ、自由度の高い働き方が実現します。さらに、独立することで、自分の専門性を活かしたサービスを提供できるため、顧客からの信頼を得やすくなります。
また、独立開業は、収入をコントロールしやすくなる点も魅力です。成功すれば、高収入を得ることも可能ですし、働き方を自分で決められるため、ライフスタイルに合わせた仕事ができます。税理士としてのスキルを活かし、独立開業を目指すことは、キャリアの選択肢として非常に有望です。
高年収が期待できる
税理士資格を取得することで高年収が期待できる理由は、その専門性の高さにあります。税理士は企業や個人の税務に関する問題を解決するプロフェッショナルであり、特に「税務申告」や「節税対策」は高度な知識と経験が求められます。日本国内では税理士の需要が高く、特に中小企業や個人事業主は税理士のサポートを必要としています。こうした背景から、税理士は安定した顧客基盤を築きやすく、高い報酬を得ることが可能です。
生涯現役でいられる
税理士資格を持つことは生涯現役でいられるための大きな強みです。高齢化社会が進む中、税理士は年齢に関係なく働ける職業の一つとして注目されています。税務に関する知識と経験は、年齢を重ねるごとに深まるため、クライアントからの信頼も高まります。
税理士試験に合格するために
税理士試験に合格するためには、計画的な学習と実践的な経験が欠かせません。試験は非常に難易度が高く、合格までに長い時間がかかることが一般的です。そのため、効率的に勉強を進めるための戦略が重要です。
科目選択を行い、スケジュールを立てる
税理士試験に合格するためには、適切な科目選択と計画的なスケジュールの立案が不可欠です。税理士試験は5科目の合格が必要で、各科目の特性や自分の得意分野を考慮しながら選ぶことが重要です。合格率が低く、平均資格取得年数が約8年と長いため、効率的な学習が求められます。スケジュールを立てる際は、平日の試験日や約4ヵ月後の合格発表日などを考慮し、計画に組み込むことが大切です。
また、受験者は試験の配点が不明であるため、過去問を活用しながら幅広い範囲をカバーする学習が必要です。合格後も税理士としての実務経験が求められるため、試験勉強と並行して実務経験を積むことも考慮すると良いでしょう。
資格取得支援をしている事務所へ転職する
試験勉強の時間を確保するために資格取得支援を行っている事務所への転職は、税理士試験合格を目指す人にとって非常に有益な選択肢です。これらの事務所は、試験対策のノウハウが豊富であり、実務経験を積みながら効率的に勉強を進めることができます。特に、試験勉強と業務の両立が難しいと感じる方にとって、資格取得支援制度は大きな助けになるでしょう。
さらに、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境は、モチベーションの維持にも役立ちます。税理士試験は難易度が高く、合格までの道のりは長いですが、支援体制が整っている事務所での経験は、合格への近道となるはずです。転職を検討する際には、支援内容や実績をしっかりと確認し、自分に合った事務所を選ぶことが重要です。
税理士試験はおかしい?-まとめ
今回は、税理士試験に疑問を持つ方に向けて、
- 試験の難易度が高すぎること
- 合格率の低さと不透明さ
- 試験内容の時代遅れ感
上記について、お話してきました。
税理士試験は非常に厳しいものであり、その難易度や合格率の低さが受験者に大きなプレッシャーを与えています。これらの要因は、試験の公平性や実用性に疑問を抱く理由となっています。あなたが試験に挑む中で感じる不安や疑問は、決して特別なものではありません。
この状況を乗り越えるためには、まずは試験の本質を理解し、自分に合った対策を練ることが重要です。これまでの努力は確実にあなたの力となっているはずです。
将来的には、試験の内容が改善されることを期待しつつ、今できることを着実に進めていきましょう。

城之内 楊
株式会社ミツカル代表取締役社長