INDEX
おすすめ記事
-

税理士試験の受験にかかる費用は?支払い方法や注意点も解説!
-

税務調査は税理士に立ち会ってもらうべき?税務調査をスムーズに進めるためのコツを解説
-
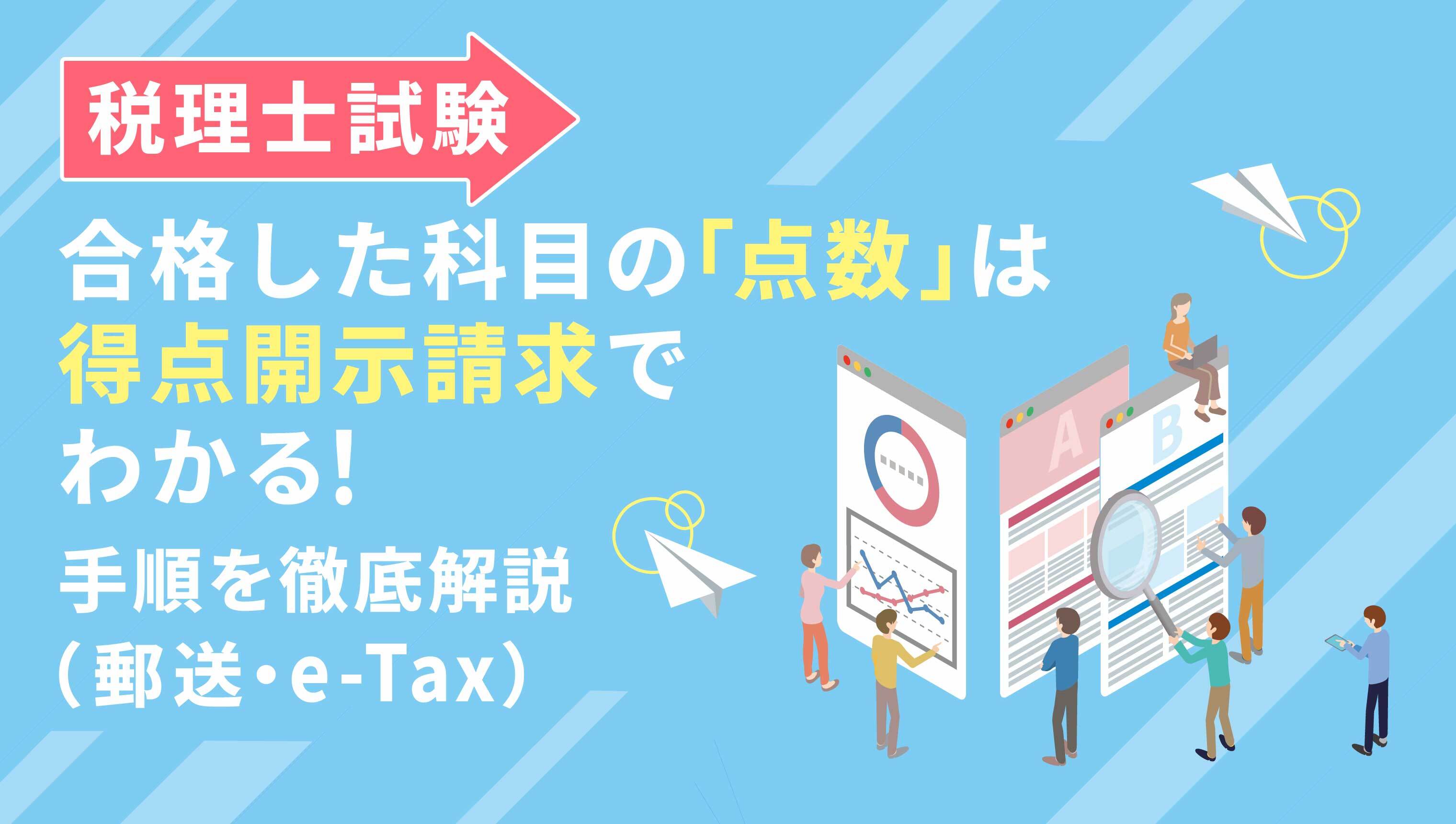
【税理士試験】合格した科目の「点数」は得点開示請求でわかる!手順を徹底解説(郵送・e-Tax)
-
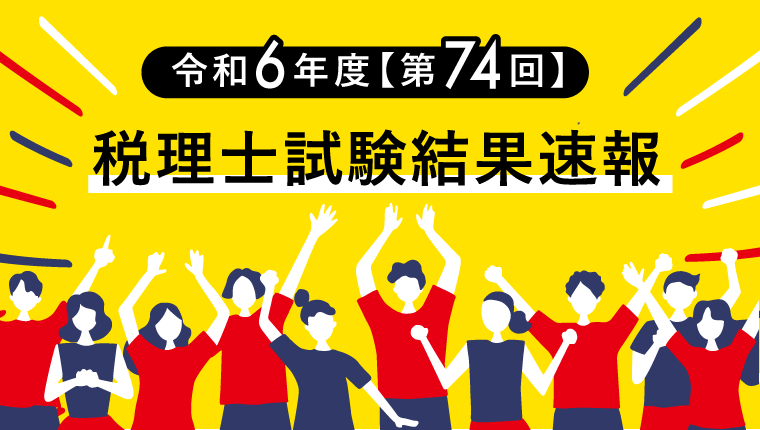
令和6年度(第74回)税理士試験合格発表 結果速報|合格率は13.5%!
-

財務コンサルタントとは?財務コンサルの仕事内容から年収までを徹底解説!
公開日:2025/03/21
最終更新日:2025/09/06
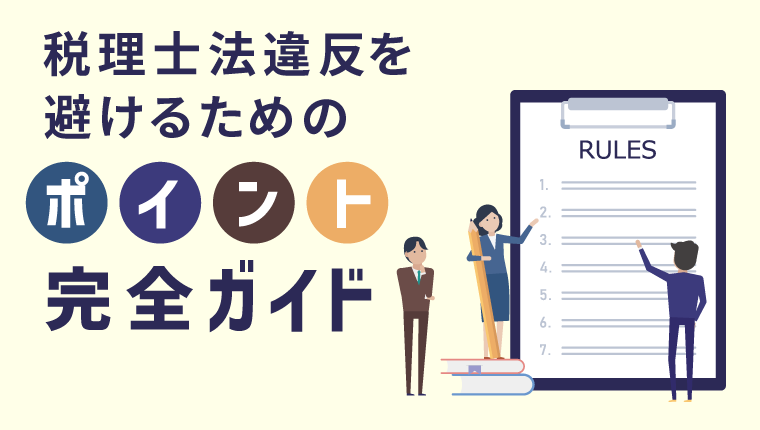
INDEX
税理士は、税理士法に基づいて業務を行うことが求められています。万が一税理士法に違反してしまった場合、「税理士資格の停止や取消し」、「刑事罰」、「民事責任・損害賠償」などの罰則が科される可能性があります。
そのため、税理士として適正に業務を行うためには、どのような行為が税理士法に違反するのかを正しく理解することが大切です。しかし、無意識のうちに違反してしまうケースも考えられます。
本記事では、「守秘義務違反」、「誠実義務違反」などを含む5つの違反行為について解説していきます。さらに、違反を防ぐためのポイントや、税理士法違反を発見した際の対応策(Step1~8)についても詳しくご紹介します。
まずは、税理士法違反とは何か、具体的な違反行為について見ていきましょう。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士法違反とは?
税理士法違反とは、税理士が業務を行うにあたり、税理士法に定められた規定に反する行為を行った場合を指します。税理士法は、税理士が適正に業務を行うことを確保し、税務の公正を維持するために定められた法律です。
税理士法違反行為
税理士法違反行為には主に以下の5つが挙げられます。
1.無資格で税理士業務を行うこと
2.税理士の資格の不正取得
3.業務範囲外の行為
4.守秘義務違反と誠実義務違反
5.不正な手段での税務申告
1.無資格で税理士業務を行うこと
無資格のまま申告書などの税務書類を作成すると、税理士法違反となり、罰則が科される可能性があります。
また、税理士の資格を持たない者が、税務に関する業務を行うことで、納税者が誤った申告をしてしまうリスクが出てきます。
無資格で税理士業務を行った場合、どのような行為が違反に該当するのか説明します。
・税務代理
◦納税者の代理として税務署に対して申告書や申請書を提出
◦税務調査を受けたりする。
・税務相談
◦納税者に対して税務に関するアドバイスを提供。
・税務書類の作成
◦確定申告書などの作成
2.税理士の資格の不正取得
税理士資格を得るためには、一定の基準や手続きに従って試験を受けることが必要であり、その過程で不正を行うことは法的に罰せられます。
3. 業務範囲外の行為
税理士は、税務に関する専門知識を活かして業務を行いますが、その業務には法律で定められた範囲があります。税理士法により、税理士が行える業務は明確に制限されており、これを超える業務を行うことは違法となります。
税理士の業務は以下の3つに大きく分かれます:
・税務代理
◦納税者に代わり、税務署への申告や申請書の提出。
◦税務調査の際に立ち会い、納税者をサポート。
・税務相談
◦納税者に対して税務に関するアドバイス。
◦節税対策や税務手続きについての相談。
・税務書類の作成
◦確定申告書、法人税申告書、相続税申告書などの税務書類を作成。
4. 守秘義務違反と誠実義務違反
税理士は、税理士法第38条により、業務を通じて知った顧客の情報を、正当な理由なく第三者に伝えてはいけません。この義務に違反すると、「守秘義務違反」に該当します。
また、税理士には「誠実義務」(税理士法第1条の2)や「公正な職務遂行義務」(税理士法第41条)も求められています。顧客の利益を第一に考え、適切に業務を行うことが大切です。不適切な対応や誠実さを欠く行為があった場合、懲戒処分を受けることもあるため、十分な注意が必要です。
5. 不正な手段での税務申告
税理士が不正な手段で税務申告を行うことは、税理士法において重大な問題とされています。 例えば、顧客のために虚偽の申告をしたり、誤った内容で申告することは法律違反にあたります。
税理士には、常に正確で誠実な申告を行うことが求められています。 しかし、意図的または不注意によって、法律に違反するケースも考えられます。特に、次の2つの行為は大きな問題となるため注意が必要です。
・脱税を助ける行為
◦税理士は、税務署に提出する書類や申告書の作成において、事実に基づいた正確な情報を提供する必要。
・高額な報酬を受け取る
◦税理士が依頼者から不正に高額な報酬を受け取る。
◦不当な約束をする。
このように、税理士は税理士法に基づいて業務を行う責任があります。法律に違反した業務を行ってしまうと、厳しい罰則が科される可能性があるため、日々の業務の中で法律をしっかり守ることが大切です。
また、税理士法にはさまざまな細かい規定があります。詳しく知りたい方は、国税庁のページをチェックしてみるのもおすすめです。
引用:国税庁:税理士法違反行為
税理士法に違反する行為について理解したところで、次にもし税理士が税理士法に違反してしまった場合に直面するリスクについて、詳しく見ていきましょう。
税理士法違反のリスクとその後の影響
税理士法に違反すると、さまざまな法的・経済的な影響を受ける可能性があります。税理士法は、税理士が適正に職務を遂行するための規範を定めたものであり、違反した場合、税理士本人や関係者に大きなリスクや悪影響をもたらすことになります。
以下に、税理士法違反による主なリスクを5つご紹介します。
1.税理士資格の停止や取り消し
2.刑事罰
3.損害賠償
4.信頼性の低下
5.税務署からの調査・追徴課税
それではこの5つを詳しく見ていきましょう。
1. 税理士資格の停止や取り消し
税理士法違反のリスクの一つは、税理士資格の停止や取り消しです。違反内容に応じて、税理士資格が一時的に停止されることや、最終的に取り消されることがあります。これにより、税理士としての業務ができなくなり、以下のような影響が生じます。
・業務停止の場合
◦ 一時的な資格停止が課せられることがある。
◦税理士業務ができない期間中、顧客にサービスを提供できず、経済的な損失。
・資格取り消しの場合
◦税理士資格が完全に取り消されると、再度税理士業務を行うことができなくなる。
◦税理士としての活動を継続できないことは、職業人生に大きな影響。
2. 刑事罰
税理士法違反の中には、刑法に基づく犯罪行為とみなされるものもあります。特に不正申告、虚偽報告、脱税などは、刑事罰に該当する可能性があります。具体的には以下の3つがあります。
・懲役刑
◦無資格で税理士業務を行った場合や、顧客に不正なアドバイスを行った場合、最大1年の懲役刑。
・罰金刑
◦無資格業務や虚偽申告に対して、最大50万円以下の罰金。
・脱税幇助
◦脱税に関与した場合、税理士法違反が脱税幇助罪として処罰され、懲役刑や罰金が科せられる。
刑事罰を受けると、刑事履歴が残り、社会的な信用を失うことにつながります。
したがって、不正申告や虚偽報告、脱税などは刑事罰の対象となることがあるため、これらの行為がもたらす影響についてしっかり理解し、十分に注意する必要があります。
3.損害賠償
税理士が税理士法に違反した場合、顧客や関係者に対して損害を与えることがあります。この場合、損害賠償責任が生じることが考えられます。例で挙げると以下になります。
・契約違反
◦顧客と結んだ契約に基づき、税理士が誠実に業務を遂行しなかった場合、契約違反として損害賠償を求められる。
4. 信頼性の低下
税理士法違反による処罰を受けると、税理士本人やその事務所の名誉や信頼が損なわれます。顧客の信頼を失うことで、今後の業務を続けるのが難しくなる可能性もあります。また、取引先や金融機関との関係にも悪影響を及ぼすことが考えられます。
信用性の低下により、以下の4つの影響が考えられます。
・顧客の離脱
◦税理士法違反が公に報じられたり、処罰を受けたりすると、顧客はその税理士を信頼できなくなり、他の税理士に切り替える可能性が高くなる。
・業界内での信用喪失
◦ 税理士業界内でも、法令を遵守していない税理士として悪名が立ち、業界内でのネットワークや新たな顧客を獲得するのが難しくなる。
・金融機関の信用低下
◦税理士事務所が不正な手段で融資や税務アドバイスを行った場合、金融機関や取引先から信用を失い、融資の取り消しや新たな取引が難しくなる。
・取引停止
◦法律違反が取引先に知られると、契約解除や取引停止されるリスクが高くなる。
5. 税務署からの調査・追徴課税
税理士法違反により、税務署からの調査を受ける可能性もあります。例えば、顧客に対して虚偽の申告を行っていた場合、税理士自身が税務署の調査対象となり、場合によっては追徴課税や罰金が課せられることがあります。
このように、税理士法違反は非常に深刻な問題であり、違反した場合には上記の5つのリスクが伴うことを理解しておく必要があります。税理士業務を行う際は、常に税理士法を遵守し、適切な対応を心がけましょう。
もう少し詳しく知りたい方は、以下の引用元を見るのも良いと思います。
引用元:国税庁
次に、税理士法に違反を発見した場合の対応方法について詳しく説明していきます。
違反が発覚した場合の対応
税理士法違反が発覚した場合の対応には、8つのステップがあります。
税理士法違反が発覚すると、法的・行政的な処置が取られる可能性が高いため、迅速かつ適切に対応することが重要です。
以下は、税理士法違反が発覚した場合に必要となる対応の一般的な流れです。
・Step1. 事実確認と内部調査
・Step 2. 弁護士への相談
・Step 3. 税理士会への報告
・Step 4. 行政機関(税務署や法務省)への対応
・Step 5. 顧客への謝罪と補償
・Step 6. 再発防止策の実施
・Step 7. 公的機関との協力
・Step 8. 公表やメディア対応
Step 1. 事実確認と内部調査
違反が発覚した場合、最初に行うべき対応は事実確認です。税理士事務所内で詳細な調査を行い、違反がどのような状況で発生したのかを明確にする必要があります。内部調査を行い、違反内容を特定することで、状況を正確に把握することにつながります。
・内部調査
◦税理士やスタッフに対して聞き取り調査を行い、違反の詳細を把握。
◦業務の記録や顧客のデータも調査対象となる。
・違反内容の特定
◦無資格で業務を行ったのか、不正な税務申告を行ったのか、名義貸しがあったのかなど、具体的な違反内容を特定。
Step 2. 弁護士への相談
税理士法違反が重大な違反に該当する場合、弁護士に相談することが不可欠です。弁護士は税理士法違反に関する専門的な法的知識を持っており、適切な対応策を提案してくれます。
・法的リスクの評価
◦弁護士は、違反がどのような罰則に該当するか、刑事罰や民事責任が問われる可能性を評価し、最適な対応策を提案。
・弁護方針の立案
◦例えば、反省を示して誠実に対応する、違反を早期に報告して協力する、顧客に謝罪して損害賠償を行うなどの方針が考えらる。
Step 3. 税理士会への報告
税理士法違反が発覚した場合、税理士法に基づき、税理士会に報告する義務が出てきます。
・報告と協力
◦速やかに所属している税理士会に違反の事実を報告し、その後の調査に協力。
◦税理士会は内部調査を行い、懲戒処分を決定する。
・税理士会の指導
◦税理士会による指導や処分を受けることがあり、場合によっては資格の一時停止や取り消しが科せられることがある。
Step 4. 行政機関(税務署や法務省)への対応
税理士法違反が税務や犯罪に関わる内容の場合、税務署や法務省などの行政機関からの調査や処罰が行われることがあります。
・税務署への報告
◦不正な税務申告や脱税に関与していた場合、税務署が調査を行い、顧客に対する追徴課税や税理士に対するペナルティを科する。
・法務省や警察への対応
◦刑事罰を受ける可能性がある場合、警察や検察機関が関与し、刑事捜査が行われる。
◦弁護士と協力して、適切な法的対応を行うことが重要。
Step 5. 顧客への謝罪と補償
税理士法違反が顧客に影響を及ぼした場合、顧客への謝罪と補償が必要です。例えば、不正確な申告や税務アドバイスにより顧客が損害を受けた場合、その損害を補償する責任があります。方法としては以下の2つが挙げられます。
・謝罪の手続き
◦顧客に対して正式に謝罪し、必要に応じて損害賠償を行う。
◦弁護士を通じて、補償金額や賠償内容について協議することが求められることがある。
・信頼回復のための措置
◦今後同じ過ちを繰り返さないために、業務改善計画を立て、再発防止策を講じる。
◦顧客に対しては、誠意を持って対応し、信頼回復に努める。
Step 6. 再発防止策の実施
税理士法違反が発覚した場合、再発防止策を講じることが不可欠です。これにより、同じような違反の再発を防ぎ、信頼回復につなげることができます。
・業務の見直し
◦税理士業務のフローや監視体制を見直し、法令遵守を徹底。
◦無資格者が業務に関わらないようにし、税務申告書や顧客対応のチェック体制を強化。
・職員教育
◦税理士事務所内のスタッフに対する法令遵守の教育
◦違反行為が再発しないように、定期的な研修やセミナーを実施。
Step 7. 公的機関との協力
税理士法違反が発覚した場合、関係する公的機関との協力が求められます。税理士法違反が非常に深刻な場合、税理士は公的機関の調査に協力し、結果として処罰を軽減する可能性があります。
・調査の協力
◦税理士法違反が疑われる場合、税務署や税理士会の調査に協力し、証拠を提出することが求められる。
◦協力的な姿勢を示すことが、処罰軽減に繋がる場合もある。
・速やかな対応
◦違反が発覚した時点で、早期に対応することで、責任を軽減できる可能性がある。
◦問題が大きくなる前に適切な対応を取ることが罰則軽減に繋がる。
Step 8. 公表やメディア対応
税理士法違反が社会的に注目されるような大きな問題になった場合、メディア対応も検討しなければならない場合があります。適切なタイミングで適切に対応することが、企業の名誉回復や影響を最小限に抑えるために必要です。
・公表のタイミング
◦法的処分や行政的処置が決定した後、遅延なく公表する
・これをすることで、信頼回復への第一歩を踏み出すことができる。
もし税理士法違反が発覚した場合、上記の8つのステップを実行することが、信頼回復につながるポイントとなります。
最も望ましいのは違反を未然に防ぐことです。そこで次に、税理士法違反を避けるために気をつけるべきポイントを説明します。
税理士法違反を避けるためのアドバイス
税理士法違反を避けるためには、税理士としての職務を適正に遂行することが大切です。税理士法を遵守し、法令に従った業務を行うことで、違反を未然に防ぐことができます。
以下に、税理士法違反を避けるための6つのポイントを示します。
・税理士法の基本的な理解と遵守
・無資格業務の徹底的な排除
・適切な税務申告の実施
・適切な記録の保存
・業務の適正化と監視体制の強化
・顧客に対する透明な説明と契約管理
税理士法の基本的な理解と遵守
税理士法に定められた規定をしっかり理解し、その規範に基づいて行動することが基本です。税理士業務に関する法令や規制は常に変わる可能性があるため、定期的に法令を確認し、最新の規定に従うことが求められます。
・税理士法を学ぶ
◦法律書や専門書、セミナーを通じて税理士法の知識を深め、職務に活かす。
・最新の法改正情報をチェック
◦税理士業務に関連する法改正があれば、すぐに対応できるようにする。
無資格業務の徹底的な排除
税理士法では、税理士以外の者が税理士業務を行うことを禁じています。無資格で税理士業務を行うことは厳しく罰せられます。そのため、税理士として業務を行う場合は、必ず資格を持っていることを確認する必要があります。
・無資格者による業務を排除
◦事務所内で無資格者が税理士業務に関与することがないよう、厳格に管理。
・業務の範囲を守る
◦税理士以外の職業が行うべき業務を税理士が行うことがないよう、職務範囲を守る。
適切な税務申告の実施
税理士は顧客の税務申告を正確に行う責任があります。不正確な申告や虚偽の申告は、税理士法違反に該当し、罰則を受ける可能性があります。顧客の税務申告に関しては、法令に基づいて正確な処理を行うことが不可欠です。対象法としては以下の2つです。
・正確な税務申告を行う
◦顧客の申告内容に間違いがないかを確認し、適切な税務処理を行う。
◦間違った申告や虚偽申告をしないように徹底する。
・税法に従ったアドバイス
◦税理士として、顧客に税法に基づく正しいアドバイスを提供。
◦不正行為を助長しないよう徹底する。
適切な記録の保存
税理士は、業務に関連するすべての書類や記録を適切に保管する義務があります。税務署の調査に備え、業務の履歴を正確に残すことは重要です。
・書類の保管
◦顧客との契約書や税務申告書、帳簿類など、すべての記録を法定の保存期間内に保管。
・電子データの管理
◦デジタルデータを使用している場合、適切な方法でバックアップを取る。
業務の適正化と監視体制の強化
税理士業務を適正に行うためには、日々の業務運営が透明で適切であることを確認するための監視体制を整えることが必要です。定期的な業務のレビューやスタッフとの連携を強化し、適切な業務が行われているかをチェックします。
税理士事務所全体で法令遵守の文化を構築し、職員全員が税理士法を守る意識を持つことで、不正を防ぐことができます。
・定期的な業務レビュー
◦自分の業務だけでなく、事務所内で行われるすべての業務を定期的にレビュー。
・法令違反がないかを確認。
・スタッフ教育
◦スタッフに対して税理士業務に関する適切な研修を実施。
・業務の正確性を高める。
・スタッフ教育と意識向上
◦税理士法や関連法令についての研修を定期的に行う。
◦職員全員が法令遵守を意識して業務を行うようにする。
・違反行為の防止策
◦事務所内で違反行為が発生しないように、適切な監督と管理を行う。
顧客に対する透明な説明と契約管理
税理士は、顧客との信頼関係を築くことが、税理士としての成功に必要不可欠です。不正な行為を防ぐためには、顧客に対して透明性のある説明を行い、契約内容をしっかりと管理することが大切です。
・契約内容を明確化
◦顧客との契約書をしっかりと作成し、業務内容や責任範囲を明確にする。
・透明な業務説明
◦顧客に対して、税務申告やアドバイスの内容について十分な説明を行い、不正な方法で利益を得ることがないようにする。
以上6つが、税理士法に違反しないための対策法です。違反を防ぐためには、税理士法をよく理解し、事務所内での共有が必要であることが理解できたと思います。今後も税理士法違反を避けるために、この6つの点は念頭に置いておきたいポイントです。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士法違反を避けるためのポイント-まとめ
税理士法違反は、税理士が法令に反する行為を行うことです。主な違反には、無資格で業務を行うこと、不正に税理士資格を取得すること、業務範囲を超える行為(例:弁護士業務)、守秘義務や誠実義務違反、虚偽の税務申告などがあります。
違反が発覚すると、税理士資格の停止や取り消し、罰金や懲役刑が科せられることがあります。また、顧客に損害を与えた場合、損害賠償責任が生じることもあります。税理士は法令を遵守し、適切に業務を行うことが求められます。

城之内 楊
株式会社ミツカル代表取締役社長


















