INDEX
おすすめ記事
-

会計事務所の職種を徹底解説|税理士・内勤・会計入力スタッフなどの仕事内容と役割
-

法人税申告書とは?申告書の作成方法と変更点まとめ【2025年最新版】
-

新事業進出補助金のメリットと活用法解説【2025年4月公募開始】
-

女性にとって税理士という職業は魅力的?働き方から年収まで女性が税理士になるメリットを解説
-
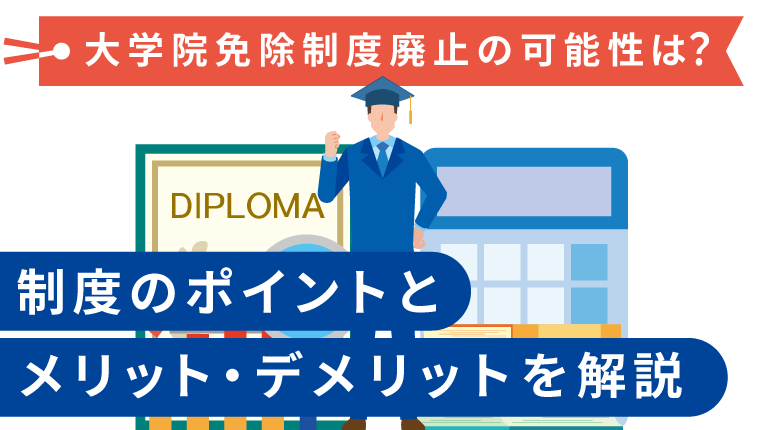
税理士試験の大学院免除制度廃止の可能性は?制度のポイントとメリット・デメリットを解説
公開日:2025/04/04
最終更新日:2025/09/06
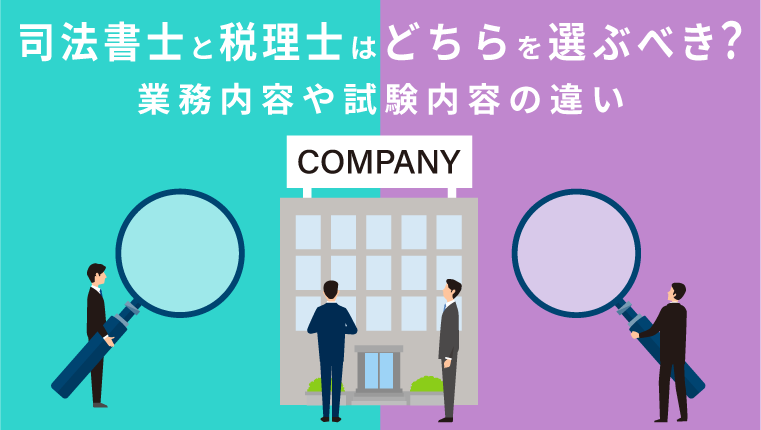
INDEX
「司法書士と税理士、どちらの資格を取るべきか?」
法律と税務、それぞれの分野で専門性を発揮するこの2つの資格は、業務内容も試験の難易度も大きく異なります。
それぞれの専門分野、試験の難易度、独立後の収入の違いを詳しく比較し、あなたに最適なキャリアを見つけるためのポイントを解説します。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
司法書士と税理士の専門は?
司法書士と税理士は、それぞれ法律と税務の専門家ですが、取り扱う業務範囲や役割が異なります。
司法書士の役割と専門分野
1. 役割
司法書士は、不動産登記や会社設立の登記手続きなど、登記業務を中心に扱う法律専門職です。また、簡易裁判所における訴訟代理や成年後見制度に関する業務も行います。
2. 専門分野
・不動産登記
◦土地や建物の所有権移転(売買・相続・贈与など)
◦抵当権設定(住宅ローンなど)
・商業・法人登記
◦会社設立(株式会社、合同会社など)
◦役員変更、商号変更、本店移転
◦解散・清算手続き
・裁判手続き(簡易裁判所代理)
◦140万円以下の民事訴訟の代理(認定司法書士のみ)
◦少額訴訟手続き
◦裁判所提出書類の作成
・成年後見業務
◦成年後見人・保佐人・補助人の申立手続き
◦任意後見契約のサポート
・債務整理
◦過払い金請求、任意整理、自己破産、個人再生の申請書類作成
司法書士は、主に登記手続きや法律文書の作成を通じて、権利関係の整理を支援する専門家です。
税理士の役割と専門分野
1. 役割
税理士は、企業や個人の税務に関する相談・申告業務を担う税務の専門家です。税務署への申告手続きや税務調査の対応など、税務全般をサポートします。
2. 専門分野
・税務代理
◦所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税の申告
◦税務署への申請・異議申し立て
◦税務調査の立ち合い・対応
・税務相談
◦節税対策のアドバイス
◦事業承継や相続税対策
◦M&Aや企業再編における税務アドバイス
・記帳代行・財務書類の作成
◦決算書・申告書の作成
◦青色申告のサポート
◦経理業務の効率化支援
・経営コンサルティング
◦資金調達支援(銀行融資対策)
◦事業計画の策定
◦経営戦略に関するアドバイス
税理士は、主に税務申告や財務管理を通じて、企業・個人の税務リスクを最小限に抑える専門家です。
まとめると、以下の様になります。
| 司法書士 | 税理士 | |
|---|---|---|
| 主な業務 | 不動産・商業登記、裁判書類作成、債務整理 | 税務申告、税務相談、財務アドバイス |
| 対象分野 | 登記、相続、成年後見、簡易裁判 | 所得税、法人税、相続税、消費税 |
| 税務業務の可否 | 税務業務は不可(税理士資格が必要) | 可能(税務代理権を持つ) |
| 裁判業務の可否 | 簡易裁判所での代理は可能(認定司法書士) | 裁判代理権はなし |
| 主な依頼者 | 不動産購入者、起業家、相続人、債務者 | 企業経営者、個人事業主、資産家 |
司法書士は「法律の手続き・登記の専門家」、税理士は「税務・財務の専門家」として、それぞれの分野で重要な役割を担っています。
司法書士と税理士の業務内容は?
司法書士が扱う主な業務
司法書士は、登記手続きや法律書類の作成を中心に扱う専門家です。特に、不動産・商業登記、裁判関連手続き、成年後見、債務整理などが主要業務となります。
| 業務カテゴリ | 具体的な業務内容 |
|---|---|
| 不動産登記 |
- 所有権移転登記(売買・相続・贈与など) - 抵当権設定・抹消登記 - 地目変更登記 - 建物表題登記・滅失登記 |
| 商業・法人登記 |
- 会社設立登記(株式会社・合同会社など) - 役員変更登記 - 本店移転登記 - 会社解散・清算登記 |
| 裁判所提出書類作成 |
- 相続放棄申述書の作成 - 破産・個人再生申立書の作成 - 特別代理人選任申立書の作成 |
| 簡易裁判所代理(認定司法書士) |
- 140万円以下の民事訴訟代理 - 少額訴訟手続き - 支払督促・債権回収 |
| 成年後見業務 |
- 成年後見人・保佐人・補助人の申立て - 任意後見契約の支援 |
| 債務整理 |
- 自己破産・個人再生の申請書作成 - 過払い金請求の書類作成 - 任意整理の支援 |
税理士が扱う主な業務
税理士は、税務に関する代理業務や財務コンサルティングを専門とし、個人・法人の税務申告や税務調査対応などを行います。
| 業務カテゴリ | 具体的な業務内容 |
|---|---|
| 税務代理 |
- 所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税の申告 - 税務調査の対応・立ち合い - 税務署への異議申し立て |
| 税務相談 |
- 節税対策のアドバイス - 事業承継・相続税対策 - M&A・企業再編の税務アドバイス |
| 記帳代行・財務書類作成 |
- 月次決算・年次決算の作成 - 法人税・消費税・所得税の計算 - 財務諸表の作成(貸借対照表・損益計算書) |
| 経営コンサルティング |
- 資金調達支援(銀行融資対策) - 企業の財務戦略策定 - キャッシュフロー管理 |
| 確定申告・青色申告支援 |
- 個人事業主・フリーランスの確定申告支援 - 青色申告・白色申告のアドバイス |
司法書士は 「登記・法律書類の作成・簡易裁判の代理」 が中心、税理士は 「税務申告・財務管理・税務相談」 が中心の業務となります。
違いをまとめると以下の様になります。
| 司法書士 | 税理士 | |
|---|---|---|
| 主な業務領域 | 不動産登記・商業登記・法律書類作成 | 税務申告・税務相談・経営アドバイス |
| 不動産関連 | 不動産登記(売買・相続) | 不動産譲渡にかかる税務申告 |
| 会社設立 | 法人登記(設立・役員変更・解散) | 法人税・消費税の申告、節税アドバイス |
| 相続関連 | 相続登記、相続放棄手続き | 相続税申告、税務対策 |
| 借金問題 | 自己破産・個人再生の申請書作成 | 借入金の税務処理、財務相談 |
| 裁判業務 | 簡易裁判所での訴訟代理(140万円以下) | 裁判代理権なし |
| 税務申告 | 税務申告不可 | 所得税・法人税・相続税などの申告 |
司法書士と税理士の試験内容・難易度の違いは?
司法書士試験の内容・難易度
1. 試験概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験方式 | 筆記試験(択一式+記述式) |
| 試験日程 | 毎年1回(7月) |
| 合格率 | 約3〜4% |
| 試験科目 | 憲法、民法、商法・会社法、不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法、刑法、供託法、司法書士法など |
| 受験資格 | なし(誰でも受験可能) |
2. 試験内容
司法書士試験は 筆記試験のみ で構成され、以下の形式で行われます。
| 試験区分 | 形式 | 配点 | 主な科目 |
|---|---|---|---|
| 午前の部(多肢択一式) | 35問(五肢択一) | 105点(1問3点) | 憲法、民法、刑法、商法・会社法 |
| 午後の部(多肢択一式) | 35問(五肢択一) | 105点(1問3点) | 不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法、供託法、司法書士法 |
| 午後の部(記述式) | 2問(不動産登記・商業登記) | 70点 | 具体的な登記申請書の作成 |
3. 難易度
✅ 司法書士試験の特徴
・出題範囲が広く、特に 民法・不動産登記法・商業登記法 の深い理解が求められる
・記述式試験では 正確な登記申請書を作成する能力 が必要
・合格率は3〜4%程度 と非常に低く、難関資格
・法律の専門知識が必須 であり、初学者にはハードルが高い
✅ 勉強時間の目安
・合格までの平均学習時間は3,000時間以上
・独学での合格は困難 とされ、予備校の講座を利用する人が多い
税理士試験の内容・難易度
1. 試験概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験方式 | 科目選択制(筆記試験) |
| 試験日程 | 毎年1回(8月) |
| 合格率 | 各科目10〜15%(5科目合格が必要) |
| 試験科目 | 必須科目(簿記論・財務諸表論)+選択科目(法人税法・所得税法・相続税法など) |
| 受験資格 | 大学で法律・経済学を学んだ者、簿記1級取得者、一定の実務経験者など(受験資格が必要) |
2. 試験内容
税理士試験は、5科目合格すれば資格を取得 できる制度です。
| 試験科目 | 選択方式 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 必須科目 | 2科目必須 | 簿記論、財務諸表論 |
| 選択必須科目 | 1科目選択 | 法人税法 or 所得税法 |
| 選択科目 | 2科目選択 | 相続税法、消費税法、固定資産税、住民税、事業税、国税徴収法 |
3. 難易度
✅ 税理士試験の特徴
・科目ごとの 合格率は10〜15% だが、5科目すべて合格するには数年かかる 人が多い
・試験科目を分割して受験できる ため、一発合格する必要はない(科目合格制度あり)
・簿記・会計の知識が重要 であり、実務経験があると有利
・試験科目に受験資格がある ため、誰でも受けられるわけではない
✅ 勉強時間の目安
・1科目あたり500〜1,000時間の学習が必要
・5科目合格まで3,000〜5,000時間 かかるのが一般的
・働きながら受験する人が多いため、取得まで 平均5年程度 かかる
違いをまとめると以下の通りです。
| 比較項目 | 司法書士試験 | 税理士試験 |
|---|---|---|
| 試験方式 | 択一式+記述式 | 科目選択制(筆記試験) |
| 受験資格 | なし(誰でも受験可能) | 大学の履修要件 or 実務経験が必要 |
| 試験科目数 | 1試験で全科目受験 | 5科目合格で資格取得(科目合格制度あり) |
| 合格率 | 3〜4% | 各科目10〜15%(5科目合格に数年かかる) |
| 主な出題分野 | 法律(民法・不動産登記法・商業登記法など) | 会計・税務(簿記論・財務諸表論・法人税法など) |
| 試験の特徴 | 一発合格が必要(合格ラインが高い) | 科目合格制度で分割受験が可能 |
| 必要な勉強時間 | 3,000時間以上 | 5科目合格まで3,000〜5,000時間 |
| 難易度の特徴 | - 合格率が低く、法律知識が必須 - 記述式試験が難関 |
- 5科目合格が必要で、取得まで時間がかかる - 簿記・会計の基礎知識が重要 |
司法書士と税理士ではどちらが稼げる?
司法書士と税理士の収入は 「勤務」か「独立」か によって大きく変わります。
1. 司法書士の年収
| キャリア | 年収の目安 |
|---|---|
| 勤務司法書士(事務所勤務) | 400万~700万円 |
| 独立開業(軌道に乗るまで) | 300万~600万円 |
| 独立開業(成功) | 1,000万円以上も可能 |
| 法人化・大手事務所経営 | 2,000万円以上も可能 |
・開業すると収入が大きく変動 する
・相続登記や不動産登記の案件が多い ほど高収入
・商業登記(企業向け)を得意とする事務所 は売上が安定しやすい
2. 税理士の年収
| キャリア | 年収の目安 |
|---|---|
| 勤務税理士(会計事務所勤務) | 500万~800万円 |
| 独立開業(軌道に乗るまで) | 300万~600万円 |
| 独立開業(成功) | 1,000万円以上も可能 |
| 大手税理士法人・顧問契約多数 | 2,000万円以上も可能 |
・独立後の安定性が高い(顧問契約で継続収入を得られる)
・法人向け顧問契約が多いほど高収入
・資産家向けの相続税専門、国際税務などの特化分野 は高単価案件が多い
まとめると以下の通りです。
| キャリア | 司法書士 | 税理士 |
|---|---|---|
| 勤務(事務所勤務) | 400万~700万円 | 500万~800万円 |
| 独立開業(軌道に乗るまで) | 300万~600万円 | 300万~600万円 |
| 独立開業(成功) | 1,000万円以上も可能 | 1,000万円以上も可能 |
| 大手事務所経営・法人化 | 2,000万円以上も可能 | 2,000万円以上も可能 |
| 収入の安定性 | 案件ごとに変動 | 顧問契約で安定しやすい |
| 高収入を得るポイント | 相続・商業登記の拡大 | 法人顧問契約・相続税案件 |
司法書士と税理士ではどちらを目指すべき?
| 項目 | 司法書士向きの人 | 税理士向きの人 |
|---|---|---|
| 得意分野 | 法律・登記手続き | 会計・税務・財務管理 |
| 収入の安定性 | 変動が大きい(案件単位の報酬) | 継続的な収入が得られる(顧問契約) |
| 試験の難易度 | 一発合格が必要(合格率3〜4%) | 科目合格制でじっくり取得可能 |
| 独立開業のしやすさ | 1人でも開業しやすい | 事務所経営には顧問契約が必要 |
| 営業・マーケティングの必要性 | 司法書士は集客が重要 | 税理士は安定した顧客基盤を作れば安定 |
✅ 法律・登記手続きを極めたいなら「司法書士」
✅ 安定した収入を狙うなら「税理士」
✅ 独立後の安定性を重視するなら税理士の方が有利
✅ 一発試験が苦手なら税理士(科目合格制度がある)
ダブルライセンスのメリットは?
司法書士と税理士の資格を両方持つことで、相乗効果による高収入・高付加価値サービス が可能になります。
1. 相続・事業承継分野で圧倒的に強い
・司法書士 → 相続登記・遺言作成
・税理士 → 相続税申告・事業承継税制の活用
→ 相続手続きをワンストップで提供でき、高単価な案件を受注可能
2. 会社設立・企業支援で強み
・司法書士 → 会社設立登記・役員変更登記
・税理士 → 法人税・消費税の申告、税務顧問契約
→ 法人向けの継続顧問契約を取りやすくなる(安定収入の確保)
3. 不動産投資家向けサービス
・司法書士 → 不動産登記(売買・担保設定)
・税理士 → 不動産所得の税務アドバイス
→ 不動産投資家向けにトータルサポートを提供し、高収益を実現
4. 競争力の向上
・司法書士は登記のみ、税理士は税務のみ だが、ダブルライセンスなら 顧客のワンストップ対応が可能
・競合との差別化 がしやすく、単価の高い案件を獲得できる
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
司法書士と税理士はどちらを選ぶべき?業務内容や試験内容の違い -まとめ
この記事では税理士と司法書士の違いを解説しました。
この記事が少しでもお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















