INDEX
おすすめ記事
-
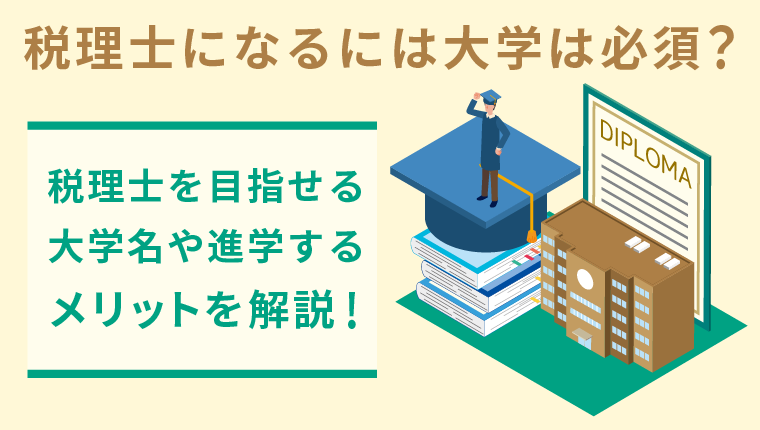
税理士になるには大学は必須?税理士を目指せる大学名や進学するメリットを解説
-
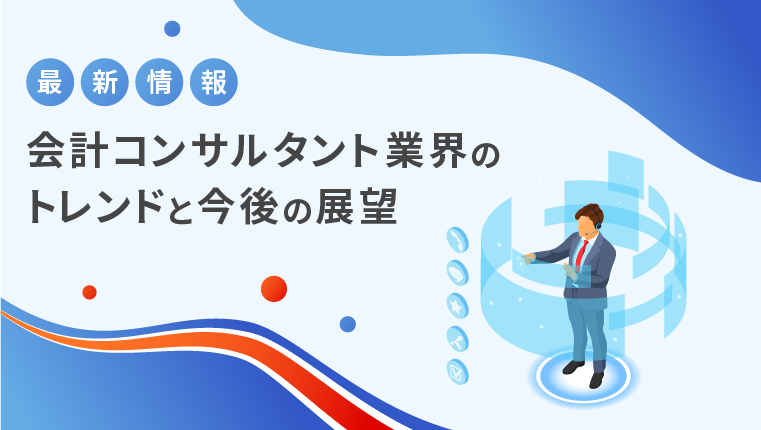
会計コンサルタント業界のトレンドと今後の展望【最新情報】
-
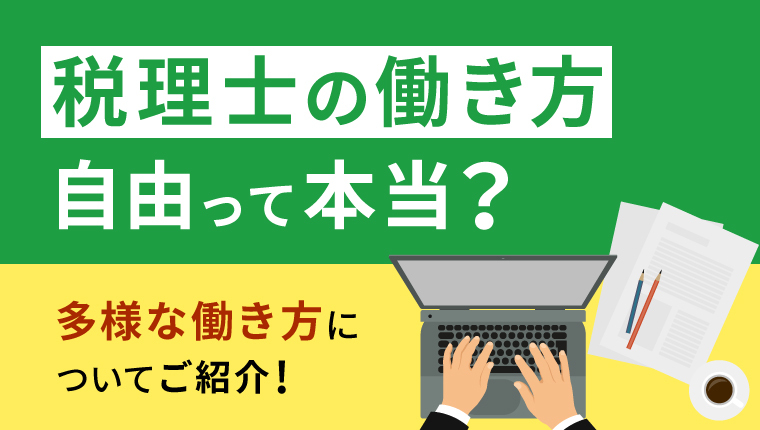
税理士の働き方は自由?税理士の多様な働き方をご紹介
-
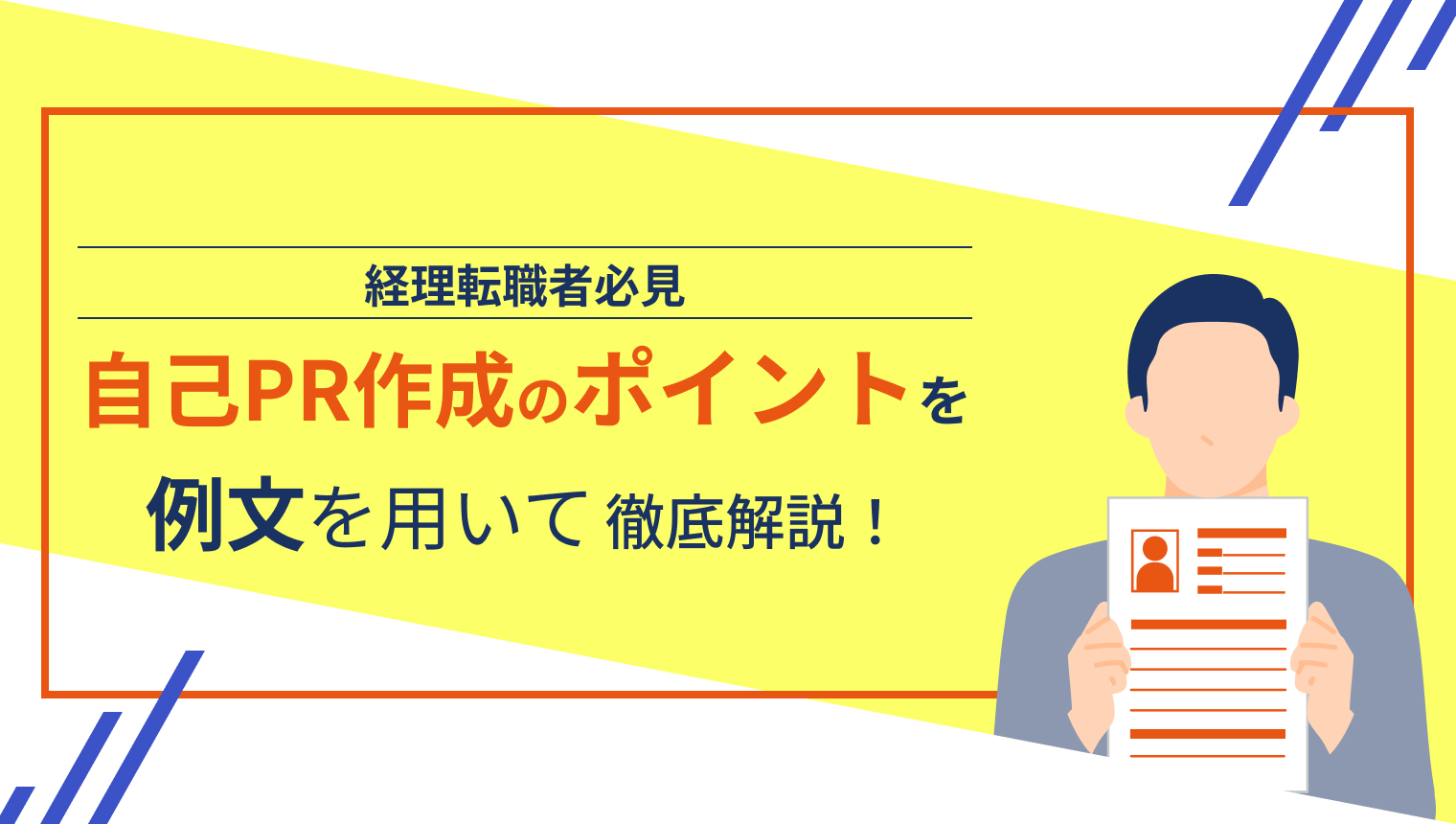
【経理転職者必見】経理の自己PR作成のポイントを例文を用いて徹底解説!
-
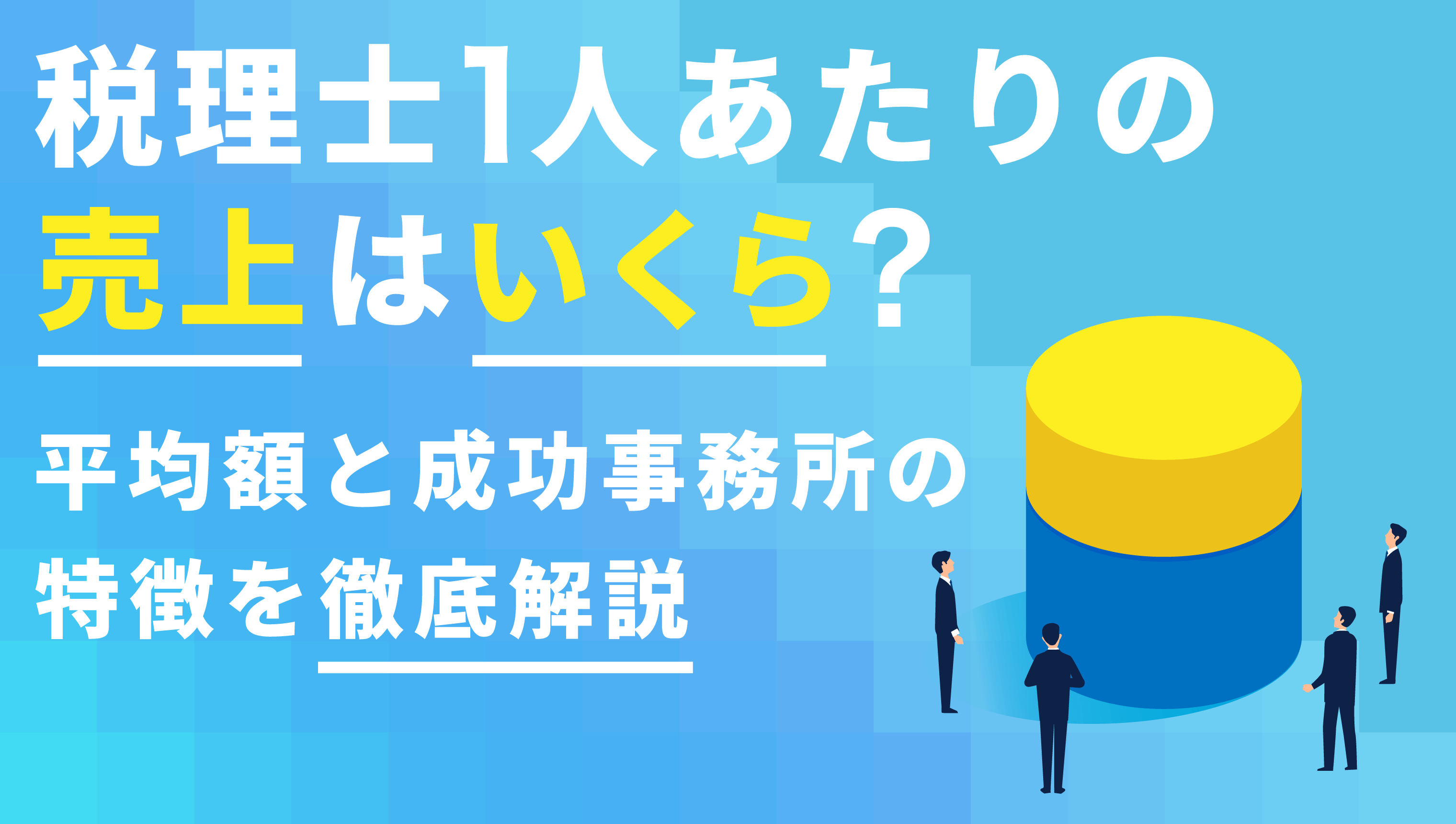
税理士1人あたりの売上はいくら?平均額と成功事務所の特徴を徹底解説
公開日:2025/05/01
最終更新日:2025/09/06

INDEX
2027年4月、リース会計の常識が大きく変わります。
これまでオペレーティング・リースは「費用処理」で済んでいた取引が、原則すべて資産・負債として計上される時代へ。
「リース=オフバランスで負担が軽い」というイメージは、もう過去のものになるかもしれません。
特に借手側では、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフローすべてに影響が及びます。
経営者から「なんで負債が急に増えたの?」と聞かれる場面も想定されます。
つまり、税理士こそがこの制度変更を正しく理解し、クライアントに橋渡しできる存在になる必要があるのです。
「会計処理を変えるだけ」で済ませてしまうと、後々、資金調達や財務指標に想定外の波紋が…。
この記事では、新リース基準の実務的な変更点から、企業がとるべき対応策、システム面の留意点まで、税理士の実務に直結する観点で徹底解説します。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
新リース会計基準の概要
2027年4月施行の背景と目的
2027年4月から適用される新リース会計基準は、これまでの日本基準と大きく異なり、すべてのリースを原則「オンバランス」処理することが求められるようになります。
これまで日本では、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分けられ、特にオペレーティング・リースについては貸借対照表に計上されない「オフバランス処理」が可能でした。しかしこの処理は、実態を正確に反映しないという批判や、国際的な整合性の問題が指摘されてきました。
今回の改正は、国際会計基準(IFRS第16号)に準拠した考え方を取り入れ、企業のリース取引をより透明にすることを目的としています。
◇ 改正の背景
・従来の「オフバランス」処理が、企業の財務状況を正確に示していないとされていた
・IFRSやUS GAAPではすでに「原則オンバランス」が採用されている
・グローバル企業との比較可能性を高める必要性が高まっていた
◇ 改正の目的
・リース取引の経済実態を正確に財務諸表へ反映させる
・国際的な整合性を保ち、海外投資家への説明力を強化する
・情報開示の透明性を向上し、企業の信頼性を高める
主な変更点と改正内容
新基準では、原則すべてのリース契約が資産(使用権資産)および負債(リース負債)として貸借対照表に計上されます。
◇ 主な改正ポイント
・原則、すべてのリース契約を「オンバランス」処理へ変更
・使用権資産(right-of-use asset)を資産として計上
・将来のリース支払義務をリース負債として計上
・一定の例外(短期リースや少額リース)を除く
・財務諸表上の開示が大幅に強化(契約内容、期間、割引率などの詳細開示が必要)
◇ 現行基準との主な違い(要点)
・【現行】オペレーティング・リース → オフバランスOK
・【新基準】すべてのリース → 原則オンバランス処理
・【現行】リース料は費用処理のみ
・【新基準】利息と減価償却に分けて処理
| 分類 | 現行基準 | 新基準(2027年4月施行予定) |
| 会計処理 | ファイナンス・リースとオペレーティング・リースで異なる処理(オフバランス可) | 原則すべてのリースを「オンバランス」(資産・負債計上) |
| 貸借対照表 | オペレーティング・リースは原則記載なし | 使用権資産・リース負債として計上(原則) |
| リース資産 | なし(オペレーティングの場合) | 使用権資産(Right-of-use asset)を計上 |
| リース負債 | なし(オペレーティングの場合) | 将来のリース料支払義務を負債として認識 |
| 例外規定 | - | 短期リース(12ヶ月以下)および少額資産リースはオフバランス可 |
| 開示 | 限定的 | リース契約の概要、期間、支払総額、割引率等を詳細に開示 |
新基準が企業に与える影響
財務諸表への影響
新リース基準により、これまでオフバランス処理されていたオペレーティング・リースも貸借対照表に計上されるようになるため、企業の財務数値に明確な変化が生じます。特に、資産・負債の増加や費用認識方法の変化がポイントです。
◇ 主な影響ポイント
・総資産・総負債の増加
◦使用権資産とリース負債を計上することで、貸借対照表が拡大
・ROA(総資産利益率)の低下
◦分母となる総資産が増加するため、同じ利益でも指標が下がる
・EBITDAの改善
◦リース料が全額費用処理されていたのが、減価償却+利息に分解されるため、営業利益やEBITDAは相対的に増加
・利益の時間的偏り
◦利息費用が初期に大きくなるため、契約初期に利益が小さく見える傾向
・キャッシュフロー表示の変化
企業の資金調達戦略への影響
リース契約のオンバランス化は、財務内容や信用力の見え方を変えるため、資金調達戦略や金融機関との関係にも影響を与えます。
◇ 主な影響ポイント
・見かけの財務レバレッジ(負債比率)が上昇
◦リース負債計上により、自己資本比率が低下する可能性がある
・借入余力の低下
◦総負債が増加することで、銀行からの新規融資が難しくなるケースも
・リース利用の再検討が必要
◦オフバランスの魅力が薄れるため、「購入」vs「リース」の再評価が必要に
・資金調達コストに影響
◦信用格付け評価に影響する場合、金利上昇のリスクも
・短期リースや少額リースの活用増加
◦オフバランスできる「例外規定」を活用した契約構造の見直しが進む可能性
具体的な適用方法と処理
借手側の会計処理の変更点
新基準では、借手が原則としてすべてのリース契約について、使用権資産(right-of-use asset)とリース負債(lease liability)を認識することになります。
◇ 主な処理の流れ(概要)
開始日における認識:
・使用権資産 = 初期測定されたリース負債 ± 初期直接費用 ± 前払リース料など
・リース負債 = リース期間中の将来リース料支払額の現在価値
リース期間中:
・使用権資産 → 減価償却処理(定額法など)
・リース負債 → 利息費用+元本返済に分けて処理
◇ 現行基準からの主な変更点
| 項目 | 現行基準 | 新基準(2027年4月〜) |
| 会計処理の対象 | ファイナンスリースのみ資産計上 | 原則すべてのリース契約が対象 |
| オペレーティング・リース | 費用処理のみ | 資産・負債として計上 |
| 表示 | リース料は販管費等で一括費用計上 | 減価償却費と利息費用に分けて処理 |
| 開示内容 | 限定的 | 契約内容やリスク情報まで詳細に開示必要 |
開始時の注意点と実務対応
新基準への対応にあたっては、単なる仕訳対応では済まず、契約見直し・システム対応・内部統制整備など多岐にわたる実務的な準備が求められます。
◇ 初度適用の実務ポイント
・過去リース契約の洗い出し
◦現在締結済みのすべてのリース契約を一覧化
・契約条件の確認
◦契約期間、更新・中途解約の条件、支払タイミング、割引率などを整理
・割引率の決定
◦通常は「借手の追加借入利率」を使用(適切な決定が重要)
・初期の会計処理設計
◦使用権資産とリース負債の算定ロジック、償却スケジュールを確定
・システム整備
◦リース管理台帳、IFRS対応会計ソフト、ERPの改修等
・会計方針の明文化
◦短期リースや少額リースの定義、更新オプション等について方針決定
◇ 実務上の課題と対策
| 課題 | 対策 |
| 契約条項が不明瞭なケース | 法務部門・外部専門家と連携して整理 |
| 割引率の設定が難しい | 銀行借入金利、社債利率等から推定 |
| 契約管理が属人的 | リース管理台帳の導入と統一運用 |
| 開示が煩雑 | 注記テンプレート整備、監査法人との連携強化 |
新リース会計基準への対応策
企業が取るべき準備と対策
新リース基準は、経理部門だけでなく、財務・法務・IT・経営層まで関わる全社的な対応が必要となります。特に、契約管理や評価の標準化がカギです。
◇ 企業としての基本的な準備ステップ
1.リース契約の洗い出しと分類
◦現在締結済みの全リース契約(オペレーティング・ファイナンス両方)を網羅的に把握
◦更新・解約オプション、残存価値保証なども整理
2.適用方針の策定
◦短期リース・少額資産リースの例外適用範囲の設定
◦割引率の決定ルール(借手の追加借入利率など)
3.使用権資産・リース負債の初期評価
◦会計処理ルールの整備(開始日、償却方法、利息計算)
4.社内マニュアル・運用ルールの整備
◦経理部門だけでなく、契約締結を行う現場や法務への教育も含めて統一方針を構築
5.監査法人・税理士との事前協議
◦判断の難しい契約(例:サブリース、変動リース料)については早期相談が望ましい
◇ 実務対応上の注意点
・会計上の影響だけでなく、財務指標の変動に対する社内・投資家説明も重要
・従来の「費用処理」から「資産・負債計上+償却・利息」への変更に伴う業績予測モデルの更新が必要
・内部統制(リース契約締結から会計処理までのプロセス)も再設計が求められる
ITシステムの改修と導入のポイント
新基準対応には、エクセルなどの手作業では対応が困難なため、専用のリース管理システムまたはERPの拡張が重要です。
◇ 必須機能・改修ポイント
・✅ リース台帳管理機能
◦契約ごとの使用権資産・リース負債の残高管理
・✅ リース料スケジュール計算
◦割引率に基づくリース負債の現在価値計算
・✅ 会計仕訳自動化
◦初期計上、利息費用、減価償却仕訳の自動生成
・✅ IFRSや日本基準の両建て対応(多基準対応)
◦海外子会社との整合が必要な場合、IFRS対応も視野に
・✅ 開示情報出力
◦注記に必要な期間別支払額、割引率、加重平均リース期間などの情報を自動集計
◇ 導入・改修時のチェックポイント
| チェック項目 | 解説 |
| 現行システムの機能把握 | 現在使用している会計・契約管理システムがリース対応しているか確認 |
| ベンダーとの連携体制 | 会計基準改正に対応可能なアップデートの提供有無 |
| 中長期的な拡張性 | IFRS対応やグローバル展開も見据えた柔軟性のある設計かどうか |
| 担当者教育・操作性 | 経理部門が日常的に使えるUI・操作フローの確認 |
| システムテストの実施 | 試算計算・帳票出力・仕訳連携など事前検証が重要 |
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
2027年4月から施行される新リース会計基準は、借手側に原則すべてのリース契約を資産・負債として計上することを求めています。これにより、財務諸表や財務指標、資金調達戦略、さらには会計システムの運用にも大きな影響が出ることが予想されます。
税理士としては以下の対応が重要です:
・顧問先のリース契約を洗い出し、影響を事前に把握する
・会計処理の変更点(減価償却+利息計上)とその指標への影響を説明できるようにしておく
・システムや内部統制の整備方針についてもアドバイスできる体制を整える
単なる仕訳の話にとどまらず、経営判断・IR・金融機関対応にまで関わる改正です。
今こそ、会計の専門家としての力を発揮するタイミングです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















