INDEX
おすすめ記事
-
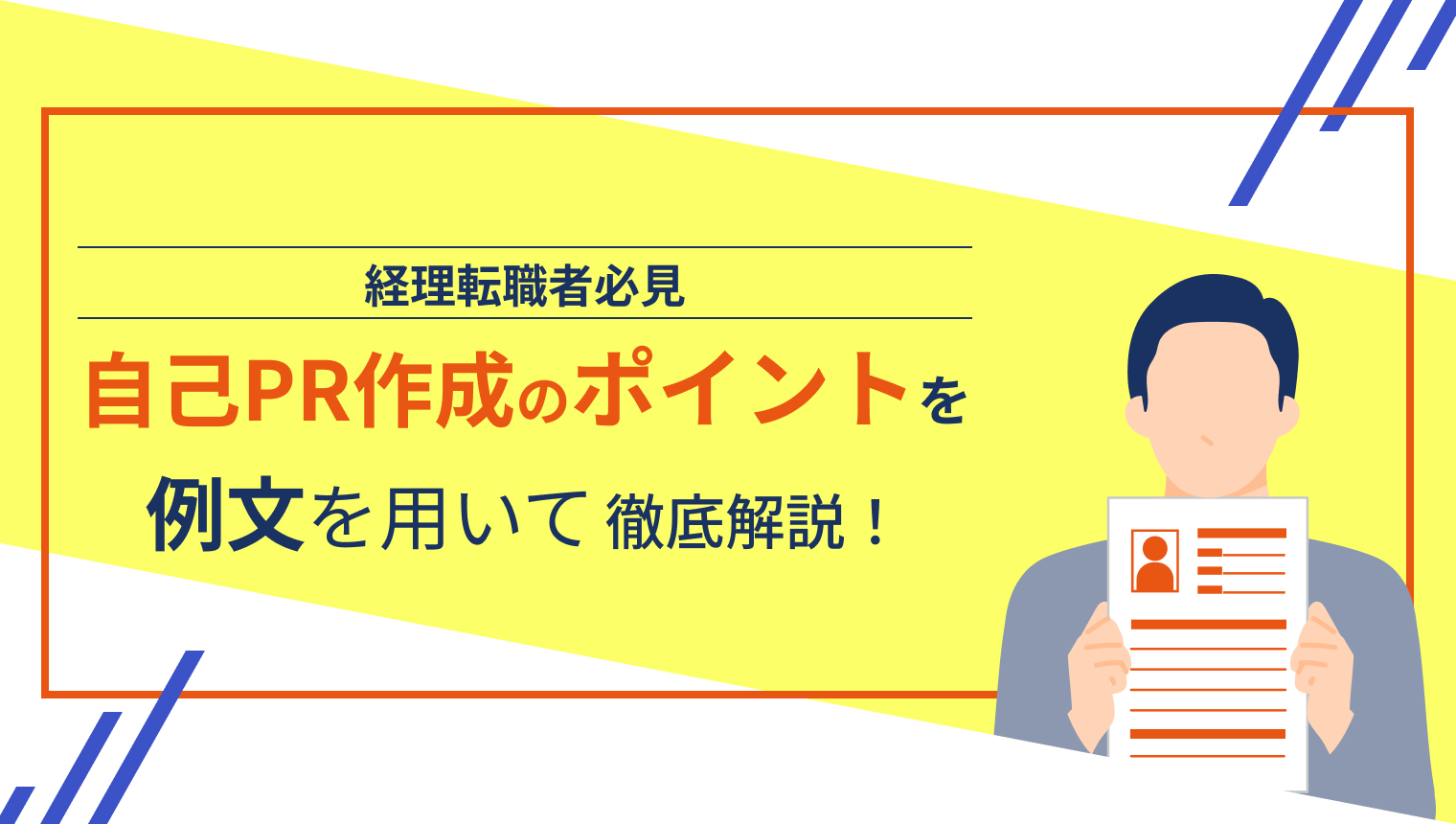
【経理転職者必見】経理の自己PR作成のポイントを例文を用いて徹底解説!
-
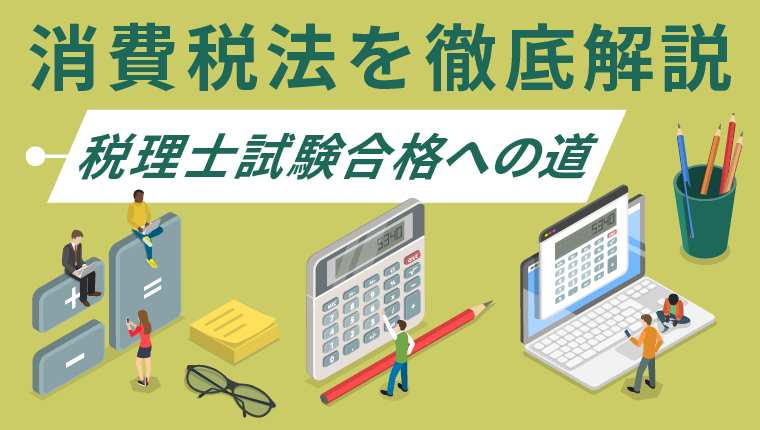
消費税法を徹底解説|税理士試験合格への道
-
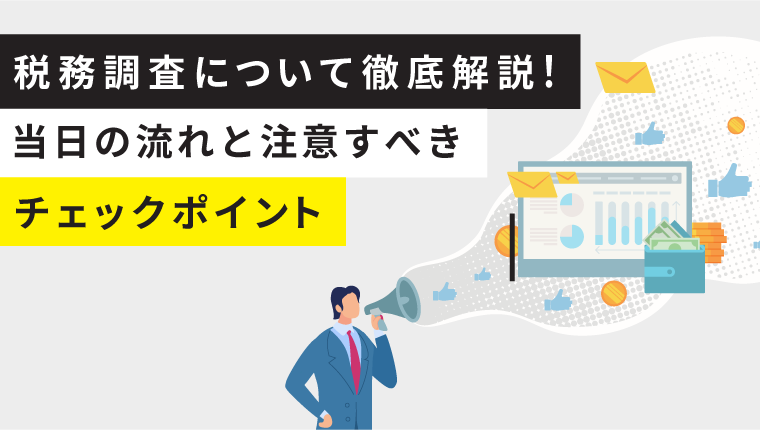
税務調査とは?当日の流れと注意すべきチェックポイントを税理士が徹底解説!
-
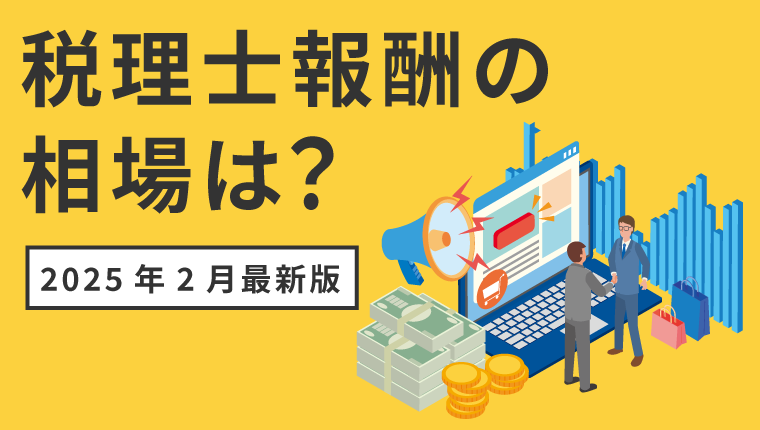
税理士報酬の相場は?2025年最新版
-
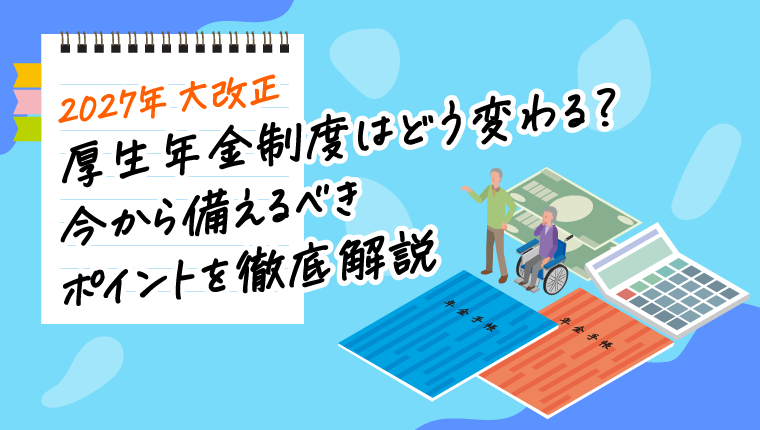
【2027年 大改正】厚生年金制度はどう変わる?今から備えるべきポイントを徹底解説
公開日:2025/04/10
最終更新日:2025/12/17

INDEX
2024年度税制改正により、外形標準課税の適用対象法人が見直され、税務対応の重要性が一段と増しています。
本稿では、外形標準課税の基本的な仕組みから、計算方法、申告手続き、そして令和6年改正による変更点までを体系的に整理します。
外形標準課税は、法人事業税の一部として、利益の有無にかかわらず、企業規模に応じて課税が行われる制度です。
特に赤字法人であっても、一定規模の人件費や資本金がある場合には課税が発生するため、顧問先企業にとっての影響は小さくありません。
また、近年では「減資による課税逃れ」や「大企業による子会社活用」への対応として、制度の厳格化が進んでいます。
会計事務所としては、単なる申告書作成にとどまらず、資本政策やグループ内再編に関する助言にも影響する論点です。
顧問先からの信頼を高めるためにも、改正内容を正確に把握し、実務にどう落とし込むかを検討する必要があります。
本記事が、皆さまの税務実務の一助となれば幸いです。
年収をシミュレーションしてみませんか?
簡単な質問に答えるだけで、一般的な会計事務所ならいくら提示されるのかを即座に算出。「今の適正額」はもちろん、「資格を取得したら年収はどう変わるのか?」など、あなたの現在地と未来の可能性を診断します。
外形標準課税とは?
外形標準課税とは、企業の利益(所得)だけでなく、事業の規模(=外形)に着目して課税する方式を取り入れた法人事業税の一種です。具体的には、企業がどれだけの利益を上げたかにかかわらず、人件費や支払利息、資本金といった企業活動の規模そのものに基づいて課税する仕組みです。この課税方式は、地方税のひとつである「法人事業税」の中に組み込まれています。
外形標準課税の基本概要
従来の法人事業税は、企業の所得(利益)に基づいて課税される「所得割」が中心でしたが、外形標準課税の導入により、「付加価値割」および「資本割」という新たな課税区分が加わりました。
・所得割:従来通り、企業の利益に応じて課税されます。
・付加価値割:企業が支払った人件費や利息、純利益などを基に計算されます。
・資本割:企業の資本金や資本準備金に基づいて課税されます。
このように、外形標準課税では、赤字であっても人件費や資本が一定以上であれば税負担が生じる点が特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税の種類 | 地方法人税(法人事業税の一部) |
| 課税根拠 | 地方法人税法および地方税法 |
| 課税方式 | 所得割+外形標準課税(付加価値割・資本割) |
| 外形とは | 企業の「事業規模」を示す指標(売上、人件費、資本金など) |
| 構成 |
- 所得割:利益に基づく課税 - 付加価値割:人件費+支払利息+純利益など - 資本割:資本金や資本準備金の額 |
導入された背景
外形標準課税が導入された背景には、以下のような複数の目的がありました。
1.税収の安定化
企業の利益は景気の変動により大きく変動しますが、企業規模は比較的安定しているため、これに基づく課税により地方自治体の税収が安定すると期待されました。
2.課税の公平性の確保
利益が出ていない赤字企業であっても、一定の規模で人件費を多く支払っていたり、巨額の資本を保有している場合があります。そうした企業にも一定の負担を求めることで、税の公平性を図ろうとしました。
3.租税回避の抑制
一部の大企業が、さまざまな会計操作や税制上の優遇を利用して法人税負担を抑えているという指摘があり、利益がゼロでも大規模な事業を展開している企業にも適正な税負担を求めるための措置として導入されました。
このような背景から、2004年度(平成16年度)の税制改正により、外形標準課税が本格的に導入されました。
| 背景の要素 | 内容 |
|---|---|
| 税収の安定化 | 景気変動に左右されにくく、安定した税収確保を目的とした |
| 課税ベースの拡大 | 利益が出ていない企業でも、一定の規模があれば課税することで公平性を図る |
| 大企業の税逃れ対策 | 赤字でも高額報酬を出していたり、事業規模の大きい企業に対しても一定の負担を求める |
| 地方財政の確保 | 地方自治体の財源確保手段として、より安定した仕組みが求められた |
対象法人
外形標準課税の対象となるのは、原則として資本金が1億円を超える大企業です。中小企業にあたる資本金1億円以下の法人については、外形標準課税の対象外となり、従来どおり所得に基づく課税(所得割)のみが適用されます。
ただし、資本金が1億円以下であっても、大企業の100%子会社など一定の要件を満たす企業は、外形標準課税の対象となる場合があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本対象 | 資本金1億円超の大法人 |
| 適用除外 | 中小企業(資本金1億円以下)は外形標準課税の対象外(所得割のみ) |
| その他の条件 | 資本金が1億円以下でも、特定の大企業の子会社などは対象になる場合あり |
外形標準課税の計算方法
外形標準課税では、法人事業税が次の3つの要素で構成されています。
| 区分 | 課税対象 | 主な構成要素 |
|---|---|---|
| 所得割 | 法人の所得(利益) | 課税所得 × 所得割税率 |
| 付加価値割 | 企業の付加価値 | 人件費、支払利息、純利益など |
| 資本割 | 資本金と資本準備金 | 資本金等の額 × 資本割税率 |
所得割
所得割は、従来どおり法人の「課税所得」に基づいて計算されます。
■ 計算式:
所得割額 = 課税所得 × 所得割の税率(都道府県によって異なるが概ね3.5%〜6.0%)
■ 例(税率5%の場合):
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 課税所得 | 1,000万円 |
| 所得割税率 | 5.0% |
| 所得割額 | 50万円 |
付加価値割
付加価値割は、企業の事業活動から生み出された「付加価値」に課税されます。以下のように計算されます。
■ 計算式:
付加価値額 = 営業利益 + 支払給与 + 支払利息 + 租税公課 付加価値割額 = 付加価値額 × 付加価値割の税率(例:1.2%)
■ 例:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 営業利益 | 500万円 |
| 支払給与 | 2,000万円 |
| 支払利息 | 100万円 |
| 租税公課 | 50万円 |
| 付加価値額 | 2,650万円 |
| 税率(例) | 1.2% |
| 付加価値割額 | 31.8万円 |
資本割
資本割は、企業の資本金などの規模に応じて課税されます。
■ 計算式:
資本割額 = 資本金等の額 × 資本割の税率(例:0.5%)
■ 例:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 資本金等 | 5億円 |
| 税率(例) | 0.5% |
| 資本割額 | 250万円 |
付加価値割の計算方法
計算方法
付加価値割では、企業の事業活動によって生み出された「付加価値額」に対して課税されます。具体的には以下のような構成要素を合算して付加価値額を算出し、それに税率を掛けて付加価値割額を計算します。
付加価値額 = 営業利益(所得金額)+報酬給与額+純支払利子額+純支払賃貸料+その他の加減調整項目
付加価値割額 = 付加価値額 × 税率(例:1.2%)
報酬給与額の算定
役員や従業員に支払った給与・賞与などの金額の合計です。
| 含まれるもの | 含まれないもの |
|---|---|
| 給与、賞与、手当等 | 福利厚生費、退職金、法定福利費など |
■ ポイント:
・法人税法上の損金算入額が基準
・社外役員や派遣社員への報酬も含まれる場合があります
純支払利子額の算定
支払利子から受取利子等を差し引いて計算します。
■ 計算式:
純支払利子額 = 支払利子等 − 受取利子等
| 支払利子等の例 | 受取利子等の例 |
|---|---|
| 借入金の利子、社債利息など | 預金利息、貸付利息など |
純支払賃貸料の算定
支払賃貸料から受取賃貸料を差し引いて計算します。
■ 計算式:
純支払賃貸料 = 支払賃貸料 − 受取賃貸料
| 支払賃貸料の例 | 受取賃貸料の例 |
|---|---|
| オフィス・機械の賃料 | 不動産の貸付収入など |
その他の調整
付加価値額を適正化するために加減算が行われる項目です。
| 代表的な調整項目 | 内容 |
|---|---|
| 交際費の損金不算入部分 | 一部加算される |
| 寄附金の一部 | 損金不算入部分が加算される場合がある |
| その他調整 | 税務会計と地方税会計の差異を是正するための加減算項目 |
外形標準課税の申告手続き
外形標準課税は、法人事業税の一部として都道府県に申告・納付する必要があります。対象となる法人(主に資本金1億円超の法人)は、事業年度ごとに法人税と併せて申告・納税を行います。
申告の流れと必要書類
申告の流れは以下の通りです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 会計決算の確定 | 事業年度末後、会計処理を行い、決算書類を作成します。 |
| 2. 法人税申告書の作成 | 税務調整を行い、法人税等の申告書を作成します(別表四・五など)。 |
| 3. 外形標準課税の申告書作成 | 法人事業税に関する申告書(付加価値割・資本割・所得割)を作成します。 |
| 4. 都道府県への提出 | 事業所等がある各都道府県に、法人事業税の申告書を提出します。複数の都道府県にまたがる場合は、各自治体に按分して申告。 |
| 5. 納税 | 法人税の納付とあわせて、事業税(外形標準課税を含む)も納付します。期限は原則として決算日から2か月以内。延長申請も可能。 |
また、必要な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 内容・備考 |
|---|---|
| 法人事業税申告書(第六号様式) | 外形標準課税を含む法人事業税の基本申告書です。 |
| 付加価値割・資本割に関する明細書 |
外形標準課税の内訳を記載します。以下の2つ: ・付加価値額等に関する明細書 ・資本金等に関する明細書 |
| 法人事業税・地方法人特別税申告書別表 | 法人事業税に関する計算過程を記載します。 |
| 法人税申告書の写し(別表四・五など) | 地方税の課税所得計算の基礎資料として必要です。 |
| 決算書(損益計算書・貸借対照表など) | 計算根拠として添付が必要な自治体が多いです。 |
2024年(令和6年)税制改正における外形標準課税の見直し内容
1. 減資への対応
従来、外形標準課税の対象法人は「資本金1億円超」の法人とされていました。しかし、一部の大企業が資本金を1億円以下に減資することで課税を回避する事例が見られたため、以下の基準が追加されました
・新たな対象基準:
◦前事業年度に外形標準課税の対象であった法人で、当事業年度に資本金1億円以下、かつ資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える法人は、引き続き外形標準課税の対象となります。
・適用開始時期:
◦2025年(令和7年)4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
2. 100%子法人等への対応
大企業が子会社の資本金を1億円以下に設定し、外形標準課税の適用を回避するケースに対応するため、以下の基準が設けられました。
・新たな対象基準:
◦資本金と資本剰余金の合計額が50億円超の法人(特定法人)の100%子法人等で、資本金1億円以下、かつ資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超える法人も、外形標準課税の対象となります。
・適用開始時期:
◦2026年(令和8年)4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
これらの改正により、形式的な資本金の調整による課税回避を防ぎ、税負担の公平性を確保することが目的とされています。
年収をシミュレーションしてみませんか?
簡単な質問に答えるだけで、一般的な会計事務所ならいくら提示されるのかを即座に算出。「今の適正額」はもちろん、「資格を取得したら年収はどう変わるのか?」など、あなたの現在地と未来の可能性を診断します。
まとめ
この記事では外形標準について説明しました。
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)



















