INDEX
おすすめ記事
-

簿記論 合格率の推移と傾向|過去10年データからわかる合格のコツ【2026年最新版】
-
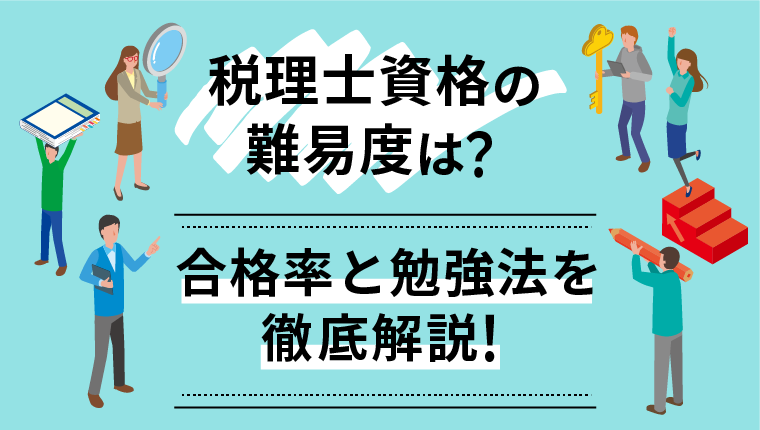
税理士資格の難易度は?合格率と勉強法を徹底解説!
-
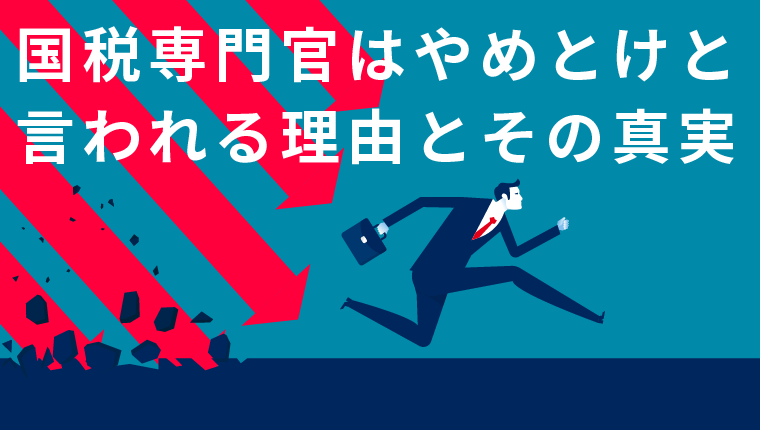
国税専門官はやめとけと言われる理由とその真実
-
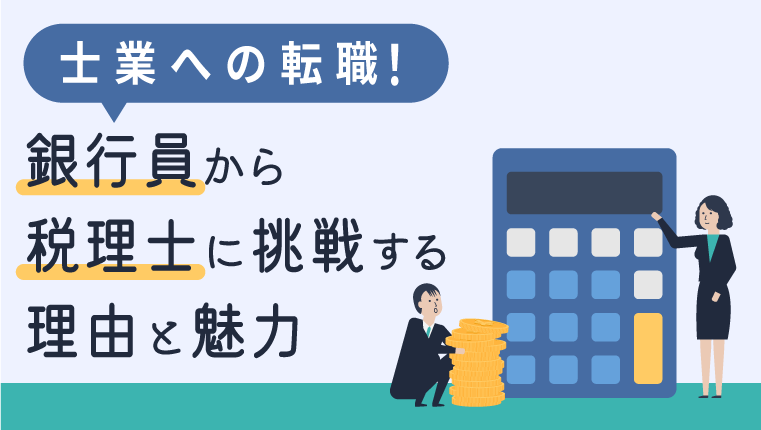
士業への転職!銀行員から税理士に挑戦する理由と魅力
-

巡回監査士補の需要と今後の展望|業界の最新情報
公開日:2025/04/17
最終更新日:2025/09/06

INDEX
2025年、超富裕層に対する新たな課税措置「ミニマムタックス」がスタートします。 これは、いわば“最後の防波堤”。年間所得が一定額を超える個人に対し、最低22.5%の税負担を求める仕組みです。 株式譲渡や配当などの金融所得に偏った納税者の税率が、年収1億円を超えたあたりからむしろ下がっていく「1億円の壁」問題──その是正を狙いとしています。
対象となるのは、年間合計所得が30億円以上の個人、または金融所得主体で10億円以上のケース。 NISAやスタートアップ再投資(エンジェル税制)などは除外されますが、実質的に株式・不動産譲渡益を中心とした超富裕層には広く影響します。
税理士にとって重要なのは、単なる追加計算の対応ではありません。 ミニマムタックスの適用可否の判定から、資産構成・取引履歴の精査、非課税枠の最適活用提案まで──高度な資産税アドバイザリー業務が求められます。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
ミニマムタックスとは?
ミニマムタックスとは、一定以上の所得を得る超富裕層に対し、最低22.5%の税負担を課すことを目的とした追加課税制度です。
2025年(令和7年)分の所得から適用され、所得の大半を金融所得(株式譲渡益、配当、不動産譲渡益など)で構成する高所得者に対して、既存の所得税では軽課されがちな構造を是正します。
本制度は、2022年に取りまとめられた令和5年度税制改正大綱に盛り込まれたもので、所得税制の公平性を回復するための措置として位置付けられています。
基本概念
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 |
- 年間合計所得が30億円超の個人 - 金融所得が主体の場合、10億円超でも対象となる可能性 |
| 課税方法 | 通常の所得税額と、以下の式で計算される「最低負担額」を比較し、不足していれば差額分を追加納税 |
| 最低負担額の計算式 | (合計所得金額 - 3.3億円) × 22.5% |
| 対象となる所得 | 給与・事業所得、譲渡所得(株式、不動産)、配当など |
| 除外される所得 |
- NISAによる非課税所得 - スタートアップ再投資(エンジェル税制) - 源泉分離課税の預金利子など |
この制度により、従来15.315%(所得税+復興特別所得税)で課税されていた株式譲渡益・配当所得だけでは、税負担が軽すぎると判断された層に、追加的な納税を求める構造となっています。
導入の目的と背景
▶ 「1億円の壁」の是正
日本の所得税は累進課税制度を採用していますが、所得が1億円を超えるあたりから実効税率が下がってしまう現象が確認されています。これは、給与や事業所得に代わり、税率の低い分離課税の金融所得が中心になるためです。
財務省資料(2022年公表)によれば、所得1億円を超えた納税者の所得構成のうち、約50%以上が株式譲渡・配当・不動産譲渡などであり、結果として「高額所得者ほど税率が低い」という逆進性が発生していました。
▶ 国際的な課税強化の流れ
欧米主要国(イギリス・フランス・ドイツなど)でも、超富裕層への課税強化が進んでおり、日本もこれに足並みを揃える形での制度導入となります。国際的な金融取引やクロスボーダー資産移転が進む中で、国境を越えても一定の負担を求めるという国際協調的な課税原則にも基づいています。
▶ 中間層への配慮
金融所得全体の税率を一律引き上げれば、中間層の投資意欲が低下するリスクがあります。
そのため、今回のミニマムタックスでは、極めて高所得な層に課税対象を限定し、制度の公平性と資産運用促進を両立させる設計としています。
実務への影響
2025年から日本で導入される「ミニマムタックス」は、企業および個人に対して新たな税務上の影響をもたらします。以下に、企業と個人所得への主な影響を整理しました。
企業への影響
✅ 富裕層オーナーを抱える企業の税務アドバイスが複雑化
オーナー経営者が高額の配当や譲渡益を得る場合、企業の資本政策や配当戦略がミニマムタックスに影響を与えることになります。
これにより、企業の財務戦略と個人の税務戦略が密接に連動し、税理士・財務アドバイザーの役割が重要に。
✅ IPO・M&A戦略の見直し
IPO後の株式売却益やストックオプションの行使に伴う金融所得が多額になると、創業者などがミニマムタックスの対象となる可能性があり、出口戦略の設計に影響します。
✅ 人材誘致や報酬制度にも影響
高額報酬や株式報酬を活用するスタートアップや外資系企業では、優遇されていた金融所得の税率が引き上げられることで、報酬設計の見直しが必要になるケースも。
個人所得への影響
個人に対するミニマムタックスは、2025年分の所得から適用され、超富裕層を対象とした追加課税措置です。
✅ 金融所得中心の人に新たな税負担
株式譲渡益・配当・投資信託など金融商品での所得が主な収入源となっている超富裕層は、**通常よりも高い税負担(22.5%)**が求められるようになります。
✅ 所得構成の見直しが必要に
これまで、金融所得に偏らせることで実効税率を抑えていた資産家や投資家は、今後は所得の構成を見直す必要性が生じます(例:事業所得とのバランス、再投資の活用など)。
✅ 税務申告の難易度上昇
ミニマムタックスの判定には、所得の総額だけでなく構成比(金融所得の割合)や控除対象の精査が必要なため、税理士による高度な判断と正確な申告が求められます。
ミニマムタックスの課税対象
2025年から導入される「ミニマムタックス」は、超富裕層を対象とした新たな課税制度です。この制度の課税対象となる所得層と、超富裕層への具体的な影響について詳しく解説します。
課税対象となる所得層
ミニマムタックスの対象は、以下のような高所得者層です。
✅ 年間合計所得が30億円以上の個人
給与所得、事業所得、株式譲渡益、不動産譲渡益など、すべての所得を合算した金額が30億円を超える個人が対象となります。
✅ 金融所得が主な収入源で年間所得が10億円以上の個人
金融所得(株式譲渡益や配当など)が主な収入源で、年間所得が10億円以上の場合も対象となる可能性があります。
ただし、以下のような所得はミニマムタックスの課税対象から除外されます。
・NISA口座での譲渡所得や配当所得
・スタートアップへの再投資による非課税所得(エンジェル税制)
・源泉分離課税の対象となる所得(預貯金の利子など)
超富裕層への影響
ミニマムタックスの導入により、超富裕層には以下のような影響が生じます。
1. 追加納税の発生
通常の所得税額が、以下の計算式で求められる「最低所得税額」を下回る場合、その差額分を追加で納税する必要があります。
(合計所得金額-3.3億円)×22.5%-通常の所得税額=追加納税額
例えば、年間所得がすべて金融所得で10億円の場合、通常の所得税額は1億5,000万円ですが、ミニマムタックス適用後は1億5,075万円となり、追加納税額は75万円となります。
2. 資産運用戦略の見直し
金融所得が多い場合、ミニマムタックスの影響を受けやすいため、資産運用の方法や投資先の見直しが必要となる可能性があります。
3. 税務対策の必要性
スタートアップへの再投資やNISAなど、非課税措置を活用することで、ミニマムタックスの影響を軽減することが可能です。これらの制度を適切に活用するためには、事前の計画と専門的な知識が必要です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | ミニマムタックス(超富裕層向け最低税負担制度) |
| 開始時期 | 2025年(令和7年)分の所得から適用 |
| 課税対象者 |
- 年間合計所得が30億円以上の個人 - 金融所得主体で年間所得が10億円以上の可能性あり |
| 対象所得 | 給与・事業所得、譲渡所得(株式・土地建物)などの合計所得金額 |
| 除外される所得 |
- NISAによる非課税所得 - スタートアップ再投資の非課税枠(エンジェル税制) - 源泉分離課税の利子等 |
| 最低税率 | 22.5%(※控除額3.3億円を差引後に適用) |
| 追加納税額の計算式 | (合計所得金額-3.3億円)×22.5%-通常の所得税額 |
| 例:所得10億円 |
- 通常の所得税(15%想定)=1億5,000万円 - ミニマムタックス=1億5,075万円 - 追加納税:75万円 |
| 影響① | 超富裕層への追加課税発生(税負担の底上げ) |
| 影響② | 資産運用戦略の見直しが必要(金融資産中心の構成だと影響大) |
| 影響③ | 確定申告の複雑化(通常税計算+ミニマムタックス計算) |
| 影響④ | 非課税制度の活用が重要(NISA・再投資特例など) |
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
ミニマムタックスとは? -まとめ-
2025年から導入される「ミニマムタックス」は、超富裕層に対して最低限の税負担を求める新たな個人課税制度です。対象は年間合計所得が30億円以上の個人、または金融所得中心で10億円以上の所得を持つ層で、通常の所得税額が最低税額(22.5%)に満たない場合、その差額を追加納税する必要があります。
これにより、「1億円の壁」に象徴される逆進的な課税構造が是正される一方で、対象者には資産運用や確定申告の見直しが求められます。
税理士にとっては、計算・申告支援に加え、NISAやエンジェル税制などの非課税制度を組み込んだ高度な資産税対策が重要なコンサルティング業務になるでしょう。実務対応と顧客コミュニケーションの双方で、専門知識が強く問われる制度です。
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















