INDEX
おすすめ記事
-
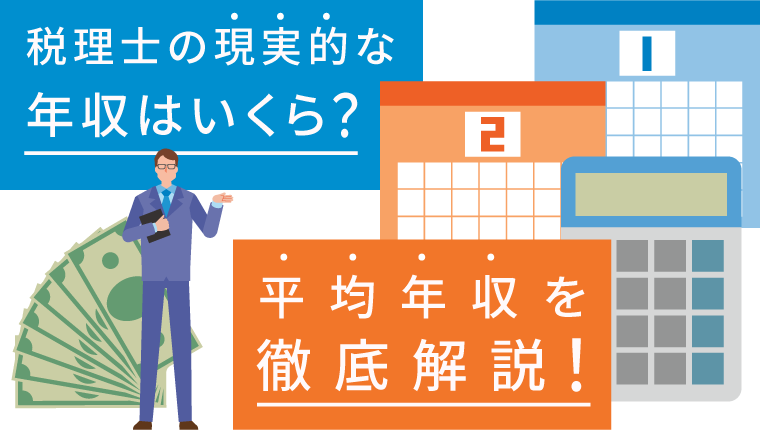
税理士の現実的な年収はいくら?平均年収を徹底解説!
-
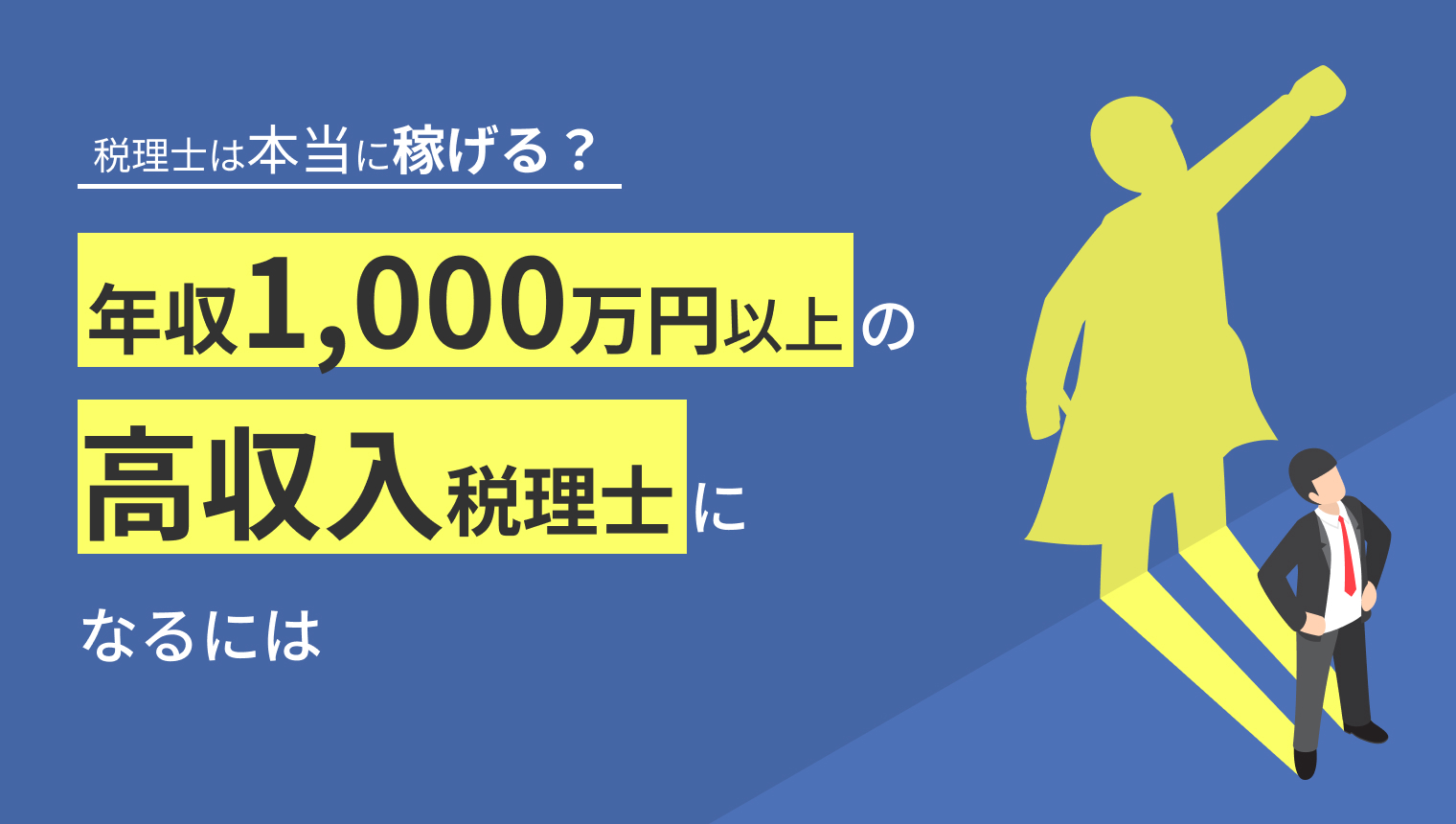
税理士は本当に稼げる?年収1000万円以上の高収入税理士になるには
-
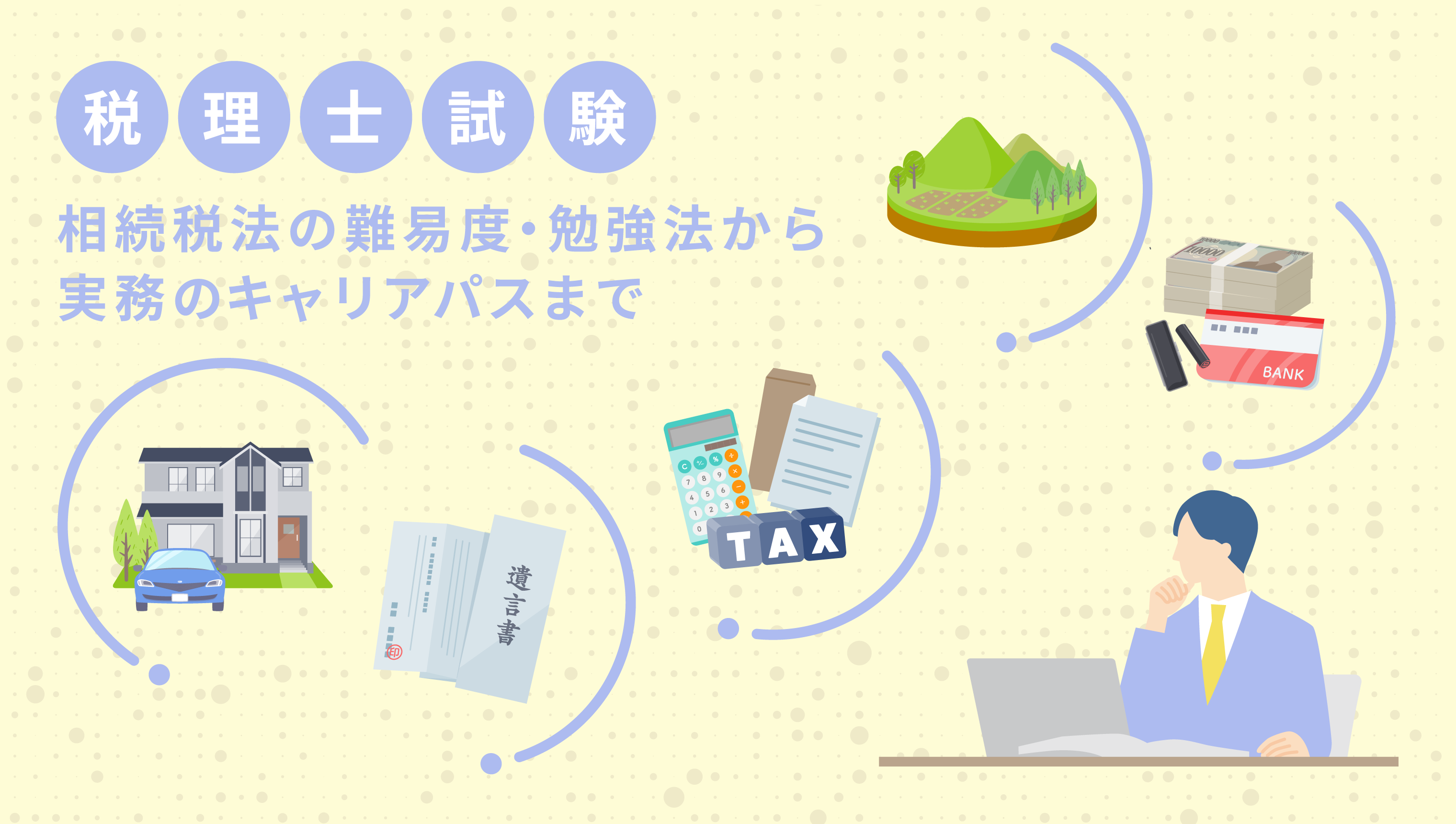
【税理士試験】相続税法の難易度・勉強法から実務のキャリアパスまで
-
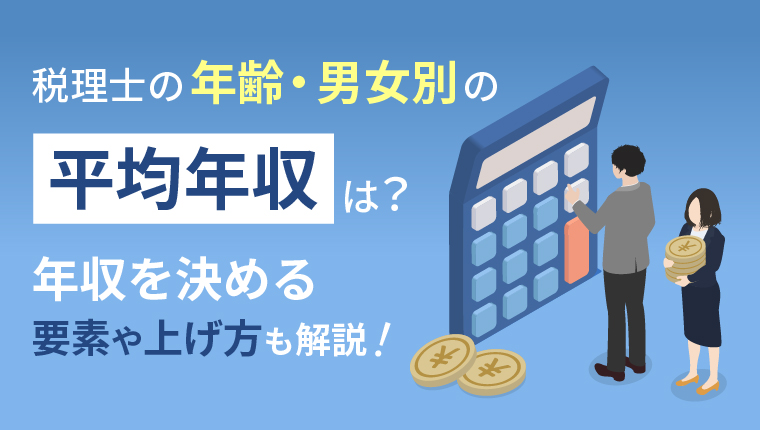
税理士の平均年収はいくら?税理士の年収を決める要素や年収の上げ方を解説!
-
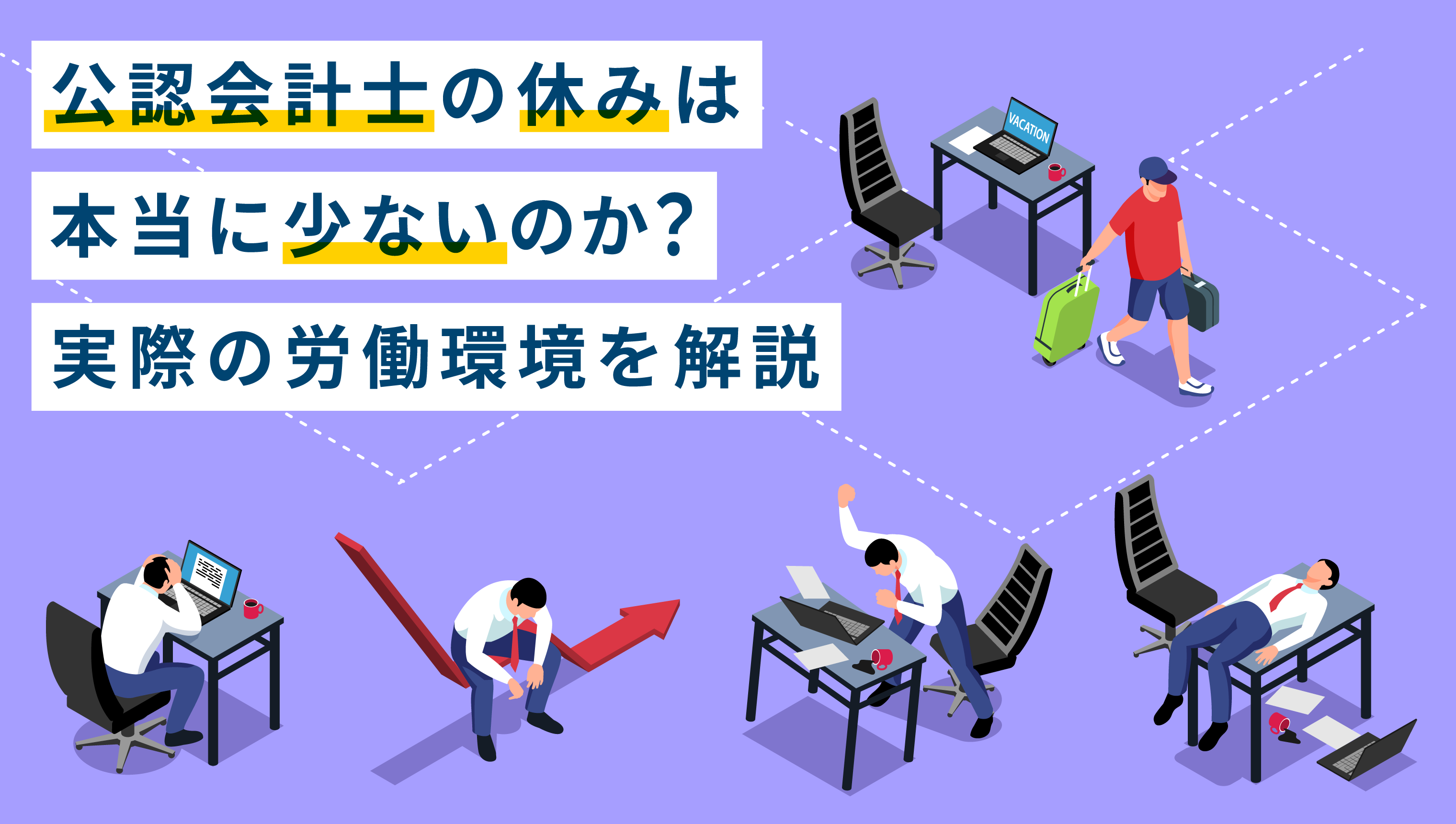
公認会計士の休みは本当に少ないのか?実際の労働環境を解説
公開日:2025/04/30
最終更新日:2025/12/17

INDEX
令和8年、生命保険料控除に関する一時的な特例措置が導入されるのをご存じでしょうか。
対象は「23歳未満の扶養親族がいる納税者」で、一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円へ拡大されます。
控除総額の上限(12万円)は据え置きのため、介護医療・年金控除との兼ね合いにも要注意です。
「年末調整の記載ミス」「証明書の提出漏れ」など、実務上のトラブルを防ぐには、事前の社内共有がカギになります。
扶養控除見直しの影響とあわせて、子育て世帯を中心に節税提案の好機となる可能性もあります。
本記事では、拡充の背景・内容・実務上の注意点をわかりやすく整理しました。
年末調整・確定申告に備え、職員全員で共通認識を持っておくことが重要です。
顧客対応で“信頼される事務所”であるために、ぜひこの制度の要点を押さえておきましょう。
年収をシミュレーションしてみませんか?
簡単な質問に答えるだけで、一般的な会計事務所ならいくら提示されるのかを即座に算出。「今の適正額」はもちろん、「資格を取得したら年収はどう変わるのか?」など、あなたの現在地と未来の可能性を診断します。
生命保険料控除の基礎知識
生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、納税者が一定の条件を満たす生命保険料を支払った場合に、その金額の一部を所得から差し引くことができる制度です。
これにより、課税対象となる所得金額が減少し、結果として所得税や住民税の税負担が軽減されます。
具体的には、保険料控除の対象となる契約(例:死亡保険、医療保険、年金保険など)に支払った金額に応じて、決められた計算式により控除額が算出されます。
生命保険料控除の仕組みと目的
| 項目 | 内容 |
| ✅ 対象となる保険 |
・生命保険(死亡保障など) ・介護医療保険(入院・手術・介護に対応) ・個人年金保険(老後資金形成を目的) |
| ✅ 控除の種類(新制度:平成24年以降) |
【3つの区分】 1. 一般生命保険料控除 2. 介護医療保険料控除 3. 個人年金保険料控除 |
| ✅ 控除額の上限(新制度) |
【所得税】各区分最大4万円、合計最大12万円 【住民税】各区分最大2.8万円、合計最大7万円 |
| ✅ 控除の目的 |
・自助努力による保障準備や老後資金形成を支援する ・公的社会保障制度の補完的な役割を果たす ・民間保険加入を促進し、国の財政負担を軽減する |
控除を受けるには、保険会社から発行される「生命保険料控除証明書」を用意し、次のいずれかの方法で手続きします。
1. 年末調整(給与所得者)
・毎年10月頃、保険会社から控除証明書が届きます。
・勤務先から配布される「保険料控除申告書」に必要事項を記入し、証明書とともに提出。
・正しく申請されれば、会社側で税額を調整してくれます。
2. 確定申告(自営業者・年末調整未対応者)
・所得税の確定申告時(翌年2月16日〜3月15日)に、控除証明書を添付して申請。
・国税庁の「確定申告書作成コーナー」を活用すると便利。
令和8年における控除額の拡充
拡充の背景と目的
令和8年(2026年)は、政府が掲げる子育て支援と税制改革の節目にあたる年です。 その一環として、子育て世帯への負担軽減と、将来的な保障への備えを後押しする目的で、「生命保険料控除」の制度が一部拡充されます。
背景
・少子化対策が喫緊の課題となる中、子育て世帯の経済的な支援強化が求められている。
・同時期に予定されている「扶養控除の見直し」により、一部の子育て世帯で税負担が増える可能性がある。
・民間の生命保険加入を通じて、自助努力によるリスク備えを支援したいという政府の意図。
目的
・✅ 子育て世帯の保険料負担への実質的な補助
・✅ 保障ニーズの高い層へのインセンティブ提供
・✅ 税制改正に伴う家計影響の緩和
| 観点 | 内容 |
| 子育て世帯の不安 | 万が一に備える生命保険の重要性が高いが、家計に余裕がないことが多い。 |
| 税制改革との連動 | 令和8年は「扶養控除の見直し」などの税制改正が予定されており、その“埋め合わせ”としての意味もある。 |
| インセンティブ設計 | 保険加入を促進することで、自助努力による保障形成を促したい。 |
具体的な拡充内容
この拡充は、23歳未満の扶養親族がいる世帯を対象とした、1年間限定(令和8年分のみ)の特例措置です。
拡充のポイント
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | 23歳未満の扶養親族がいる納税者(=子育て世帯) |
| 適用年 | 令和8年分(2026年)の所得税申告時 |
| 拡充内容 | 一般生命保険料控除の上限: 4万円 → 6万円に引き上げ(+2万円) |
| 他の控除(介護医療・年金) | 変更なし(各4万円のまま) |
| 所得税の合計控除上限 | 12万円で据え置き(超えた分は適用されない) |
| 住民税の控除 | 現時点では変更なし(上限7万円) |
具体的な効果(例)
たとえば課税所得500万円、所得税率20%の家庭であれば:
・従来:4万円 × 20% = 8,000円の節税
・拡充後:6万円 × 20% = 12,000円の節税
・差額 4,000円の軽減効果
拡充対象となる世帯と条件
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | 23歳未満の扶養親族がいる納税者(=主に子育て世帯) |
| 年齢の基準 | 原則としてその年の12月31日時点で23歳未満 |
| 適用年度 | 令和8年(2026年)分所得税のみ(1年間の時限措置) |
| 必要手続き | 保険会社発行の「控除証明書」を年末調整または確定申告で提出 |
生命保険料控除の申請方法
生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告で所定の手続きを行う必要があります。控除を受けることにより、所得税および住民税の負担を軽くすることができます。
必要な書類と作成手順
まず、控除申請には「生命保険料控除証明書」が必須です。これは、契約している保険会社から毎年10月頃に郵送または電子交付されるもので、年間の保険料支払額が記載されています。
給与所得者(会社員や公務員など)の場合は、勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に、生命保険料控除証明書の内容をもとに必要事項を記入し、会社に提出します。これがいわゆる年末調整の一環であり、正しく提出すれば自動的に控除が適用されます。
一方、自営業者や年末調整で控除の手続きをしなかった方は、確定申告によって控除申請を行います。この場合は、「確定申告書(第一表・第二表)」に加えて、控除証明書を添付し、税務署に提出する必要があります。国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで必要な書類を自動作成することができます。
申請時期と注意点
年末調整での申請は、勤務先が指定する期限までに申告書と控除証明書を提出する必要があります。通常、提出期限は11月中旬から12月上旬に設定されています。期限を過ぎると、年末調整での適用はされず、自分で確定申告をする必要があります。
確定申告の場合は、毎年2月16日から3月15日までの期間内に行うのが原則です。ただし、申告期限を過ぎてしまっても、最大5年以内であれば「更正の請求」により控除を受けることが可能です。
また、控除証明書を紛失してしまった場合には、保険会社に連絡すれば再発行してもらえますが、発行には時間がかかる場合もあるため、早めに手配しておくことが重要です。
子育て世帯への影響
令和8年に予定されている生命保険料控除の拡充は、23歳未満の扶養親族がいる世帯(=子育て世帯)を対象とした時限的な税制優遇措置です。
この措置により、保険料控除の枠が広がり、所得税の軽減額が増加することで、実質的な家計支援となります。
| 項目 | 内容 |
| 制度名 | 生命保険料控除の特例拡充(令和8年分 所得税のみ) |
| 対象者 | 23歳未満の扶養親族がいる納税者(主に子育て世帯) |
| 適用期間 | 令和8年分(2026年分)の所得税申告時のみ(時限措置) |
| 拡充内容 | 一般生命保険料控除の限度額が 4万円 → 6万円 に引き上げ |
| 控除上限(所得税) | 合計12万円(変更なし) ※介護医療保険料・個人年金保険料含む |
| 控除上限(住民税) | 現時点で変更なし(最大7万円) |
控除拡充が子育て世帯に与えるメリット
控除拡充の内容は、特に生命保険に加入している子育て世帯にとって、以下のようなメリットがあります。
✅ 家計へのプラス効果
・控除額上限の増加により、最大で2万円分の課税所得が追加で控除される
→ 所得税率10%の家庭なら約2,000円、20%なら約4,000円の税負担が軽減されます。
✅ 保険加入への後押し
・教育費などの支出が増える時期に、保険への加入・継続のインセンティブが得られる。
・万一に備えた保障の確保と、税制優遇の「ダブルのメリット」。
✅ 扶養控除見直しへの“埋め合わせ”
・同時期に予定されている扶養控除の縮小に対する、実質的な「税負担増緩和措置」として機能
| メリット項目 | 内容 |
| 家計負担の軽減 | 所得税の負担が軽減される(例:課税率20%なら最大4,000円の減税) |
| 保険加入の後押し | 税制優遇があることで、保険加入・継続のモチベーションに |
| 扶養控除見直しのカバー | 扶養控除縮小の代替措置として家計支援の役割を果たす |
子育て世帯が注意すべきポイント
この控除拡充の恩恵をきちんと受けるためには、以下の点に注意が必要です。
適用対象の明確化
・控除拡充の対象は「23歳未満の扶養親族」がいる場合に限定されます。 → 高校・大学・専門学校に通う子どもが対象になることが多いです。
期間限定(令和8年分のみ)
・この制度はあくまで「1年間限定の特例措置」です。 → 翌年以降も続くかは未定のため、令和8年に確実に申請しましょう。
証明書の提出漏れに注意
・保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」が必要。
・年末調整または確定申告の際に必ず提出すること。
控除の上限に注意
・一般生命保険控除の上限が6万円に増加しても、全体の控除合計は12万円(所得税)まで据え置き。
→ 他の控除(介護医療・個人年金)との兼ね合いに注意。
| 注意点 | 内容 |
| 対象条件の確認 | 扶養している子どもが「23歳未満」であることが必須 |
| 提出書類の漏れ | 保険会社から届く「控除証明書」を年末調整または確定申告時に提出 |
| 控除の競合 | 他の控除(医療・年金)との合計で12万円が上限なので注意 |
| 限定的な措置 | 令和8年の1年間だけの制度なので早めに活用を |
年収をシミュレーションしてみませんか?
簡単な質問に答えるだけで、一般的な会計事務所ならいくら提示されるのかを即座に算出。「今の適正額」はもちろん、「資格を取得したら年収はどう変わるのか?」など、あなたの現在地と未来の可能性を診断します。
まとめ
令和8年に予定されている生命保険料控除の拡充は、子育て世帯への支援強化と税制改革への対応を目的とした重要な時限的措置です。
以下の点を押さえておくことで、制度を最大限に活用することができます。
✅ ポイント整理
◇ 生命保険料控除とは?
→ 民間の保険料支払いに対する税負担軽減措置。対象契約は「一般」「介護医療」「年金」の3区分。
◇ 令和8年の拡充内容
→ 一般生命保険料控除の上限が4万円 → 6万円に引き上げ(所得税のみ)。
ただし控除総額の上限(12万円)は据え置き。
◇ 対象者
→ 23歳未満の扶養親族がいる納税者(=子育て世帯)
◇ メリット
・家計負担軽減(所得税が数千円〜6,000円前後軽減)
・保険加入のモチベーションUP
・扶養控除縮小のカバー
◇ 注意点
・対象は令和8年分(2026年分)所得税のみの1年限り
・控除証明書の提出が必須
・他の控除とのバランスを確認(合計12万円の枠を超えないように)
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)



















