INDEX
おすすめ記事
-
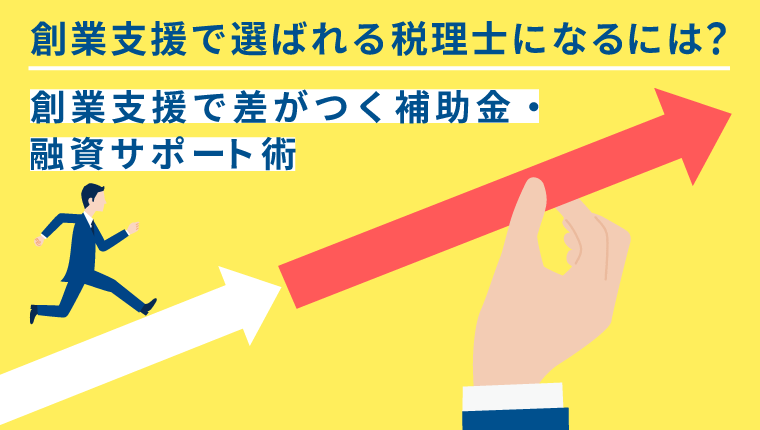
創業支援で選ばれる税理士になるには?創業支援で差がつく補助金・融資サポート術
-
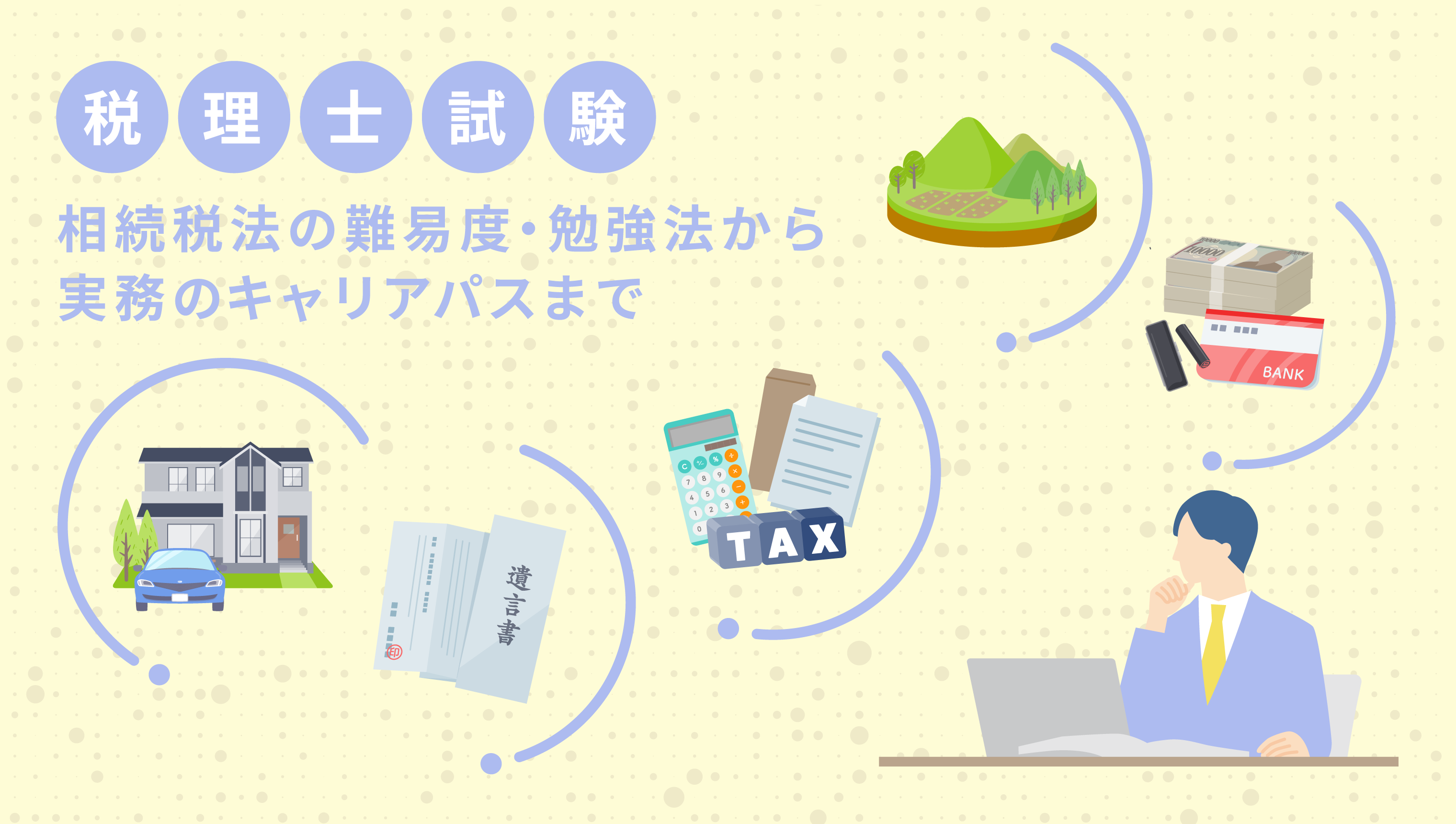
【税理士試験】相続税法の難易度・勉強法から実務のキャリアパスまで
-
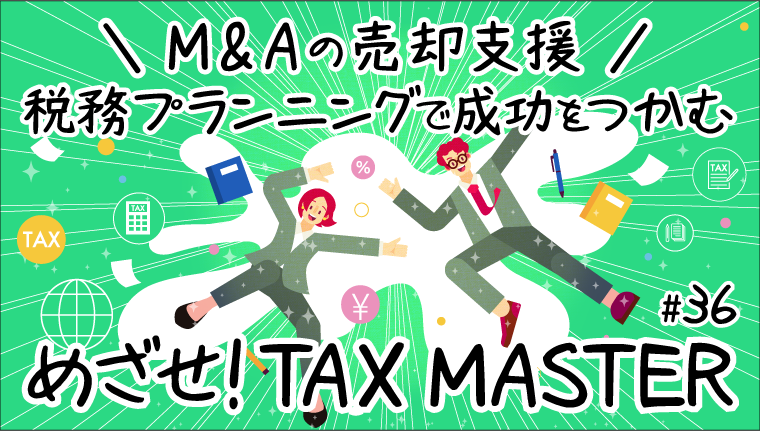
【M&Aの売却支援】税務プランニングで成功をつかむ【めざせ!TAX MASTER#36】
-
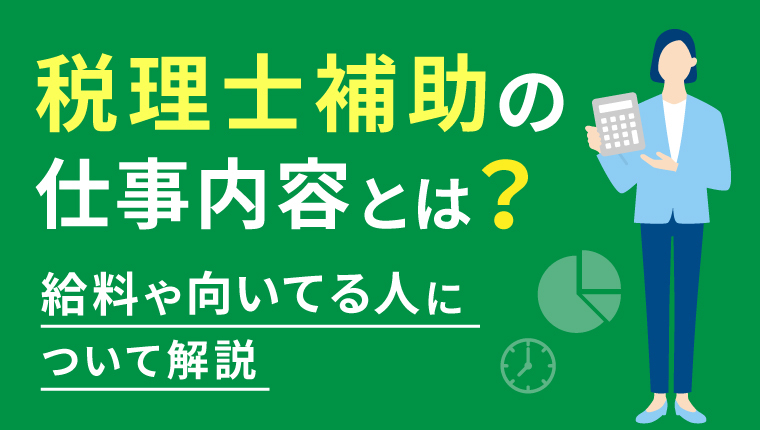
税理士補助の仕事内容とは?給料や向いてる人について解説
-

税理士の仕事内容とは?とある1日のリアルスケジュールを大公開!
公開日:2025/05/09
最終更新日:2025/09/06

INDEX
「固定資産税って、結局試験だけの話じゃないの?」
そう思っている人にこそ、知ってほしい。
この税目は、税理士試験で頻出なだけでなく、実務でもバリバリ使います。
特に償却資産の申告や住宅用地の特例、評価額の異議対応など──
ちょっとした知識の差が、顧問先の税負担や信頼に直結する世界。
試験で暗記した条文が、実務での「武器」になる瞬間は意外と多い。
だからこそ、合格を目指すなら“実務を意識した勉強”が効果的。
この記事では、固定資産税の試験知識と実務のつながりを、具体的な事例で解説します。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
固定資産税とは?その基本と法的背景
固定資産税の定義と役割
固定資産税とは、土地・家屋・償却資産などの固定資産を所有している者に対して、市町村(東京23区は都)が課税する地方税です。毎年1月1日現在の所有者に課税され、地域のインフラ整備や公共サービスの財源として用いられます。
対象資産:
◦土地(宅地・農地など)
◦家屋(住宅・事業用建物など)
◦償却資産(事業用の機械・器具備品など)
課税標準:
◦原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が基準。
◦評価替えは3年ごとに実施される(直近は2024年度)。
税率:
◦原則 1.4%(市町村が条例で変更可)
納税義務者:
◦毎年1月1日現在で、固定資産を所有している者(登記簿などに記載された名義人)
法改正が税理士試験に与える影響
税理士試験では「固定資産税」は、以下のような点で影響が出る可能性があります。
① 評価方法・特例措置の改正
・たとえば、住宅用地の軽減特例や小規模住宅用地の特例(課税標準1/6)などに見直しがあった場合、論点化されやすい。
・スマート農業用施設・再生可能エネルギー関連施設への特例導入も、近年注目されるテーマ。
② 評価替えの実施年度との連動
・評価替えの年(例:2024年度)は、評価額算出の仕組みや影響度が問われやすい。
・地価の動向に応じて、課税額変動の理論的背景も出題対象になりうる。
③ 償却資産課税に関する申告制度の変更
・例えば申告不要対象資産の見直しなどは、実務対応を問う出題が予想される。
税理士試験における固定資産税の位置づけ
試験における難易度の分析
難易度:★★★☆☆(中堅レベル)
| 観点 | 難易度の分析 |
| 学習負荷 | 他の主要税法(法人・所得)より範囲は狭いが、条文暗記と定義理解が必須。科目としては「学者肌」「公務員試験的」な色が強い。 |
| 合格率 | 合格率は概ね10〜15%前後(年により変動)。選択科目の中ではやや低め。 |
| 出題形式 | 理論問題中心(記述式)で、条文理解+事例への適用力が求められる。計算問題は限定的。 |
| 頻出トピック | 課税標準の決定方法 |
固定資産税に関する勉強方法
| ステップ | 内容 | ポイント |
| STEP1:基礎理解(インプット) | 条文・評価基準・特例制度を一通りインプット | ・市販の理論テキスト+法令集を併用 ・表や図で制度構造を整理する ・「土地」「家屋」「償却資産」で章立てして学ぶ |
| STEP2:条文暗記(定着) | 頻出条文を優先し、語句レベルで覚える | ・条文番号とキーワードの対応表を作成 ・1日10条ずつ+週末復習の「スパイラル学習」 ・アウトプット用に「穴埋め問題」活用 |
| STEP3:論点適用(アウトプット) | 過去問で事例を解き、記述に慣れる | ・10年分の本試験問題を分類整理 ・「住宅用地特例」などテーマごとに演習 ・予備校の模試や答練で文章表現力を養成 |
優先してマスターすべき固定資産税の論点
| 論点 | 理由 |
| 住宅用地の課税標準の特例(1/6) | 毎年のように出題される「王道テーマ」 |
| 償却資産の申告制度・評価方法 | 実務でも超重要、誤答が多いので差がつく |
| 固定資産評価基準(特に家屋評価) | 評価方式(再建築費方式など)の理解が要 |
| 評価替え(3年ごと)とその影響 | 評価時期と税額の関係性を整理しておく |
| 条例による特例・軽減措置 | 地方自治体の裁量による例外ルールの代表格 |
■ 合格者が実践した勉強法の紹介
使用ツール:
◦理論マスター
◦答練(基礎・応用・直前)
◦模試(全国公開模試)
◦過去問
合格者の勉強スケジュール例:
◦平日2時間:条文暗記+ミニテスト復習
◦休日5時間:答練の復習+本試験形式の論述練習
◦直前1ヶ月は間違った部分を確認
成功要因:
・講師の解説で「法文の言い回し」に慣れる
・自分で書いた答案を「採点者目線」で見直すクセをつけた
独学での合格は可能?
固定資産税は税法科目でも有、改正の影響等も考えると独学での勉強は望ましくありません。可能であれば、TACや大原等の予備校に通い学習を進めましょう。
固定資産税の実務解説
1. 実務で関与するケースの全体像
税理士が関与する主な固定資産税関連業務は、以下のとおりです。
| 実務領域 | 内容 | 対応タイミング |
| 償却資産申告 | 毎年1月末までに事業用資産を申告(所有者が市区町村へ) | 年初(1月) |
| 課税明細書の確認 | 市区町村から送付される明細をチェックし、金額・内容を精査 | 4〜5月頃 |
| 特例・減免の確認 | 小規模住宅用地特例、耐震改修減税、自治体独自の軽減措置など | 通年 |
| 顧客からの相談対応 | 「この資産に税金がかかる?」「評価額は妥当?」など | 随時 |
| 納付相談・異議申立て支援 | 不服申し立て(納税者異議申立)や誤課税への対応 | 5〜6月頃 |
2. 試験知識と実務の関連性
| 試験論点 | 実務へのつながり | 実務での活かし方 |
| 償却資産の評価方法 | 償却資産申告の際に正確な評価額算定が必須 | 顧問先が漏れなく・過大評価せずに申告できるようアドバイス |
| 住宅用地の課税標準の特例(1/6・1/3) | 課税明細で「なぜこの税額なのか」を説明できる | 課税根拠を示し、誤課税リスクをチェック |
| 評価替え制度(3年ごと) | 評価額の急変動の説明や問い合わせ対応に使える | 「今年なぜ評価が上がったか?」に根拠をもって回答 |
| 地方税法の条文構成 | 異議申立て・減免判断の際の根拠として活用 | 曖昧な制度にも法的裏付けをもって対応可能 |
3. 試験知識の業務への応用事例
事例1:償却資産の申告漏れを防ぐ
・背景:顧問先が新たに工場を建てたが、空調設備を「建物」として建築費に計上し、申告から漏れていた
・対応:税理士が評価基準に基づき「空調は償却資産」と指摘し、申告を修正
・試験知識:償却資産評価基準・対象資産の区分の理解
事例2:固定資産税が高すぎると相談された
・背景:顧問先が課税明細を見て「税額が高い」と不満
・対応:評価額・課税標準・税率の流れを説明し、1/6特例が適用されていない土地があったことを指摘
・試験知識:住宅用地特例の適用要件(面積・用途・登記名義)理解が必要
事例3:自治体独自の減免措置を発見
・背景:顧問先の倉庫が災害復旧中。市の条例で「災害減免措置」があったが未申請だった
・対応:市条例を調査し、申請サポート
・試験知識:地方自治体による条例課税の仕組み(地方税法+条例の2層構造)を理解していたことが鍵
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
この記事では固定資産税の勉強法について解説しました。
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















