INDEX
おすすめ記事
-

財務コンサルタントとは?財務コンサルの仕事内容から年収までを徹底解説!
-

税理士への不満ランキングTOP5|気を付けるべきポイントと改善策
-
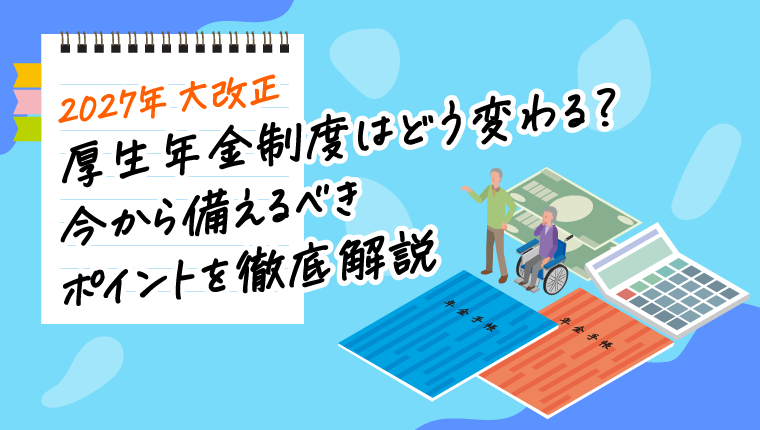
【2027年 大改正】厚生年金制度はどう変わる?今から備えるべきポイントを徹底解説
-
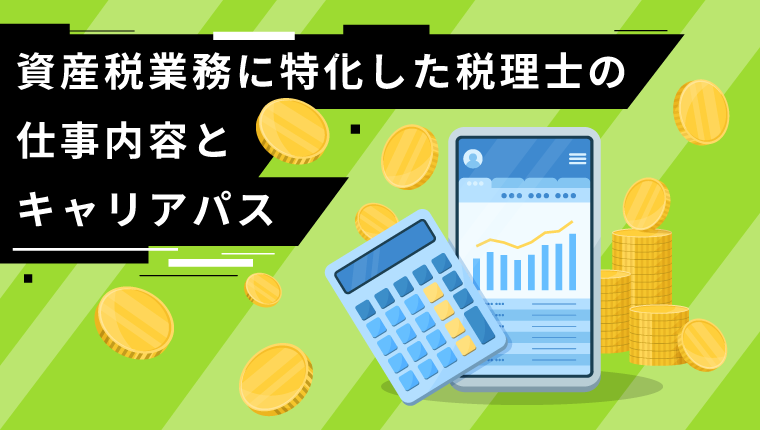
資産税業務に特化した税理士の仕事内容とキャリアパス
-
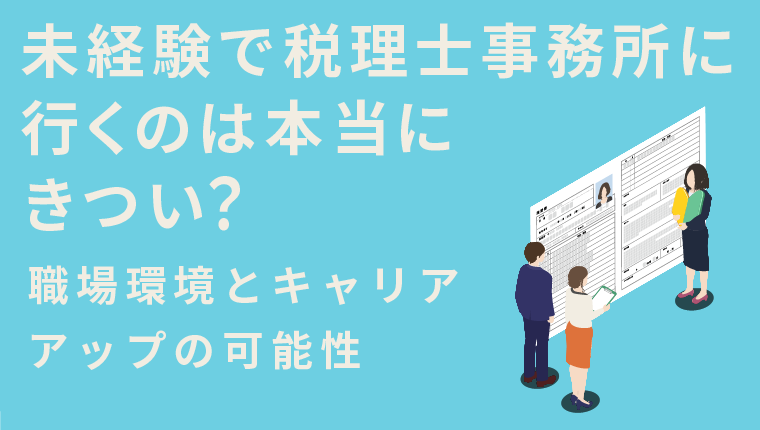
未経験で税理士事務所に行くのは本当にきつい?職場環境とキャリアアップの可能性
公開日:2025/05/02
最終更新日:2025/09/06

INDEX
「税理士になりたいけど、受験資格って難しいんでしょ?」そう思っているあなたに朗報です。
2023年度から、税理士試験の受験資格が大きく緩和され、チャレンジしやすくなりました。
特に会計科目(簿記論・財務諸表論)は、誰でも受験できるように改正されました。
これまで必要だった学歴や資格が不要となり、高校生や大学1・2年生でも挑戦可能に。
さらに、税法科目も「法律・経済」に限られていた履修要件が「社会科学」全体に広がり、文系の多くの学部が対象になりました。
この変化は、税理士を目指す人にとって大きなチャンスです。
本記事では、受験資格の詳細から緩和の背景、実際の影響までわかりやすく解説します。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士試験受験資格とは
税理士試験の受験資格は、試験科目によって異なります。
| 区分 | 対象科目 | 受験資格の種類 | 詳細条件 |
| 1. 会計学に属する科目 | 簿記論・財務諸表論 | 制限なし | 誰でも受験可能(学歴・職歴・資格不問) |
| 2. 税法に属する科目 | 所得税法、法人税法、相続税法、消費税法/酒税法、国税徴収法、住民税/事業税、固定資産税 | 学識による資格 |
・大学・短大・高専卒+社会科学系科目1科目以上履修 ・大学3年以上在学+62単位以上(社会科学系1科目以上含む) ・一定の専門学校修了+社会科学系1科目以上履修 ・司法試験合格者 ・公認会計士試験短答式合格(平成18年以降) |
| 資格による資格 |
・日商簿記1級 合格 ・全経簿記上級 合格(昭和58年度以降) |
||
| 職歴による資格 |
・法人や個人事業の会計事務 2年以上 ・金融機関等で資金貸付・運用事務 2年以上 ・税理士・弁護士・会計士等の補助事務 2年以上 |
税理士試験受験資格の緩和とは
税理士試験の受験資格は、令和5年度(2023年度)から以下のように緩和されました。
1. 会計学に属する科目(簿記論・財務諸表論)の受験資格撤廃
以前は、これらの科目を受験するために特定の学歴や資格が必要でしたが、改正により誰でも受験できるようになりました。
2. 税法に属する科目の学識要件の緩和
税法科目の受験資格として、これまで「法律学または経済学に属する科目」を履修する必要がありましたが、改正後は「社会科学に属する科目」へと範囲が拡大されました。
受験資格緩和の背景と理由
税法科目に関してこれまで一定の学歴や職歴などの「受験資格」が必要だったところ、2023年(令和5年)試験から、会計科目について誰でも受験できるように緩和 されました。その背景と理由は以下の通りです。
| 背景・理由 | 内容 |
| ① 受験者数の減少 | 長期的に税理士試験の受験者が減少しており、将来的な人材不足が懸念されていた。特に若年層の受験者が減っていた。 |
| ② 試験制度の柔軟化 | 他の資格試験(例:公認会計士試験など)では受験資格がないことが多く、税理士試験だけが厳しい条件となっていた。公平性やアクセス向上の観点から見直しが求められた。 |
| ③ 人材の多様化の促進 | 多様なバックグラウンドを持つ人材に門戸を開き、士業業界の活性化を図る目的もあった。 |
どのように緩和されたのか
以下に、受験資格緩和の具体的な内容をまとめます。
会計学に属する科目(簿記論・財務諸表論)
・変更前:受験には、学歴・資格・職歴などの一定の要件を満たす必要がありました。
・変更後:受験資格の要件が撤廃され、どなたでも受験できるようになりました。
税法に属する科目
・変更前:「法律学または経済学に属する科目」を履修していることが受験資格の条件とされていました。
・変更後:受験資格の対象が「社会科学に属する科目」へと広がり、より多くの学部・学科の方が受験できるようになりました。
受験資格緩和の具体的な影響
受験者数の変化
受験資格の緩和により、税理士試験の受験者数は顕著に増加しました。
受験申込者数の増加
令和5年度(2023年)の受験申込者数は41,256名となり、前年の36,852名から4,404名(約12%)増加しました。
特に会計科目の受験者数が大きく増加しており、
・簿記論は前年比3,205名増(124.9%)
・財務諸表論は前年比3,142名増(131.1%)
と、いずれも前年を大きく上回る結果となりました。
若年層の受験者が顕著に増加
25歳以下の受験者数は前年比142.4%と大幅に増えており、 受験資格緩和が若年層の受験促進に寄与していると考えられます。
社会への影響
多様な人材の参入を後押し
これまで受験資格の制限によって受験が難しかった 高校生、大学1・2年生、他学部の学生なども受験できるようになり、 税理士業界への多様な人材の参入が期待されています。
税理士業界の活性化に貢献
受験者数の増加は、将来的な税理士不足の解消につながるだけでなく、 業界全体の活性化にも寄与すると見込まれています。
試験科目への影響
受験資格緩和により、試験科目にも以下の変化が見られます。
・会計科目の受験者増加:
◦簿記論・財務諸表論の受験資格が撤廃されたことで、これらの科目の受験者数が大幅に増加しました。
・税法科目の受験資格要件緩和:
◦税法科目の受験資格要件が「法律学または経済学に属する科目の履修」から「社会科学に属する科目の履修」へと拡大され、より多くの学生が受験資格を満たしやすくなりました。
| 分類 | 項目 | 具体的な影響 | 出典・補足 |
| 1. 受験者数の変化 | 総受験者数の増加 | 36,852人(2022)→ 41,256人(2023) 前年比112% | 国税庁・会計人コースなど |
| 会計科目の受験者増 | 簿記論:+3,205人(前年比124.9%) 財表:+3,142人(前年比131.1%) | 緩和で誰でも受験可に | |
| 若年層(25歳以下)の増加 | 対前年比142.4% | 高校・大学低学年層の受験増 | |
| 2. 社会への影響 | 多様な人材の参入 | 学歴・職歴の制限が緩和され、多様な背景の受験者が増加 | 他学部・社会人なども受験可能に |
| 業界の将来的人材確保 | 長期的な税理士不足への対応 | 人口減少・高齢化を見越して対策 | |
| 学生の早期挑戦の機会拡大 | 受験年齢の若年化 → 税理士のキャリアパスが早期化 | 高校〜大学1・2年生から挑戦可能に | |
| 3. 試験科目への影響 | 会計学科目の競争激化 | 母集団が急増 → 合格率に影響の可能性 | 特に初学者・独学組は要注意 |
| 税法科目の受験可能者拡大 | 学識条件が「法律・経済学」→「社会科学」に緩和 | 文系学部全般が対象に(例:社会学、心理学など) | |
| 学習支援市場の拡大 | 新規参入層向けの教材・講座が増加中 | 資格学校・独学支援サービスが活性化 |
受験資格緩和に関する最新情報
2023年度の改正点と今後の予測
2023年度(令和5年度)から、税理士試験の受験資格が以下のように緩和されました。
1.会計学に属する科目(簿記論・財務諸表論):
◦受験資格の撤廃: これまで必要とされていた受験資格が撤廃され、どなたでも受験が可能となりました。
2.税法に属する科目:
◦学識要件の緩和: 受験資格のうち、「学識」に関する要件が緩和され、これまで「法律学または経済学に属する科目」の履修が必要だったものが、「社会科学に属する科目」へと拡大されました。これにより、より多くの学部・学科の方が受験資格を満たしやすくなりました。
受験資格の緩和により、以下のような影響が予測されます。
1.受験者数の増加:
◦受験資格のハードルが下がったことで、特に若年層や他分野からの受験者が増加すると予想されます。
2.多様な人材の参入:
◦これまで受験が難しかった他学部出身者や社会人が受験しやすくなり、税理士業界に多様なバックグラウンドを持つ人材が参入することが期待されます。
3.競争の激化:
◦受験者数の増加に伴い、試験の競争率が上がる可能性があります。
受験生へのアドバイスと注意点
・早期の学習開始:
◦受験資格が緩和された今、早めに学習を開始することで、他の受験者との差別化を図ることが重要です。
・受験資格の確認:
◦税法科目を受験する際は、引き続き受験資格が必要です。自身が要件を満たしているか、事前に確認しましょう。
・計画的な学習:
◦税理士試験は科目合格制です。自身のペースに合わせて、計画的に科目を選択し、学習を進めることが合格への近道です。
・最新情報の収集:
◦試験制度や税制は変更される可能性があります。国税庁の公式サイトなどで最新情報を定期的に確認しましょう。
| 項目 | 内容 | 詳細 |
| 改正時期 | 令和5年度(2023年度)試験より適用 | 2023年4月1日以降に実施される試験から適用 |
| 会計学科目の受験資格撤廃 | 簿記論・財務諸表論は受験資格不要に | 学歴・職歴・資格に関係なく、誰でも受験可能となった |
| 税法科目の学識要件緩和 | 必要な履修科目が「社会科学」に拡大 | 従来の「法律学または経済学」から「社会科学」に属する科目へと範囲が広がり、より多くの学部・学科の学生が受験資格を満たしやすくなった |
| 社会科学に属する科目の例 | 法律学、経済学、社会学、政治学、行政学、政策学、教育学、福祉学、心理学、統計学など | 具体的な科目例として、これらが挙げられる |
| 受験者数の変化 | 受験資格緩和後、受験者数が増加傾向 | 具体的な数値は今後の統計データを参照 |
| 受験生への影響 | 受験のハードルが下がり、挑戦しやすくなった | 特に高校生や大学低学年の学生が早期に受験を検討できるようになった |
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
税理士試験の受験資格は、会計学科目(簿記論・財務諸表論)には制限がなく、誰でも受験可能です。
税法科目は従来、学歴・資格・職歴のいずれかの要件を満たす必要がありました。
令和5年度(2023年度)から、会計学科目の受験資格が撤廃され、全ての人が受験可能となりました。
また、税法科目に関しても、学識要件の対象が「法律学・経済学」から「社会科学」全体へと拡大されました。
これらの改正の背景には、受験者数の減少、制度の柔軟化、多様な人材の確保といった課題がありました。
実際に、2023年度の受験者数は前年より約12%増加し、特に若年層の増加が顕著でした。
試験科目別では簿記論・財務諸表論の受験者が大幅に増え、競争が激化しています。
今後の受験に向けては、早期の学習開始、受験資格の確認、計画的な科目選択が重要です。
この記事が皆様のお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















