INDEX
おすすめ記事
-
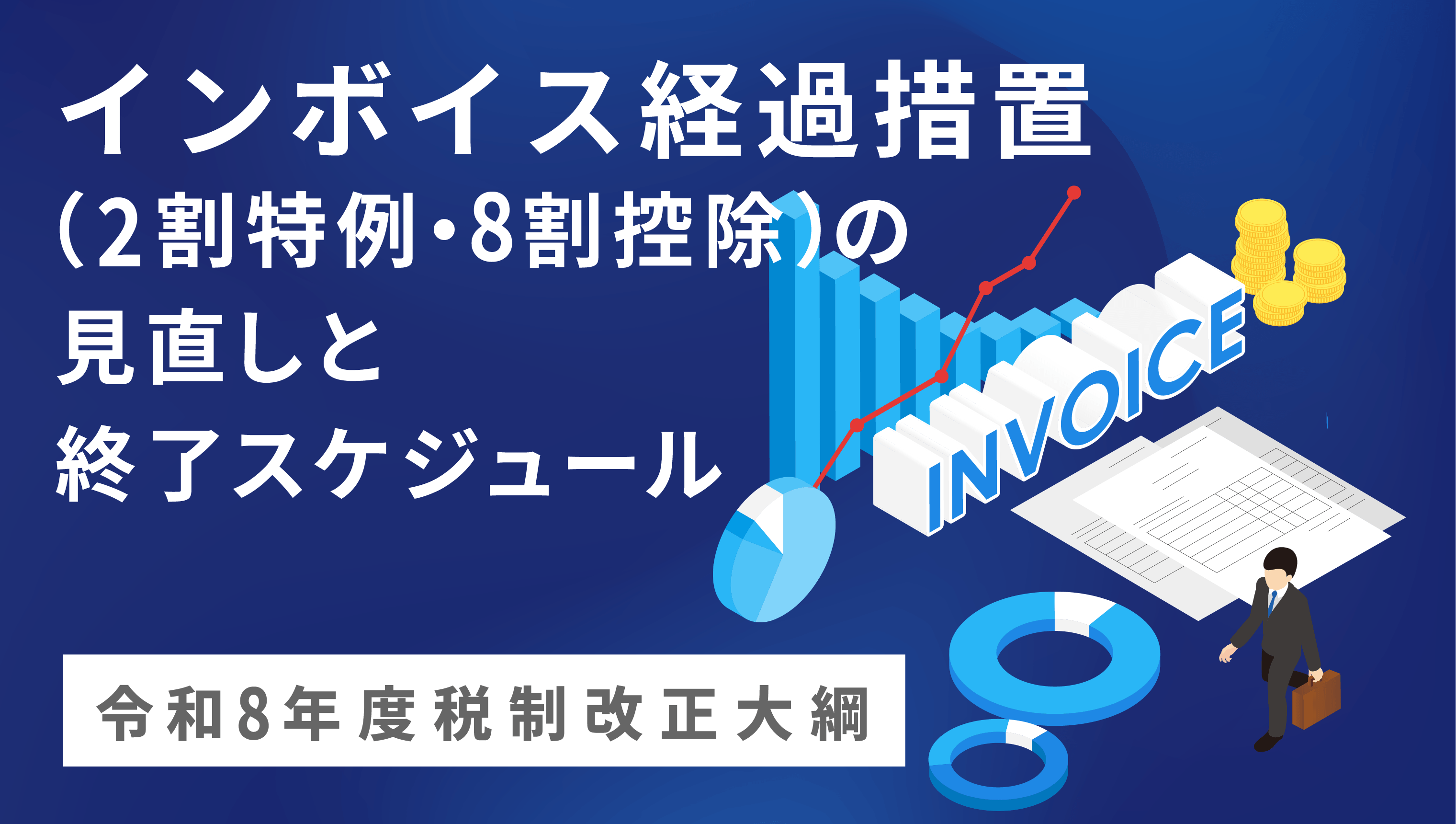
インボイス経過措置はいつまで?見直しと終了スケジュール【令和8年度税制改正大綱】
-

働きながら税理士試験に合格するには?無理なく仕事と勉強の両立を実現!
-
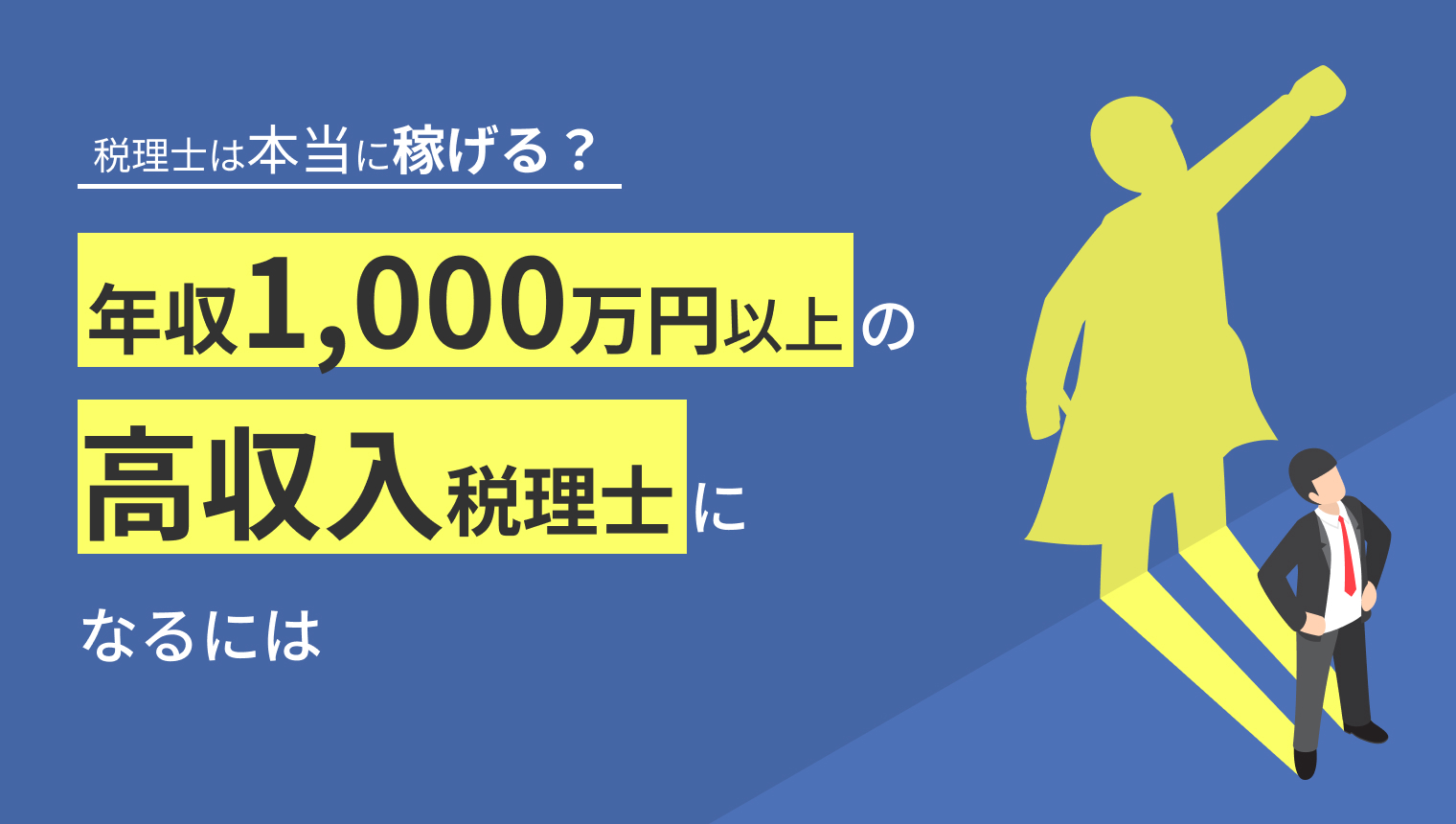
税理士は本当に稼げる?年収1000万円以上の高収入税理士になるには
-
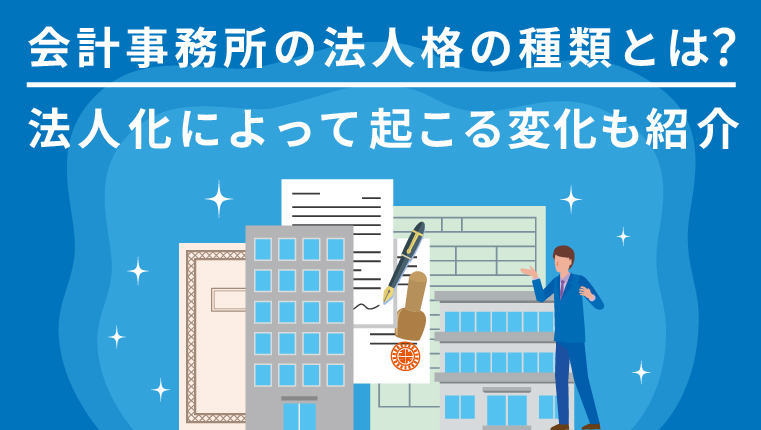
会計事務所の法人格の種類とは?法人化によって起こる変化も紹介
-

「戦略分野国内生産促進税制」とは?制度概要と申請の留意点を徹底解説
公開日:2025/05/09
最終更新日:2025/09/06

INDEX
「公務員の安定」を捨ててまで、転職を考えるべきだろうか?
そんな迷いを抱えている国税専門官の方は、決して少なくありません。
専門性を活かしてきた自負はある一方で、このままのキャリアで良いのか、ふと立ち止まる瞬間もあるはずです。
実際、近年は税理士法人や一般企業、コンサル業界へとキャリアを広げる人も増えてきています。
とはいえ、転職にはメリットもあればリスクもある――慎重に見極めたいところです。
この記事では、国税専門官が転職を考える理由から、業界別のおすすめ職種、必要なスキル、面接での伝え方まで網羅的にご紹介します。
「今の経験は本当に民間で通用するのか?」「そもそも何から始めればいいのか?」という疑問にもお答えします。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
国税専門官の転職を考える理由
国税専門官は、税務のプロフェッショナルとして専門性の高い業務を担い、社会的信頼も厚い職種です。しかしその一方で、近年はキャリアチェンジを検討する人も増えてきています。理由はさまざまですが、以下のようなものが代表的です。
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 1. キャリアの成長に限界を感じる | 一定のスキルは身につくが、年功序列・昇進スピードの遅さに不満を感じる人も。 |
| 2. 民間でのスキル活用を目指す | 税務調査や法人対応の経験を、コンサル・税理士法人・経理職などに活かしたい。 |
| 3. ワークライフバランスの見直し | 忙しい部署や調査時期により長時間労働となることもあり、働き方を見直したい人も。 |
| 4. 組織文化に馴染めない | 公務員ならではの風通しの悪さや硬直した意思決定プロセスに違和感を覚えることも。 |
| 5. 地方転勤・異動がある | 転居を伴う人事異動がネックとなるケースも。 |
| 6. 独立志向がある | 税理士やコンサルタントとして独立するためのステップと考える人もいる。 |
キャリアチェンジのメリットとデメリット
転職にはチャンスもリスクも伴います。国税専門官からのキャリアチェンジについて、以下のようなメリット・デメリットが考えられます。
◎ メリット
・専門スキルを幅広く活かせる
◦税務知識、調査能力、法人対応などは会計事務所や企業の経理部門で高く評価される。
・年収アップの可能性がある
◦税理士法人やコンサルファーム、外資系企業などでは高年収も狙える。
・キャリアの選択肢が広がる
◦フリーランスや起業なども視野に入れやすくなる。
・若いうちなら軌道修正がしやすい
◦30代前半までであれば民間への転職にも柔軟に対応できる。
特に「自分の市場価値を高めたい」「専門家としてキャリアを伸ばしたい」という思考の方にとっては、大きな転機となる可能性があります。
▲ デメリット
・公務員としての安定性を失う
◦終身雇用や福利厚生といった「安定の代名詞」を手放すことになる。
・年収が一時的に下がるケースも
◦未経験業界に飛び込む場合や、経験を十分に活かしきれないと初年度の年収が下がる可能性もある。
・ビジネススキルのギャップ
◦民間企業では、スピード感・収益意識・社内調整力など、公務員時代には不要だった能力が求められる。
・周囲の理解が得られにくいこともある
◦両親や友人から「せっかく公務員になったのに…」と言われることも。
業界別おすすめ職種
会計事務所での税理士
国税専門官としての経験が最もストレートに活かせる業界です。税務調査の知識や法人税の深い理解は、即戦力として評価されやすいです。
◎ おすすめ職種
・税務顧問(法人・個人事業主対応)
・相続・資産税対応
・税務調査対応担当
・税理士法人のマネージャー職(経験に応じて)
向いている人
・税務の専門性を活かし続けたい人
・将来的に独立を目指している人
・地域密着型の仕事に興味がある人
✅ メリット
・専門性がダイレクトに活きる
・転職先が多く選択肢が広い
・独立開業のステップとしても優秀
▲ デメリット
・繁忙期の長時間労働(特に確定申告時期)
・年収は最初は抑えられる傾向も(資格の有無による)
コンサルティング会社での活躍
税務に限らず、事業再生・M&A・組織再編・国際税務など、幅広い案件に関われます。大手ファームでは、税理士としての実務経験が評価され、キャリアアップが望めます。
◎ おすすめ職種
・税務コンサルタント(法人税・国際税務・移転価格など)
・FAS系(財務デューデリジェンス、バリュエーション)
・IPO支援コンサル
・公共政策・税制改正対応コンサル(官民連携プロジェクト等)
向いている人
・高年収・高難度の環境に挑戦したい人
・税務+ビジネス視点で物事を考えたい人
・英語やデジタル領域にも興味がある人
✅ メリット
・成果次第で年収は大きく上がる
・幅広い業界・企業と関われる
・優秀な人材と刺激を受けながら働ける
▲ デメリット
・プレッシャーや長時間労働にさらされやすい
・ビジネススキル・対人調整力が求められる
・転職初期はインプット量が非常に多い
一般企業の経理職
事業会社で経理・財務部門として働く選択肢です。調査される側から、する側への視点転換が求められますが、企業運営の根幹に関わるやりがいがあります。
◎ おすすめ職種
・経理(仕訳・決算・税務申告など)
・税務担当(企業内税務対応・顧問税理士との連携)
・財務(資金繰り、資金調達)
・経営企画(数字を元にした経営判断支援)
向いている人
・安定した働き方を求める人
・特定の業界や会社に深く関わりたい人
・将来的にCFO(最高財務責任者)を目指したい人
✅ メリット
・ワークライフバランスを取りやすい企業も多い
・経営に近い立場で数字を見る経験ができる
・定着すれば長期的に安定したキャリアが築ける
▲ デメリット
・組織内での昇進に時間がかかる場合もある
・税務以外の会計・業務知識の習得が必要
・税務の専門性が活かしきれない職場もある
| 業界名 | おすすめ職種 | 向いている人 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 会計事務所・税理士法人 |
・税務顧問(法人・個人) ・相続・資産税対応 ・税務調査対応 ・マネージャー職 |
・税務を極めたい人 ・独立志向のある人 ・地域密着で働きたい人 |
・専門性がダイレクトに活かせる ・独立のステップになる ・求人が多く転職しやすい |
・繁忙期に忙しい ・年収が最初は低めの場合あり(特に無資格) |
| コンサルティング会社 |
・税務コンサル(法人税・国際税務) ・財務DD/FAS関連 ・IPO支援コンサル ・公共政策系コンサル |
・高難度環境に挑戦したい人 ・ビジネス視点で税を扱いたい人 ・英語やITにも関心がある人 |
・成果次第で年収アップ ・業界横断の知見が得られる ・優秀な人と働ける |
・激務になりやすい ・高度な対人スキルが求められる ・初期インプットが多い |
| 一般企業(事業会社) |
・経理(仕訳~決算) ・税務担当 ・財務(資金繰り等) ・経営企画 |
・安定志向の人 ・特定の企業に深く関わりたい人 ・長期的に働きたい人 |
・WLB(ワークライフバランス)◎の企業も多い ・経営視点が身につく ・安定した勤務環境 |
・昇進に時間がかかることも ・税務以外の知識も必要 ・専門性が埋もれる可能性あり |
転職に必要なスキルと資格
国税専門官から民間企業や士業・コンサル業界へ転職する際には、実務経験の強みを活かしつつ、不足しているスキルや資格を補完することが重要です。特に、以下の3つの観点がよく問われます。
税理士資格の取得方法
民間で税務の専門家として活動するうえで、税理士資格は非常に有利です。
国税専門官としての一定期間の実務経験は、「試験免除」の対象にもなります。
● 税理士資格の基本情報
・原則は「5科目合格」で取得(例:簿記論・財務諸表論・法人税法など)
・国税OBは、実務経験により最大2科目免除される制度あり
・多くの会計事務所や税理士法人で、資格保有者は「即戦力」と見なされやすい
● 試験免除のポイント
・原則として、5年以上の国税実務経験(査察・調査部門など)が必要
・一部の部門・職歴によっては該当しないケースもあるため、早めの確認が大切
転職前後に税理士資格取得を目指すことで、キャリアの選択肢が大きく広がります。
会計知識の強化
税務の知識が豊富でも、企業会計の基礎(仕訳・決算・財務諸表など)に不慣れな方も多いです。特に経理職やコンサル業界では、会計の知識は必須です。
● おすすめの知識・分野
・簿記(できれば日商簿記2級以上)
・財務三表(PL・BS・CF)の理解
・法人決算の流れ、申告書の構造
・会計ソフト(弥生会計、freee、マネーフォワードなど)
● 学び直しの方法
・社会人向けの簿記講座やオンライン教材(YouTubeやUdemy)
・会計スクールや通信講座(TAC、大原など)
・転職後にOJTで学ぶケースもあるが、事前に基礎は押さえておくのが安心
特に事業会社では「経理=税務+会計」の視点が求められるため、バランス感覚が重要です。
コミュニケーション能力の重要性
公務員時代とは異なり、民間では「説明力・説得力・チームとの連携力」が重視されます。 特にコンサル業界や社内経理では、一人で完結しない仕事が多いため、コミュニケーション力は非常に大きな武器になります。
● 民間で求められるコミュニケーションの種類
・顧客への提案・報告・ヒアリング(会計事務所・コンサル)
・社内調整・経営層への報告(一般企業)
・チームマネジメントや部下育成(マネージャー職)
● 強化のポイント
・相手の立場に立って説明する練習を積む
・プレゼン・報告資料をシンプルに整理する力を磨く
・ロジカルに話す力(結論→理由→具体例)を意識する
「自分は話が苦手だから…」と思う人でも、訓練でかなり改善できます。転職活動の面接から意識しておくと◎。
転職活動の進め方
国税専門官からの転職は、自分の経験をどう“見せるか”がカギです。以下のようなステップで進めるのが一般的です。
✅ 基本的な流れ
1.自己分析・キャリアの棚卸し
◦これまでの職務内容(調査、査察、相談業務など)を言語化
◦「どんな強みがあるか」「何を活かしたいか」を明確にする
2.希望職種・業界の方向性を決める
3.会計事務所? 一般企業? コンサル? それぞれの違いを理解して選択
4.求人情報を集める
◦エージェント、求人サイト、知人の紹介など複数ルートを活用
5.職務経歴書・履歴書の作成
◦民間向けにわかりやすくアピールする構成にする
6.応募・面接対策
◦面接で「なぜ転職?」「何をしたいのか?」を明確に語れるよう準備
7.内定・退職交渉・入社準備
◦公務員は引き継ぎに時間がかかるため、余裕のあるスケジュールを
求人情報の探し方と選び方
転職の方向性に応じて、探し方と選び方を戦略的に使い分けることが重要です。
✅ 求人の探し方(情報収集ルート)
・転職エージェントを活用(おすすめ)
◦マイナビ税理士、ミツカル、MS-Japan、リクルートエージェントなど
◦税務・会計・管理部門に強い特化型がおすすめ
・転職サイトを直接見る
◦ビズリーチ、doda、indeedなどで「税務」「経理」などのキーワードで検索
・知人・元同僚からの紹介
◦税理士事務所や企業経理への「リファラル採用」も意外と多い
・OB・OG訪問やセミナー参加
◦転職経験者から生の情報を得られる貴重な場
✅ 求人の選び方(見極めポイント)
・業務内容が自分の経験にマッチしているか
・残業・繁忙期の有無や働き方
・企業の規模感や教育体制
・「独立支援あり」「税理士資格保有者歓迎」などの記載
・年収や待遇の現実性
特に最初の転職は「成長できる環境かどうか」が非常に重要です。
面接でのアピールポイント
面接では、「なぜ公務員を辞めて民間に行くのか?」という点が特に重視されます。
自分の経験をどう企業目線で伝えるかがカギです。
✅ 主なアピール材料
・税務調査・法人対応経験
◦多くのクライアントとやり取りしてきた経験は、対外折衝力として強みになる
・法令解釈や文書作成能力
◦難解な税法を読み解き、論理的に文章化する力は、民間でも高評価
・コンプライアンス意識
◦税務リスクに敏感な姿勢は、企業側にとって大きな安心材料
・誠実で落ち着いた対応力
◦国税出身者ならではの「信頼感・丁寧さ」も武器になる
✅ よく聞かれる質問と答え方の例
| 質問 | 回答のポイント |
|---|---|
| なぜ公務員を辞めるのか? | 「スキルをより広く活かしたい」「事業に近い立場で価値を提供したい」など前向きな理由で答える |
| 民間で何をやりたいか? | 具体的な職種と役割を明確にし、「貢献できる分野」を語る |
| 国税での経験はどう活かせる? | 調査経験・法令理解・対人対応などを、企業課題にどう活かせるかを伝える |
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
この記事では国税専門官の転職について取り扱いました。この記事が皆様のお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















