INDEX
おすすめ記事
-
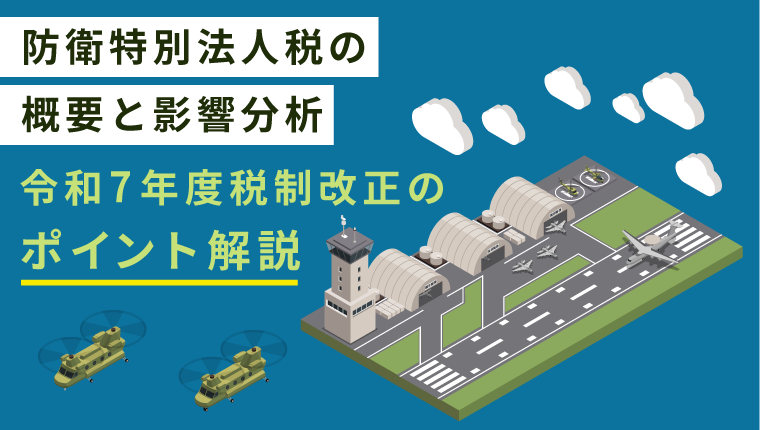
防衛特別法人税の概要と影響分析:令和7年度(2025年度)税制改正のポイント解説
-
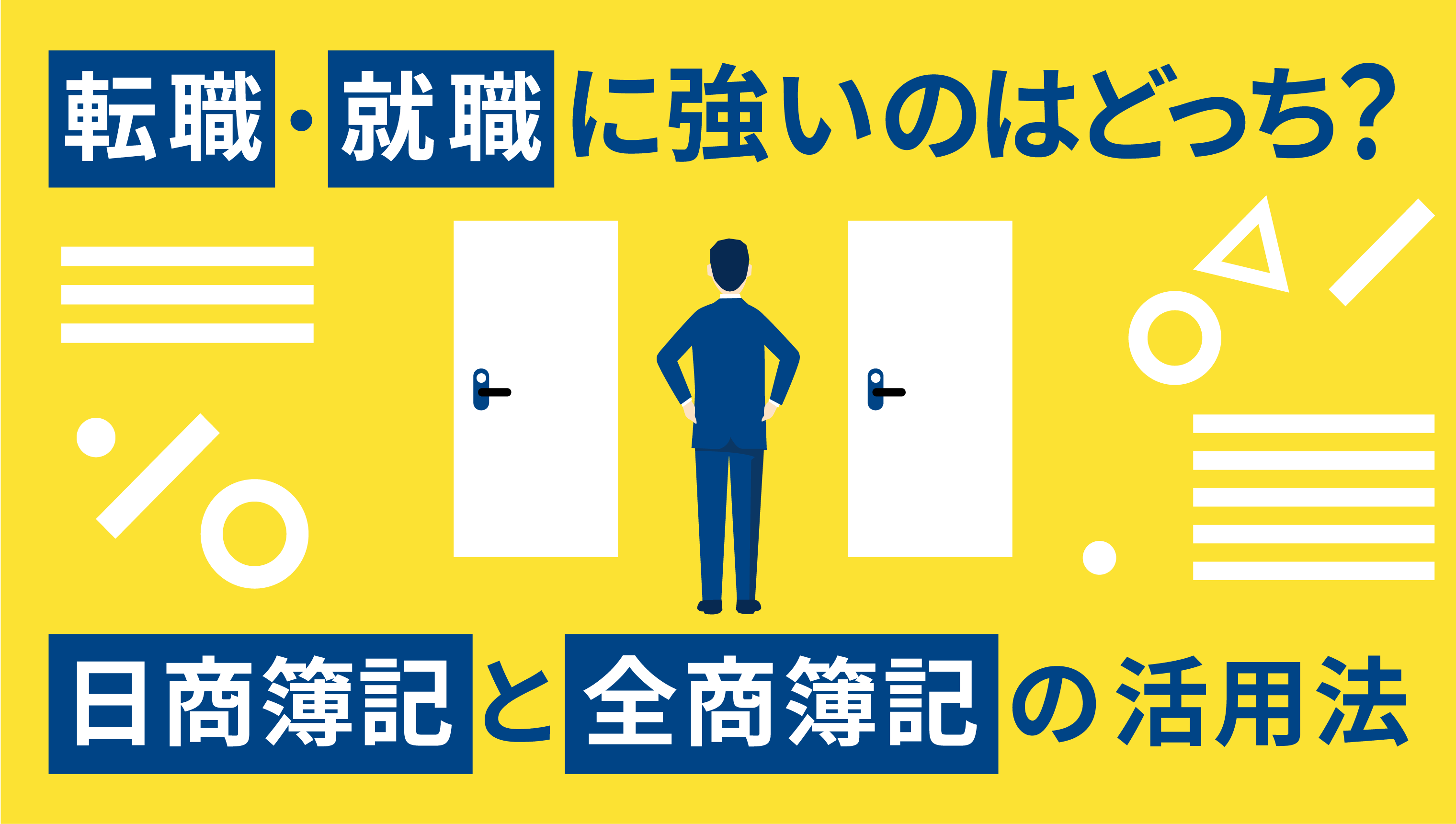
日商簿記と全商簿記の違いは?就職・転職での強みと活用法
-
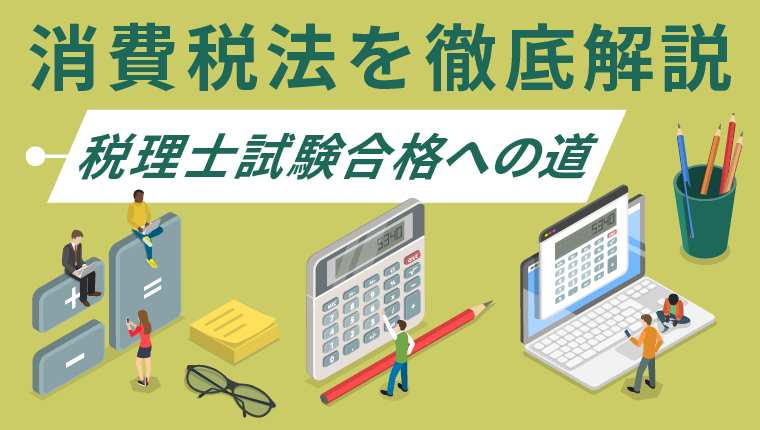
消費税法を徹底解説|税理士試験合格への道
-
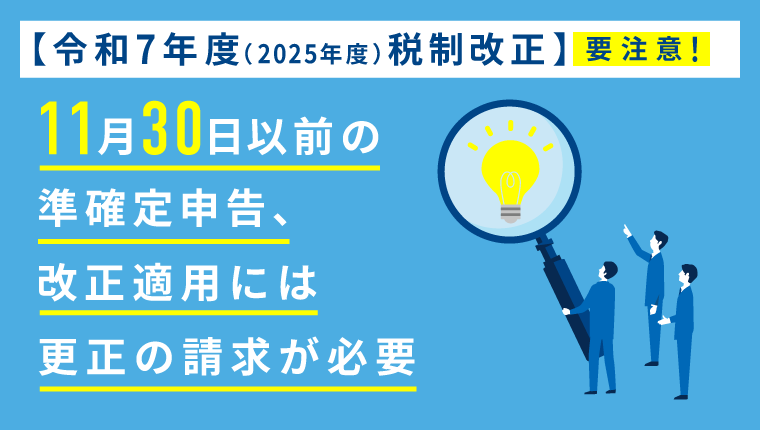
【令和7年度(2025年度)税制改正】要注意!11月30日以前の準確定申告、改正適用には更正の請求が必要
-
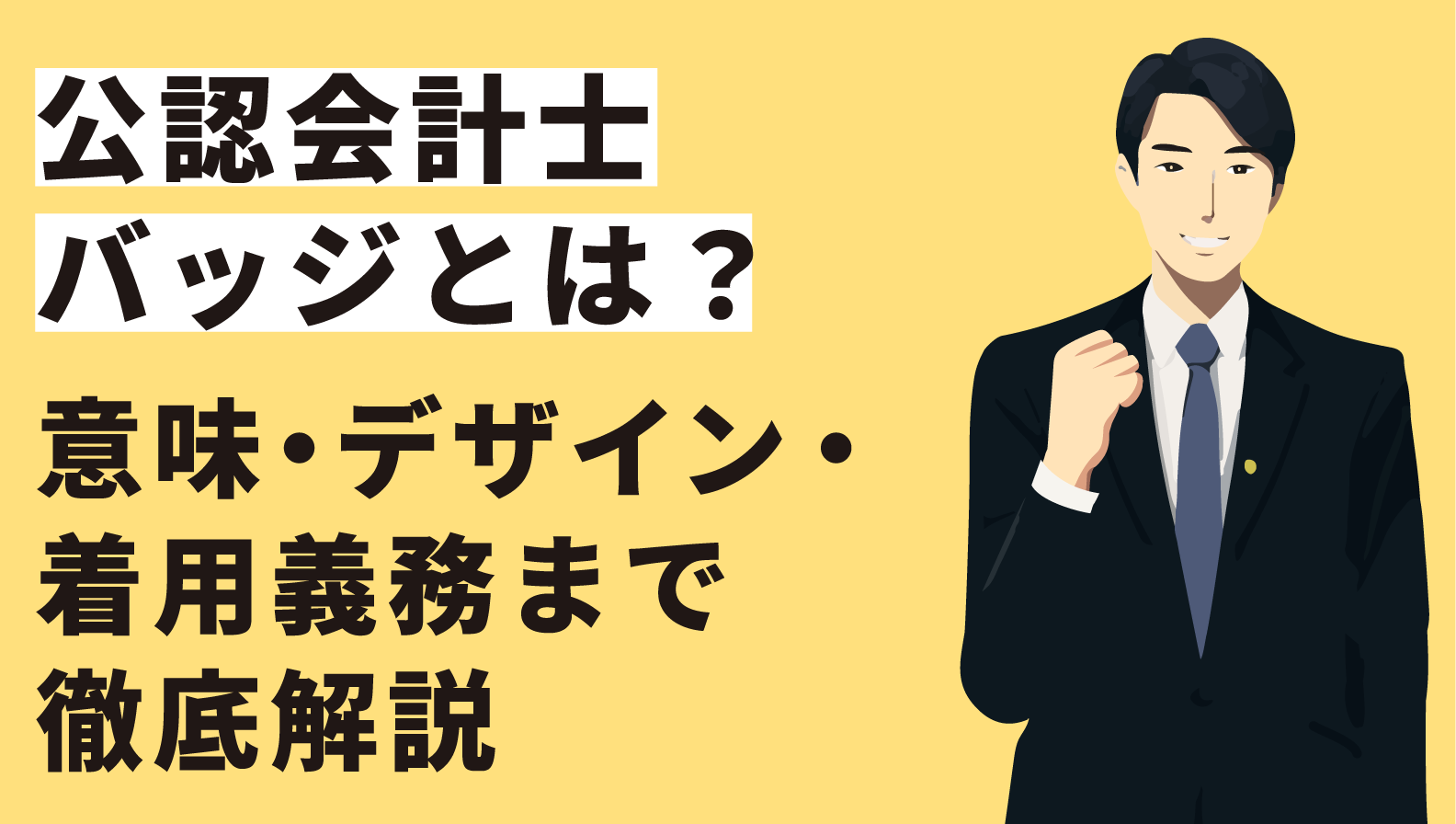
公認会計士バッジとは?意味・デザイン・着用義務まで徹底解説
公開日:2025/05/16
最終更新日:2025/09/06
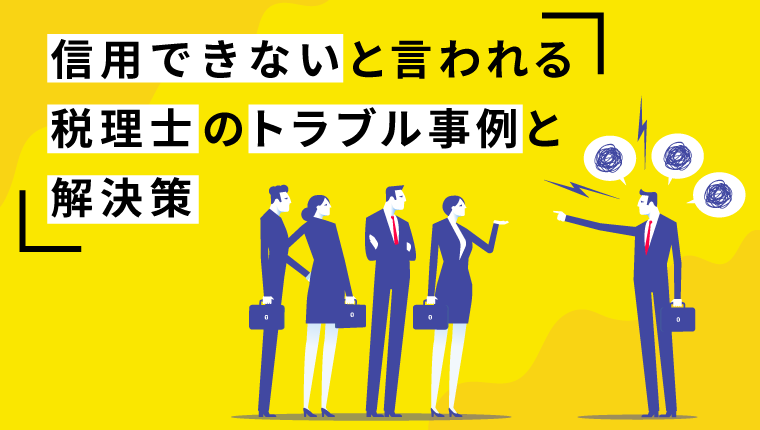
INDEX
税理士にとって、顧問契約の「継続」は経営基盤を支える大切な要素です。
しかし現実には、事業者側のさまざまな理由から「税理士の変更」が行われることも少なくありません。
「どこに不満を感じていたのか?」「なぜ乗り換えられたのか?」その背景を知ることは、契約継続率を高めるためのヒントになります。
また、新たな顧問先から「引き継ぎ」案件として相談を受ける機会もあるでしょう。
その際、適切な対応ができるかどうかで信頼度は大きく変わります。
本記事では、税理士変更の主な理由、変更のタイミング、スムーズな引き継ぎの進め方について整理しています。
「選ばれる税理士」であり続けるために、ぜひチェックしておきたいポイントを網羅しました。
現場対応の質を一段階高めるための参考にしていただければ幸いです。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
信用できない税理士の特徴
税理士は専門性が高い職業でありながら、クライアントとの信頼関係が非常に重要です。しかし中には、依頼者にとって不利益になるような対応をする税理士も存在します。以下のような特徴が見られる場合は、注意が必要です。
● 曖昧な回答しかしない
質問しても「たぶん」「おそらく」といった曖昧な返答が多く、根拠がはっきりしない。
● 専門用語を並べるだけで説明になっていない
知識をひけらかすだけで、クライアントの理解を助けようという姿勢がない。
● 連絡が遅い、または対応が雑
メールや電話の返信が数日かかる、急ぎの相談に応じないなど、誠実さに欠ける。
● 安易な節税策ばかりすすめてくる
将来的なリスクや税務調査のリスクを考慮せず、「今得すること」だけを強調する。
● 顧問料の説明が不透明
料金の内訳を明かさず、「とにかくこの金額です」と押し切る。
● 担当者が頻繁に変わる
担当がコロコロ変わることで、一貫したサポートが期待できない。
● 最新の法改正に無関心
年々変わる税制への感度が低く、提案の質が古いまま止まっていることも。
| 特徴 | 解説 |
| ❌ 質問に対して曖昧な返答をする | 「たぶん…」「おそらく…」など自信なさげな回答が多い |
| ❌ 説明が専門用語だらけで理解できない | 素人にわかる言葉で話す努力がない |
| ❌ 連絡のレスポンスが遅い | メールや電話の返答が2〜3日以上遅れることが常態化 |
| ❌ 節税の話しかしない | リスクや将来の見通しに言及せず、節税至上主義 |
| ❌ 顧問料の内訳や根拠を明かさない | 「うちはこの金額です」で済ませる |
| ❌ 頻繁に担当者が変わる | 一貫した対応ができず、過去の経緯を知らないことも |
| ❌ 最新の法改正に疎い | 毎年の税制改正へのアンテナが低い |
税理士との金銭トラブル事例
料金に関するトラブル
税理士とのトラブルで特に多いのが、「報酬(料金)」に関する金銭的な行き違いです。以下のような事例が実際に発生しています。
● 事例1:事前説明なしの追加請求
決算時期になって「特別な対応があったので」と、事前説明なしに高額な追加請求が行われた。依頼者は驚き、不信感を募らせる結果に。
● 事例2:契約内容と実際の請求内容が違う
月額顧問料だけで対応してくれると聞いていたのに、年末調整や法定調書の提出ごとに別途料金が発生。契約時の説明が曖昧だったため、後々トラブルに。
● 事例3:解約時に高額な違約金を請求された
他の税理士に切り替えようとしたところ、「解約は1年前までに通知が必要」などの特約が契約書に記載されており、高額な違約金を請求された。
| トラブル内容 | 説明 |
| ❌ 「顧問料に含まれる範囲」が曖昧 | 年末調整・償却資産申告・経営相談などが別料金扱いになることがある |
| ❌ 成果報酬・成功報酬の割合が不明 | 税務調査対応後に高額な成功報酬を請求されるケースも |
| ❌ 契約書が存在しない | 口頭での約束のみで、後から「言った・言わない」の争いに発展 |
| ❌ 解約条件が不明確 | 中途解約時のペナルティが契約時に説明されていなかった |
| ❌ 請求書の明細がなく、一括請求 | 何にいくらかかっているのかが分からない |
不透明な料金体系のリスク
不透明な料金体系には、以下のようなリスクが潜んでいます
● 想定外の費用が発生しやすい
業務範囲や追加料金の条件が不明確なため、「そんなはずではなかった」という出費が発生しやすい。
● 信頼関係の悪化につながる
お金に関する不信感は、税理士との関係全体を壊す引き金になる。
● 経営判断がブレやすくなる
費用の見通しが立たないことで、資金繰りや外注判断が甘くなってしまう。
● トラブル時に法的な争いに発展することも
契約内容が不明瞭なまま請求が発生すると、最悪の場合、民事訴訟に発展することも。
税務アドバイスの的確さに関する問題
税理士に求められる最大の価値の一つは、「的確な税務判断」と「リスクを踏まえた助言」です。しかし、すべての税理士が常に正確かつ最新の知識を持っているとは限らず、場合によっては依頼者に損害を与えるような誤った助言が行われることもあります。
的確さを欠いたアドバイスには、以下のような問題が生じます:
・税務調査で否認され、追徴課税や加算税が発生する
・会社や個人の資金計画に狂いが生じる
・不要なリスクを負った経営判断を下してしまう
・顧問税理士に対する信頼が失われる
税務的に不適切な助言の例
● 誤:赤字のうちは消費税は気にしなくていい
→ 実際には、赤字でも課税売上高によっては消費税の納税義務が発生する。免税期間が終了するタイミングでの注意が必要。
● 誤:交際費はすべて経費になるから気にしなくていい
→ 法人には交際費の損金算入限度があり、特に中小企業でも金額超過分は損金にならない。
● 誤:役員報酬はあとから決めてもいい
→ 定期同額給与は「期首からの支給」が原則。あとから増減すると損金算入が否認される可能性がある。
● 誤:個人の生活費を会社の経費で落としてもバレない
→ 明らかに私的な支出は税務調査で否認されるだけでなく、重加算税や最悪の場合は脱税認定されるリスクも。
● 誤:適当に減価償却すれば税金減らせますよ
→ 減価償却の方法(定率法・定額法)、耐用年数、期中取得の按分などは厳密なルールがあり、逸脱すれば否認される。
● 誤:どんな取引も顧問契約に含まれているから相談不要
→ 例えばM&Aや相続対策などは別途専門性を要する領域で、一般顧問料に含まれないケースが多い。
● 誤:クラウド会計を導入すれば節税になる
→ 節税にはならず、効率化の手段にすぎない。導入目的や運用体制によって効果は異なる。
税理士選びで考慮されるポイント
税理士は経営や資産に深く関わるパートナーです。そのため「誰に依頼するか」は非常に重要です。料金や実務能力だけでなく、信頼性・相性・将来への提案力など、複合的に判断する必要があります。
主な考慮ポイント:
✅ 対応エリア・コミュニケーション手段(訪問・オンライン)
✅ 業種や規模に対する理解度
✅ 税務以外(経営相談・資金繰り支援など)の対応範囲
✅ 税務調査の対応経験
✅ 相性・誠実さ(話しやすさ、説明の丁寧さ)
信頼できる税理士の選び方
● 専門性と経験がある
→ 自社と同じ業種・規模のクライアントを多く持っているかを確認
● 話がわかりやすい・かみ砕いて説明してくれる
→ 税務の素人にも寄り添った対応ができる人は安心感がある
● レスポンスが早く、対応が丁寧
→ 質問への返答が早く、調べてくれる姿勢がある
● 契約内容・報酬体系が明確
→ 「何を・いくらでやってくれるか」が事前に文書で明示されている
● 節税だけでなくリスクや将来も見据えてくれる
→ 一時的な節税よりも、長期的な経営の健全性を考えたアドバイスができる
● 税務以外の専門家とも連携している
→ 社労士、弁護士、司法書士などとチームで対応できる体制があると安心
● クラウドツールや電子申告などITにも対応している
→ 時代に合った業務効率化が可能で、スピードも早い
依頼前に確認すべき事項
| 確認事項 | 解説 |
| ✅ 顧問契約の業務範囲 | 記帳代行・決算・年末調整・税務調査立ち合いなど、含まれる内容を確認 |
| ✅ 基本報酬と追加費用の条件 | 月額・年額、年末調整・法定調書・消費税などのオプション料金 |
| ✅ 契約期間と解約条件 | 最低契約期間、解約の通知期限、違約金の有無 |
| ✅ 相談対応のルール | メール・電話相談の可否、頻度、対応時間帯など |
| ✅ 得意分野・専門領域 | 節税、資金調達、会社設立、相続、医業など専門性が合うかどうか |
| ✅ 使用する会計ソフト | 自社と合っているか(freee、マネーフォワード、弥生など) |
| ✅ 税務調査時のサポート体制 | 立ち合い対応の有無、成功報酬の有無 |
税理士変更のタイミングと方法
税理士の変更は、会社にとって大きな意思決定の一つですが、適切なタイミングと方法を選べばスムーズに進めることが可能です。
✴️変更のタイミング(代表例)
✅ 決算終了直後(引き継ぎがしやすい)
✅ 税務調査が終わった後
✅ 法人化、事業承継、事業拡大などの大きな転機
✅ 税理士との信頼関係が破綻したとき(連絡がつかない、助言がずれる等)
注意点:
年度途中での変更も可能ですが、決算期が近い場合や申告直前は避けるのが無難です。
変更する理由の整理
| 理由 | 解説 |
| ✅ 対応が遅く、コミュニケーションに不満がある | 返信が遅い、連絡がつかない、話がかみ合わないなど |
| ✅ 説明が不十分、専門的すぎてわからない | 素人にも伝わる説明がない |
| ✅ 税務調査での対応に不満があった | 消極的だった、説明が一貫していなかったなど |
| ✅ 料金が高い or 不明瞭 | 料金体系が不透明、毎年の請求が変動しすぎるなど |
| ✅ 経営や節税のアドバイスが少ない | 単なる処理屋にとどまっている |
| ✅ 会社の成長に対応できていない | 会計ソフトやクラウドに対応していない、法人化支援ができない等 |
スムーズな変更手続きのポイント
税理士を変更する際は、感情的にならず、冷静に「手続き」と「引き継ぎ」を進めることが大切です。
✅ 手続きのステップ
1.変更理由の整理と新しい税理士の選定
→上記の「信頼できる税理士の選び方」を参考に比較・面談
2.現税理士に解約の意向を伝える
→メールまたは書面で「解約日・引き継ぎ方法」を明確に伝える
→礼儀として、感謝の言葉を添えると印象が良い
3.解約にあたっての確認事項を整理
→未払報酬の有無・契約書上の解約条件・引き継ぎ資料の返却
4.新税理士と引き継ぎを進める
→過去の申告書、会計データ、税務署とのやり取り履歴などを共有
5.税務署への「異動届」の提出(必要な場合)
→個人事業主が税理士を変更する場合、「税理士変更届出書」の提出が必要になるケースあり
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
税理士変更は、顧問先にとっても大きな判断であり、その背景には明確な不満やニーズの変化があります。
対応の遅さや不明瞭な料金体系、説明不足など、基本的な対応への不満が理由となるケースが多く見られます。
また、クラウド対応の遅れや事業ステージの変化に税理士がついていけないことも、変更の引き金になりがちです。
一方、変更手続きをサポートする立場としては、適切な引き継ぎ資料の確認や、前任税理士との調整など、実務的な配慮が求められます。
契約を守るだけでなく、期待を上回る価値を提供することが、顧問先からの継続的な信頼につながります。
税理士としての信頼を維持・向上させるためにも、「なぜ変更されたのか」「どう対応すべきか」を冷静に見直すことが重要です。
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















