INDEX
おすすめ記事
-

会計事務所の職種を徹底解説|税理士・内勤・会計入力スタッフなどの仕事内容と役割
-
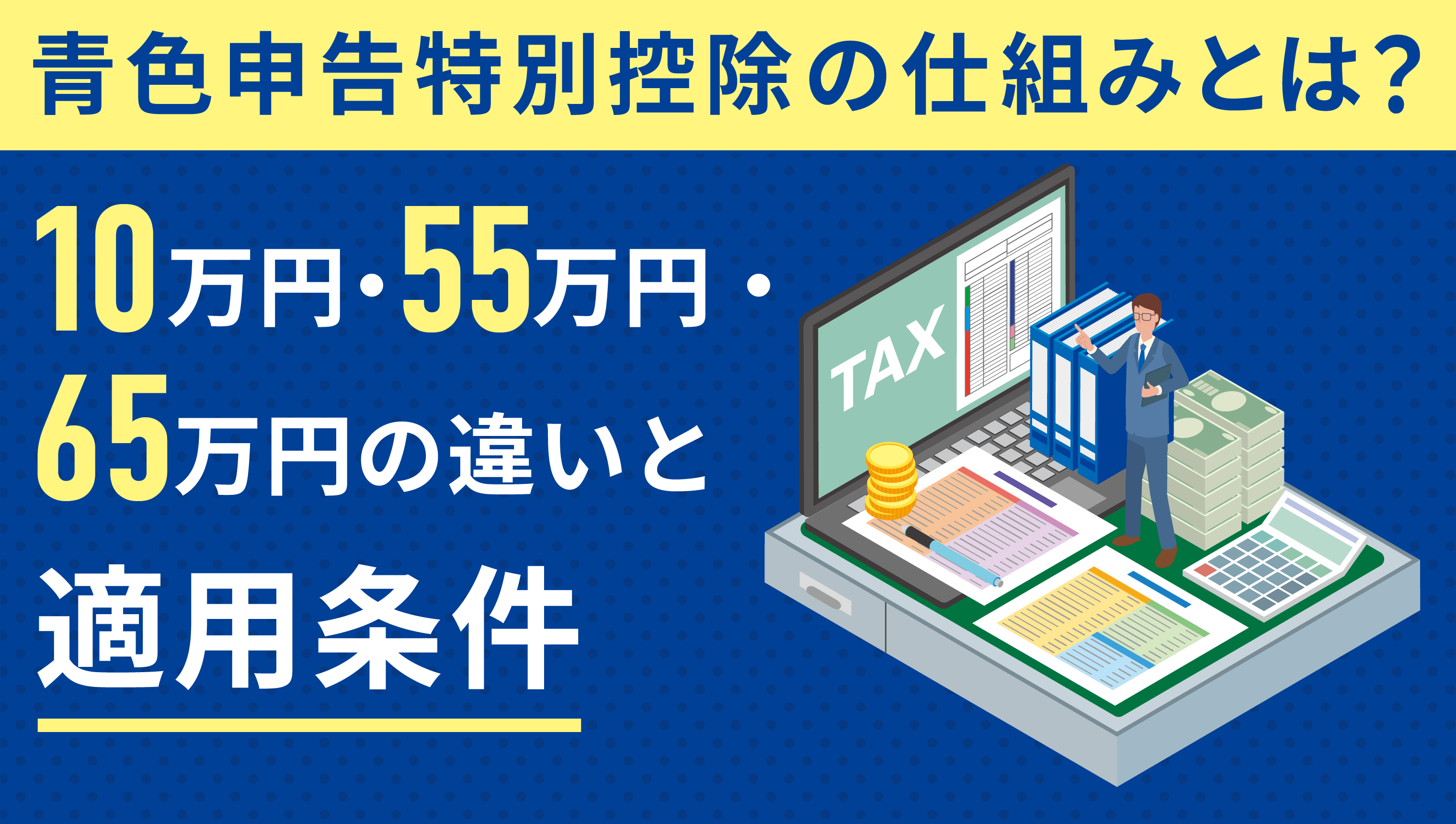
青色申告特別控除の仕組みとは?10万円・55万円・65万円の違いと適用条件
-

M&A特化・ブティック型事務所のサービスはなぜ市場価値が高いのか?【めざせ!TAX MASTER#35】
-
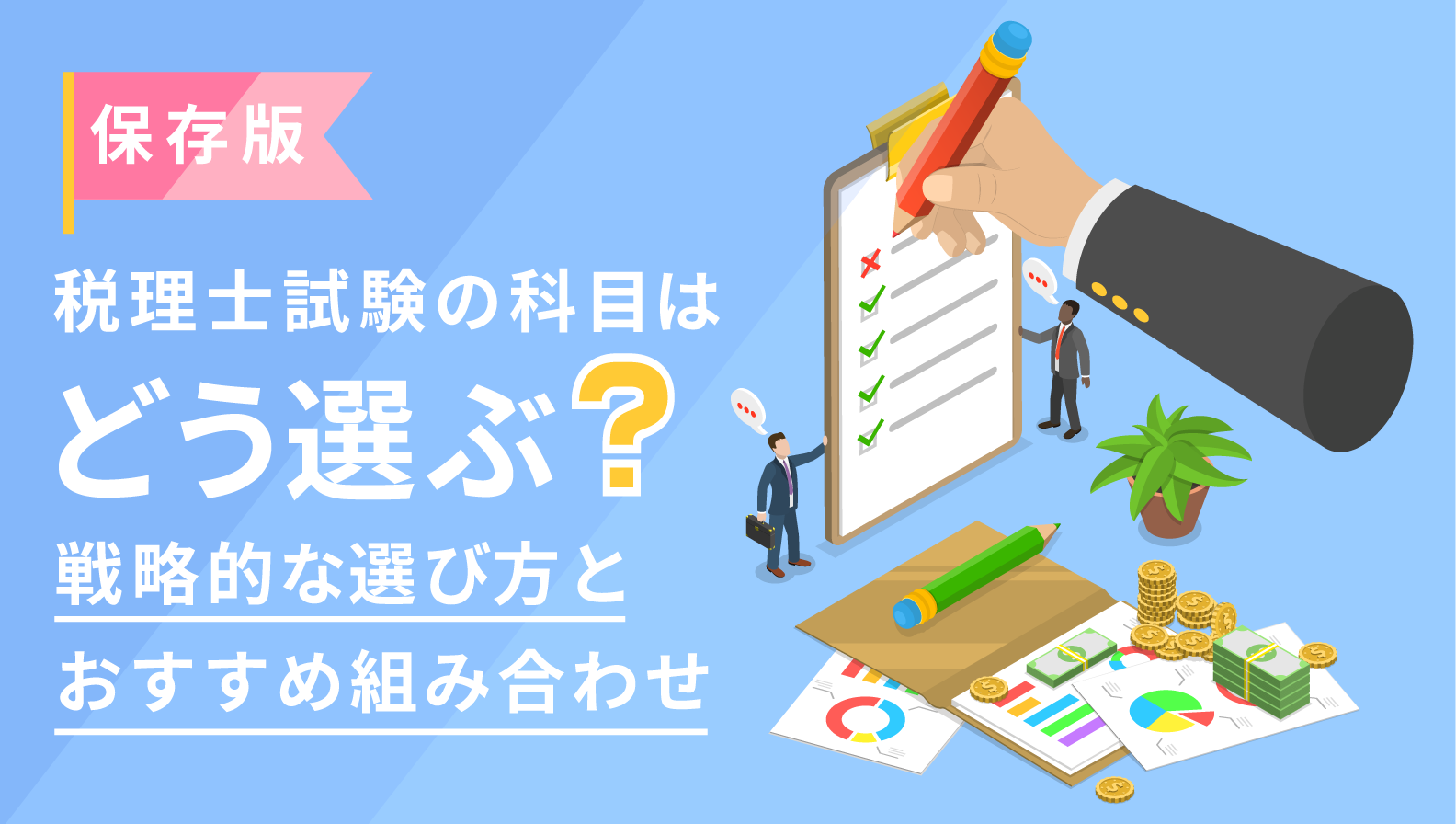
【保存版】税理士試験の科目はどう選ぶ?戦略的な選び方とおすすめ組み合わせ
-
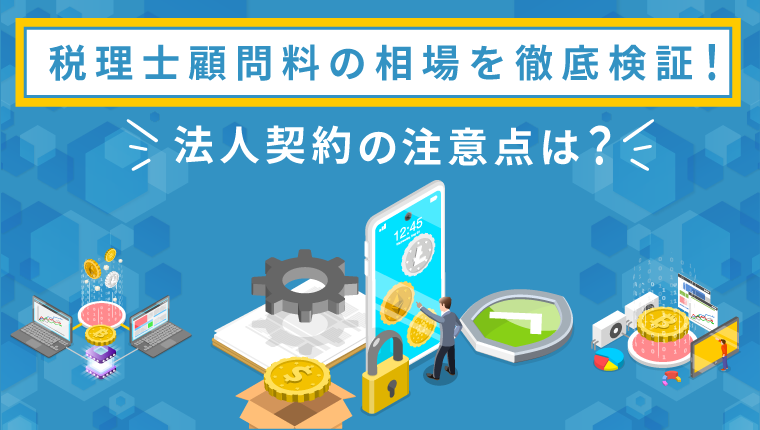
税理士顧問料の相場を徹底検証!法人契約の注意点は?【保存版】
公開日:2025/05/23
最終更新日:2025/09/11
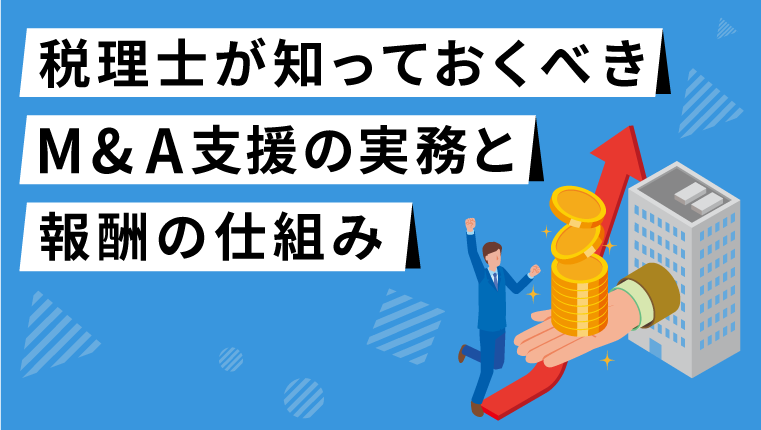
INDEX
「顧問料は上げづらい」「相続案件も限界がある」
そう感じている税理士の方にこそ、いま注目してほしいのがM&A支援です。
後継者不在に悩む中小企業が急増し、M&Aのニーズは年々高まっています。
一方で、信頼できる税理士がM&Aに関与するケースは、まだまだ限られています。
実は、顧問先の誰よりも財務を理解し、経営者と継続的に対話している税理士こそ、
「M&Aの種」を最も早く見つけ、的確に支援できるポジションにあるのです。
この記事では、M&Aにおいて税理士が果たす主な役割と、なぜ税理士にM&A支援が求められているのかについて詳しく解説します。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
なぜ今、税理士にM&A支援が求められるのか?
近年、M&Aは大企業だけの戦略ではなく、中小企業にとっても重要な経営手段となりつつあります。特に事業承継や成長戦略の一環として、第三者への引き継ぎや資本提携を検討するケースが増加しています。
こうした流れの中で、税理士がM&A支援の現場で活躍する機会も着実に広がっています。税務の専門家としての知見に加え、顧問先との信頼関係や財務状況への深い理解を持つ税理士はM&Aの成功に欠かせない存在となりつつあります。
では、なぜ今、税理士がM&A支援の担い手として求められているのでしょうか。背景となる3つの要因を見ていきましょう。
1. 中小企業の事業承継問題が深刻化している
日本の中小企業は、経営者の高齢化に伴い、後継者不在という課題に直面しています。帝国データバンクの調査によれば、60歳以上の経営者の約半数が後継者未定という状況にあります。こうした背景から、第三者への事業承継=M&Aが注目を集めています。
2. M&Aニーズの増加と実務的な課題
M&Aは単なる買収・売却の手続きではなく、税務・会計・法務・経営戦略が複雑に絡む領域です。特に中小企業では、買収価格の妥当性評価やスキーム設計において税務の視点が極めて重要になります。ここに、税理士の知見が不可欠です。
3. 税理士ならではの「信頼性」と「中立性」
税理士は日頃から顧問先の財務内容を把握し、節税や税務申告を支援しているパートナーです。この継続的な関係性に基づいた深い信頼と、第三者としての中立的な立場は、M&Aプロセスにおいても大きな価値を持ちます。
また、税理士は税務リスクや資産評価に関する専門的知見を持ち、適切な助言ができる存在として、M&Aの成功に貢献できます。
M&A業務における税理士の主な役割とは?
特に中小企業のM&Aでは、税務リスクの見極めやスキーム設計の良し悪しが、取引の成否や経済的メリットに直結します。
税理士は、日常的に企業の財務状況を把握している立場だからこそ、M&Aにおいても実務的かつ信頼性の高い支援が可能です。ここでは、税理士がM&A業務で担う主な役割について、4つの観点から詳しく見ていきましょう。
1. スキーム設計の支援
M&Aにおいて最も初期かつ重要なのが「どのようなスキームで実行するか」の設計です。
税理士は、以下の観点から最適なストラクチャーを検討・提案します。
・株式譲渡 vs 事業譲渡の比較(法人税・消費税・登録免許税など)
・持株会社化や分社化による税負担の軽減
・役員退職金・資産売却等を活用したキャッシュ最適化
・再編スキーム(合併・会社分割等)の活用
税務を無視したスキームは、想定外の税負担を招くリスクがあるため、税理士の関与は必須です。
2. 税務デューデリジェンス(Tax DD)の実施
買収側にとって、対象会社に過去の税務リスクや潜在債務がないかを事前に把握することは極めて重要です。
税理士は以下の観点でDDを行います。
・過去の申告内容や税務調査履歴の確認
・未認識の簿外債務や不適切な経費処理の洗い出し
・税務上の欠損金・繰延税金資産の引継可否の判断
・節税スキームが不適切かどうかの検証
この作業により、価格交渉材料や契約条件への反映が可能になります。
3. 株式譲渡・事業譲渡における税務論点の整理
税理士は、譲渡形式ごとに異なる税務処理を整理し、顧客に正確な助言を提供します。
| 項目 | 株式譲渡 | 事業譲渡 |
| 課税主体 | 個人/法人の株主 | 譲渡法人 |
| 主な税目 | 譲渡所得税 | 法人税、消費税、登録免許税など |
| 簿外債務の引継ぎ | 原則なし | 原則なし(債権者同意が必要) |
| のれんの発生 | あり(買収側で償却) | あり(資産超過時) |
| 手続の複雑さ | 比較的簡易 | 契約・資産個別移転が必要 |
4. 節税を意識したストラクチャー提案
税理士は、税務面での最適化を図りながら、依頼者にとって最も有利なスキームを設計します。
・株主への譲渡所得課税 vs 役員退職金による損金処理
・売却益の圧縮に向けた固定資産売却・引当金計上のタイミング調整
・資本政策との連携(事前の持株比率見直し)
・個人事業主から法人化したケースのM&A対策
このように、節税の観点を持ったストラクチャー設計は税理士の得意分野です。
M&A支援に必要な知識とスキルセット
M&A支援において税理士が果たす役割は、単なる税務アドバイスにとどまりません。スキーム設計から企業価値評価、他士業との連携まで、幅広い専門知識と実務スキルが求められる高度な業務領域です。
特に中小企業のM&Aでは、限られた情報やリソースの中で、的確な判断と実行支援が必要とされる場面が多く、税理士の専門性が大きな武器になります。ここでは、税理士がM&A支援を行う上で押さえておくべき主要な知識とスキルセットについて、3つの観点から詳しく解説します。
1. 会計・税務・法務の基本知識
M&Aは、複数の分野が交差する総合格闘技のような業務です。以下の基礎知識は必須です。
会計の知識
・企業の財務諸表分析(BS/PL/CFの読み解き)
・のれん、繰延税金資産、減損などの会計論点
・会計基準(日本基準/IFRSなど)の違い
税務の知識
・株式譲渡・事業譲渡・合併・分割等の再編税制
・グループ法人税制、欠損金の引継ぎ要件
・所得税・相続税・消費税を含めたクロス税目の視点
法務の基礎
・株主構成、登記、契約書(譲渡契約・表明保証等)
・労務・許認可・債権債務の承継可否など、取引スキームに応じた法的制約
2. 企業価値評価(バリュエーション)の理解
買い手・売り手双方にとって「適正価格」の把握は最重要です。税理士は会計データに強みを持つため、以下のバリュエーション知識は実務で役立ちます。
主な評価手法
・DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー):将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価
・マルチプル法:EBITDAや売上高倍率など、業界指標を用いた相対評価
・純資産法(簿価/時価):資産の時価修正を反映した評価
税理士が貢献できる点
・BS・PLからの正確な調整(過大債務・引当金・簿外資産の発見)
・税効果会計を含めたキャッシュベースの利益把握
・「実効税率」を加味した企業価値の見積もり
3. 他士業との連携体制の構築
M&Aはワンストップ対応が求められるため、税理士単独では限界があります。他士業との連携体制の構築が成功のカギを握ります。
連携が必要な士業・専門家
| 士業・専門家 | 主な役割 |
| 弁護士 | 契約書作成、法的リスクの確認、労務問題 |
| 公認会計士 | 会計DD、PPA、IFRS対応 |
| 中小企業診断士 | 経営戦略、シナジー分析、PMI支援 |
| M&A仲介・FA | マッチング、交渉、相場感の提供 |
税理士は「税務の総合窓口」として、全体の進行管理と専門家連携のハブとなる役割も期待されています。
M&A支援における報酬体系と収益モデル
税理士がM&A支援に関与する機会が増える中で、報酬体系や収益モデルの設計は、事務所経営の観点からも重要です。
ここでは、M&A支援における代表的な報酬体系や契約形態について、実例を交えながら詳しく解説します。
1. 着手金・成功報酬の相場と実例
M&A支援では、通常「着手金+成功報酬」の二段構えの報酬体系が採用されます。
■ 着手金
・業務に着手する段階で支払われる報酬
・相場:30万円〜100万円程度
・デューデリジェンスや企業価値評価の資料作成等の初期コストをカバー
■ 成功報酬(主にレーマン方式)
以下のような段階的料率が一般的:
| 譲渡価格帯 | 料率(目安) |
| 5億円以下 | 5% |
| 5~10億円 | 4% |
| 10~50億円 | 3% |
| 50~100億円 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
※ 税理士が単独で対応する場合は、中小案件中心のため「最低成功報酬300万円〜500万円」を基準とする事務所もあります。
■ 事例:地方中小企業の株式譲渡支援
・着手金:50万円
・成功報酬:譲渡額1億円 × 5% → 500万円
・総報酬:550万円(+消費税)
2. スポット契約と継続契約の使い分け
■ スポット契約
M&A単体業務(譲渡スキーム設計、DD、契約支援など)に限定して対応
→ 「単発の高単価案件」に対応できる一方、業務が不定期
■ 継続契約(顧問契約ベース)
通常の税務顧問契約に加えて、
「M&A対応オプション」を付けることで平時から関係性を維持し、
いざというときに自然な流れで支援を提供可能。
例:
・月額顧問料+M&A発生時には成功報酬(特約条項あり)
・顧問契約先の後継者不在問題にM&A提案 → 自然なクロージングへ
顧問税理士だからこそできるM&Aの種の見つけ方
1. 顧問先の「隠れ売り手・買い手」を見つける視点
税理士は、他の専門家に比べて定期的に経営者と対話し、財務情報にアクセスできる稀有な存在です。そのため、本人が自覚していない「潜在的な売り手・買い手」の兆候を最前線で察知できます。
■ 隠れ“売り手”の兆候
| 観点 | アラートとなる要素 |
| 経営者年齢 | 60歳を超えても後継者が決まっていない |
| 役員構成 | 代表1名で役員に子弟や後継候補がいない |
| 業績推移 | 売上・利益が数年横ばいor緩やかに下落中 |
| 資産状況 | 過剰な現預金、遊休資産、株式などの含み益保有 |
| 私生活 | 相続や資産整理の話題が増える、健康面の懸念など |
■ 隠れ“買い手”の兆候
| 観点 | アラートとなる要素 |
| 財務余力 | キャッシュが潤沢で新規投資に悩んでいる |
| 成長意欲 | 新規事業やエリア拡大の意向がある |
| 組織構成 | 若手経営者や幹部が育ってきている |
| 業界構造 | 周囲の同業他社が高齢化・廃業傾向にある |
| 借入状況 | 借入枠に余裕があり、金融機関との関係も良好 |
2. 定量・定性の「アラート指標」を設ける
税務顧問先をリストアップし、以下のようなアラート項目にフラグを立てておくことで、継続的なM&A支援候補リストを作成できます。
定量的なアラート例(帳簿から拾える情報):
・代表者の年齢が65歳以上
・売上高が3年連続横ばい以下
・借入がなく、現預金が年商の50%以上
・非上場株式の含み益が大きい
・長年顧問をしていても事業承継の話題が出てこない
定性的なアラート例(面談や対話から得られる情報):
・「子どもには継がせたくない」と発言
・「人手不足で限界だ」と漏らす
・「近くの○○さんが会社を売ったらしい」などの反応
・経営者自身が新規事業に関心を持ち始めている
3. 顧問先への自然なアプローチ方法
税理士が顧問という立場でいきなり「会社を売りませんか?」とは言いづらい場面も多いですが、次のような切り口で話題を導入できます:
・「最近、同業他社がM&Aで事業承継したという例がありまして…」
・「このキャッシュの厚さなら、M&Aによる投資も一つの選択肢になりますよ」
・「後継者問題が話題になることが多いですが、○○社長はお考えありますか?」
「提案」ではなく「共有」から入ることで、相手の抵抗感を下げるのがポイントです
M&A業務を始めたい税理士が最初にやるべきこと
1. M&A専門研修の受講と「中小企業庁・支援機関」への登録
なぜ必要か
M&Aは会計・税務に加え、法務・契約・バリュエーションなど多面的な知識が求められます。また、国の補助制度を活用するには、所定の登録要件を満たす必要があります。
取り組むべきこと
・M&A実務研修を受講し、基礎知識と実務対応力を習得する
(例:日本M&Aセンター、バトンズアカデミーなど)
・中小企業庁の「登録M&A支援機関」への登録を検討
・利益相反の管理や倫理規定、社内体制の整備
支援機関に登録することで、譲渡企業・買収企業に対し補助金の対象案件として支援が可能になります。
2. 提携先のM&A仲介会社との関係構築
なぜ必要か
税理士のみでは案件の探索や交渉、マッチング対応までカバーするのは難しい場面も多く、他士業や仲介事業者との連携が不可欠です。
取り組むべきこと
・地域の仲介会社(日本M&Aセンター、バトンズ、トランビ等)と提携交渉を行う
・「売却ニーズを紹介」「DDのみ対応」「譲渡側アドバイザーに専念」など、自身の役割を明確化する
・必要に応じて弁護士や公認会計士との連携体制を構築する
税理士は顧問先の信頼を得ているため、最初の相談窓口として機能しやすい点が大きな強みです。
3. 自身の業務モデルの棚卸しとパートナー戦略
なぜ必要か
顧問契約との親和性を意識しながら、自事務所の強みや方針に合ったM&A支援の形を構築することで、継続性のある収益化が可能になります。
取り組むべきこと
・自事務所の顧問先を整理し、経営者年齢・後継者の有無・業績推移などからM&A対象を把握する
・自身のスタイルに応じたモデルを設計する(スキーム設計特化型、紹介連携型、顧問先深耕型など)
・他士業やM&A関連団体(士業連携ネットワークなど)に加入し、情報共有や案件紹介ルートを確保する
単なる案件対応ではなく、「事務所としての支援モデル」として組み込むことで、営業力や再現性が高まります。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士が知っておくべきM&A支援の実務と報酬の仕組み -まとめ
M&A支援に取り組む税理士には、実務スキルの習得だけでなく、信頼できる外部パートナーとの連携や、自事務所の業務モデルとの整合性が求められます。
最初の一歩は、「学ぶこと」「つながること」「整理すること」。この三つを着実に進めることで、税理士はM&Aの現場でも価値を発揮し、顧問先の経営課題に応える存在となれます。
この記事が少しでもお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















