INDEX
おすすめ記事
-

タックスプランニングとは?知って得するタックスプランニングの最新トレンドと手法
-
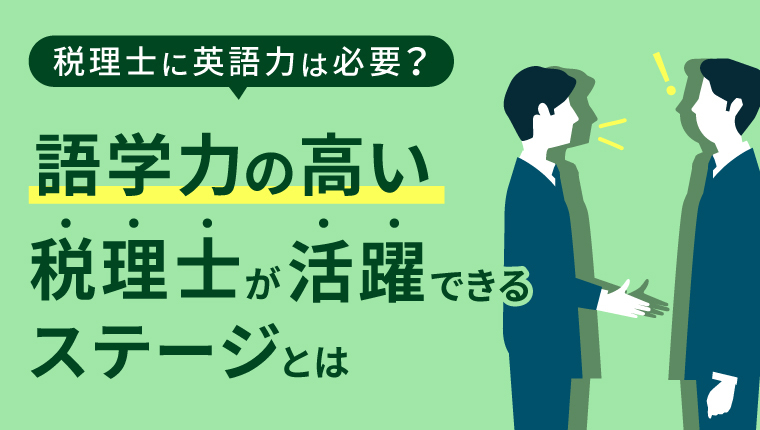
税理士に英語力は必要?語学力の高い税理士が活躍できるステージとは
-
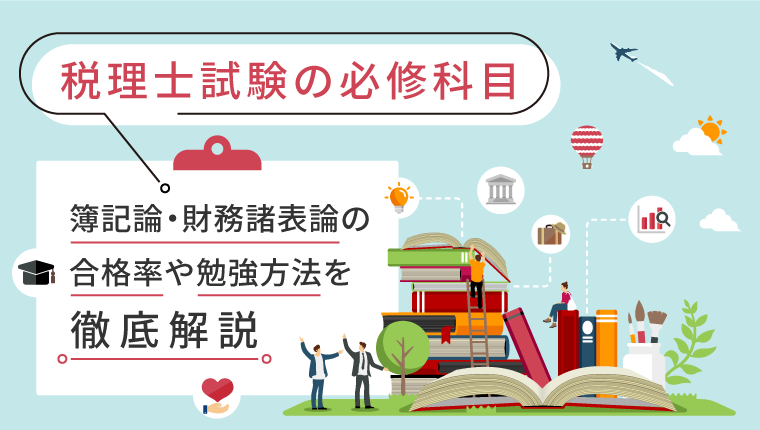
【税理士試験の必修科目】簿記論・財務諸表論の合格率や勉強方法を徹底解説
-
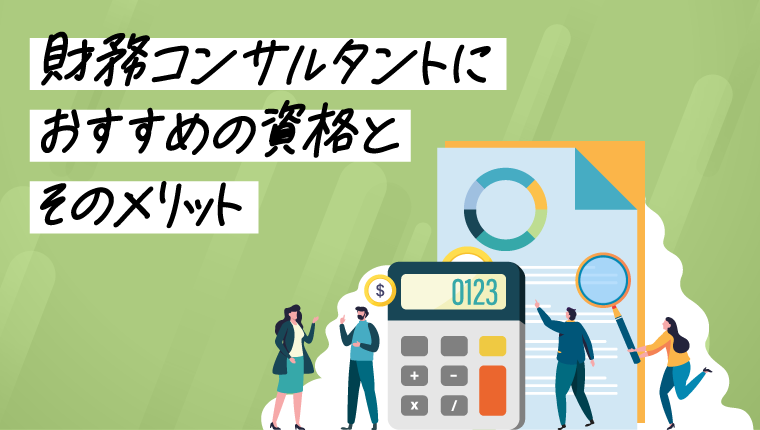
財務コンサルタントにおすすめの資格とそのメリット
-
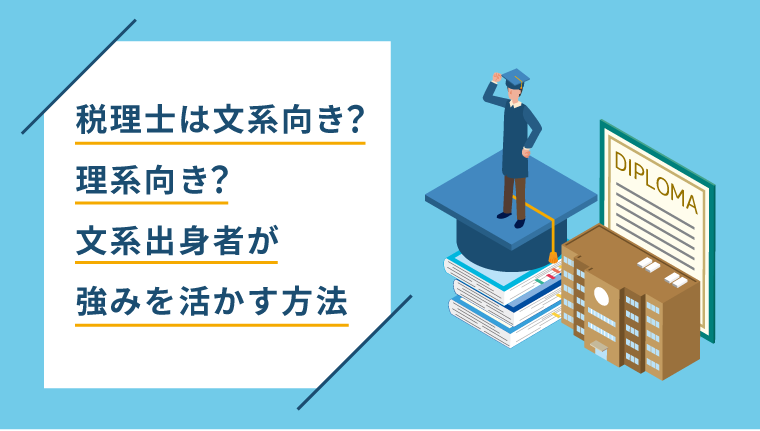
税理士は文系向き?理系向き?文系出身者が強みを活かす方法
公開日:2024/12/21
最終更新日:2025/09/08
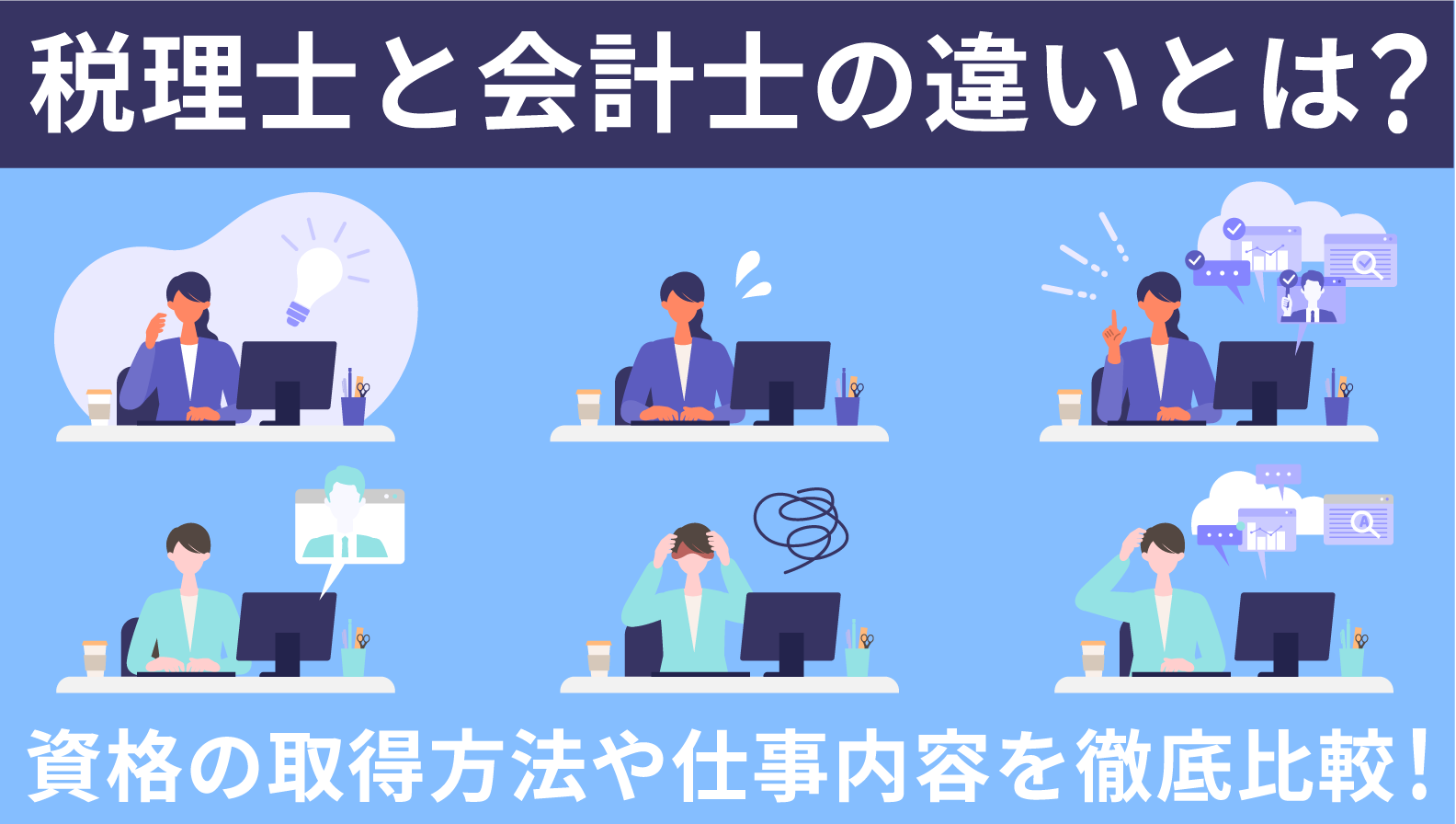
INDEX
「税理士と会計士、向いている人はどんな人?」
「将来独立するならばどちらがいいんだろう?」
と悩んでいる人はいませんか?
税理士・会計士ともにやりがいのある仕事であるため、悩む人も多いことでしょう。
この記事では、税理士と会計士の違い
について、徹底解説していきます。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
基本的な税理士と会計士の違いとは
会計士と税理士の違いとしては、主に以下の点が挙げられます。
税理士と会計士の仕事内容の違い
税理士と公認会計士は数字や経営戦略に強い専門職 ですが、税務に特化する税理士と、会計や財務分析、経営支援を中心に行う公認会計士では業務の種類や範囲が大きく異なります。税理士と公認会計士がどのような仕事内容を担い、どのように業務範囲やクライアント対応が異なるのかを深く掘り下げていきましょう。
税理士の仕事内容
「税務」を中心としたサポート業務を行います。扱う分野は広範囲にわたり、経営者や個人事業主にとって欠かせない専門家です。
税務相談業務
税務相談は経営者や個人が頼りにする仕事
の一つです。具体的には以下の内容が含まれます。
・節税対策のアドバイス
・税法改正後の適切な対応方法
・納税方法や期限のサポート
税務相談は企業の経営状況や業務の内容に応じて変わるため、幅広い専門知識や経験が必要 です。
税務調査対応
税務署から税務調査を受けた際には、税理士が代理となって対応 します。クライアントが税務署に提出した書類や申告内容の誤りや不明点がある場合、税理士がクライアントをサポートしながら調査対応を進めるため、専門知識がフルに発揮される場です。
経営支援と財務アドバイス
税務業務に加えて、経営支援や財務アドバイスを行う
場合があり、提供する経営支援には以下の内容が含まれます。
・経営状況の分析
・コスト削減策の提案
・財務データをもとにした戦略策定
経営支援は税務問題の解消のみならず、経営の継続性や成長戦略の立案に関わる重要なサポート です。経営者と密接に関わることで、経営面でも信頼されるパートナーとなります。
公認会計士の仕事内容
会計監査
代表的な業務が「会計監査」 です。監査では、企業が作成する財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)が適切かどうかを第三者の立場から検証します。企業が投資家や株主、金融機関に向けて報告する情報が正確であることを保証するため、監査は企業経営の透明性確保にもつながっています。
経営戦略サポート
会計データや市場データを収集・分析し、経営者が経営判断を行う際の戦略立案をサポート します。経済市場の変動や企業の成長戦略をデータに基づき分析し、最適な経営戦略を提案する役割です。
経理業務改善のアドバイス
経理部門の業務効率化や、システム導入を通じた業務改善の提案 を行うこともあります。業務の無駄を排除し、経理業務の生産性を向上させることで、企業全体の経営改善にも貢献することも業務の一つです。
税理士と会計士のクライアント先の違い?
税理士と公認会計士では、クライアントとの関わり方や対象となる顧客が異なります。
税理士は主に中小企業や個人事業主を対象として支援 を行います。クライアントとの関係性は日常的で、密な信頼関係が必要 です。また、税理士は税務申告や税務相談を行ったり、経営に関するアドバイスを提供したりします。
公認会計士は大企業や上場企業の経営戦略やガバナンス強化をサポートするため、クライアントとの関わり方がより経営的視点に立ったもの になります。
会計士と税理士の違いを表にまとめます。
| 要素 | 税理士 | 公認会計士 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 |
|
|
| 業務範囲 | 税務分野のみ | 監査、財務分析、経営支援分野 |
| クライアント対象 | 中小企業や個人事業主 | 大企業、上場企業 |
| 主な独占業務 |
|
|
税理士と会計士の就職先の違い
税理士と公認会計士では、働き方や就職先、将来のキャリア展望 が大きく異なります。働き方や就職先の選択肢、年収の違い、そしてキャリアの展望を深掘りしていきます。
税理士の就職先
税理士の働き方は、主に以下のような種類があります。
1.税理士事務所勤務
多くの税理士は、税理士事務所に所属し、クライアントへのサービスを提供しています。税理士事務所では、税務申告や税務相談、確定申告支援などを行います。
2.企業内税理士として働く
税理士資格を活かして、企業の経理や税務部門で働くケースもあります。企業内税理士として働く場合、主に以下の業務を担当します。
・税務申告書類の作成
・税務調査対応
・税務コンサルティング
3.フリーランス・独立開業
税理士は独立して事務所の開設も可能です。
フリーランスとして働くことで、自分のペースで業務ができる一方、経営や営業活動にも責任がともないます。
税理士の働き方は比較的柔軟であり、個々のライフスタイルや専門性に応じて働き方を選択 できます。
公認会計士の就職先
公認会計士の主な働き方や就職先は以下の通りです。
1.監査法人勤務
公認会計士の約4割は「監査法人」に所属し、会計監査や経営アドバイザリー業務に従事します。
監査法人で働くことで、大企業や上場企業の財務データを第三者の立場で精査し、透明性を担保する重要な役割を担います。
2.企業内会計士
として働く
公認会計士資格を取得後、経理部門や財務部門で企業の財務戦略や経営支援を行う道もあります。企業内でのキャリアパスとして、経理業務改善や事業戦略の立案が担当できます。
3.コンサルティング業務
公認会計士は、監査だけでなく、経営戦略や業務改善支援、財務データ分析を行うコンサルティング業務にも従事できます。
公認会計士の職場環境は、税理士事務所よりも企業や組織、監査法人に集中し、より専門性の高い業務 を行います。
税理士と会計士の年収の違い
税理士と公認会計士の給与には明確な違い があり、業務範囲や働き方が異なるため、年収や報酬面にも違いが生じます。
税理士の年収
税理士の年収は、就職先や勤務形態によって幅があり
ます。
・税理士事務所勤務:年収400万円~700万円程度
・企業内税理士:年収500万円~900万円程度
・独立開業税理士:年収の幅が広く、年収1,000万円を超えるケースもあり
税理士は個人経営者のクライアントが多いため、収入は安定している場合と不安定になる場合が存在 します。
会計士の年収
公認会計士は、業務内容の専門性が高いため、年収も比較的高い水準
です。
・監査法人勤務:年収600万円~1,200万円程度
・企業内会計士:年収700万円~1,500万円程度
・経営コンサルティング業務:年収800万円~1,500万円程度
公認会計士は大企業や監査法人での勤務が多いため、報酬水準も比較的高く、将来的にも安定した収入 が見込めます。
税理士と会計士の資格取得の方法と難易度の違い
税理士の受験資格
税理士試験の受験資格には以下のような条件があります。
1.学歴による受験資格
2.資格による受験資格
3.実務経験による受験資格
なお、これらの受験資格については税法のみが必要で、2023年より、簿記論・財務諸表論の受験資格は撤廃
されました。
税理士試験の概要
税理士試験は必須科目と選択科目から選択する形で行われます。
【必須科目】
簿記論、財務諸表論
【選択必須科目】
所得税法または法人税法から選択
【選択科目】
消費税法、相続税法または酒税法、国税徴収法、住民税または事業税、固定資産税です。
税理士試験の合格率と難易度
税理士試験は、科目ごとに選択受験ができるため、全科目を勉強する必要はありませんが、専門性が求められます。
【 難易度】
税理士試験の難易度は高く、合格率は10%〜20%程度
です。
【勉強時間】
一般的には各科目で2〜3年程度、平均で8年程度の勉強が必要
です。
税理士試験は特定の科目に絞って勉強し、税務知識を深める形になります。
公認会計士の受験資格
公認会計士試験は、税理士試験のように受験資格の条件が無く、基本的には学歴や年齢に関係なく誰でも受験できます 。 ただし、試験の難易度が高いため、しっかりと勉強する必要があります。
公認会計士試験の概要
公認会計士試験は短答式試験と論文式試験の内容から構成されています。
【短答式試験】
財務会計論、管理会計論、監査論、企業法です。
【論文式試験】
必須科目と選択科目があります。
必須科目は、会計学、監査論、企業法、租税法です。
選択科目は、経営学、経済学、民法、統計学から1つ選択します。
公認会計士試験の合格率と難易度
公認会計士試験は幅広い範囲を対象とし、より高度な知識が求められます。
【 難易度】
難易度は税理士試験よりも高く、合格率は10%前後
です。
【勉強時間】
2~4年程度の勉強
が求められます。
公認会計士試験は、単なる暗記ではなく、論理的な思考や複雑な計算力も必要です。
試験における会計士と税理士の違いを表にまとめます。
| 要素 | 税理士試験 | 公認会計士試験 |
|---|---|---|
| 受験資格 | 学歴、資格、実務経験のいずれかが必要 | 誰でも受験可能 |
| 試験範囲 |
|
|
| 難易度 | 難易度は高いが選択科目で受験できる | 税理士試験よりも高い難易度で範囲が広い |
| 勉強時間 | 平均で8年程度の勉強が必要 | 2~4年程度の勉強が必要 |
公認会計士試験に合格すると税理士登録ができるようになるって本当?
公認会計士資格を取得した後に税理士登録を行うことが可能
です。そうすることで、複数の業務に対応できる柔軟性が手に入ります。
具体的な税理士登録の利点としては以下のとおりです。
- 1.税務申告や税務相談ができるようになる
公認会計士資格は会計や監査に特化していますが、税理士登録を行えば税務業務にも対応できるようになります。
- 2.業務範囲の広がり
税理士資格を併せ持つことで、税務・会計・経営戦略の領域をカバーでき、クライアントの多岐にわたるニーズへの対応が可能です。 - 3.市場価値が高まる
税理士と公認会計士の資格を両方取得していることで、転職市場や企業側からの評価が高くなります。
税理士と公認会計士に向いている人は?
税理士と公認会計士は、独自の業務内容やキャリアパス、働き方が異なるため、どちらを選ぶべきか悩んでいる方も少なくありません。「仕事内容」「試験制度」を基準に、どちらが自分に合っているかを考えるポイントを解説していきます。
仕事内容で選ぶポイント
税理士は「税務専門」、公認会計士は「幅広い経営支援や監査」を行う専門職であるため、この点を基準に考えましょう。
税理士が向いている人の特徴
- 1. 税務関連業務に興味がある
税務に強く関心があり、クライアントの税務支援を直接行いたい場合。 - 2. クライアントと関わる仕事が好き
税理士はクライアントとの関わりが多いため、人と接するのが好きな方。
公認会計士が向いている人の特徴
- 1. 財務分析や経営戦略に関心がある
公認会計士は、経営戦略や財務分析、経営コンサルティングを行うことが多く、経営全般に興味がある方。 - 2. 監査やデータ分析が得意
会計やデータ分析が得意で、企業や大手監査法人で働きたい場合。
試験制度で選ぶポイント
試験制度が異なるため、試験内容や難易度、勉強時間の観点から自分に向いている試験を考えましょう。
税理士試験が向いている場合
- 1. 科目ごとに分けて勉強したい方
税理士試験は複数の科目の中から興味のある科目を選べるため、集中して学びたい分野を選ぶことが可能です。 - 2. 時間をかけて資格を取得したい方
税理士は1科目ずつ受験が可能であり、個人のペースに合わせやすいため、計画的に資格を取得したい方に向いています。
公認会計士試験が向いている場合
- 1. 広い範囲の専門知識を身につけたい方
財務会計や税法、経済学、監査論など多岐にわたる試験科目が対象なため、幅広い知識を身につけることで、さまざまな業務へ対応することが可能です。 - 2. 難易度の高い試験に挑戦したい方
難易度が高い試験に挑戦し、専門性や問題解決力を鍛えたい方に適しています。
最新情報をGetしよう!
税理士と会計士の違い-まとめ
この記事では税理士と会計士を仕事内容や年収などの様々な観点で比較しました。
税理士と公認会計士は、それぞれ異なるキャリアパスと魅力を持つ職業です。
それぞれの業務の特性や試験の難易度等を鑑み、自身の興味や得意分野、キャリア目標に合わせて適切な資格を選択してください。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















