INDEX
おすすめ記事
-
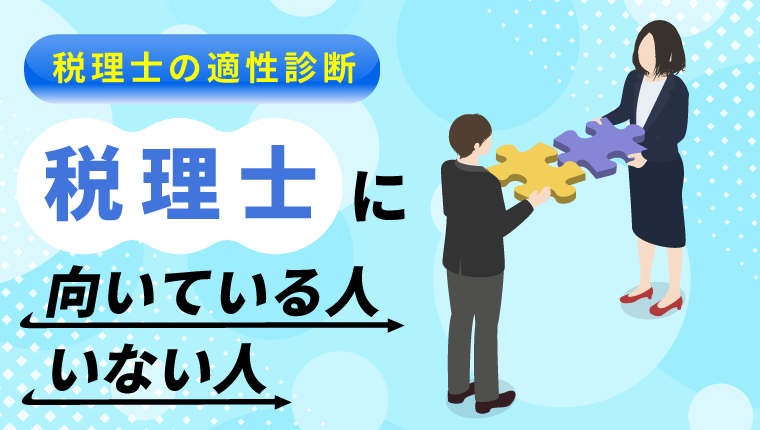
【税理士の適性診断】税理士に向いている人いない人
-

倒産寸前からV字回復!!税理士の事業再生支援【めざせ!TAX MASTER#34】
-
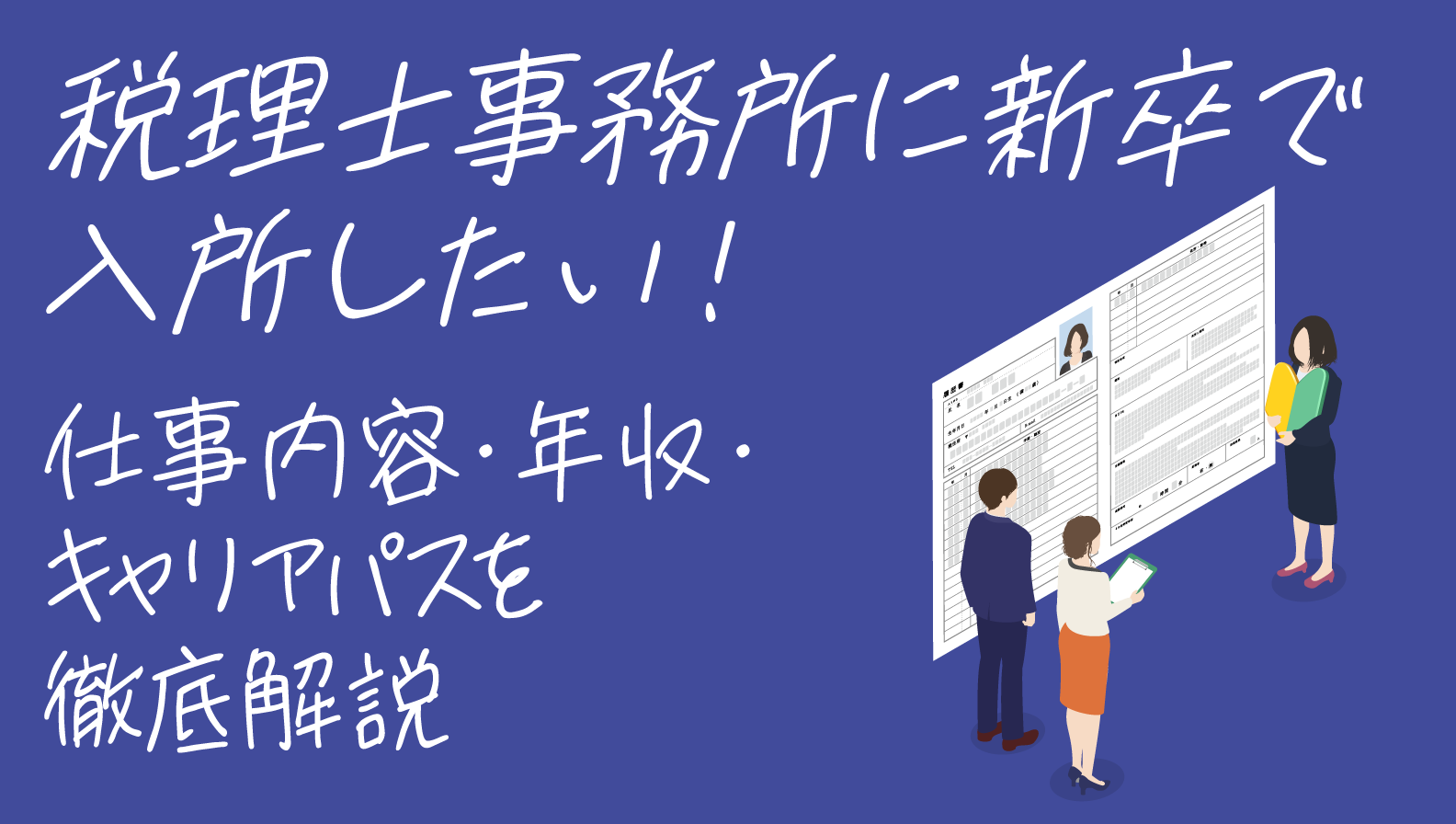
税理士事務所に新卒で入所したい!仕事内容・年収・キャリアパスを徹底解説
-
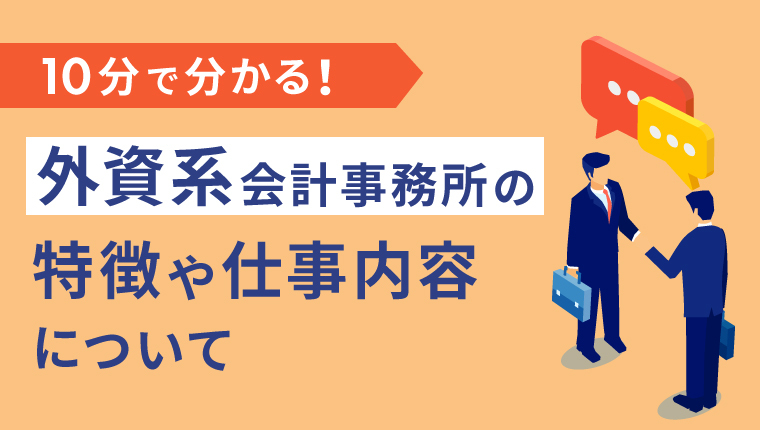
【10分で分かる!】外資系会計事務所の特徴や仕事内容について
-

税理士顧問料の値上げの理由やタイミングは?
公開日:2025/07/17
最終更新日:2025/09/06
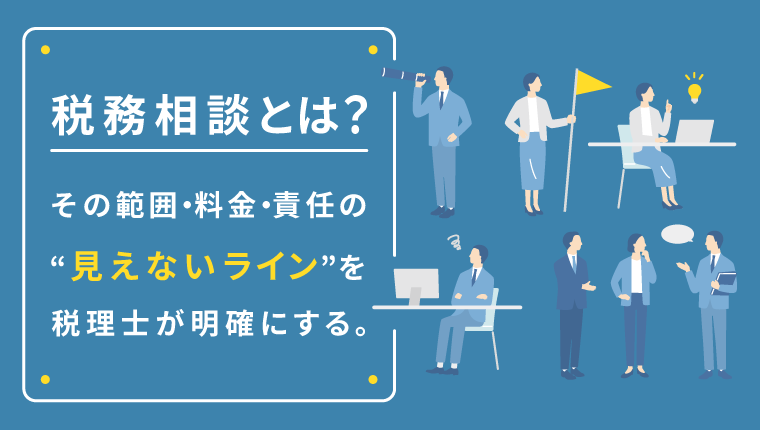
INDEX
「これって経費になりますか?」「副業の所得、申告しないとバレますか?」
こんな“ちょっとした税金の話”、あなたは誰に相談していますか?
ファイナンシャルプランナー?知り合いの起業家?ネットの掲示板?
実はそれ、法律違反になる可能性があります。
税務相談とは、専門的な知識と国家資格に基づいて行われる税理士の独占業務です。しかし、相談する側にとっても、受ける側にとっても、その「範囲」や「料金」、そして「責任の所在」が曖昧なまま進んでしまうことが多いのが実情です。
この記事では、現役税理士が「税務相談とはそもそも何なのか?」から始まり、その業務の境界線、料金の相場、責任のあり方まで、グレーになりがちな“見えないライン”を明確にしていきます。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
第1章 そもそも「税務相談」とは何か?
税理士法における「税務相談」の定義
税理士法第2条では、税理士の独占業務として以下の3つが定められています。
1.税務代理(申告・申請・不服申立て等の代理)
2.税務書類の作成
3.税務相談
このうち「税務相談」とは、簡単にいえば税法に基づく判断やアドバイスを行う行為全般を指します。たとえば、
・「これは経費になりますか?」
・「この取引、贈与税がかかりますか?」
・「この不動産の売却、税率いくらですか?」
こういった相談は、すべて税務相談の範囲に含まれます。
つまり、税法に基づいて“答えを出す”行為は、税理士の独占業務であり、税理士以外が報酬を得て行うと法律違反となります(税理士法第52条:2年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
「税務相談」と「経営相談」「節税アドバイス」の違い
ここでよく混同されるのが、「節税アドバイス」や「経営相談」との違いです。
たとえば、
・「この保険、節税になりますよ」は“営業トーク”に見えますが、「保険料を全額損金算入してOKです」は“税務相談”です。
また、経営的な助言の中にも税務判断が含まれる場合があります。ここで税務に踏み込んだ判断をするには、やはり税理士資格が必要になります。
したがって、FPや経営コンサルタント、行政書士が「税務的にこうです」と断定的な回答をするのは、一線を越えている可能性があるという点に注意が必要です。
よくある誤解:「税金の話=誰でもしていい」ではない
「知人に税理士がいるから、ちょっとだけ相談してみた」
「ネットで拾った情報をもとにアドバイスしてあげた」
こうした行為が悪意なく行われることもありますが、場合によっては違法行為になり得ることを、多くの人が知りません。
特に報酬を受け取る場合(現金でなくても“実質的な対価”があれば該当)、相談に応じる側にはリスクが伴いますし、相談する側も間違ったアドバイスで損害を被っても誰にも責任を問えないという結果になりかねません。
税務相談とは、「税務上どうなるか?」という“判断”を提供することです。その判断には専門知識と責任が伴い、安易に行うべきものではないのです。
税務相談の“範囲”をめぐるグレーゾーン
税務署への問い合わせと税理士の違い
「それなら税務署に聞けばよいのでは?」
確かに、税務署でも税に関する一般的な質問には答えてくれます。しかし、ここには明確な“壁”があります。
税務署はあくまで「法令の一般的解釈」に基づく説明しかできません。つまり、個別具体的なケースへの判断や助言は行えません。たとえば、「あなたのケースなら経費になります」とは原則言えないのです。
一方、税理士は依頼者の事情をふまえて、責任をもって「判断」し、対応を助言することができます。ここが最大の違いです。
FP・行政書士・コンサルとの業務境界
最近では、ファイナンシャルプランナー(FP)や行政書士、経営コンサルタントなどが副業的に“税務的なアドバイス”を行うケースも増えています。
・FP:「この保険商品は相続税対策に有効です」
・行政書士:「開業届を出す際、この所得の申告方法が有利です」
・コンサル:「役員報酬を下げれば節税になりますよ」
一見すると自然なアドバイスに思えますが、これらはすでに“税務相談”の範囲に含まれる可能性があります。特に「税法上どうなるか」の“判断”を伴うものは、税理士以外が報酬付きで行うと違法です。
税理士でない人が「うっかり違法」になるケースとは?
例えば、法人設立支援を行う行政書士が、顧客の節税希望に対し「消費税がかからない時期に設立した方がいいですよ」とアドバイスした場合、これは税法に基づく“判断”とみなされる可能性があります。
こうした「善意の助言」でも、受任者の資格と業務範囲を超えていれば法的リスクを抱えています。
税理士からすれば、「判断する以上は、その責任も引き受ける」ことになります。判断を下すのは資格者だけに許された“重い行為”です。
税務相談の料金相場と注意点
無料・初回相談の扱いとその意図
「初回相談無料」と掲げている税理士事務所もあります。しかし、ここには明確な意図があります。
・関係構築のきっかけにしたい
・顧問契約の導入前の相性確認
・相談の“質”を見極めるため
とはいえ、無料だからといって何でも相談していいわけではなく、無料相談では、税務リスクを伴う判断を避け、一般論の範囲にとどめる税理士も少なくありません。
顧問契約と単発相談の違い
税理士との相談には主に2つの形式があります。
| 形式 | 特徴 | 向いている人 |
| 顧問契約 | 継続的な相談・申告業務・税務代理など包括対応 | 会社経営者、事業者 |
| 単発相談 | 1時間○○円でその場限りの相談 | スポットで税務判断が必要な個人 |
顧問契約であれば、顧客の状況や過去の取引を継続的に把握しているため、背景を踏まえた判断が可能です。一方、単発相談では情報が限定されているため、税理士側も慎重にならざるを得ません。
「30分○○円」の料金形態の内訳と背景
税理士の相談料は以下のような形で設定されることが一般的です。
| 時間 | 料金の目安 |
| 30分 | 5,000円〜10,000円 |
| 60分 | 10,000円〜20,000円 |
「高い」と感じるかもしれませんが、この中には以下のような要素が含まれています。
・専門知識と法的責任
・準備・事前調査・相談記録の管理
・誤った判断が及ぼす損害リスク
税理士は単に“答え”を提供しているのではなく、相談者の税務リスクを背負って判断しているという点が、料金の背景にあります。
税務相談の“責任”は誰が持つのか?
■ 誤ったアドバイスの責任範囲
税務相談では「その場しのぎ」のアドバイスが、後々大きなトラブルに発展することがあります。
例えば――
「それ、経費で落とせますよ」と言われたので実行したところ、
税務調査で否認され、追徴課税と延滞税で数十万円の追加負担になった。
このとき、もし税理士による助言であれば、一定の責任追及が可能です。税理士は「専門家としての注意義務」を負っており、明らかな過失があれば損害賠償請求の対象となることもあります。
一方、税理士資格を持たない者の“好意の助言”であれば、誤っていても誰にも責任は問えません。
つまり、「責任を持てない人に相談すると、すべて自己責任になる」ということになります。
税理士の責任と“職業的懲戒”
税理士は、税理士会や国税庁に登録された国家資格者であり、業務上の不正や過失に対しては懲戒処分が科されます。
具体的には――
・戒告
・業務停止
・登録抹消
などの懲戒があり、実際に年に数十件の処分例があります。これは裏を返せば、税理士が業務に対して高い倫理性と責任を持っているという証拠でもあります。
「名前を出して責任を取る」という姿勢は、相談者にとって大きな安心材料になります。
記帳代行・申告書作成とのリスクの違い
記帳代行や申告書の作成だけであれば、形式的な業務に留まる部分もありますが、税務相談には「判断」が常に伴います。
たとえば、以下のような判断は、形式作業ではなく専門的な見解が問われます。
・この支出は費用か?資産か?
・減価償却の方法はどうすべきか?
・適用される税率や特例の選択
これらに間違いがあれば、申告自体が間違っていたという話になるため、税務相談こそ最も慎重に行うべき分野なのです。
こんな税務相談には要注意!
「友達価格で相談に乗って」と言われたとき
知人や友人から「ちょっと教えて」と頼まれたとき。
つい親切心で答えてしまいがちですが、これは最もトラブルが多いパターンです。
なぜなら、友人関係があることで
・無償=責任も曖昧
・誤解が起きても指摘しづらい
・後になって「言った/言わない」論争になりやすい
という構造的リスクがあるからです。
「税務相談は、友達だからこそ慎重に」
この意識を持つだけで、後のトラブルを大きく減らせます。
ネットで拾った情報をベースに聞かれたとき
「ネットでこう書いてあったけど、実際どうなの?」という相談も、近年よくあります。
しかし、インターネット上の情報は
・法改正前の古い記事
・個別事例でしか通用しない話
・曖昧な表現や誤解を生む書き方
が非常に多く、税理士としても安易に肯定も否定もできません。
こういった場合は、「一般論と違う可能性があります。具体的に確認させてください」と丁寧に対応する必要があります。
依頼者の「言った/聞いてない」問題を回避するには?
税務相談では、依頼者が後になって「そんな説明はなかった」と主張するケースもあります。
このリスクに備えるため、税理士としては
・相談内容の記録(メモ・メール等)
・アドバイスの根拠を明記
・結論を文書で残す
といった対応が重要になります。
また、相談者側としても「言った/聞いてない」問題を防ぐためには、相談内容を自分でも記録する姿勢が望まれます。
税務相談を“価値あるもの”にするために
相談前に整理すべきこと
税務相談の価値は、どれだけ情報が的確に伝えられるかで大きく変わります。
税理士は「判断」を行う専門家ですが、情報が不足していてはその判断の精度も下がってしまいます。
相談前に、以下の点を整理しておくと効果的です。
・相談内容の概要(何に悩んでいるのか)
・関連する金額・時期・契約内容
・すでに取った行動(購入済・契約済など)
・使いたい制度や特例(あれば)
このように事前準備をすることで、税理士側もより深く状況を把握でき、その場限りではない、実務に根ざしたアドバイスが可能になります。
良い税理士の見分け方・質問の仕方
税務相談は、「答えてもらう」だけの場ではありません。
むしろ、相談の仕方次第で、得られる価値は大きく変わります。
▼良い税理士の特徴
・質問に対して明確な根拠を示す
・「それは判断できません」と必要に応じて線を引ける
・リスクと選択肢を並列で説明できる
・一方的に押しつけず、判断材料を提示してくれる
▼良い質問の仕方
・「こういう前提のとき、どうなるか教えてください」
・「この制度は使えますか?」よりも「この状況で何か使える制度はありますか?」
・「何が一番いいですか?」よりも「AとBを比べて、それぞれのメリット・デメリットは?」
こうしたやりとりができる関係こそが、信頼できる税理士との“知的パートナーシップ”の始まりです。
単なる情報提供ではなく「判断」の価値を買っている
無料のネット記事やAIでも、一定の税務情報は手に入る時代です。
しかしそれはあくまで「材料」でしかありません。
税理士の仕事は、その材料をもとに「最適な答えを出す」こと。
その答えには、資格に裏打ちされた法的判断と、実務経験に基づくバランス感覚が宿っています。
税務相談とは、「その答えに対する責任も含めて、料金を支払う行為」です。
だからこそ、安すぎる相談には慎重になり、高い相談料には「判断の重み」が含まれていることを知っておくべきです。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
この記事では「税務相談とは?」について解説させていただきました。
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















