INDEX
おすすめ記事
-
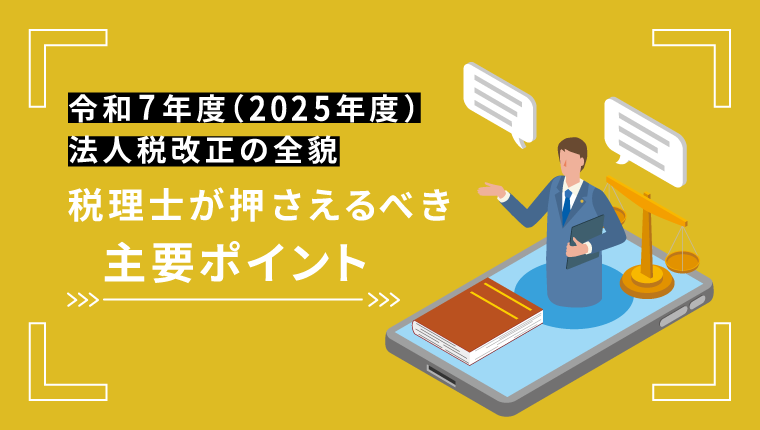
令和7年度(2025年度)法人税改正の全貌:税理士が押さえるべき主要ポイント
-
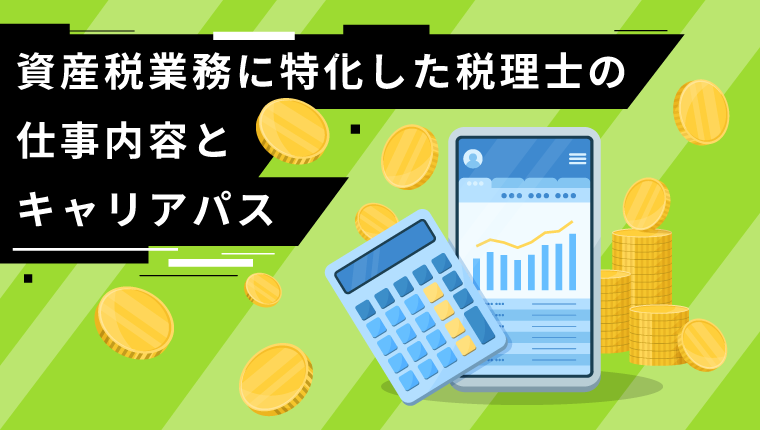
資産税業務に特化した税理士の仕事内容とキャリアパス
-

外形標準課税とは?対象法人や計算方法、2024年(令和6年)税制改正内容を徹底解説
-
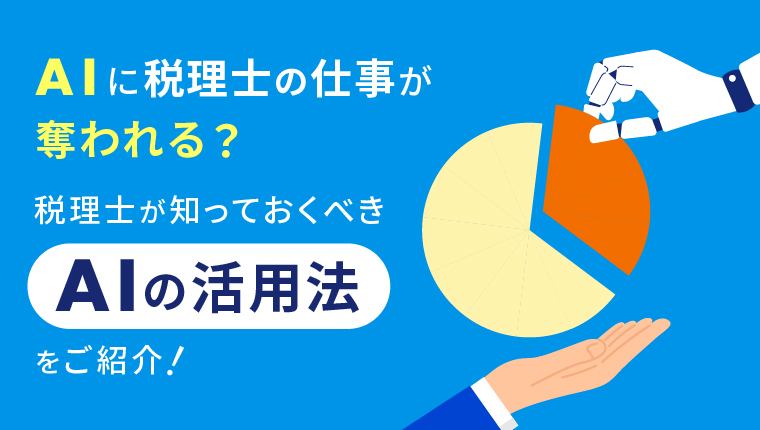
AIに税理士の仕事が奪われる?税理士が知っておくべきAIの活用法をご紹介
-
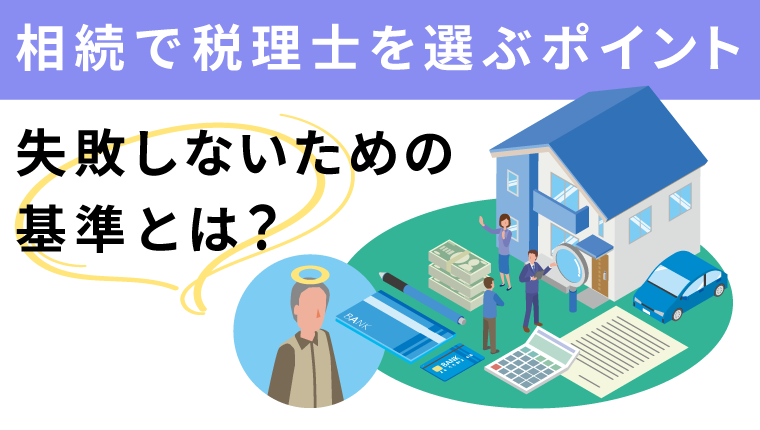
相続で税理士を選ぶポイント:失敗しないための基準とは?
公開日:2025/09/28
最終更新日:2025/09/28
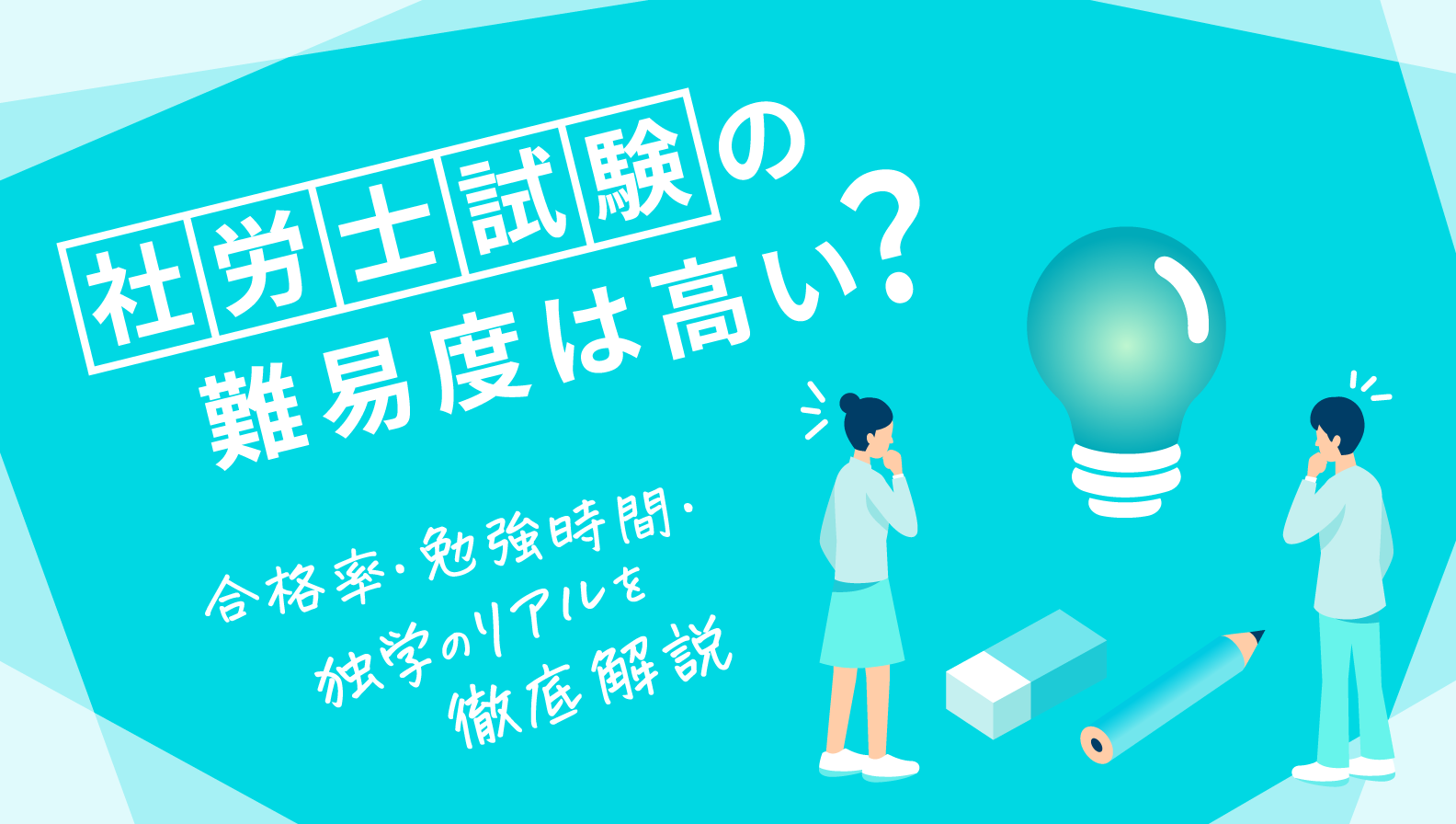
INDEX
「社労士(社会保険労務士)に挑戦したいけど、試験の難易度って実際どうなんだろう?」
そう思って調べている方は多いでしょう。社労士は社会保険や労働法の専門家として高い需要があり、独立開業や企業内キャリアアップにも直結する国家資格です。
しかし、合格率は一桁台と低く「難関資格」と言われることもしばしば。本記事では、社労士試験の難易度を 合格率・必要勉強時間・科目の特徴・独学の可否 といった視点から徹底解説します。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
社労士試験の基本概要
まずは試験の全体像を整理します。
・受験資格:学歴・実務経験など一定条件あり(大卒以上が一般的)
・試験形式:選択式(マークシート・空欄補充)+択一式(マークシート)
・試験科目:労働基準法、社会保険、労災、年金、労務管理など合計10科目
・実施時期:毎年8月下旬
・合格基準:総得点で一定以上かつ科目ごとに基準点をクリアすること
ポイントは「総得点だけでなく科目ごとに基準点がある」ため、得意不得意の偏りで落ちるケースが多いことです。
合格率から見る難易度
直近5年間の合格率の推移は以下の通りです。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 約37,000人 | 約2,200人 | 6.4% |
| 2021年 | 約41,000人 | 約2,900人 | 7.1% |
| 2022年 | 約41,000人 | 約2,500人 | 6.1% |
| 2023年 | 約40,000人 | 約2,600人 | 6.5% |
| 2024年 | 約39,000人 | 約2,500人 | 6.4% |
平均すると 合格率は約6〜7%。毎年40人に1人程度しか合格できません。
合格率だけ見れば司法書士や税理士と並ぶ「難関資格」と言えるでしょう。
社労士試験が難しい理由
1. 試験範囲の広さ
社労士試験の最大の特徴は、10科目にわたる膨大な範囲を網羅する必要があることです。
カバーすべき科目は以下の通りです。
・労働基準法
・労働安全衛生法
・労働者災害補償保険法(労災保険)
・雇用保険法
・労働保険徴収法
・健康保険法
・国民年金法
・厚生年金保険法
・労務管理その他労働に関する一般常識
・社会保険に関する一般常識
法律系資格試験の中でも、これだけ幅広い法律・制度を横断的に学ぶ資格は多くありません。
例えば、労働基準法だけでも労働時間・休日・割増賃金・解雇・休業補償など細かい規定が多数あり、それを「暗記する」だけでなく「関連する他法令と組み合わせて理解する」ことが求められます。
さらに試験では「総得点」だけでなく「科目ごとの基準点」をクリアする必要があるため、一つでも苦手科目があると不合格になってしまいます。この「科目の広さ+基準点制度」が社労士試験を一層難しくしている大きな理由です。
2. 法改正への対応
社労士試験が難しいもう一つの要因は、頻繁に行われる法改正です。
労働・社会保険に関する制度は、少子高齢化や労働環境の変化に応じて毎年のように改正されます。
例えば:
・年金制度の支給開始年齢や受給額の見直し
・働き方改革関連法による労働時間規制の強化
・育児・介護休業法の改正
・雇用保険の給付条件や料率の変更
こうした改正内容は試験に即座に反映されるため、過去問を解くだけでは不十分です。常に最新の法改正情報を把握し、知識をアップデートし続ける必要があります。
特に独学者にとっては「法改正対応」が最大の壁になりやすいのです。
3. 実務的な出題
社労士試験は単純な暗記試験ではありません。実務を踏まえた応用的な出題が多いのも特徴です。
例えば:
・「労働者が業務中にけがをした場合、労災保険と健康保険のどちらが優先されるか」
・「賃金の未払いがあったとき、労働基準法と民法のどちらの規定が優先されるか」
・「厚生年金に加入している人が退職後に国民年金へ切り替える手続き」
こうした問題は条文を丸暗記しているだけでは対応できません。制度趣旨や実務運用を理解していないと正解にたどり着けないのです。
また「一般常識」科目では、労務管理や統計データなど幅広い分野から出題されるため、知識の深さだけでなく柔軟な思考力も求められます。
他の国家資格との難易度比較から見る社労士試験の位置づけ
社労士試験の難易度を正しく理解するためには、単体で評価するよりも、他の代表的な国家資格と比較してみるのが分かりやすい方法です。以下は主要な資格の 合格率・必要勉強時間・難易度レベル を整理した表です。
| 資格名 | 合格率 | 必要勉強時間 | 難易度レベル |
|---|---|---|---|
| 司法書士 | 3〜4% | 約3,000時間 | 最高難易度 |
| 税理士 | 10〜20%(科目別) | 約2,000〜4,000時間 | 最高難易度 |
| 社労士 | 6〜7% | 約800〜1,000時間 | 高難易度 |
| 中小企業診断士 | 約5% | 約800〜1,000時間 | 高難易度 |
| 行政書士 | 約10〜13% | 約500〜800時間 | 中〜高難易度 |
| 宅建士 | 約15〜18% | 約300〜500時間 | 中難易度 |
難易度の位置づけ
この比較からわかる通り、社労士試験は 「中堅どころ」ではなく、難関資格に属するポジション にあります。
・司法書士・税理士よりは易しい
司法書士は法律系資格の中でも最高峰で、3,000時間以上の学習が必須。税理士も科目合格制とはいえ、全体で2,000〜4,000時間の学習を要し、合格まで数年かかるのが一般的です。これらと比べれば社労士は学習負担が少なく、短期合格も狙いやすい資格といえます。
・行政書士・宅建士よりは難しい
一方で行政書士や宅建士は学習時間が500時間前後でも到達可能で、合格率も二桁。これらと比較すると、社労士は「1,000時間近い学習」と「一桁台の合格率」が必要となり、難易度の高さが際立ちます。
社労士試験と中小企業診断士の比較
同じ「高難易度」に分類される中小企業診断士と比べても興味深い違いがあります。
・診断士は 一次試験(7科目)+二次試験(記述・口述) の二段階構成で、幅広いビジネス知識が必要。
・社労士は 10科目の法律知識を網羅 する点で、範囲の広さと法改正対応がハードルになります。
つまり、両者は「広範囲かつ応用力が問われる」という点で似ていますが、社労士は 法律寄り・診断士は経営寄り という性格の違いがあります。
難易度比較から見える社労士の魅力
難易度の比較を整理すると、社労士試験は次のようなポジションにあります。
・司法書士・税理士ほどの超難関ではないが、行政書士・宅建士よりは一段難しい
・労働・社会保険という実務直結の専門性を持ちながら、1,000時間前後の学習で現実的に狙える
つまり社労士は、現実的な努力で取得可能な“ハイリターン資格” であり、キャリアアップや独立開業を目指す社会人にとって挑戦しがいのある国家資格といえるでしょう。
必要な勉強時間の目安
難易度を測る指標の一つが「合格までに必要な勉強時間」です。
・初学者(法律系知識なし):800〜1,000時間
・法学部出身や行政書士などの資格保持者:500〜700時間
・社会人が働きながら合格を目指す場合:1〜2年かけて学習 が現実的
例えば、平日2時間+休日5時間を確保できたとして、年間で 約900時間。ちょうど合格ラインに届くイメージです。
学習期間別の計画例
1年間での合格を目指す場合
・1日3時間×週5日 = 週15時間
・年間約780時間(52週×15時間)
・基礎学習から直前対策まで余裕を持った計画
6ヶ月での短期合格を目指す場合
・1日5時間×週6日 = 週30時間
・6ヶ月で約720時間(24週×30時間)
・集中的な学習が必要
科目別の難しさ
社労士試験の難しさは「科目数の多さ」と「毎年変わる出題傾向」にあります。
・労働基準法・労災保険:条文暗記中心。出題頻度高く、落とせない。
・健康保険・厚生年金保険:計算問題や細かい制度変更があり難易度高め。
・労務管理・一般常識:範囲が広く、対策がしにくい「鬼門科目」。
特に「一般常識」は多くの受験生が基準点割れで不合格になる原因となっています。
独学で合格できる?
「独学で合格できるのか?」は多くの人が気になるポイントです。
結論から言えば、独学でも合格は可能。ただし条件があります。
独学で成功する人の特徴
・強い自己管理力がある
・学習計画を立てて継続できる
・法律用語への抵抗が少ない
・過去問・市販教材を効率よく使える
独学のメリット
・費用を抑えられる(テキスト+過去問で3〜5万円程度)
・自分のペースで学習できる
独学のデメリット
・情報不足で出題傾向に対応しづらい
・モチベーション維持が難しい
・苦手科目を克服しにくい
予備校・通信講座を活用する選択肢
独学が不安な方は予備校や通信講座を利用するのも有効です。
・予備校(通学型):講師に直接質問できる。費用は30〜40万円。
・通信講座:動画やテキストで学習。費用は10〜20万円。時間効率が高い。
特に働きながら受験する人は「通信講座+独学」でのハイブリッド学習が人気です。
独学での効果的な勉強法
1. 基礎学習期(学習開始~6ヶ月)
テキスト選びのポイント
以下を意識してテキストを選択しましょう。
・最新年度版を選択する
・図表が豊富で理解しやすいものを選ぶ
・1冊に絞って完璧にマスターする
学習方法
学習方法については、以下の点を意識することが重要です。
1.各科目の全体像を把握
2.重要条文の理解と暗記
3.制度の趣旨・目的を理解
4.関連法令の横断的学習
2. 実力養成期(6ヶ月~9ヶ月)
問題演習の重要性
問題演習は社労士試験を攻略するために
・過去問を中心とした問題演習
・選択式・択一式両方の対策
・間違えた問題の徹底復習
・弱点科目の重点強化
3. 直前対策期(9ヶ月~試験直前)
総仕上げのポイント
・模擬試験による実戦練習
・法改正事項の最終確認
・暗記項目の反復学習
・時間配分の練習
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
社労士試験の現実
2024年度の合格率6.9%という数字が示すように、社労士試験は確実に「高難易度」の国家資格です。しかし、適切な学習方法と十分な準備期間を確保すれば、独学での合格も十分に可能です。
合格に必要な要素
1.計画性:800~1,000時間の学習時間を確実に確保
2.継続性:毎日の学習習慣を確立
3.戦略性:全科目の足切り突破を最優先
4.柔軟性:弱点科目への学習時間配分調整
5.情報収集:法改正情報の継続的な把握
独学成功者の共通点
・長期的な学習計画の策定と実行
・基礎知識の徹底的な理解
・過去問演習による実戦力向上
・最新情報への継続的な対応
・諦めない強い意志
社労士試験は確かに難易度の高い試験ですが、正しい学習方法と継続的な努力により、独学での合格も夢ではありません。自分に合った学習スタイルを見つけ、計画的に学習を進めることが成功への鍵となります。
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















