INDEX
おすすめ記事
-
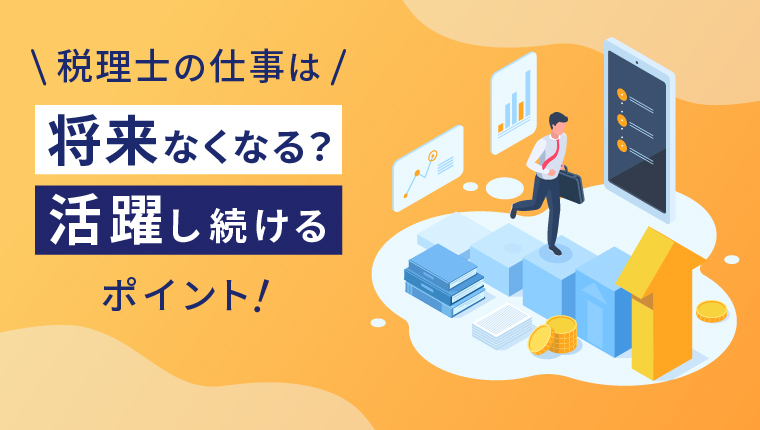
税理士の仕事は将来性が無い?活躍し続けるポイント
-

税理士が独立開業を本気で成功させるためにするべきこと
-
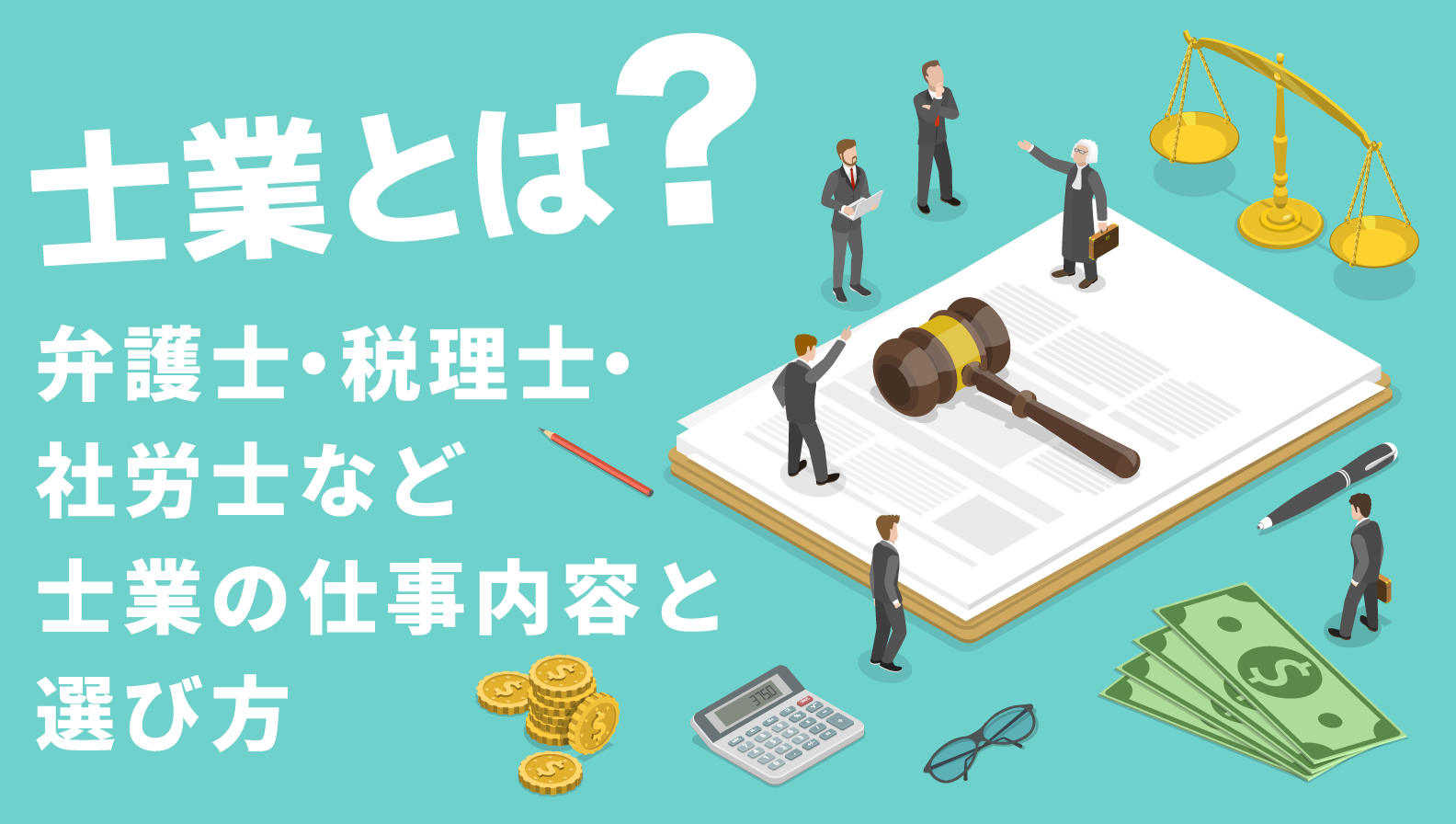
士業とは?弁護士・税理士・社労士など士業の仕事内容と選び方
-
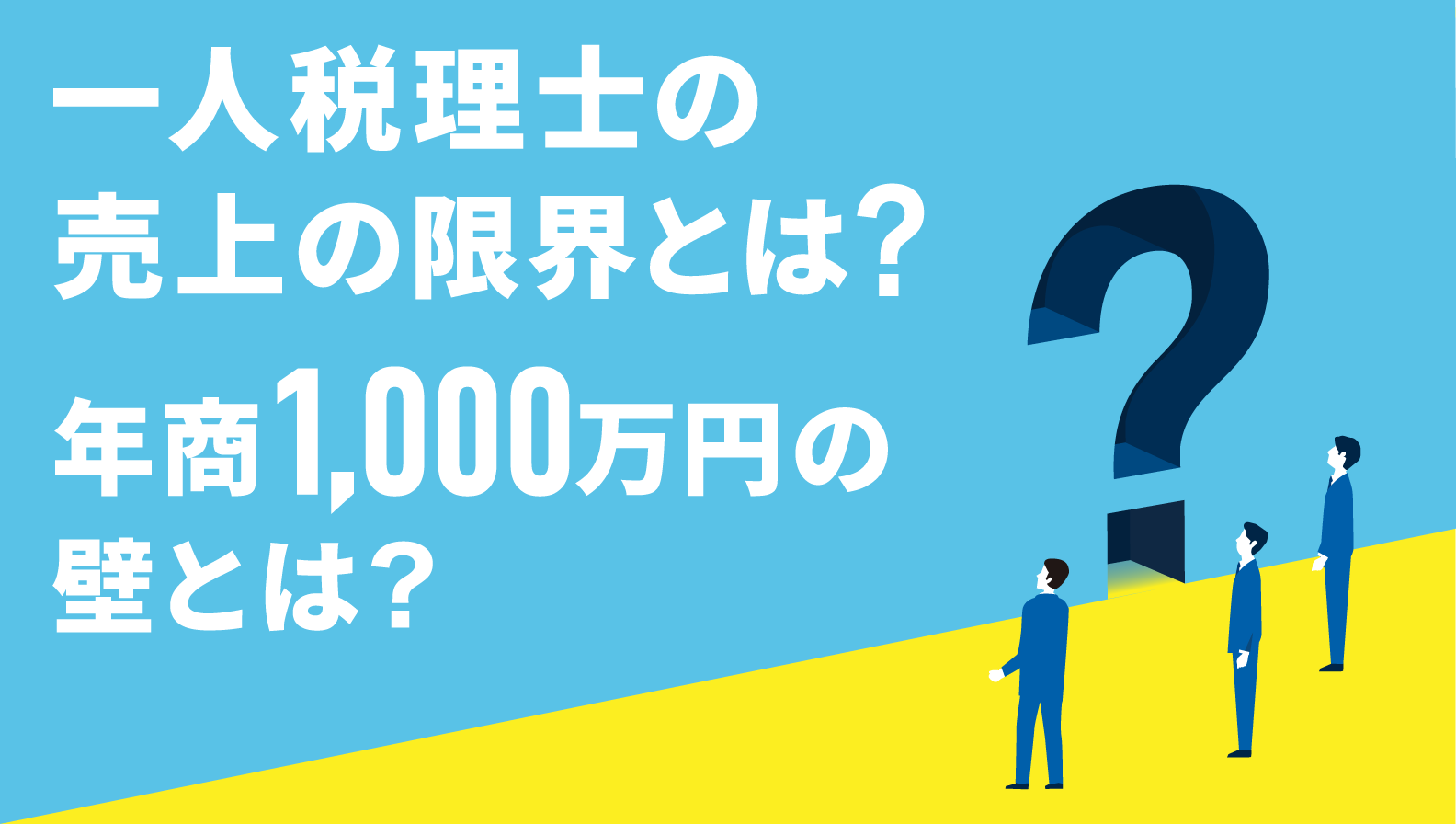
一人税理士の売上の限界とは?年商1,000万円の壁とは?
-

固定資産税|税理士試験での成功のためのステップ
公開日:2025/09/28
最終更新日:2025/09/28

INDEX
簿記は、企業や個人の経済活動を正確に記録・管理し、財務状況を明らかにする重要な技術システムです。現代社会において、経営判断・投資・融資など、あらゆる経済活動の基盤となっています。
この記事では簿記の歴史や原理、役割、学習方法まで幅広く解説します。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
簿記とは何か
簿記とは、企業や個人の経済活動を帳簿に記録・整理し、財務状況を明らかにする技術のことです。
「お金の流れを“見える化”する仕組み」と言い換えると理解しやすいでしょう。
日々の売上や仕入、経費や給与の支払いなどをルールに従って記録し、最終的には貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)といった財務諸表を作成します。
これにより、会社経営者は経営判断を下しやすくなり、投資家や金融機関も正しい情報を得ることができます。
簿記の歴史と原理
複式簿記の誕生
複式簿記の起源は、15世紀のイタリア・ベネチア共和国にさかのぼります。地中海貿易が盛んな中世イタリアで、数学者で修道僧でもあったルカ・パチョーリ(1445-1517年)が1494年に出版した数学書『スムマ(算術、幾何、比および比例に関する全集)』で初めて複式簿記が学術的に説明されたため、パチョーリは「近代会計学の父」と呼ばれています。
日本への導入
日本では、福沢諭吉が明治6年(1873年)にアメリカのテキストを翻訳した「帳合之法(ちょうあいのほう)」という書籍が複式簿記の始まりです。「借方」「貸方」という用語も福沢諭吉による翻訳によって生まれました。
基本原理:借方と貸方
複式簿記は、すべての取引を「借方(左側)」と「貸方(右側)」の二面から記録する仕組みです。
覚え方のコツ:
・借方の「り」は左にはらっている → 左側
・貸方の「し」は右にはらっている → 右側
仕訳の5つのグループ
| グループ | 増加する場合 | 減少する場合 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 資産 | 借方 | 貸方 | 現金、売掛金、建物、備品 |
| 負債 | 貸方 | 借方 | 買掛金、借入金、未払金 |
| 純資産(資本) | 貸方 | 借方 | 資本金、利益剰余金 |
| 収益 | 貸方 | 借方 | 売上、受取利息 |
| 費用 | 借方 | 貸方 | 仕入、給料、光熱費 |
簿記の役割と目的
簿記の役割は大きく分けて3つあります。
1.記録
日々の取引を正確に残すことで、将来のトラブルや不正防止につながります。
2.報告
財務諸表としてまとめ、株主や金融機関、税務署などの外部に報告します。
3.経営判断
利益率や資金繰りを把握し、投資・経営戦略の意思決定に役立ちます。
つまり簿記は、単なる会計処理ではなく、経営の羅針盤ともいえる存在です。
簿記の種類
簿記にはいくつかの種類があり、用途や利用者によって区別されます。
| 種類 | 概要 | 利用される場面 |
|---|---|---|
| 商業簿記 | 商品売買やサービス提供を扱う簿記 | 会社・個人事業の経理 |
| 工業簿記 | 製造業での原価計算を中心に扱う | 工場やメーカー |
| 会計学的簿記 | 財務諸表作成や理論的側面に重点 | 大学の研究や会計士試験 |
| 単式簿記 | 家計簿のようにシンプルに収支を記録 | 個人事業主の簡易帳簿 |
| 複式簿記 | 借方・貸方の両面から記録 | 法人会計、税務申告必須 |
多くの企業では複式簿記が採用されており、税務申告でも必須です。
それぞれの特徴は以下の通りです。
商業簿記
・対象:商品売買、サービス業
・特徴:売上、仕入、在庫管理が中心
・主要取引:商品仕入、売上、掛取引
工業簿記
・対象:製造業
・特徴:原価計算が複雑
・主要要素:材料費、労務費、経費の管理
建設業会計
・特徴:工事進行基準、完成工事高
・複雑さ:長期プロジェクトの収益認識
金融業会計
・特徴:金利計算、貸倒引当金
・規制:金融商品取引法などの厳格な基準
簿記を学ぶメリット
簿記は「経理担当者が使うもの」と思われがちですが、実際には幅広い人に役立つスキルです。ここでは、代表的なメリットを具体例を交えて紹介します。
1. 就職・転職に有利
簿記の知識を持っていることは、採用担当者から高く評価されやすいポイントです。
・経理・会計職では、必須スキルとしてほぼ確実にチェックされます。特に日商簿記2級以上を持っていれば即戦力として期待されます。
・営業職や管理職にとっても有利です。売上やコストの数字を理解できれば、経営陣や顧客との会話がスムーズになり、説得力が増します。
・転職市場でも「簿記資格あり」は求人票で優遇条件になることが多く、キャリアチェンジの際に大きな武器になります。
例:営業職から経理職への転職に成功したケース、または管理職昇進時に数字理解が評価されたケースなどが挙げられます。
2. お金のリテラシー向上
簿記を学ぶと、日常生活や投資判断に直結する「お金の見える化力」が身につきます。
・家計管理では、単なる収支の記録ではなく「資産・負債・収入・支出」をバランスよく把握できるようになります。住宅ローンや教育費といった将来支出の計画にも強くなります。
・投資判断にも役立ちます。企業の財務諸表を読めるようになれば、株式投資や不動産投資のリスクを見極める力が養われます。
・副業・フリーランスでも必須です。青色申告や確定申告で必要な帳簿付けがスムーズにでき、節税にもつながります。
「数字が苦手で家計簿が続かない…」という人でも、簿記を学ぶと“お金の流れ”を体系的に理解できるため、自然と継続できるようになります。
3. キャリアアップにつながる
簿記は、さらなるキャリアのステップアップにつながる基礎資格です。
・日商簿記2級取得後は、税理士試験や公認会計士試験など、より高度な会計・税務資格に挑戦する人が多いです。
・中小企業診断士やMBAを目指す場合でも、簿記知識は前提となる会計リテラシーとして必須です。
・社内昇進でも有利です。数字に強い社員は管理職候補として抜擢されやすく、経営企画や財務部門への異動にもつながります。
例えば「営業職 → 管理職 → 経営幹部」とキャリアを歩む人の多くは、早い段階で簿記を学び、財務理解を武器にしています。
簿記検定の種類とレベル
日本で最も認知度が高いのが日商簿記検定です。
| 級 | 難易度 | 主な内容 | 学習時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 3級 | 初心者向け | 基本的な仕訳と財務諸表 | 100~150時間 |
| 2級 | 中級者向け | 商業簿記+工業簿記 | 200~300時間 |
| 1級 | 上級者向け | 会計学・工業簿記・原価計算 | 500時間以上 |
| 簿記論/財務諸表論 | 税理士試験科目 | 会計・税務の実務レベル | 1,000時間超 |
まずは3級から始め、就職・転職で評価される2級を目指す人が多いです。
簿記を活かすキャリアパスと年収
簿記資格別年収相場は以下の通り
| 資格レベル | 平均年収 | 年収レンジ | 主な就職先 |
|---|---|---|---|
| 簿記3級 | 350-400万円 | 300-500万円 | 経理事務、一般企業 |
| 簿記2級 | 400-500万円 | 350-600万円 | 経理主任、中小企業経理 |
| 簿記1級 | 500-700万円 | 400-900万円 | 経理管理職、会計事務所 |
以下、詳細を解説します。
簿記3級:ビジネス基礎を固めるスタートライン
・平均年収:350〜400万円
・年収レンジ:300〜500万円
・主な就職先:経理事務、一般企業のバックオフィス
簿記3級は「会計の入門資格」として位置づけられます。
日常的な仕訳や帳簿付け、簡単な財務諸表の理解ができるレベルのため、一般事務や経理アシスタント職への就職・転職に有利です。
特に「数字が苦手で不安…」という人でも、3級から学べば実務で必要な最低限の知識を無理なく習得できます。
簿記2級:実務で即戦力となるレベル
・平均年収:400〜500万円
・年収レンジ:350〜600万円
・主な就職先:経理主任、中小企業の経理担当
簿記2級を取得すると、財務諸表を深く理解し、企業の経理実務を一通りこなせる力がつきます。
そのため、経理職の採用条件として「日商簿記2級以上」と指定する企業は多く、就職市場での評価は非常に高いです。
中小企業では「一人経理」として経理全般を任されることもあり、責任の分だけ年収レンジの上限も伸びやすい資格です。
簿記1級:経理の管理職候補
・平均年収:500〜700万円
・年収レンジ:400〜900万円
・主な就職先:経理管理職、会計事務所、上場企業の財務部門
簿記1級は難易度が高く、合格率は10%前後。
しかしその分、経理部長や経営企画、会計事務所での実務といった「企業の数字を動かす」役割に就ける可能性が広がります。
特に上場企業や大手企業では、簿記1級レベルの知識を持つ人材は少なく、評価が高まりやすいです。
上位資格へのステップアップ
簿記1級を取得すると、さらに難関資格への道が拓けます。
税理士
・平均年収:580万円(転職時)
・主な業務:税務申告、税務相談、税務代理
・特徴:独立開業が可能で、年収1,000万円以上も現実的
中小企業の顧問税理士として安定収入を得る人もいれば、M&Aや国際税務などに強みを持ち高収益を上げる人もいます。
公認会計士
・平均年収:747万円(2022年調査)
・主な業務:監査、会計コンサルティング、M&A支援
・特徴:Big4監査法人では年収1,000万円以上も可能
特に若手でも評価されやすく、20代後半で年収800万円超を目指せる点が大きな魅力です。
キャリアパスの例
| 簿記3級 | → | 簿記2級 | → | 簿記1級 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 一般事務 | → | 経理担当 | → | 経理主任 | → | 経理部長 |
| ↓ | ||||||
| 税理士試験 | → | 税理士 | ||||
| ↓ | ||||||
| 公認会計士試験 | → | 公認会計士 |
簿記の学習方法
簿記を学ぶ方法は大きく3つに分かれます。
1.独学
参考書や過去問を使い、コストを抑えて学習可能。
→ 3級なら独学でも十分合格可能。
2.通信講座
動画やテキストが充実しており、スキマ時間で効率的に学べる。
→ 忙しい社会人におすすめ。
3.専門学校・スクール
講師から直接学べ、短期間で合格を目指せる。
→ 2級以上を狙う人や資格を早く取りたい人に最適。
簿記と会計・経理の違い
・簿記:取引をルールに従って記録すること
・会計:簿記で得た情報をもとに分析・報告すること
・経理:実際に日常業務で簿記を行い、会計処理を担当する人や部門
つまり、簿記は会計や経理の“基礎技術”です。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
簿記とは、お金の流れを正しく記録し、経営や生活に役立てる技術です。
資格としても人気が高く、就職・転職、副業や起業にも役立ちます。
「簿記を学ぼうかな」と思った時が始めどきです。まずは日商簿記3級からチャレンジし、実務やキャリアに活かしましょう。
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















