INDEX
おすすめ記事
-
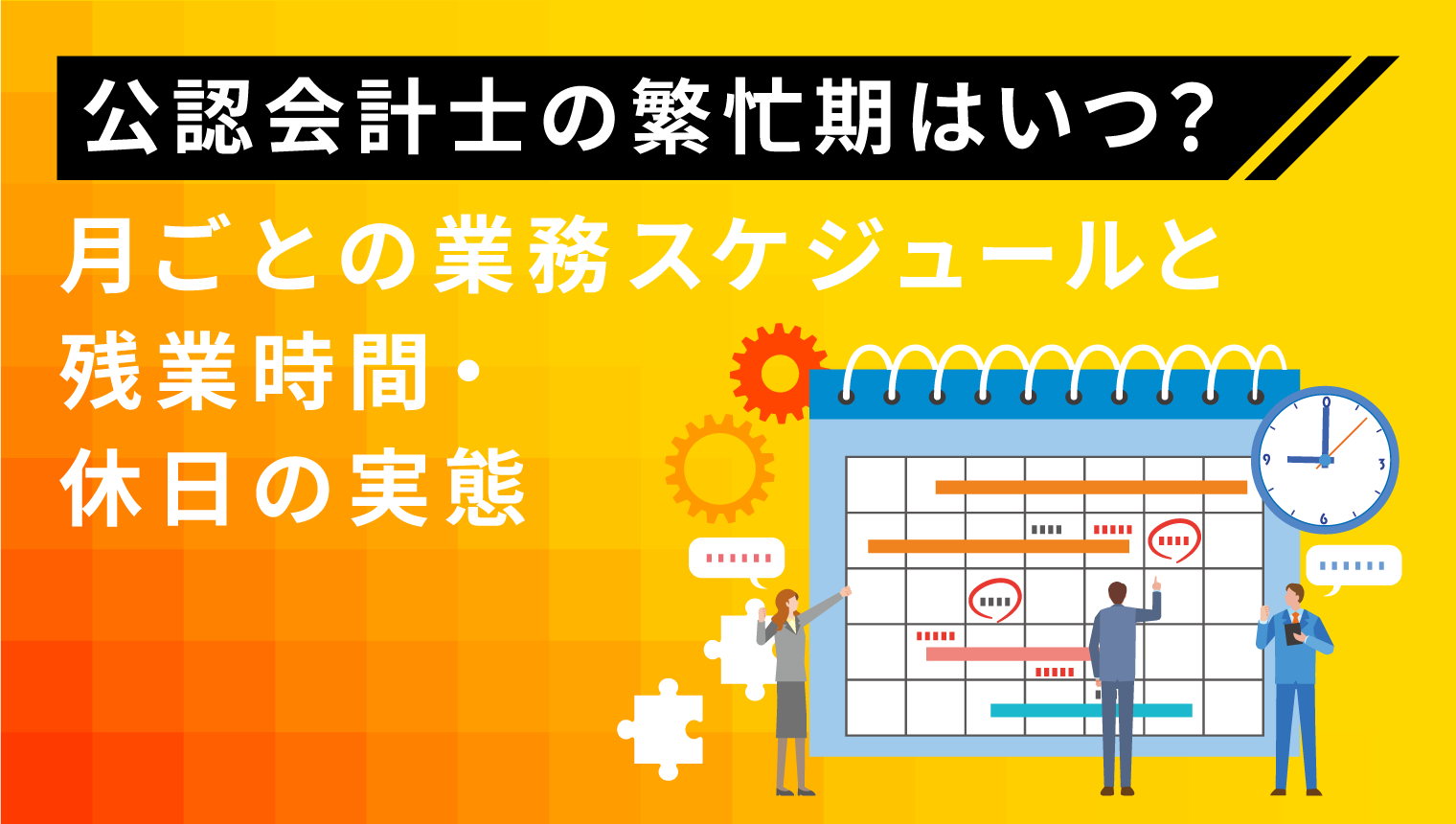
公認会計士の繁忙期はいつ?月ごとの業務スケジュールと残業時間・休日の実態
-
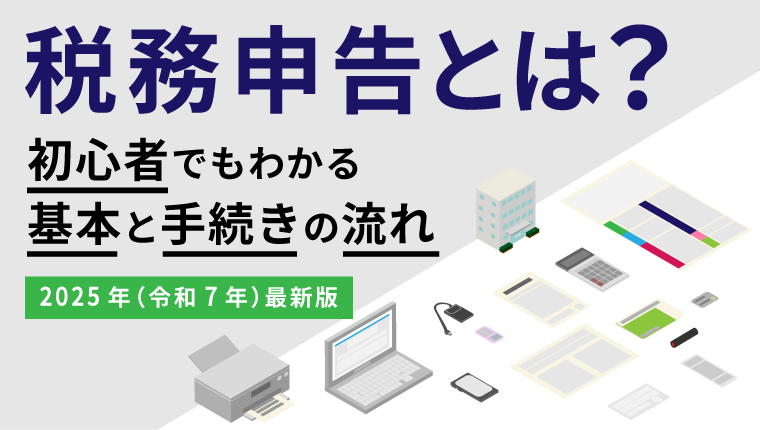
税務申告とは?初心者でもわかる基本と手続きの流れ【2025年(令和7年)最新版】
-
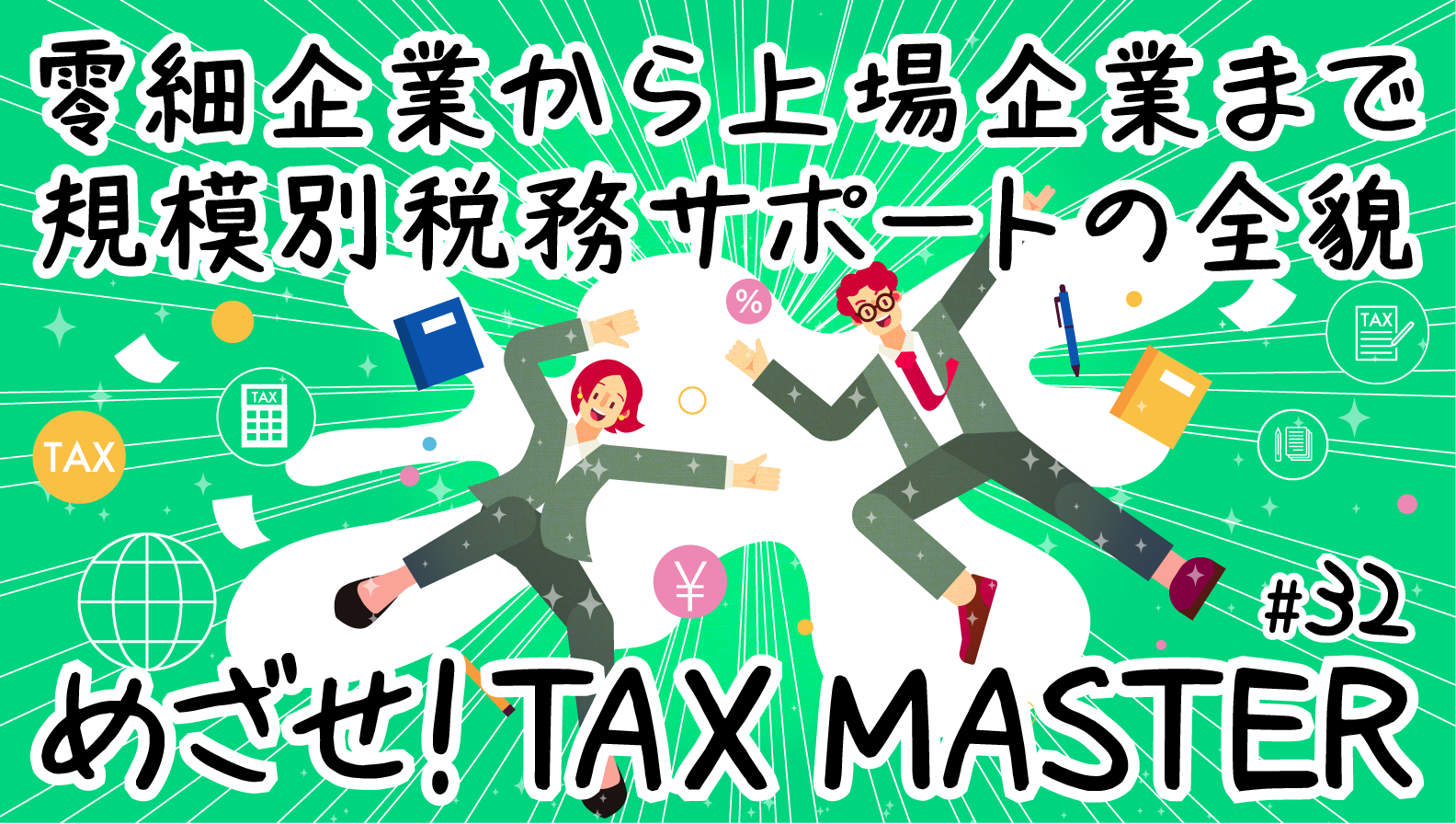
零細企業から上場企業まで!規模別税務サポートの全貌【めざせ!TAX MASTER#32】
-
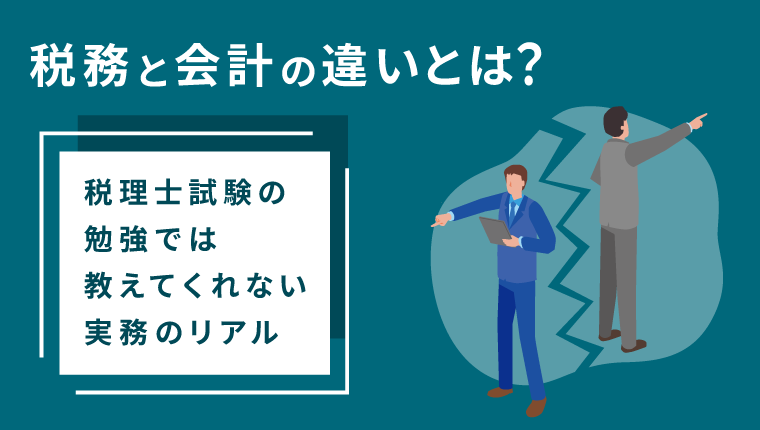
税務と会計の違いとは?税理士試験の勉強では教えてくれない実務のリアル
-
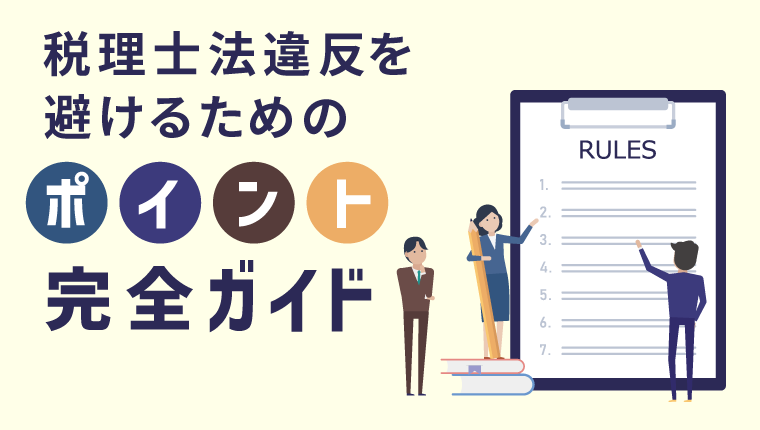
税理士法違反を避けるためのポイント|完全ガイド
公開日:2025/11/07
最終更新日:2025/11/25
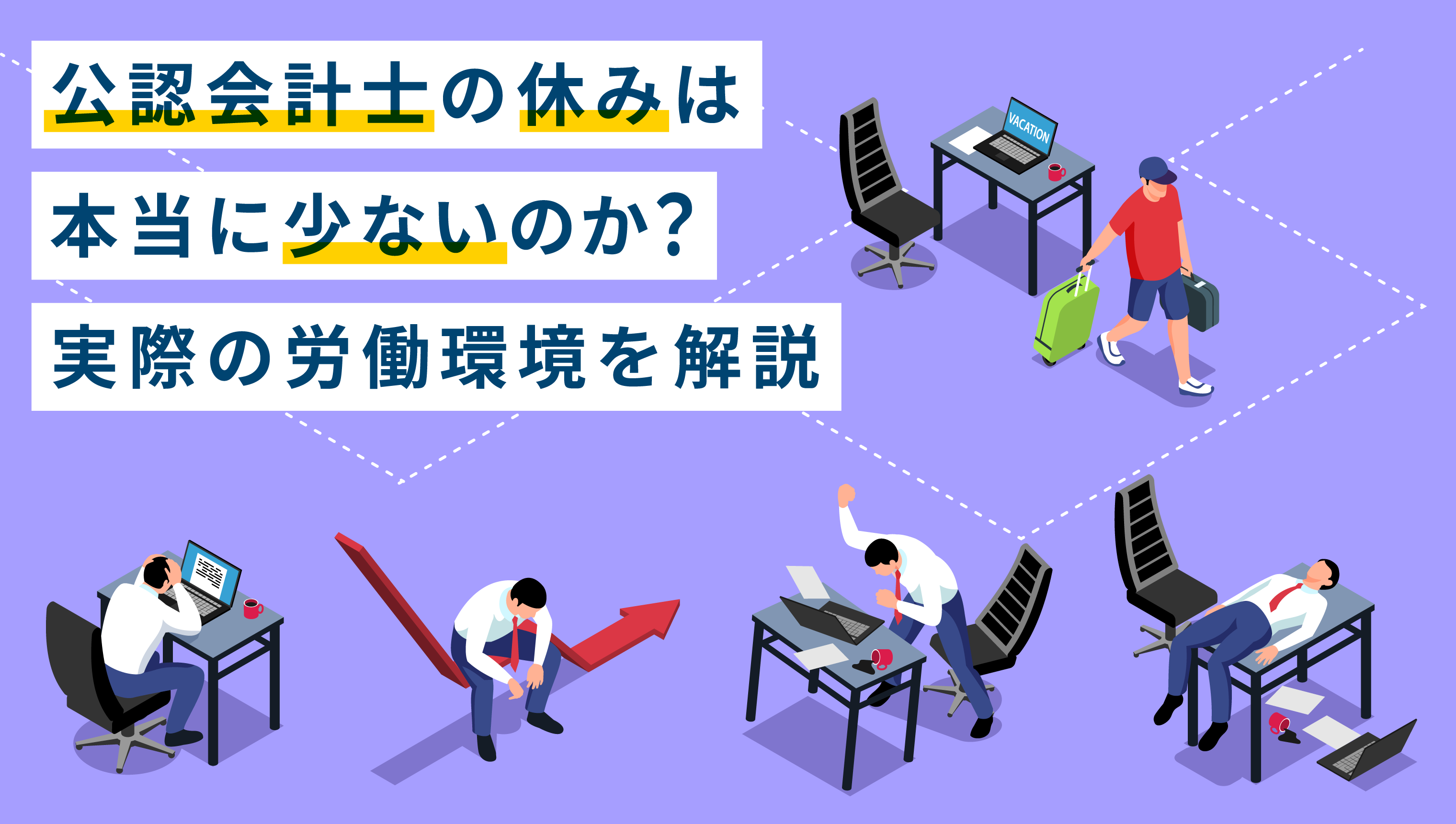
INDEX
「公認会計士は休みが少ない」「激務でプライベートの時間が取れない」といった声を耳にすることがあります。
確かに、繁忙期には長時間労働や休日出勤も発生しやすく、ハードなイメージを持たれがちです。
しかし実際には、時期や勤務先、業務内容によって休みの取りやすさが大きく異なり、働き方を工夫すればしっかりと休暇を確保することも可能です。
この記事では、公認会計士の休みは本当に少ないのかというテーマを深掘りし、労働環境の実態、繁忙期と閑散期の差、休暇制度や休みを増やす工夫、そしてキャリア形成との両立まで詳しく解説します。
あなたの「適正年収」を調べてみませんか?
簡単な質問に答えるだけで、一般的な会計事務所ならいくら提示されるのかを即座に算出。「今の適正額」はもちろん、「資格を取得したら年収はどう変わるのか?」など、あなたの現在地と未来の可能性を診断します。
公認会計士の休みは本当に少ないのか?
公認会計士の一般的な労働環境とは
まず押さえておきたいのは、公認会計士の多くが働く監査法人の労働環境です。
監査法人は一般企業よりも繁閑の差が大きく、特定の時期に業務が集中する傾向があります。
ただし、年間休日は120〜140日程度が平均であり、有給やリフレッシュ休暇なども制度として整備されているケースが多く、「休暇制度的には一般企業と大きな差がない」というのが実情です。
「休みが少ない」と言われる背景には、繁忙期に集中する業務負担やクライアント対応の影響が大きいといえます。
この点を踏まえ、次章では「繁忙期と閑散期の違い」から、公認会計士の“休める時期”をより具体的に見ていきましょう。
繁忙期と閑散期の違い
公認会計士の働き方を理解する上で欠かせないのが、「繁忙期」と「閑散期」の存在です。
たとえば3月決算企業を担当する場合、1〜5月頃が最も忙しい時期となり、監査・レビュー・報告書作成が立て込みます。
この時期は残業時間が増加し、休日出勤を余儀なくされることもあります。
一方で、8月下旬〜9月中旬、11月〜12月中旬は比較的業務が落ち着きやすく、有給休暇や長期休暇を取りやすい時期です。
多くの監査法人ではこの閑散期に「リフレッシュ休暇」や「長期旅行」を推奨しており、プライベートを充実させるチャンスとなります。
つまり、「公認会計士の休みが少ない」というよりも、「休みを取れる時期が偏っている」というのが正確な表現でしょう。
次に、こうした季節変動が1日の働き方にどう影響しているかを見ていきます。
公認会計士の1日のスケジュールと休みやすい時期
閑散期の1日
閑散期を中心とした通常期は比較的落ち着いたスケジュールになります。
スケジュール例)
・9:00〜10:00 出社、メール確認、クライアントとの連絡
・午前中 監査資料の確認、チームミーティング
・12:00 昼休憩
・午後 報告書作成、進捗確認、会議など
・18:00頃 退社
このように、繁忙期を除けば定時退社も十分に可能です。
実際、監査法人によっては「有給を毎月取得している」「子育てと両立している」という会計士も少なくありません。
次に、繁忙期の1日を対比させることで、どのような働き方の違いがあるのかを見ていきます。
繁忙期の1日
繁忙期に入ると、スケジュールは一変します。
・8:00前後 出社、資料準備・現場監査開始
・午前中 棚卸立会い・実査対応など出張業務
・昼休み 短縮して対応継続
・午後 チームレビュー、資料整理、報告書作成
・20:00以降 残業(時期によっては22時を超えることも)
繁忙期には「残業80時間超」「休日出勤あり」といった声もあり、確かにハードな時期です。
しかし、法人によっては繁忙期後に「長期リフレッシュ休暇」を奨励しており、働き詰めにならないようバランスを取る仕組みも整っています。
ここまで見てきたように、公認会計士は“時期によって波がある”働き方です。
この波をどうコントロールするかが、次章で扱う「休暇制度」と「法人選び」の重要なポイントになります。
監査法人における休みの取りやすさと休暇制度
一般的な休みの取りやすさ
監査法人では、多くの場合「有給休暇」「リフレッシュ休暇」「試験休暇」「育児休暇」などが休暇制度として設けられています。
入社1年目から10日以上の有給が付与され、年次ごとに休みが増えていくケースも一般的です。
また、繁忙期を避けた閑散期にまとめて1〜2週間の休みを取得できる法人もあり、制度面ではむしろ「休みやすい業界」といえます。
ただし、制度があっても“実際に使えるかどうか”は法人の文化やチーム体制に左右されます。
次項では、監査法人ごとの休みの違いを見てみましょう。
監査法人間での違い
休暇制度の内容は似ていても、実際の取りやすさには差があります。
たとえば、四大監査法人(トーマツ、あずさ、EY新日本、PwCあらた)は、いずれもリフレッシュ休暇やテレワーク制度を整備していますが、繁忙期中の取得は難しい場合があります。
一方で、中堅・地方監査法人では、業務ボリュームが比較的安定しており、有給取得率が高いという傾向も見られます。
したがって、転職や就職を考える際は「休暇制度があるか」ではなく、
“実際にどの程度休暇制度が活用されているか”を確認することが重要です。
この違いを理解したうえで、次の章では休みを増やすための実践的な工夫を紹介します。
公認会計士の休みを増やすための工夫
効率的な業務の進め方
公認会計士が休みを増やすには、まず「自分の業務サイクルを把握する」ことが第一歩です。
担当クライアントの決算期やチームの繁忙時期を明確にし、事前に“休める時期”を見極めて計画的に休暇を取ることが大切です。
その上で、以下のような工夫が効果的です。
・タスクの見える化と前倒し処理
繁忙期前に処理できる資料やレビューを早めに片づける。
・チームとの情報共有
休暇前に引き継ぎやフォロー体制を整えることで、安心して休める。
・制度の積極的活用
リフレッシュ休暇や特別休暇を「遠慮せず申請」する。
こうした工夫によって、業務効率を維持しつつ休みを確保できます。
次に、そもそも「休みを取りやすい法人」を選ぶためのポイントを整理します。
- 法人選びのポイント
休みを増やしたい公認会計士にとって、勤務先選びは非常に重要です。
以下の観点をチェックしましょう。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 年間休日数 | 120〜140日程度の休みが確保されているか |
| 休暇制度 | 有給、リフレッシュ、試験、育児などが整備されているか |
| 繁忙期対応 | 代休取得や業務分担体制があるか |
| 働き方改革 | フレックス、在宅勤務など柔軟な働き方が可能か |
| 実績 | 有給消化率・長期休暇取得率を確認 |
近年は、テレワークや時短勤務を導入する監査法人も増えており、ライフステージに合わせた柔軟な働き方が可能です。
ここまでで「休みを確保する方法」を整理しましたが、最後に“休みをどう活かすか”という長期的視点からキャリア形成を考えてみましょう。
公認会計士としてのキャリアと休みの両立
長期的な視野でのキャリア形成
公認会計士として長く働くためには、「休暇を取ること=キャリアを犠牲にする」と考えないことが重要です。
むしろ、適切に休みを取ることで、スキルアップをする時間が増えたり、業務効率や集中力が高まり、結果的に評価につながるケースもあります。
また、キャリアの選択肢は多様です。監査以外にも、税務、アドバイザリー、IPO支援、事業承継など、分野を広げることで繁忙期の偏りを減らすことも可能です。
「時間の使い方を自分でコントロールできるポジション」を目指すことが、長期的なワークライフバランスの鍵となります。
休暇を活かしたスキルアップの方法
せっかくの休みを、リフレッシュだけでなく“学びの時間”に活用するのも有効です。
・閑散期に専門資格(IFRS・内部統制・IT監査など)を学ぶ
・海外旅行で異文化を学び、国際会計基準への理解を深める
・セミナーや勉強会への参加で最新トレンドをキャッチアップ
このように「休暇=成長機会」と捉えることで、キャリアの質が向上し、将来的には働き方の自由度も増していきます。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
公認会計士の休みは本当に少ないのか? -まとめ
「公認会計士は休みが少ない」というテーマの答えは、“少ない”ではなく“波がある”です。
・年間休日は一般企業並みに確保されている
・繁忙期には確かに忙しいが、閑散期には長期休暇も可能
・法人選び・業務効率化・制度活用で休みを増やせる
・休暇を成長やキャリア形成に活かすことで、より豊かな働き方ができる
公認会計士として充実したキャリアを築くには、「働く時は働く」「休む時は休む」というメリハリが重要です。
休暇を上手に取り入れ、自分に合った働き方を設計することが、長く活躍し続けるための第一歩となるでしょう。

高梨 茉奈(たかなし まな)
めざせ!TAX MASTER パーソナリティ



















