INDEX
おすすめ記事
-
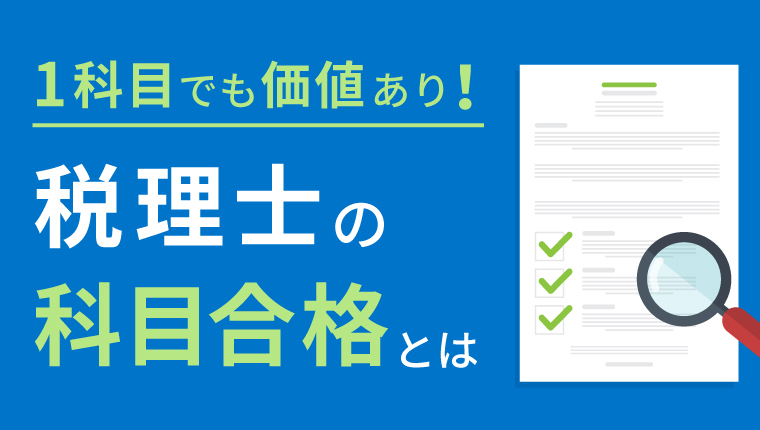
1科目でも価値あり!税理士試験の科目合格とは
-
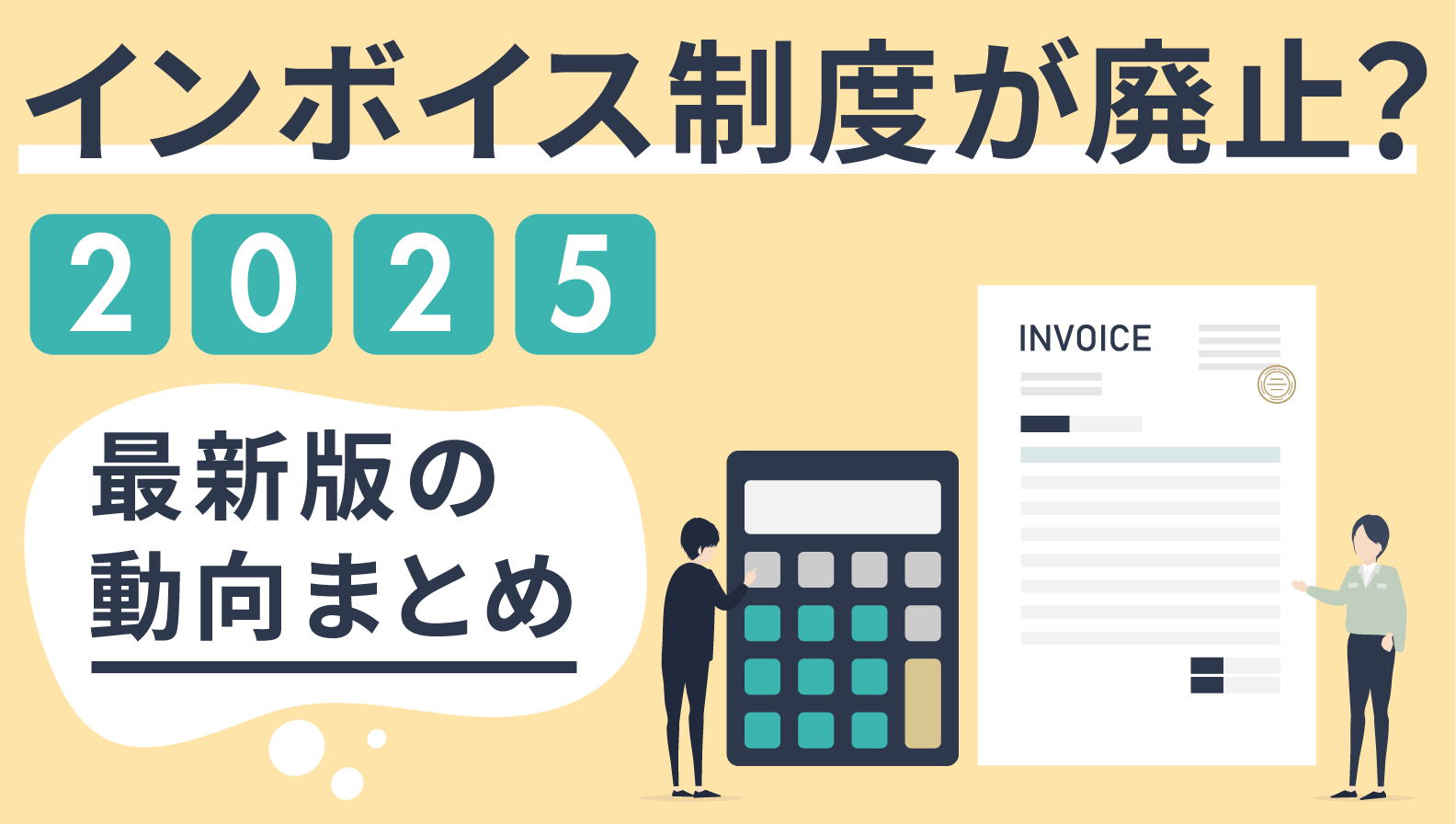
インボイス制度が廃止?2025年最新版の動向まとめ
-
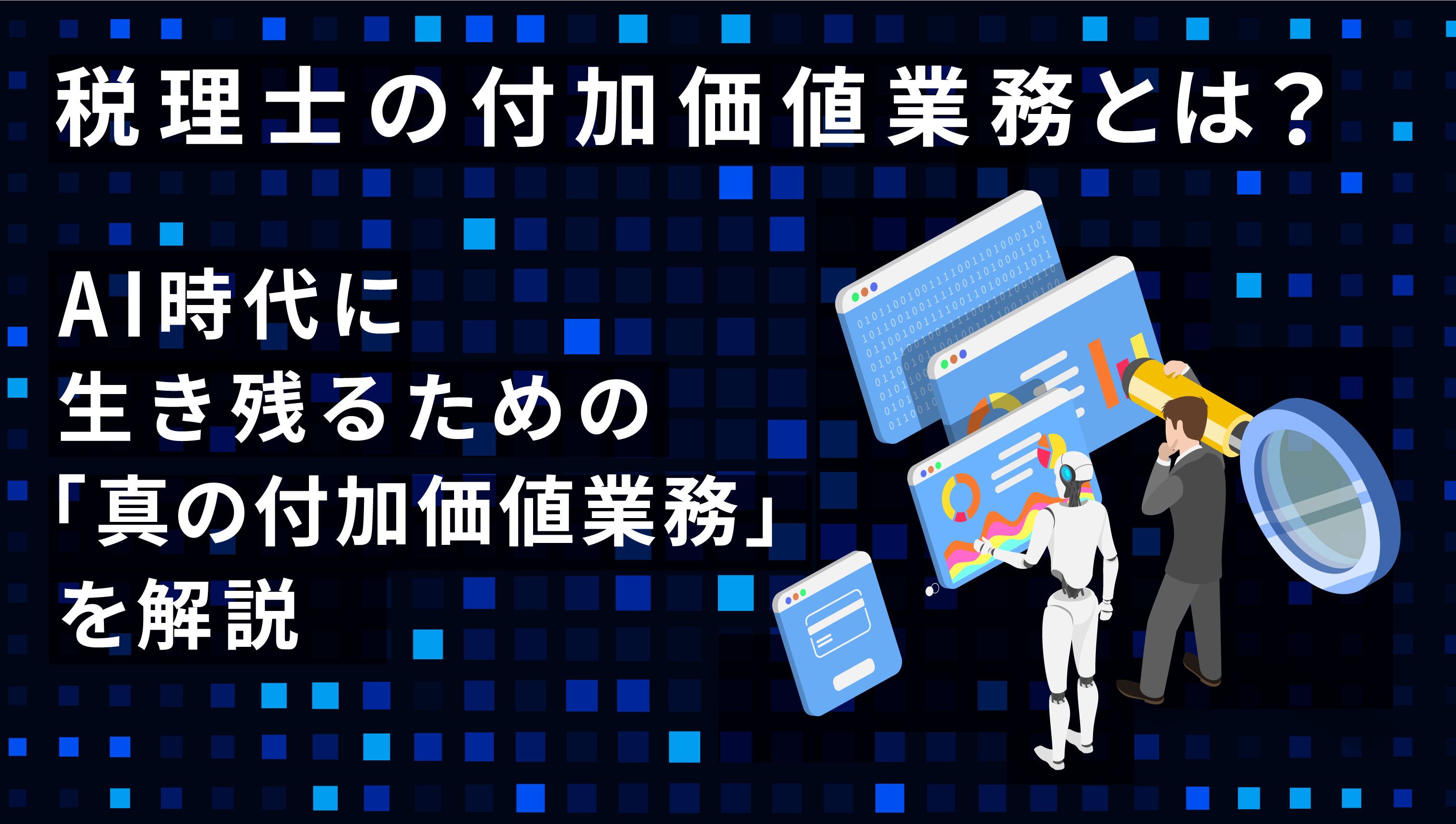
税理士の付加価値業務とは?AI時代に生き残るための『真の付加価値業務』を解説
-
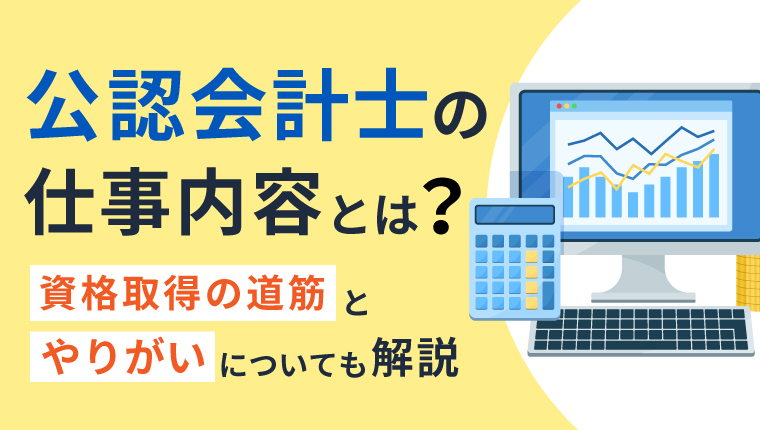
公認会計士の仕事内容とは?資格取得の道筋とやりがいについても解説
-

法人税申告書とは?申告書の作成方法と変更点まとめ【2025年最新版】
公開日:2025/11/14
最終更新日:2025/11/25

INDEX
税理士の登録者数は、昭和35年の約1万人から、令和7年には8万人超へと拡大してきました。国家資格としての安定性と専門性を背景に、長期的には増加傾向を維持してきた一方で、近年はその伸びが鈍化しつつあります。本記事では、最新の税理士登録者数データと過去60年超の推移をもとに、税理士業界の構造変化と今後の見通しを読み解きます。
あなたの「適正年収」を調べてみませんか?
簡単な質問に答えるだけで、一般的な会計事務所ならいくら提示されるのかを即座に算出。「今の適正額」はもちろん、「資格を取得したら年収はどう変わるのか?」など、あなたの現在地と未来の可能性を診断します。
1. 税理士人数の最新データと長期推移
税理士は日本国内に何人いるのでしょうか。AIの発展やインボイス制度など、税務を取り巻く環境が激変する中、その動向が注目されています。
1-1.【最新データ】登録者人数は82,114人(2025年10月末)
日本税理士会連合会(日税連)が公表している最新のデータによると、2025年(令和7年)10月末日時点での税理士の登録人数は、82,114人 です。あわせて、税理士業務を行う組織形態である「税理士法人」の届出数は、「主たる事務所」と「従たる事務所」を合わせて8,269事務所(2025年10月末時点)となっています。税理士の人数は、個人事務所だけでなく、こうした法人組織に所属する人数も含まれています。
1-2.登録者数は増えている? 長期的な人数推移
では、税理士の人数は増えているのでしょうか、それとも減っているのでしょうか。 結論から言えば、過去数十年にわたり一貫して増加し続けています。
以下の表は、国税庁や日税連のデータを基にした、過去の税理士登録人数の推移を示したものです。
| 年度 | 「税理士」登録「人数」 |
|---|---|
| 昭和35 (1960) 年度 | 10,888人 |
| 昭和50 (1975) 年度 | 32,436人 |
| 平成2 (1990) 年度 | 57,073人 |
| 平成12 (2000) 年度 | 65,144人 |
| 平成22 (2010) 年度 | 72,039人 |
| 平成30 (2018) 年度 | 78,028人 |
| 令和4 (2022) 年度 | 80,692人 |
| 令和6 (2024) 年度末 | 81,696人 |
| 令和7 (2025) 年10月末 | 82,114人 |
このように、昭和35年度に約1万人だった税理士の人数は、平成に入って急増し、令和の時代になっても8万人の大台を超え、緩やかながらも増加を続けていることがわかります。
1-3.【近年の動向】増加ペースは鈍化
さて、近年の動向に目を向けると、増加ペースは鈍化 しているという事実があります。
例えば、令和6年度末(2025年3月末)時点の人数(81,696人)は、前年度からの純増数が9年ぶりに500人を割り込むなど、増加の勢いは弱まっています。
これは、新規で税理士として登録する人数がいる一方で、高齢化などを背景に廃業・死亡などで登録の抹消も増えているためです。(実際、令和4年度・5年度は2年連続で登録抹消が2,000人を超えています)
税理士の総人数は増えていますが、その内側では「新規登録」と「登録抹消」のバランスが変化し始めているのです。
2. 【年齢別】の人数構成割合
2-1. 60代以上が過半数
日本税理士会連合会が約10年ごとに実施している「税理士実態調査」の最新版(第7回・令和6年1月公表)によると、税理士の年齢別人数構成は以下のようになっています。
| 年齢階層 | 人数構成比 |
|---|---|
| 29歳以下 | 0.4% |
| 30~39歳 | 6.2% |
| 40~49歳 | 18.1% |
| 50~59歳 | 21.5% |
| 60~69歳 | 25.7% |
| 70~79歳 | 22.0% |
| 80歳以上 | 5.9% |
| 無回答 | 0.3% |
このデータが示す実態は衝撃的です。
・60代以上の合計は 53.6%(25.7% + 22.0% + 5.9%)
・70代以上だけでも 27.9%
つまり、税理士の過半数以上が60歳以上であり、約3割が70歳以上で人数構成されているのが実情です。
2-2. 若手税理士は極めて少人数
一方で、若手の構成比は非常に低くなっています。
・30代以下の合計は 6.6%(0.4% + 6.2%)
・20代(29歳以下)に至っては、わずか 0.4%
税理士の総人数が82,000人であることを考えると、20代は単純計算で約400人弱しか存在しないことになります。
税理士業界は、人数の総数こそ増えているものの、その構成は極端に高齢層に偏っており、若手が非常に少ないという構造的な課題を抱えていることが鮮明にわかります。
2-3. なぜ高年齢層の人数が多いのか?
年齢構成がこれほど高齢層に偏るのには、主に3つの理由があります。
1.「税理士」に定年がないため
税理士は国家資格に基づく専門職であり、会社員のような定年制度がありません。そのため、健康であれば70代、80代でも現役として活躍し続ける人数が多く、これが高齢層の割合を高める一因となっています。
2.「税務署OB」の登録が多いため
税理士資格は、試験合格以外にも取得ルートがあります。特に税務署に一定年数勤務した「税務署OB」は、試験免除によって税理士資格を得ることができます。この多くは、税務署を定年退職する60歳前後で「税理士」として登録するため、60代以上の人数構成比を大きく押し上げています。
3.「5科目合格者」自体の平均年齢が高いため
税理士試験(5科目合格)の合格者も、若手ばかりではありません。働きながら数年かけて合格する人数が多いため、合格時の平均年齢自体が40歳前後になることも珍しくありません。これも若手人数が少ない一因です。
3. 【資格取得別】の人数構成割合
税理士資格を得る主なルートは、以下の3つです。
1.税理士試験 5科目合格
2.大学院進学による試験科目免除(院免)
3.税務署勤務(OB)による試験免除
この人数構成比が、税理士業界の動態を理解する上で非常に重要です。
3-1. 全体の人数構成:税務署OBが約3割
最新の「第7回 税理士実態調査」(令和6年1月)では、資格取得別の人数構成も示されています。
| 資格取得の内訳 | 人数構成比 |
|---|---|
| 試験合格(5科目合格者) | 45.5% |
| 試験免除(大学院免除など) | 28.3% |
| 税務署OB(特別試験免除) | 26.2% |
このデータから、5科目合格者の人数は半数を割り込み 45.5% であることがわかります。
対して、大学院免除や税務署OBといった「試験免除組」の人数が、合計で 54.5% と過半数を占めています。
特に「税務署OB」が 26.2%(約3割弱) を占めている点が、税理士の人数構成を特徴づける大きな要因です。第2章で解説した通り、多くは税務署を定年退職する60歳前後で税理士登録するため、60代以上の構成比を直接的に押し上げています。
3-2. 新規登録者の人数内訳:税理士試験「5科目合格者」は25%未満
さらに、税理士の未来を占う新規登録者の人数内訳を見ると、この傾向はより顕著になります。
少し古いデータ(2021年度の新規登録者)ではありますが、その人数内訳は以下のようになっています。
・試験合格(5科目合格者): 約25%
・試験免除(大学院免除など): 約25%
・税務署OB(特別試験免除): 約50%
(※注:年度によって「税務署OB」の退職タイミングなどで割合は変動しますが、大まかな傾向を示しています)
近年の新規登録人数においては、5科目合格者の人数は全体の4分の1程度に過ぎず、残りの 75%が試験免除組で占められているのです。
この背景には、税理士試験(5科目合格)の難易度の高さから、大学院進学で科目を免除するルートを選択する人数が増加していることや、団塊の世代の「税務署OB」が大量に退職し税理士登録した時期があることなどが挙げられます。
このように、税理士の人数は、約82,000人という総人数だけを見るのではなく、その内訳が「5科目合格者」「大学院免除者」「税務署OB」という異なる背景を持つ人によって人数構成されていることを理解することが重要です。
4. 【男女別・地域別】の人数構成割合
4-1. 女性の割合 - 増加傾向
まず、男女別の人数構成です。 税理士は長らく男性中心の職業というイメージがありましたが、近年は女性税理士の人数が着実に増加しています。
最新の「第7回 税理士実態調査」(令和6年1月)によると、税理士の人数に占める女性の割合は 16.1% でした。
・男性税理士の人数割合: 83.9%
・女性税理士の人数割合: 16.1%
前回の調査(第6回・平成26年)では女性の人数割合が14.7%だったことから、女性税理士の人数および割合は明確に増加傾向にあります。総人数が約82,000人であることを考えると、現在、女性税理士の人数は約13,000人を超えている計算になります。他の士業(例:弁護士の女性比率約19%)と比較するとまだ低い水準ではありますが、税理士業界における女性の人数は着実に増え続けています。
4-2. 地域別の税理士人数 - 東京への一極集中
税理士の人数分布を語る上で最も重要な特徴が、地域的な偏在、特に東京への一極集中です。税理士の人数は、全国に均等に分布しているわけではありません。経済活動の規模に比例し、大都市圏に集中しています。
日本税理士会連合会が公表している最新の所属税理士会別人数(2025年10月末時点)を見ると、その実態が明らかです。
| 所属税理士会 | 税理士登録人数 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 東京会 | 23,803人 | 約29.0% |
| 関東信越会 | 13,000人 | 約15.8% |
| 近畿会 | 12,654人 | 約15.4% |
| 東海会 | 6,339人 | 約7.7% |
| 九州北部会 | 3,927人 | 約4.8% |
| (その他) | … | … |
| 全国合計 | 82,114人 | 100% |
データが示す通り、東京税理士会に所属する税理士人数だけで 23,803人 と、全国の税理士人数の約3割(29.0%) が東京に集中していることがわかります。次点の関東信越会(約1.3万人)、近畿会(約1.2万人)と比較しても、東京税理士会の人数は突出しています。一方で、地方の税理士会(例えば四国会、東北会など)は、それぞれ2,000人前後にとどまります。
このように、税理士の人数は、総人数は増え続けているものの、その内訳は「高齢層に偏り」「東京に一極集中している」という、構造的なアンバランスを抱えているのです。
5. 税理士人数の今後の見通し
では、AI(人工知能)の台頭なども叫ばれる中、未来の税理士人数はどうなっていくのでしょうか。
5-1. 「税理士試験」受験人数の動向
税理士の人数は、高齢化による引退(登録抹消)人数と、新規登録人数のバランスで決まります。その新規登録の源泉となるのが税理士試験の受験人数です。税理士試験の受験人数は、AIによる将来性の不安などから一時期減少し続け、令和4年度(2022年)には約28,000人まで落ち込みました。しかし、ここで大きな転換点が訪れます。令和5年度(2023年度)からの「受験資格緩和」です。 これにより、大学での履修科目要件などが撤廃され、会計学科目(簿記論・財務諸表論)は誰でも受験可能になりました。
・令和5年度(2023年)の受験申込人数は 32,893人(対前年比114.6%)
・令和6年度(2024年)の受験申込人数も 34,704人(対前年比105.5%)
と、受験人数は2年連続で大幅に増加(V字回復)しています。特に、受験資格緩和によって大学生など若年層の受験人数が増加していることは、第2章で見た「若手の少なさ」という課題を解決するポジティブな兆候です。この受験人数の増加が数年後に税理士登録人数の増加につながり、高齢税理士の引退人数をカバーする可能性があります。
5-2. AI時代に税理士人数は減るのか?
税理士の将来性を語る上で、AIによる代替の議論は避けられません。「AIの発展で税理士は不要になり、人数も減る」という意見もありますが、実態は異なります。
・代替される業務
単純な記帳代行、定型的な申告書の作成作業は、AIや会計ソフトの進化により確実に自動化されます。これらの業務しか行えない税理士の人数は、今後淘汰されていく可能性が高いです。
・「税理士」にしかできない業務
一方で、税務相談、税務調査の立ち会い(税務代理)、複雑な税法の解釈、経営コンサルティング、事業承継、M&A支援といった、高度な専門知識とコミュニケーション能力、経営判断を要する業務はAIには代替できません。
AI時代において、税理士の人数がゼロになることは考えられません。むしろ、AIを使いこなし、経営者のパートナーとして高付加価値なサービスを提供できる税理士は、ますます強く求められることになります。
5-3. 税理士人数の今後の見通し -結論-
今後の税理士の人数は、以下の2つの力が綱引き状態になると予測されます。
1.減少要因:60代以上が半数を占める高齢税理士の、今後10年~20年での大量引退。
2.増加要因:受験資格緩和による、若手を中心とした新規受験人数のV字回復。
この結果、税理士の総人数が現在の約82,000人から急激に減少するとは考えにくいでしょう。総人数は、当面の間、微増・微減、あるいは横ばいで推移する可能性が高いと見られます。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
6. 税理士の人数は全国に何人?税理士登録者の人数推移と今後の見通しを解説【まとめ】
今後は、高齢税理士の引退人数と、受験者数が増えている若手人数が入れ替わる「世代交代」が進むと見られます。税理士の総人数が急に減ることは考えにくいですが、AI時代を迎え、単純な人数の多さよりも、専門性の高い税理士がどれだけの人数いるかという「質」が、ますます重要になっていきます。




















