INDEX
おすすめ記事
-

税理士の仕事内容とは?とある1日のリアルスケジュールを大公開!
-

税理士の事業承継業務とは?税理士が押さえるべき事業承継の実務と支援ポイント
-
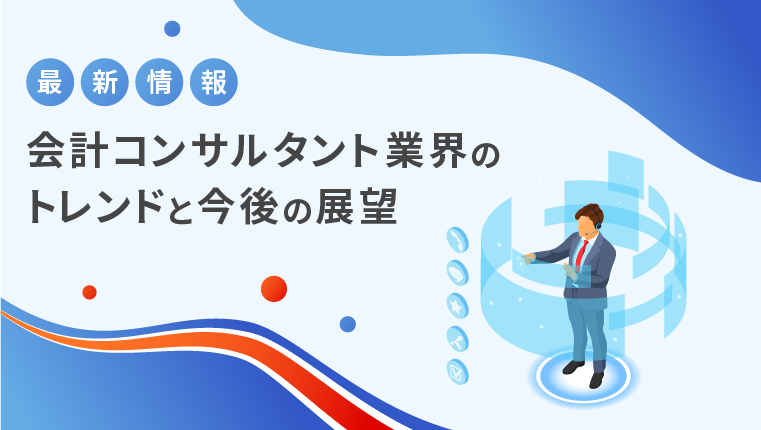
会計コンサルタント業界のトレンドと今後の展望【最新情報】
-
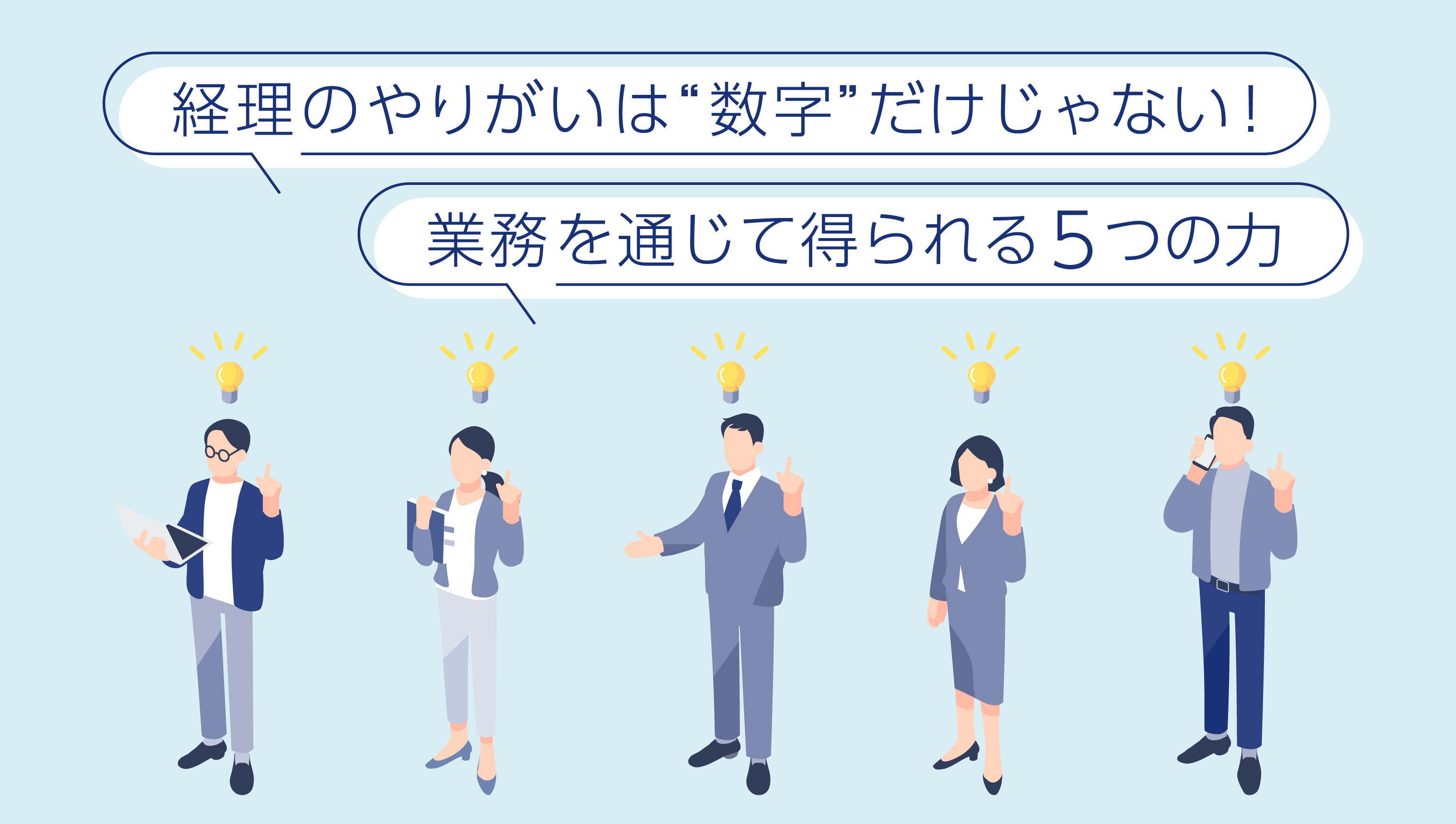
経理のやりがいは“数字”だけじゃない!業務を通じて得られる5つの力
-
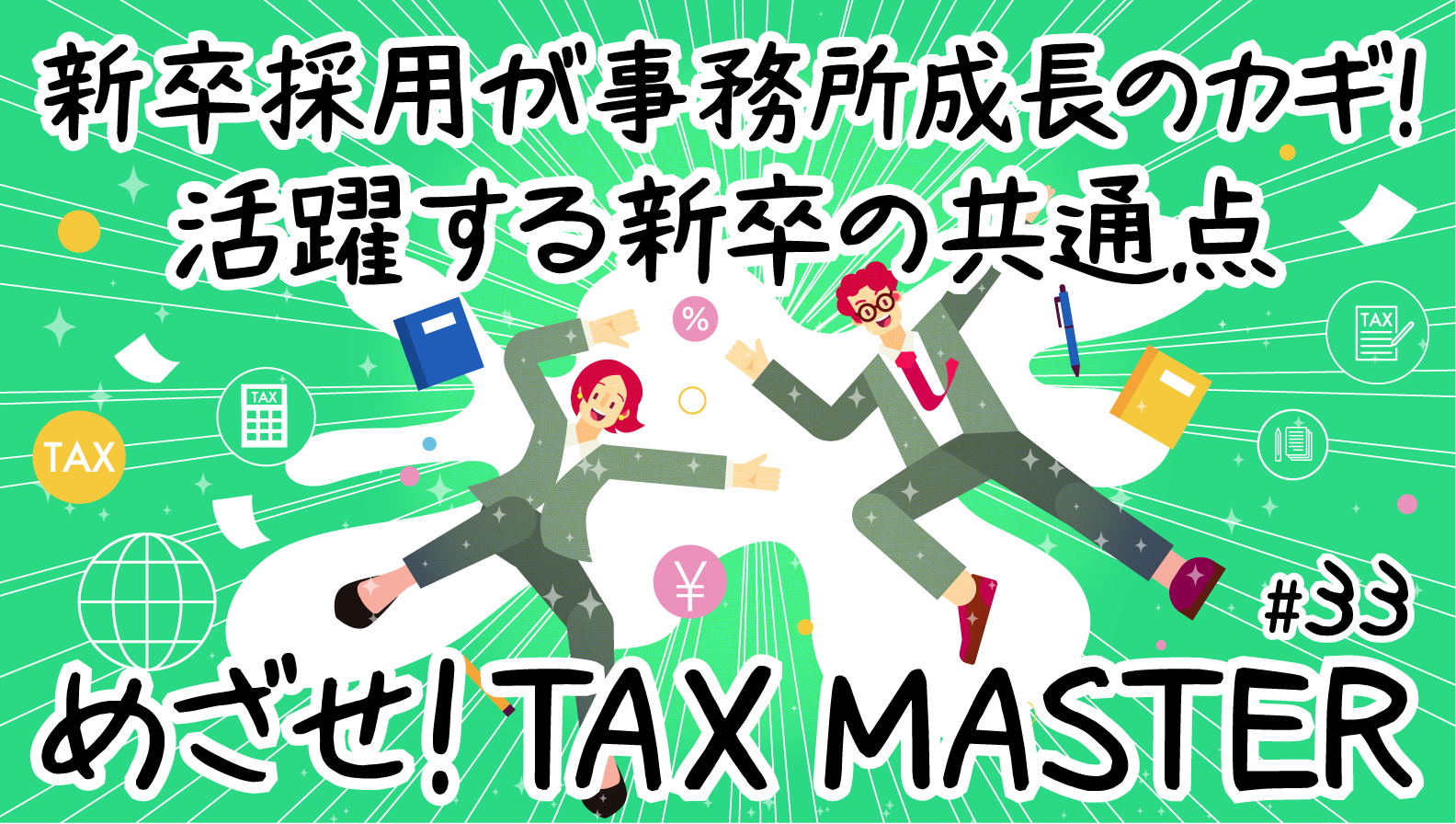
新卒採用が事務所成長のカギ!活躍する新卒の共通点【めざせ!TAX MASTER#33】
公開日:2025/11/14
最終更新日:2025/11/25
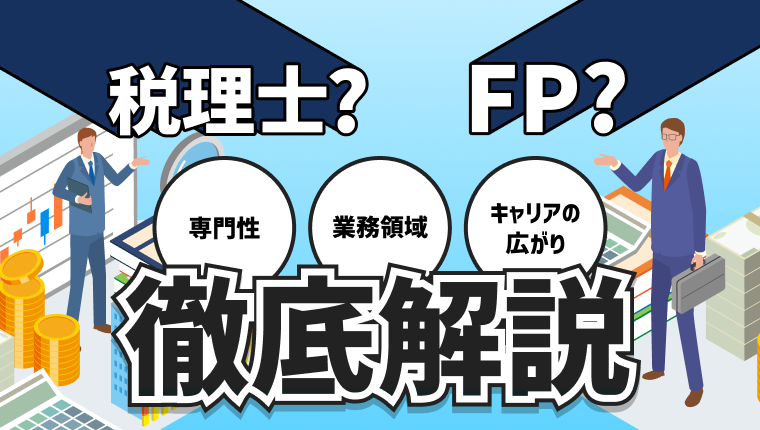
INDEX
「税理士」と「FP(ファイナンシャルプランナー)」は、いずれもお金に関する専門家として知られています。しかし、両者の資格制度や業務内容、活躍フィールドには明確な違いがあります。税理士は税務のプロフェッショナルとして法人・個人事業主の申告や会計を担い、FPは個人のライフプランや資産形成を支援するアドバイザーです。
近年では、相続や資産形成、老後資金などの相談が増加しており、税理士とFPの連携が求められる場面も増えています。本記事では、税理士とFPそれぞれの特徴を丁寧に解説し、どんな場面で活躍できるのかを具体的に紹介します。最後に、両資格を取得する「ダブルライセンス」という選択肢についても触れます。
あなたの「適正年収」を調べてみませんか?
簡単な質問に答えるだけで、一般的な会計事務所ならいくら提示されるのかを即座に算出。「今の適正額」はもちろん、「資格を取得したら年収はどう変わるのか?」など、あなたの現在地と未来の可能性を診断します。
税理士とは
税理士は、税理士法に基づく国家資格であり、税務に関する独占業務を持つ専門職です。税理士になるためには、税理士試験に合格するか、一定の条件を満たすことで試験科目の一部を免除されるルートがあります。主な取得ルートは以下の3つです:
・税理士試験に合格(科目合格制)
・公認会計士・弁護士資格保有者による免除
・大学院修了による一部科目免除
税理士試験は簿記論・財務諸表論・税法科目(法人税・所得税・相続税など)から構成され、合格までに数年かかることも珍しくありません。特に税法科目は専門性が高く、実務に直結する内容が多いため、受験生は実務経験を積みながら学習するケースも多く見られます。
税理士の業務は以下の3つに分類されます:
1.税務代理:税務署への申告・相談の代行
2.税務書類の作成:確定申告書・決算書などの作成
3.税務相談:税金に関する助言・指導
これらは税理士にしか認められていない独占業務であり、特に法人顧問としての会計業務や、個人の相続税申告などで活躍しています。税理士の顧客層は法人・個人事業主が中心で、経営者との長期的な関係構築が重要です。
最近では資産税や事業承継など、個人富裕層向けのサービスも増加しており、税理士の業務領域は広がりを見せています。また、クラウド会計やAIの導入により、定型業務の効率化が進む一方で、コンサルティング型の税理士が求められる傾向も強まっています。
FPとは
FP(ファイナンシャルプランナー)は、個人の生活設計や資産形成を支援する専門家です。税理士のような独占業務はありませんが、幅広い金融知識を活かして助言を行います。FP資格には大きく分けて「国家資格」と「民間資格」があり、それぞれに特徴と役割があります。
| 資格名 | 種類 | 特徴 |
|---|---|---|
| FP技能士(1〜3級) | 国家資格 | 実務経験に応じて受験可能。3級は誰でも受験可。 |
| AFP | 民間資格 | 日本FP協会認定。2級相当。提案書の提出が必要。 |
| CFP | 民間資格 | 国際資格。6科目合格が必要。難易度高め。 |
国家資格:FP技能士(1級・2級・3級)
FP技能士は、厚生労働省が管轄する国家資格で、技能検定制度に基づいて実施されます。等級は3級・2級・1級の3段階に分かれており、数字が小さいほど難易度が高く、実務的な専門性も増します。
・3級FP技能士:FPの入門資格。誰でも受験可能で、学生や社会人の初学者が多く受験します。ライフプラン・保険・年金・不動産・税金・相続など、基礎的な知識を幅広く学べます。
・2級FP技能士:実務レベルの資格。受験には一定の実務経験や、3級合格・AFP認定研修修了などの条件が必要です。税理士資格保有者はこの2級から直接受験可能です。
・1級FP技能士:高度な実務能力を証明する最上位資格。受験には2級合格後の実務経験が必要で、学科試験と実技試験の両方に合格する必要があります。合格率は10〜15%程度と難関です。
FP技能士は、企業内FPや保険・金融業界での評価が高く、特に2級以上は「実務で使えるFP」として一定の信頼を得られます。
民間資格:AFP・CFP(日本FP協会)
AFP・CFPは日本FP協会が認定する国際基準に基づいた民間の資格制度
で、特にCFPは世界25カ国以上で通用するグローバル資格です。
・AFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー):2級FP技能士と同等レベル。日本FP協会が認定する研修を修了し、提案書(ライフプラン設計書)を提出することで取得できます。実務的な提案力が重視され、保険・金融業界での評価も高いです。
・CFP(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー):AFPの上位資格で、国際的に認知されたFP資格。6つの専門分野(ライフプラン、リスク管理、金融資産運用、不動産、タックスプランニング、相続・事業承継)ごとに試験があり、すべて合格する必要があります。さらに、実務経験や倫理研修も求められます。
CFPは「FPのプロフェッショナル」としての証明であり、独立系FPや資産運用アドバイザー、相続コンサルタントなど、専門性の高い分野で活躍する人にとっては大きな武器になります。
国家資格と民間資格の違いと補完関係
FP技能士は「技能検定」としての公的な信頼性があり、企業内での昇進や資格手当などに直結しやすい一方、AFP・CFPは「実務力」や「提案力」を重視した資格であり、顧客対応や独立開業を視野に入れる人に適しています。
実際には、2級FP技能士とAFPを同時に取得する人が多く、国家資格と民間資格を補完的に活用するのが一般的です。CFPを目指す場合も、まずはAFPを取得し、段階的にステップアップしていくのが王道ルートです。
FPの主な業務
FPの主な業務は以下の通りです:
・ライフプラン設計
・保険の見直し
・老後資金・年金の相談
・住宅ローン・教育資金の計画
・資産運用(NISA・iDeCoなど)
FPの顧客層は個人・家庭が中心で、保険代理店・金融機関・不動産会社などで活躍するほか、独立系FPとしてセミナー講師や執筆活動を行う人もいます。FPは「相談しやすい存在」として、顧客の人生設計に寄り添う役割を担っています。
また、FPは金融商品の販売に関わることもありますが、助言業務に特化した「中立型FP」も増えており、顧客の利益を最優先に考える姿勢が評価されています。税制や社会保障制度との関連も深いため、FPには幅広い知識と継続的な学習が求められます。
税理士とFPの違いと連携の可能性
税理士とFPは、いずれも「お金」に関する専門家ですが、資格制度・業務内容・顧客層・活躍フィールドにおいて明確な違いがあります。
| 項目 | 税理士 | FP資格 |
|---|---|---|
| 資格区分 | 国家資格(税理士法) | 国家資格+民間資格 |
| 独占業務 | 税務代理・税務書類作成・税務相談 | なし(助言業務のみ) |
| 主な相談領域 | 税務・会計・相続 | ライフプラン・保険・資産運用 |
| 顧客層 | 法人・個人事業主 | 個人・家庭 |
| 活躍場所 | 税理士事務所・税理士法人 | 金融機関・保険会社・独立FP |
たとえば、相続に関する相談では、税理士が相続税申告や財産評価を担当し、FPが納税資金の確保や生命保険の活用、遺産分割に関するライフプラン的な助言を行うことで、顧客にとってより安心できるサポートが可能になります。
住宅購入に関する相談では、FPが住宅ローンの選定や返済計画、教育資金とのバランスなどを助言し、税理士が住宅ローン控除の適用や確定申告の手続きを担当することで、制度の活用がスムーズになります。
老後資金や年金の受け取りに関しても、FPがiDeCoやNISAなどの資産形成制度の活用方法を助言し、税理士が年金受給時の課税関係や確定申告の方法を説明することで、税負担を抑えながら安心して老後を迎える準備ができます。
ダブルライセンスという選択肢
税理士がFP資格を取得することで、相談領域が広がり、顧客満足度の向上やキャリアの幅が広がる可能性があります。逆に、FPが税理士資格を目指すケースもありますが、税理士試験の難易度や実務経験要件を考慮する必要があります。
税理士がFP資格を取得するメリット
・相続・資産税分野での提案力強化
・顧客との信頼関係構築
・転職・独立時の差別化要素
税理士はAFP認定研修の一部が免除されるため、比較的短期間でFP資格を取得することが可能です。特に資産税や相続分野に強みを持つ税理士にとっては、FP的視点を持つことで、顧客の「人生全体」を見据えた提案が可能になります。たとえば、相続税申告を行う際に、納税資金の確保や遺産分割の助言、生命保険の活用など、税務以外の視点が求められる場面は少なくありません。FP資格を持つことで、こうしたニーズに対応できる幅が広がります。
また、税理士がFP資格を取得することで、金融機関や保険会社との連携がしやすくなり、顧客紹介や業務提携の機会も増える可能性があります。特に独立開業を目指す税理士にとっては、「相談しやすい税理士」としてのブランディングに役立ちます。
一方、FPが税理士資格を目指す場合は、税理士試験の難易度や受験資格要件を十分に理解しておく必要があります。税理士試験は科目合格制であり、長期的な学習が必要です。また、実務経験や大学院修了などの条件を満たす必要があるため、計画的なキャリア設計が求められます。
ダブルライセンスは万能ではありませんが、顧客ニーズが複雑化する現代においては、選択肢として十分に検討する価値があります。特に「税務+ライフプラン」の両面から支援できる専門家は、今後ますます求められるでしょう。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士とFPの違いは? -まとめ
税理士とFPは、それぞれ異なる専門性を持ちながらも、顧客の「お金」に関する課題を支援するという共通の目的を持っています。税理士は税務の専門家として、法人や個人事業主の申告・会計・相続税対応などを担い、FPは個人のライフプラン設計や資産形成、保険・年金・住宅ローンなどの助言を行います。
両者の違いを理解することで、相談先としての選択肢が広がるだけでなく、キャリア設計にも役立ちます。税理士とFPが連携することで、顧客にとっては「税金+生活設計」の両面から包括的な支援を受けることができ、より安心して人生の選択を進めることが可能になります。
また、ダブルライセンスという選択肢もあります。税理士がFP資格を取得することで、相談領域が広がり、顧客満足度の向上やキャリアの幅が広がる可能性があります。逆に、FPが税理士資格を目指す場合は、制度や試験の難易度を理解した上で、計画的に取り組むことが重要です。
今後の社会では、税務とライフプランの両面から支援できる専門家がますます求められるでしょう。まずはそれぞれの役割を正しく理解し、自身の目的に応じて連携や取得を検討することが、より良いキャリアとサービス提供につながります。

高梨 茉奈(たかなし まな)
めざせ!TAX MASTER パーソナリティ



















