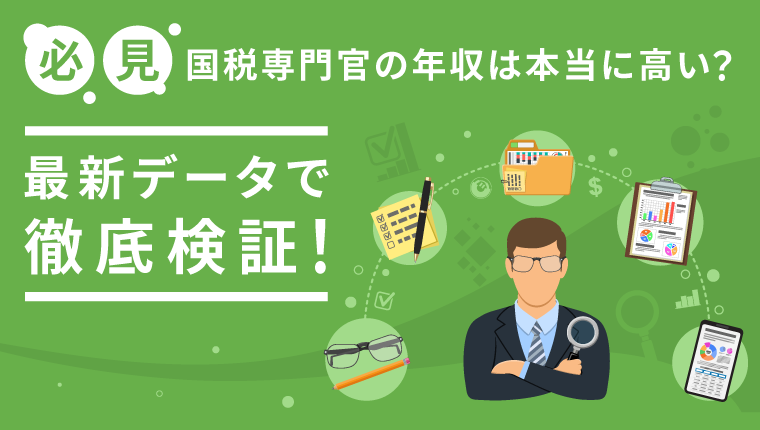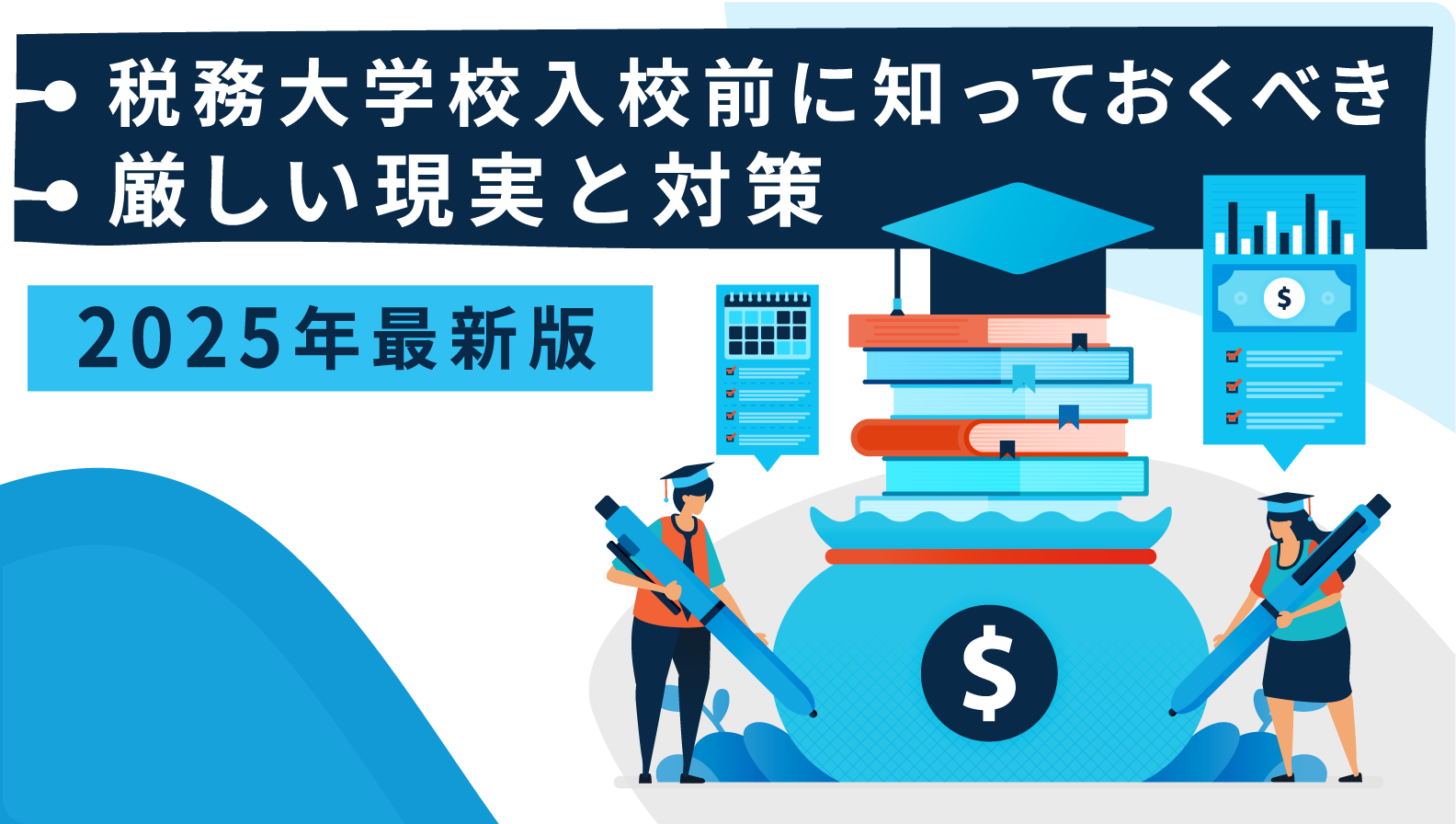INDEX
おすすめ記事
-
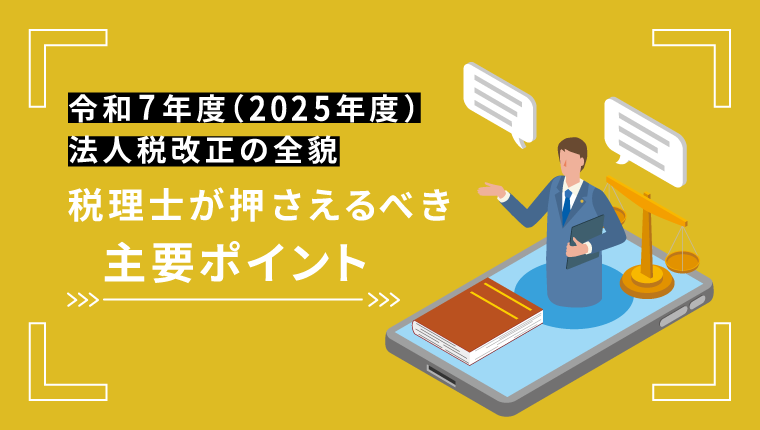
令和7年度(2025年度)法人税改正の全貌:税理士が押さえるべき主要ポイント
-
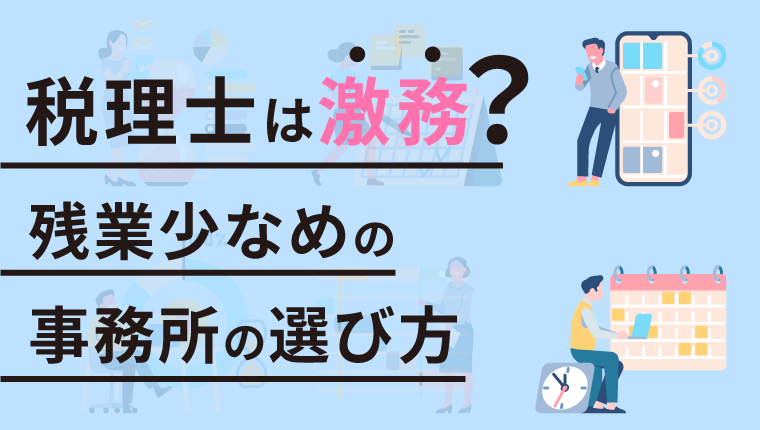
税理士は激務?残業少なめの事務所の選び方
-
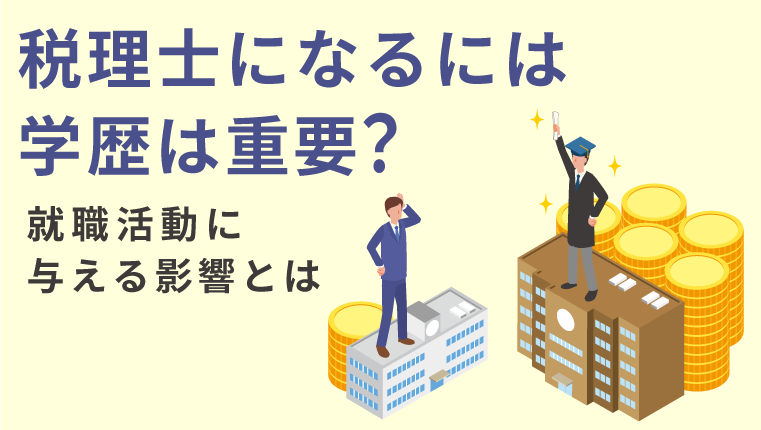
税理士になるには学歴は重要?就職活動に与える影響とは
-

【2025年度版】税理士試験の受験資格と注意点を解説!
-
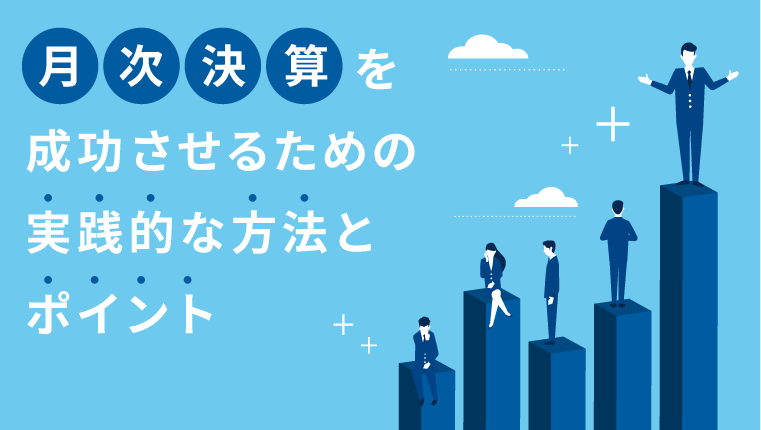
月次決算とは?月次決算を成功させるための実践ポイントを税理士が解説
公開日:2025/03/14
最終更新日:2025/11/25
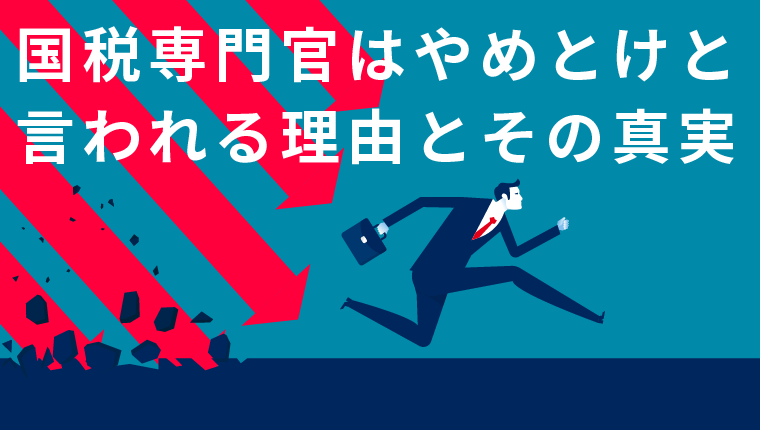
INDEX
「国税専門官って安定してて高収入だけど、実際どうなの?」
こんな疑問を抱いたことはありませんか?
ネットで「国税専門官はやめとけ」なんて言葉を見つけて、不安になった方も多いはず。確かに、公務員の中でも特殊なポジションである国税専門官には、ハードな現実と魅力的なメリットが共存しています。
・「本当にワークライフバランスは最悪なの?」
・「税理士資格が無試験で取れるって本当?」
・「向いている人と向いていない人の違いは?」
この記事では、そんな疑問を徹底解剖! 国税専門官のリアルな実情と、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
「受験するか迷っている…」「税務の仕事に興味がある!」そんなあなたに役立つ内容が満載です。ぜひ最後までお読みください。
あなたの「適正年収」を調べてみませんか?
簡単な質問に答えるだけで、一般的な会計事務所ならいくら提示されるのかを即座に算出。「今の適正額」はもちろん、「資格を取得したら年収はどう変わるのか?」など、あなたの現在地と未来の可能性を診断します。
国税専門官はやめとけと言われる理由は?
「国税専門官はやめとけ」と言われる理由として、以下の点がよく挙げられます。
ワークライフバランスが悪い
繁忙期(特に確定申告時期や税務調査の締め切り前)には残業が多くなり、休日出勤も発生することがあります。特に調査部門に配属されると、納税者への訪問調査や書類作成で長時間労働になりがちです。
精神的なストレスが大きい
税務調査では、納税者や企業と対立する場面も少なくなく、時には強い反発やクレームを受けることもあります。加えて、脱税や不正を見抜くプレッシャーも大きく、精神的な負担がかかることがあります。
仕事の責任が多い
国税専門官は税務行政の一翼を担う立場にあり、正確な調査や公正な判断が求められます。特に追徴課税や罰則の判断など、納税者に大きな影響を与える決定を行うため、責任感を強く求められます。
専門知識を身に付けることを求められる
税法は頻繁に改正されるため、常に最新の知識を学び続ける必要があります。さらに、法人税、所得税、相続税など幅広い税目に対応するため、幅広い知識を身につけなければなりません。
その他の理由
・出世競争や人間関係のストレス
公務員とはいえ、出世や昇進において競争が存在します。また、縦割りの組織文化や上司との関係にストレスを感じることもあります。
・転勤の可能性
国税局管内での転勤が数年ごとにあるため、家庭の事情やライフプランに影響を及ぼすことがあります。
国税専門官になるメリット
国税専門官になるメリットとして、以下のポイントが挙げられます。
年収が高く安定している
・安定した収入:公務員であるため、景気に左右されず安定した給与が保証されています。
・年功序列型の昇給:毎年の昇給と定期的な昇格があり、勤続年数に応じて収入が増えていきます。
・各種手当が充実:扶養手当、住宅手当、地域手当、通勤手当などの各種手当が支給されるため、実質的な年収は高めです。
・退職金制度:退職時には公務員特有の厚い退職金制度があり、長期的な安定性も魅力です。
なお、国税調査官の年収詳細については以下の記事をご確認ください。
専門性が身につく
・幅広い税法知識:所得税・法人税・相続税など多岐にわたる税法に精通できます。
・調査・徴収のスキル:税務調査や徴収の実務経験を通じて、法律の適用や企業分析力が身につきます。
・交渉力・論理的思考力:調査対象者との折衝や交渉を通じて、高度なコミュニケーションスキルが養われます。
・コンプライアンスや内部統制の知識:企業の税務監査を通じて、会計や内部統制に関する深い理解が得られます。
税理士の資格を得られる
・
実務経験で資格取得:国税専門官として23年以上の勤務をした場合全科目、10年以上勤務した場合税法3科目が免除されます。
・セカンドキャリアの選択肢:退職後に税理士として独立開業したり、税理士法人に転職する道が開けます。特に元国税の肩書きは信頼性が高く、顧客獲得に有利です。
研修制度が整っている
・
充実した初任研修:採用後には、数か月にわたる体系的な研修が用意されており、税法や実務知識を基礎から学べます。
・OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング):配属後は先輩職員の指導のもと、実務を通じてスキルを習得します。
・定期的なスキルアップ研修:税法改正や新たな業務に対応するための定期的な研修が実施され、常に最新の知識を身につけられます。
・外部研修や資格取得の支援:必要に応じて、会計・法律・コミュニケーションスキルなど、外部研修の受講も可能です。
なお、税務大学校については以下の記事をご参照ください。
その他のメリット
・ワークライフバランス(部署による):配属先によっては比較的落ち着いた勤務が可能で、定時退庁できる場合もあります。
・社会的信頼性が高い:国税専門官は社会的信用度が高く、ローンの審査や住宅の契約などでも有利に働くことがあります。
・転職市場での評価が高い:退職後の民間企業への転職において、財務・経理部門などで高い評価を受けることがあります。
メリットとデメリットを比較すると以下のような表になります。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 給与・待遇 | 安定した収入と充実した手当。退職金制度もあり。 | 繁忙期には残業・休日出勤が増え、時間単価が低く感じることも。 |
| 専門性 | 幅広い税法知識と調査・交渉スキルが身につく。 | 継続的な学習と法改正への対応が必須。 |
| キャリア形成 | 税理士資格を取得でき、将来的に独立や転職の選択肢が広がる。 | 実務経験を積むまでに長期間(10年以上)が必要。 |
| ワークライフバランス | 部署によっては定時退庁も可能。 | 確定申告時期などは長時間労働になりがち。 |
| 精神的負担 | 社会的意義のある仕事に携わる充実感。 | 納税者との対立やクレーム対応で強いストレスを感じる場面が多い。 |
| 勤務地・異動 | 全国各地の経験を積める可能性。 | 数年ごとの転勤で、家族やライフプランに影響することがある。 |
| 福利厚生・社会的信用 | 公務員特有の福利厚生が整っており、社会的信用度も高い。 | 民間企業と比較すると、柔軟な働き方(リモート勤務など)の導入が遅れている場合がある。 |
国税専門官に向いている人は?
向いている人の特徴
1.論理的思考力がある人
◦複雑な税法や会計ルールを理解し、論理的に考えられる人。
◦税務調査では証拠をもとに冷静な判断を下す力が求められる。
2.正義感・倫理観が強い人
◦公平・公正な立場で税務調査を行うため、不正や不公平に対して毅然と対応できる人。
◦法令順守を徹底し、正しいことを貫く強い意志がある人。
3.コミュニケーション能力が高い人
◦納税者や企業担当者と円滑なやりとりができる人。
◦調査対象者との交渉や説得が必要な場面が多いため、柔軟な対応力や交渉力が求められる。
4.責任感・粘り強さがある人
◦税務調査は長期戦になることも多く、最後まで諦めずに取り組める粘り強さが必要。
◦自分の判断が納税者に大きな影響を与えるため、責任感の強い人が向いている。
5.学び続ける意欲がある人
◦税法は頻繁に改正されるため、常に最新の知識を学び続ける必要がある。
◦法律・会計だけでなく、経済や金融など幅広い分野に関心を持てる人。
6.ストレス耐性が高い人
◦納税者との対立やクレーム対応で精神的な負担が大きくなることがあるため、ストレスに強い人が適している。
◦長時間労働や繁忙期のプレッシャーにも耐えられる人。
7.協調性がある人
◦チームでの調査や連携が必要な場面が多く、周囲と協力して業務を進められる人。
◦上司や同僚との報告・連絡・相談を適切に行える人。
向いていない人の特徴
1.ストレス耐性が低い人
◦クレーム対応や対立場面に弱い人は、精神的に負担を感じやすい。
◦プレッシャーの強い場面(追徴課税の判断など)に耐えられない場合は難しい。
2.コミュニケーションが苦手な人
◦税務調査では説明や説得が不可欠なため、対人関係に苦手意識があると苦労する。
◦単独で仕事を進めたいタイプの人は、チームワークが求められる職場にストレスを感じる可能性がある。
3.ルールに縛られるのが苦手な人
◦税務業務は法令に基づくため、厳格なルール遵守が求められる。
◦自由な発想や柔軟な仕事を好む人には窮屈に感じることがある。
4.長時間労働や繁忙期に耐えられない人
◦確定申告時期や税務調査の締め切り前には、残業や休日出勤が発生することがある。
◦ワークライフバランスを重視し、定時退社を徹底したい人には不向き。
5.学び続けることが苦手な人
◦税法改正への対応や最新の会計基準の理解など、継続的な学習が必要。
◦新しい知識を習得することに消極的な人は適応が難しい。
6.責任の重さにプレッシャーを感じやすい人
◦税務調査の結果が企業や個人の経済状況に大きな影響を与えるため、責任感が重くのしかかることがある。
◦重要な判断を下すプレッシャーに弱い人には不向き。
| 項目 | 向いている人の特徴 | 向いていない人の特徴 |
|---|---|---|
| 思考力・知識 | 論理的思考力があり、税法や会計に興味を持てる人。 | ルールに縛られるのが苦手で、学び続けることに消極的な人。 |
| 対人スキル | コミュニケーション能力が高く、交渉や説得が得意な人。 | 対人関係が苦手で、クレーム対応にストレスを感じる人。 |
| 性格・価値観 | 正義感や責任感が強く、公正さを大切にできる人。 | 責任の重さにプレッシャーを感じやすい人。 |
| 働き方への適応力 | 繁忙期にも粘り強く働けるストレス耐性がある人。 | 繁忙期の長時間労働やプレッシャーに耐えられない人。 |
| 学習意欲 | 税法改正など新しい知識を積極的に学べる人。 | 知識習得や学習に対して消極的な人。 |
| 協調性 | チームワークを大切にし、周囲と協力できる人。 | 一人で仕事を完結させたいと考える人。 |
国税専門官になる方法は?
国税専門官になるためには、国家公務員採用試験(国税専門官採用試験)に合格し、その後の研修を経て正式に採用されます。以下の手順で進めることができます。
① 国税専門官採用試験に申し込む
・試験実施機関:人事院
・試験区分:国家公務員採用試験(国税専門官)
・受験資格:
◦年齢要件:21歳以上30歳未満(試験年度の4月1日時点)
◦学歴要件:短大・専門学校卒業以上(学部学科不問)
◦※既卒者や社会人の受験も可能です。
・申込期間:例年4月上旬〜4月下旬
・試験日程:
◦1次試験:6月中旬
◦2次試験:7月下旬〜8月上旬
◦最終合格発表:8月下旬〜9月上旬
② 試験内容
1次試験(筆記試験)
・基礎能力試験(40問):
◦一般知能分野(数的処理、文章理解など)
◦一般知識分野(政治・経済・社会・時事など)
・専門試験(択一式)(40問):
◦憲法、民法、行政法、経済学、会計学、商法、財務諸表論など
◦※特に会計学・商法・財務諸表論の重要度が高いです。
・記述式試験:
◦民法、経済学、会計学などから1科目選択し、論述問題に解答。
2次試験(人物試験)
・面接試験(個別面接):
◦志望動機、適性、人物像を確認。
◦税務職員としての責任感や倫理観が重視されます。
・適性検査:
◦事務処理能力や論理的思考力を確認する筆記試験。
・身体検査:
◦一般的な健康状態の確認。
③ 試験対策方法
1.専門試験対策(会計・商法・民法など)
◦出題範囲が広いため、過去問演習と基礎固めが重要。
◦特に「会計学」や「財務諸表論」は頻出なので重点的に学習。
2.基礎能力試験対策(数的処理・文章理解など)
◦数的推理・判断推理を中心に演習問題を繰り返す。
◦時事問題にも対応できるよう、日頃からニュースをチェック。
3.記述式試験対策
◦論理的な構成力を身につけるため、過去問で練習。
◦採点者にわかりやすく伝える文章力が求められる。
4.面接対策
◦税務行政の役割や国税専門官の業務内容を理解しておく。
◦自己分析と志望動機の明確化が重要。模擬面接の活用も効果的。
5.予備校や通信講座の活用
◦独学が不安な場合は、公務員試験専門の予備校や通信講座を利用。
◦国税専門官に特化したカリキュラムがある学校も多数。
④ 採用後の流れ
1.採用内定後
◦2次試験合格後、国税局ごとに配属先が決定されます。
2.初任研修
◦国税専門官研修所(各地に拠点あり)で数か月間の初任研修を受講。
◦税法、会計、税務調査の基本知識を習得します。
3.現場配属
◦研修終了後、税務署などに配属され、実務がスタートします。
◦初年度はOJT形式で先輩職員から実務を学びます。
4.キャリアアップ
◦数年ごとに異動や昇進の機会があります。
◦調査部門、徴収部門、国税局本局などへの異動も可能。
◦長期的には、国税調査官や特別国税調査官への昇進の道もあります。
⑤ 国税専門官へのキャリアパスの魅力
・安定した職業:国家公務員としての安定性があり、景気に左右されない。
・専門性の習得:税務・会計・法律など幅広い知識を実務で学べる。
・税理士資格の取得:実務経験(23年または調査部門10年)で無試験取得が可能。
・セカンドキャリアの選択肢:税理士事務所への転職や独立開業が視野に入る。
国税専門官はやめとけと言われる理由とその真実 -まとめ
この記事では国税専門官について解説しました。
「国税専門官はやめとけ」と言われることもありますが、国税専門官は安定性と専門性を兼ね備えた職業であり、将来的なキャリア形成の選択肢も豊富です。しっかりとした試験対策と明確な志望動機を準備し、着実にステップを踏んで合格を目指しましょう。
この記事が少しでも参考になれば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)