INDEX
おすすめ記事
-

iDeCo改悪の真実とその影響を徹底解説!【2025年(令和7年)最新版】
-
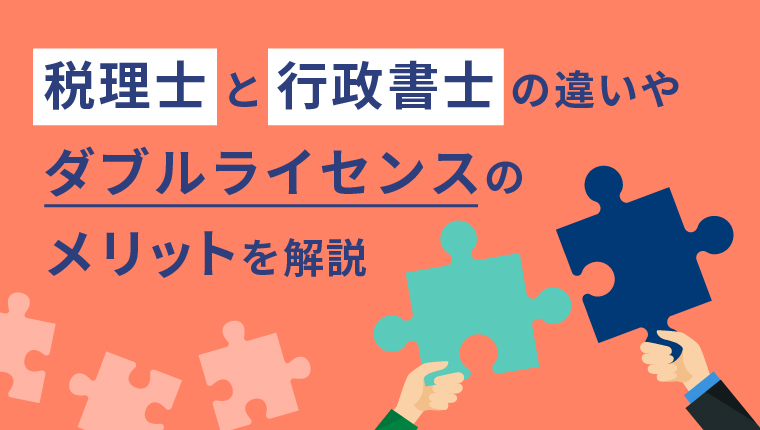
税理士と行政書士の違いやダブルライセンスのメリットを解説
-
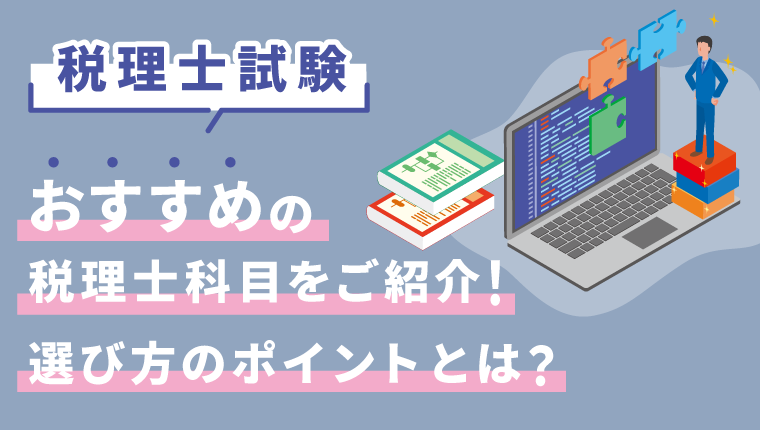
【税理士試験】おすすめの税理士科目をご紹介!選び方のポイントとは?
-
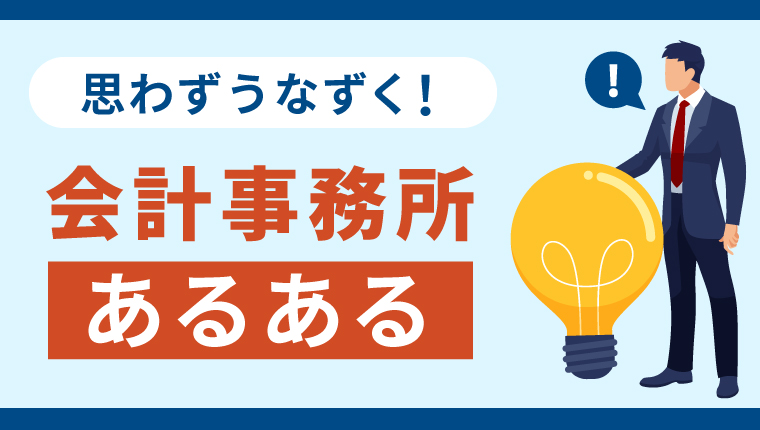
思わずうなずく!会計事務所あるある
-
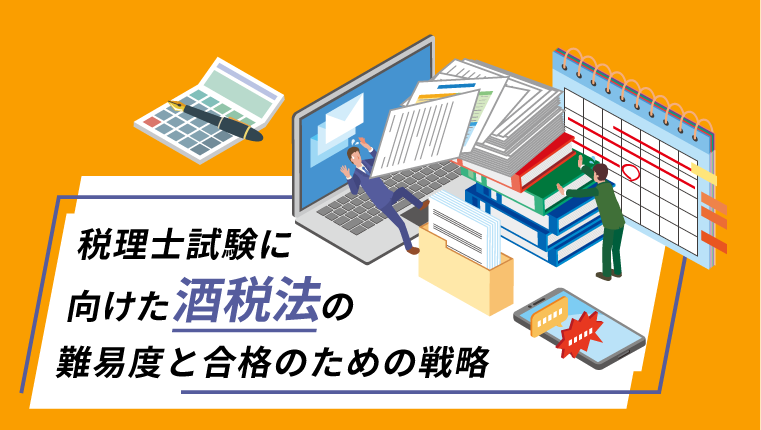
税理士試験に向けた酒税法の難易度と合格のための戦略
公開日:2025/03/14
最終更新日:2025/09/06

INDEX
税理士が広告活動を行う際は、広告規制を遵守し、適切な情報を発信することが求められます。
平成13年の税理士法改正により、税理士の広告は原則として自由となりましたが、「虚偽・誇大広告」や「他者を誹謗中傷する広告」、「過度な比較広告」などは引き続き禁止されています。このほかにも、4つの規制が定められています。
これらの広告規制を理解することで、違反行為を避けることができます。
よって、今回の記事では、広告規制について詳しく解説するとともに、広告手段や、最新の税理士業界における広告トレンドをご紹介します。
それでは、まずなぜ税理士には広告が必要なのかについて見ていきましょう。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士の広告とは?
税理士の広告とは、税理士が自身の業務を宣伝し、顧客を獲得するための情報発信を指します税理士は全員が同じ資格を有しているため、資格をアピールするだけでは差別化につながりません。そのため、サービス内容、価格設定、信頼性などを強調し、他の税理士との差別化を図ることで、顧客の獲得につなげています。
税理士にとって広告は、自身の強みを知ってもらうためのツールとして活用されます。適切な広告手段を選択することで、より効果的な集客戦略を実施できます。
税理士の広告手段
税理士が活用できる広告の主な方法は、以下の5つがあります。
・ウェブサイト・ブログ
◦事務所の公式サイトやブログで業務内容や得意分野を紹介。
◦税務の知識や最新情報を発信することで信頼を獲得。
・SNS(X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、YouTubeなど)
◦税務情報や節税対策などの有益な情報を発信。
・パンフレット・チラシ
◦ 事務所紹介のパンフレットを作成し、顧客に配布。
・新聞・雑誌広告
◦一定のルールを守れば、新聞や専門誌などに広告を出すことも可能。
・紹介・口コミ
◦既存の顧客や知人を通じた紹介が主な集客手段となる。
このようにさまざまな広告手段がありますが、初めに説明したように、
税理士には広告規制が存在します。これらの規制は、税理士の社会的信用を守り、誤解や不当な競争を防ぐために設けられています。
それではこの誤解や不当な行為について詳しく見ていきましょう。
税理士は避けたい広告活動での違反行為
税理士の広告活動の中で禁止されている行為は以下の7つがあります。
1.虚偽・誇大広告
2.他者を誹謗中傷する広告
3.根拠のない成功事例を強調
4.不特定多数への大量配布・過剰な広告
5.過度なランキングや比較広告
6.紹介料や特典をエサにする広告
7.SNSやYouTubeでの不適切な広告
この7つの違反行為をもう少し細かく説明していきます。
1. 虚偽・誇大広告
税理士には「虚偽・誇大広告」が禁止されています。これは、事実と異なる内容や誤解を招く表現を使って顧客を獲得しようとする行為を指します。税理士としての信頼を損なうだけでなく、広告規制に違反する行為となるため、注意しておきたいポイントです。
・ 虚偽・誇大広告例
◦「100%節税成功!」
◦「税務調査を完全回避できます!」
税理士法に違反しないためには、事実に基づいた適切な広告を行うことが重要です。例えば、「豊富な経験を活かし、お客様に最適な節税対策をご提案します。」のようにサービスの提供と豊富な経験をアピールする広告は効果的と言えます。
2. 他者を誹謗中傷する広告
税理士には「他者を誹謗中傷する広告」が禁止されています。これは、
他の税理士や会計事務所を貶めるような内容を広告に含める行為を指します。税理士は自らの強みを適正にアピールすることは許されています。しかし、他の税理士や事務所の評価を落とすような広告は禁止されています。
・他者を誹謗中傷する広告例
◦「○○税理士事務所は対応が遅いです。」
◦「他の税理士は信用できませんが、当事務所は違います!」
したがって、他者を批判して自身を優位に見せるような広告は違反行為とみなされます。他事務所との比較を避け、公正で誠実な宣伝活動を行うことが求められます。
例えば、「当事務所では迅速な対応を心掛けております。」のように、自身の強みを強調する表現が有効です。
3. 根拠のない成功事例を強調
税理士には「根拠のない成功事例を強調する広告」も禁止されています。これは、客観的な証拠や具体的なデータがないにもかかわらず、自身の業務実績を誇張し、顧客に誤解を与えるような表現を使う行為を指します。
・根拠のない成功事例を強調する広告例
◦「すべての顧問先で税務調査ゼロ!」
◦「1年間でクライアントの税金を90%削減しました!」
上記のように、証明できない事例やデータを使って顧客獲得を行うことは違反行為にあたります。したがって、適切な表現を用いて、公正で効果的な広告を作成することが求められます。
4. 不特定多数への大量配布・過剰な広告
「不特定多数への大量配布・過剰な宣伝活動」とは、無差別にチラシやDM(ダイレクトメール)を大量配布したり、過度な宣伝活動を行ったりすることを指します。
・ 不特定多数への大量配布・過剰活動例
◦ポストやメールボックスへの無差別チラシ投函
◦迷惑メール
税理士の広告は適切な方法で行う必要があり、ターゲットを絞った情報発信や、専門性を活かしたコンテンツの提供など、信頼を維持しながら実施することが不可欠です。
5. 過度なランキングや比較広告
「過度なランキングや比較広告」とは、客観的な根拠が不明確なまま、自身の事務所を他の税理士と比較して優位性を強調する広告を指します。税理士が広告を行う際は、正確で客観的な情報をもとに、見る人に誤解を与えないよう配慮することが大切です。
・過度なランキングや比較広告例
◦「○○市No.1税理士!」
・客観的な証拠がない場合は違反行為となる
◦「競合税理士よりも安い&高品質!」
上記のように、数値で比較しにくい広告や、根拠のないランキングを使って他事務所との比較を行う広告方法は、違反行為に値します。
もし、事務所のサービスの良さを伝えたい場合は、他社との比較ではなく、顧客満足度などを使って事務所の好感度が高い点をアピールすることが大切です。
6. 紹介料や特典をエサにする広告
税理士には「紹介料や特典を利用した広告」が禁止されています。これは、新規顧客の獲得を目的として、金銭や物品などの特典を提供することを宣伝する行為を指します。
・紹介料や特典をエサにする広告例
◦「当事務所をご紹介いただいた方に1万円プレゼント!」
◦「契約でAmazonギフト券プレゼント!」
税理士は公正かつ適正な方法で業務を行うことが求められており、金銭や特典を使った集客は倫理的にも問題となります。税理士は紹介を通じて顧客獲得に繋がる場合がありますが、紹介を金銭や物品で誘導することは違反行為となります。
紹介は税理士にとって欠かせない営業手法の一つです。そのため、広告に紹介を含める場合は、「お客様のご紹介を心よりお待ちしております。」のように、報酬や特典を伴わない表現を用いることを意識しましょう。
7. SNSやYouTubeでの不適切な広告
税理士には「SNSやYouTubeでの不適切な広告」が禁止されています。これは、税理士としての品位を損なう内容や、誤解を招く情報を拡散する行為を指します。さらに、視聴者を過度に煽るタイトルや、過激な言葉を使って注目を集める行為も問題となる場合があるため、その点にも注意が必要です。
・SNSでの不適切な広告例
◦「100%節税できる方法を教えます!」
◦「どんな税務調査も完全に回避できます!」
◦「顧問契約すれば、必ず税金が50%減ります!」
税理士は事務所の認知度を高めるために広告を使用しますが、税理士には7つの広告規制が存在し、これらの違反行為を避けるためには、適切な表現を使用する必要があります。
違反行為を避けるために、次に合法的な広告方法について説明します。
合法的なプロモーション方法
上記を読んでいただいた通り、税理士の広告方法にはさまざまな規制があり、表現方法を誤ると違反行為に繋がる可能性があります。そのため、違反行為を避けるために、以下では適切な広告活動について解説していきます。
合法的な広告活動には以下の5つが挙げられます。
1.公式ウェブサイトを運営し、正確で最新の情報を提供
2.SNSやYouTubeで有益な情報を提供し、専門性をアピール
3.セミナーやウェビナーを通じて新規顧客と接点を持つ
4.Googleビジネスプロフィールを活用して、地域の顧客にアプローチ
5.紹介や口コミを活用し、自然な形で顧客を増やす
それではこれらを細かく解説していきます。
1. 公式ウェブサイトを活用し、正確な情報を発信
・事務所の基本情報(所在地・連絡先・営業時間)を明記
・提供するサービス(顧問契約・確定申告・節税対策)を詳細に説明
・定期的なブログ・ニュース更新で専門性をアピール
2. SNSやYouTubeで有益な情報を提供し、専門性をPR
・最新の税務情報や節税対策を発信
・顧問契約のメリットやサービス内容を自然に紹介
・顧客との交流を通じて信頼関係を構築
・「確定申告の手順」や「節税対策」などの解説動画を制作
・税務の専門知識を分かりやすく伝え、信頼を構築
・コメント欄や視聴者の質問に回答し、関係性を深める
3. セミナーやウェビナーを通じて新規顧客と接点を持つ
・地域の商工会議所やオンラインで無料セミナーを実施
・副業・フリーランス向けの税務相談会を開催
・参加者との接点を持ち、顧客獲得に繋がる機会を作る
4. Googleビジネスプロフィールで地域の顧客にアプローチ
・Googleマップに事務所を登録し、検索での認知度を向上
・口コミを活用し、信頼性を高める
・料金や提供サービスを詳細に記載
5. 紹介や口コミを活用し、自然な形で顧客を増やす
・満足度の高いサービスを提供し、自然に口コミを促す
・既存の顧客に「知人で税務の相談が必要な方がいたらご紹介ください」と依頼
・弁護士・社労士・行政書士と連携し、相互紹介のネットワークを作る
注意点
・「紹介してくれたら1万円キャッシュバック!」など報酬を伴う紹介制度は禁止
上記のように、広告方法は正しい手段で行うと効果的であることがわかります。それでは、最後に近年よく使われている税理士の広告方法を見ていきましょう。
税理士広告の最新動向とトレンド
1. デジタルマーケティング
・ホームページの最適化(SEO対策)
◦検索エンジンで上位表示されるよう、キーワード選定やコンテンツの質を高めることが重要。
◦特に「地域名+税理士」をターゲットにしたSEO対策(ローカルSEO)が効果的。
・ MEO対策
◦Googleビジネスプロフィールを活用し、Googleマップの検索結果での上位表示を目指す手法。
◦地域密着型のサービスを提供する税理士事務所にとって、重要な集客手段。
・SNSの活用
◦FacebookやInstagram、X(旧Twitter)などのSNSを活用して、税務情報や事務所の雰囲気を発信することで、潜在顧客との接点を増やすことが可能。
・リスティング広告
◦リスティング広告(GoogleやYahoo!の検索結果に表示される広告)は、特定のキーワード検索時に自社サイトを上位に表示させる。
◦即効性が期待できますが、適切なキーワード選定と予算管理が求められる。
2. コンテンツマーケティング
・ブログやコラムの執筆
◦税務に関する最新情報や有益なアドバイスを定期的に発信することで、専門性をアピールし、顧客からの信頼を得る。
・ 動画コンテンツの制作
◦YouTubeなどのプラットフォームで、税務相談や手続きの解説動画を公開することで、視覚的に情報を伝え、視聴者の理解を深める。
3. 顧客との信頼関係構築
・セミナーや勉強会の開催
◦地域の商工会議所や企業向けの税務セミナーを開催することで、顧客との直接的な信頼関係を構築することができる。
4.コンプライアンスを維持した広告戦略
・チラシやパンフレットの配布
◦ターゲットとなる顧客層に対して、事務所のサービス内容や強みをまとめたチラシを配布することで、認知度を高めることが可能。
このように、近年ではデジタルマーケティングが広告の主流となっています。より効果的な広告を作成するためには、SEO対策などの工夫が欠かせないことも、ご理解いただけたのではないでしょうか。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士向け広告規制 -まとめ
税理士の広告活動には、適切な手法と規制が存在します。広告を通じて顧客を獲得することは可能ですが、税理士法に基づく広告規制を遵守することが大切です。
具体的には、「虚偽や誇大な表現」、「他者の誹謗中傷」、「不適切な特典やランキングを使った広告」などは厳しく禁止されています。
税理士の広告活動における最新動向としては、「デジタルマーケティング」、「コンテンツマーケティング」、そして「顧客との信頼関係構築」が近年のトレンドとして挙げられます。
このように、税理士の広告活動は、合法的で適正な方法を選択することが不可欠です。税理士法に従い、顧客に対して誠実で信頼できる情報を提供することが、最も効果的な広告戦略となります。

城之内 楊
株式会社ミツカル代表取締役社長


















