INDEX
おすすめ記事
-
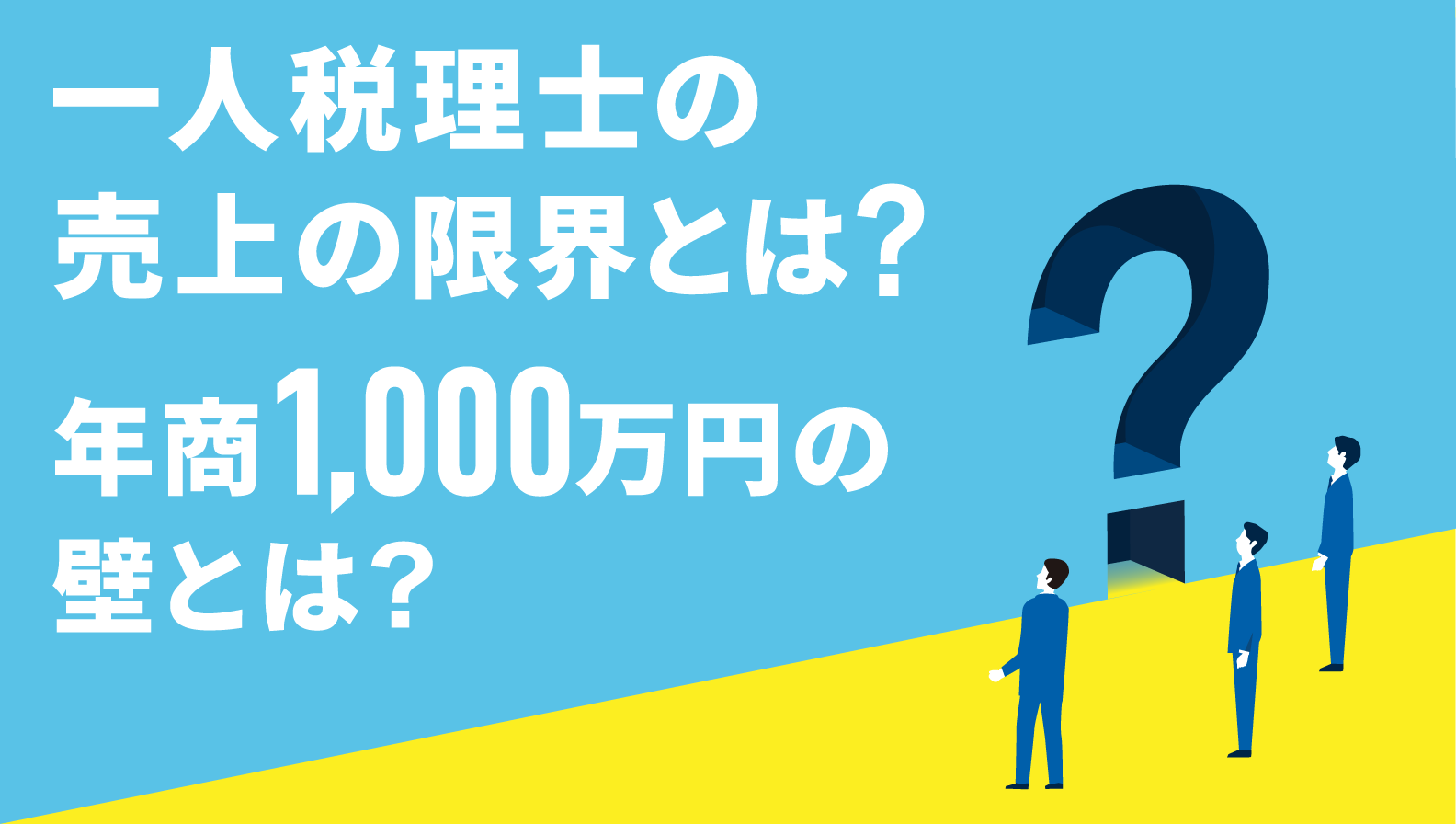
一人税理士の売上の限界とは?年商1,000万円の壁とは?
-
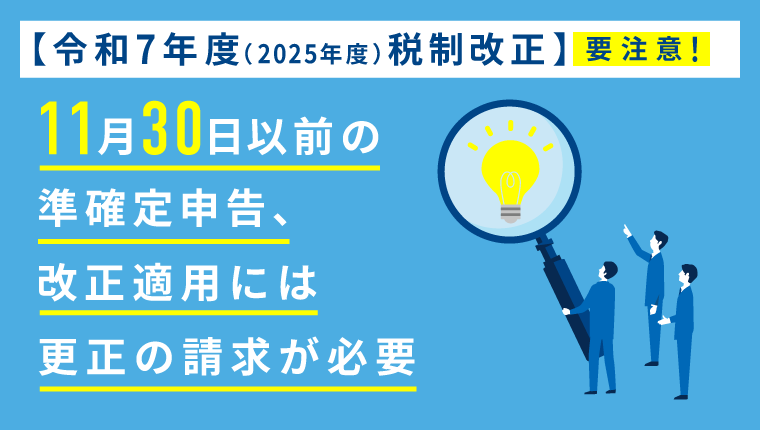
【令和7年度(2025年度)税制改正】要注意!11月30日以前の準確定申告、改正適用には更正の請求が必要
-
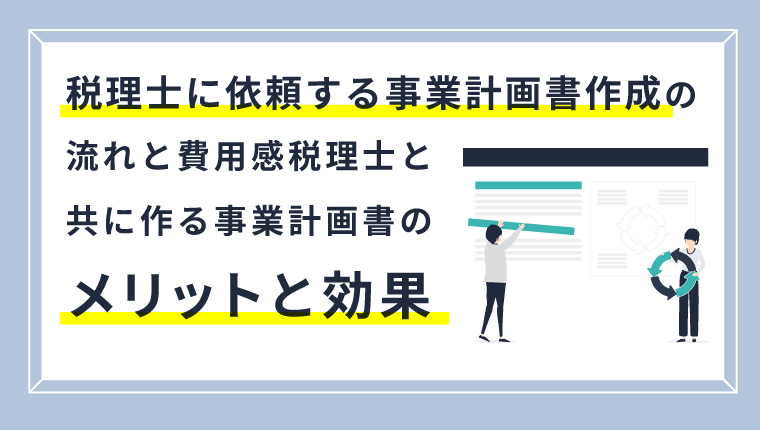
事業計画書の作成は税理士に依頼すべき?税理士に依頼するメリットと費用を解説
-
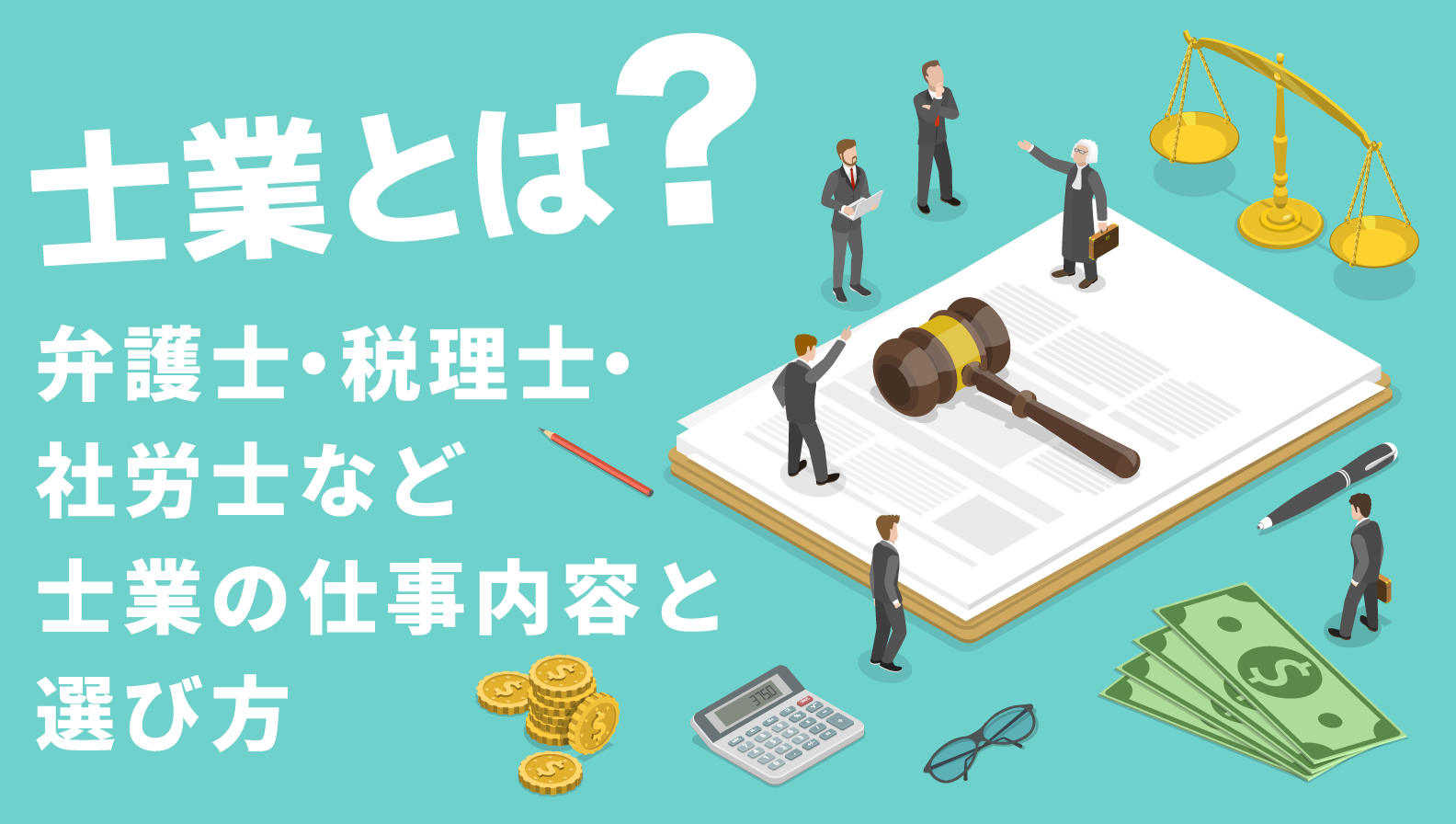
士業とは?弁護士・税理士・社労士など士業の仕事内容と選び方
-

フリーランス税理士になるメリットやデメリットについて解説
公開日:2025/05/16
最終更新日:2025/09/06
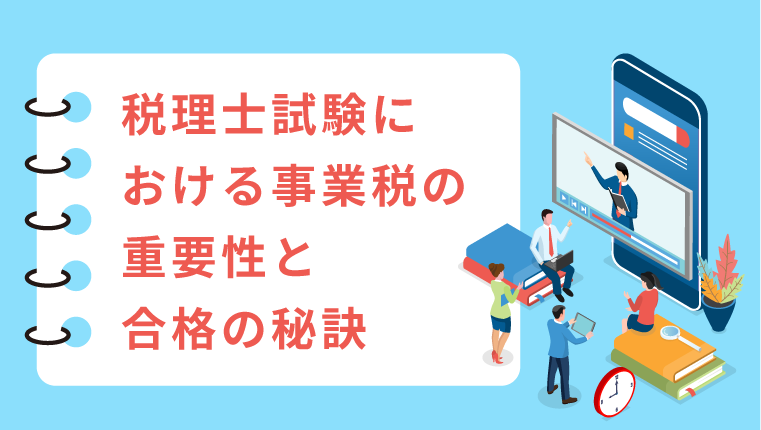
INDEX
税理士試験の科目選びで悩んでいませんか?
実は「合格率が高く、実務にも役立ちやすい」意外な狙い目科目があるんです。
それが、地方税法に基づく《事業税法》。
法人税や所得税とのつながりが強く、理解が深まるうえに点も取りやすい。
しかも出題パターンが超安定。
過去問を制す者が、合格を制す──そんな再現性の高い世界です。
税法科目で効率よく1科目クリアしたい方、
この記事を読めば、きっと「事業税ってアリだな」と思えるはずです。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士試験における事業税とは?
税理士試験の選択科目の一つである「事業税法」は、地方税法に基づいて課される「事業税」に関する専門知識を問う科目です。
事業税には、以下の2つの種類があります。
| 種類 | 対象 | 課税主体 | 主な特徴 |
| 個人事業税 | 個人事業主 | 都道府県 | 所得に基づく課税(事業主控除あり) |
| 法人事業税 | 法人 | 都道府県 | 所得課税+資本金1億円超には外形標準課税も適用 |
この科目では、個人と法人の両方における課税制度の理解、計算、理論的説明能力が問われます。
● 試験科目としての位置づけ
・分類:税理士試験の税法科目(9科目中の選択科目)
・科目群:「ミニ税法」と呼ばれる科目の一つ(他に酒税法、住民税、国税徴収法など)
・受験制限:住民税との選択制(どちらか1科目のみ選択可能)
● 法的根拠と制度設計
・根拠法:地方税法第72条以降
・課税主体:都道府県
・税の目的:
◦地方自治体の財源確保
◦地域での事業活動に対する経済的負担の適正配分
・納税義務者:
◦個人:一定業種の個人事業主
◦法人:日本国内に事業所等を持つ法人
● 課税内容の比較
| 項目 | 個人事業税 | 法人事業税 |
| 課税対象 | 事業所得・不動産所得など | 所得、付加価値、資本など |
| 非課税業種 | 一定の条件に当てはまる人 | なし(ただし業種ごとに税率の違いあり) |
| 主な控除 | 年間290万円の事業主控除 | なし(別途法人税との調整あり) |
| 外形標準課税 | 対象外 | 資本金1億円超の法人に対して適用 |
税理士試験での重要性
● なぜ事業税法は重要なのか?
・地方税の基礎理解に直結:税理士として法人・個人事業者の顧問業務を行ううえで、地方税の申告指導は不可欠。
・所得税法・法人税法との密接な連携:事業税の課税標準はこれらの国税と深く関係しているため、税制の全体像を理解するうえで有効。
・出題傾向が安定し、対策しやすい:過去問を中心に学習すれば、高得点を狙いやすい実践的な科目。
・実務的な重要性:多くの都道府県で地方税の電子申告が進んでおり、事業税の処理能力は現場での即戦力となる。
● 税理士実務とのつながり
| 実務での場面 | 事業税知識の活用例 |
| 法人の決算申告 | 法人事業税の計算と外形標準課税の適用有無の判断 |
| 個人事業主の確定申告支援 | 事業主控除や非課税業種の判定、複数事業の所得配分など |
| 多拠点企業の申告管理 | 分割基準に基づく都道府県ごとの課税の按分計算 |
| 地方自治体との折衝 | 課税誤りや更正処分対応において法令根拠を説明する能力 |
事業税の試験内容と出題傾向
| 項目 | 内容 |
| 科目名 | 地方税法に基づく「事業税法」 |
| 出題形式 | 記述式(大問2問) |
| 試験時間 | 2時間(120分) |
| 配点構成 | 理論問題 50点/計算問題 50点(年による可能性有) |
| 出題分野 | 個人事業税・法人事業税の両方から出題 |
| 合格基準 | 60点以上(相対評価により実際は7〜8割が合格ライン) |
| 試験日程 | 税理士試験3日目の午後(例年:8月上旬) |
出題傾向の全体像
・出題傾向は非常に安定的であり、毎年、基礎的な理論・計算が中心
・応用問題の比率は少なく、定型パターンを押さえた学習が効果的
・毎年、個人・法人両方に関連する問題がバランスよく出題される
・理論問題では「定義」「趣旨」「条文の説明」「制度設計の背景」などが頻出
・計算問題では「課税標準の算定」「税率の適用」「分割計算」などが軸
過去5年の出題傾向一覧
| 年度 | 大問1(理論) | 大問2(計算) |
| 令和5年度 | 法人が複数の事業を行う際の課税標準・税率の理論 | 法人の外形標準課税・分割計算 |
| 令和4年度 | 個人事業税の非課税業種・事業主控除に関する論述 | 個人事業主の年途中廃業に伴う複数県の申告計算 |
| 令和3年度 | 外形標準課税の制度趣旨と構成要素の説明 | 資本金1億円超の法人における3割の計算 |
| 令和2年度 | 分割基準に関する法的根拠と具体的適用例 | 法人事業税の課税標準と税率の組み合わせ計算 |
| 令和元年度 | 外形標準課税導入の背景と構造 | 法人の所得割・資本割・付加価値割の具体的計算 |
傾向:
・外形標準課税は毎年のように計算で問われる鉄板論点
・理論では制度趣旨や条文の構造の説明を問う問題が多い
・実務上の事例をベースに理論を問う「準ケーススタディ型」の出題が増加傾向
頻出テーマまとめ(理論)
| 頻出テーマ | ポイント例 |
| 外形標準課税の構造 | 所得割・付加価値割・資本割の定義と制度趣旨 |
| 課税標準の算定 | 所得ベース・収入ベース・控除項目の考え方 |
| 非課税業種・控除規定 | 医師や助産師の非課税規定、事業主控除の論拠 |
| 分割基準と申告義務 | 法人の複数事業所保有時における申告義務の所在 |
| 法定調書・条例課税 | 都道府県独自条例との関係、法定調書提出義務の所在 |
● 頻出テーマまとめ(計算)
| 項目 | 内容の具体例 |
| 法人事業税課税 | 所得の算出、損金算入制限、所得割の税率適用 |
| 外形標準課税 | 資本割・付加価値割・所得割の計算と控除限度額 |
| 複数事業所・事業種 | 分割基準(従業者数・売上高等)による各県の税額按分計算 |
| 個人事業主の申告計算 | 年間事業主控除、非課税業種の除外、年途中廃業時の対応 |
| 法人の中間申告 | 中間納付税額の計算、仮決算方式と予定申告方式の比較 |
● 理論・計算の出題バランスと評価ポイント
| 観点 | 理論 | 計算 |
| 難易度 | 中〜やや高 | 中程度(パターン暗記で対応可能) |
| 評価基準 | 条文理解・趣旨説明・構成要素の正確性 | 計算過程・根拠の明示・ケアレスミスの有無 |
| 傾向 | 制度の本質理解が重視される | 手順・形式への忠実性が重視される |
| 出題形式 | 記述式(300〜500字程度) | 資料を基にした実務的な税額算定 |
試験範囲(地方税法に基づく)
| 試験範囲分類 | 内容例 |
| 地方税法の基本 | 地方税の分類、課税主体、法令構造 |
| 個人事業税 | 対象業種(法定業種)、所得算定、事業主控除、非課税業種 |
| 法人事業税 | 所得割の課税標準と税率、外形標準課税(資本割・付加価値割)の適用範囲 |
| 分割基準 | 法人の複数県への納税、按分方法(従業員数・売上高・固定資産など) |
| 税率と計算 | 個人・法人それぞれの標準税率、条例税率の扱い |
| 条例課税 | 各都道府県が定める特例税率や非課税措置の取り扱い |
| 特例・免除規定 | 地域産業支援策としての税制優遇、事業転換時の取り扱いなど |
事業税の勉強方法と時間管理
事業税法は、所得税法や法人税法と比較して出題範囲が狭く、出題傾向も安定しているため、パターン学習と過去問演習の相性が非常に良い科目です。 一方で、地方税特有の「外形標準課税」や「分割基準」など、国税にはない論点も多く、初学者にとってはなじみづらい部分もあります。
必要な学習時間の目安
| 受験者タイプ | 必要な学習時間の目安 | 解説 |
| 初学者(税法初挑戦) | 約300~400時間 | 地方税の基本からインプットが必要 |
| 所得税・法人税合格者 | 約150~250時間 | 重複部分が多く、事業税特有論点に集中すれば短縮可能 |
| 科目合格経験者 | 約100~150時間 | 外形標準課税・分割計算など重点攻略で済む |
スケジュール例(6か月前スタート)
| 学習期間 | 内容 | ポイント |
| 6~4か月前 | インプット期 | テキスト・講義で基礎理論と計算構造を把握 |
| 4~2か月前 | アウトプット期 | 過去問演習を開始。理論暗記と計算練習を繰り返す |
| 2か月前~直前 | 実戦演習+弱点補強 | 模擬試験や予想問題を通して時間配分の感覚を養う |
学習の進め方のポイント
✔ 理論学習(暗記+応用)
・条文や制度趣旨を理解したうえで、書けるレベルで暗記する
・頻出テーマ(外形標準課税の構成要素、課税標準、非課税業種など)を優先
・構造化メモ(骨子→展開)で論述訓練する
✔ 計算学習(手を動かす)
・基本的な公式を毎日1回は手書きで練習
・外形標準課税、分割計算、事業主控除のような典型パターンを徹底的に反復
・ミスした問題の「理由メモ」作りが効果的
事業税の難易度と合格率
事業税法は、税理士試験の中でも「中堅レベルの難易度」とされる選択科目です。出題傾向が安定しており、対策が取りやすいことから、比較的短期間での合格が狙える科目とされています。
▷ 合格率の推移(直近5年間)
| 年度 | 合格率 | 備考 |
| 令和5年度 | 16.4% | ミニ税法の中では最も高い水準 |
| 令和4年度 | 15.6% | 例年並み |
| 令和3年度 | 12.6% | 計算問題がやや難化 |
| 令和2年度 | 13.9% | 配点が理論・計算50:50へ完全移行 |
| 令和元年度 | 12.4% | 外形標準課税の出題 |
【分析】
・合格率は概ね12~16%前後で推移
・回答しやすい年度は16%前後まで上昇、難化年でも10%を下回ることは稀
他の科目との比較
| 科目名 | 難易度感 | 学習時間目安 | 出題傾向 | コメント |
| 酒税法 | 易しめ | 約150時間 | 基本論点中心 | 初学者向け、暗記量はやや多め |
| 国税徴収法 | やや易しめ | 約200時間 | 判例や手続き系 | 法律思考が求められ、暗記に偏りがち |
| 事業税法 | 中程度(標準) | 約250時間 | 安定出題 | 計算+理論のバランス型。実務的価値も高い |
| 住民税 | やや難しめ | 約300時間 | 地方税特有が多い | 条例や二重課税調整など論点が細かい |
| 消費税法 | 難しめ | 約400時間 | 応用計算多め | 検算しづらく計算力が問われる |
合格のための戦略とコツ
① 出題パターンを徹底分析せよ
・過去10年の出題傾向を押さえるだけで、7割得点は狙える
・頻出テーマ(外形標準課税、分割基準、所得算定)を繰り返し演習
② 理論は「書ける暗記」重視
・暗記カードや要点整理ノートで「見て覚える」から「書いて覚える」へ
・300~500字の答案を「構造化」して組み立てる練習が重要
③ 計算は「定型化」&「速解き」訓練
・外形標準課税、事業主控除などは手順がほぼ決まっている
・1問あたり30分以内で正確に解ける訓練を積む
④ 理論と計算の配点を意識した時間管理
・本試験は120分=理論55~60分+計算60~65分が目安
| 学習法 | 実践ポイント |
|---|---|
| 毎朝1テーマ暗記 | 理論カードを1日1セット覚える習慣で記憶を定着 |
| 解いた問題のミスノート | 計算ミス・理論の失点原因を「1冊に集約」して復習 |
| 自分で「ミニ模試」 | 過去問を時間内に解き、自作で理論+計算セットを作成 |
| 条文音読 | 地方税法の条文を声に出して読むことで理解力UP |
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
税理士試験における事業税法は、地方税法に基づく個人・法人への課税制度を扱う選択科目です。
出題傾向は非常に安定しており、頻出論点を押さえた学習ができれば、比較的短期間での合格が狙えます。
理論・計算のバランスが求められ、外形標準課税や分割基準など、地方税独特の論点への理解も不可欠です。
学習時間は200〜300時間が目安で、過去問を中心にしたアウトプット重視の勉強が効果的。
合格率は12〜16%前後と比較的高めで、他のミニ税法と比べても実務性・得点再現性ともに高いコストパフォーマンスの良い科目です。
理論は「構造で覚えて書けること」、計算は「パターン化して速く正確に解くこと」がカギ。
時間配分の管理と、暗記・計算両面の強化によって合格が見えてくる科目と言えます。
特に所得税法や法人税法との並行受験者にとっては、知識の相乗効果も期待できる、おすすめの選択科目です。
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















