INDEX
おすすめ記事
-

2025年税理士試験合格発表|合格率は21.6%!
-
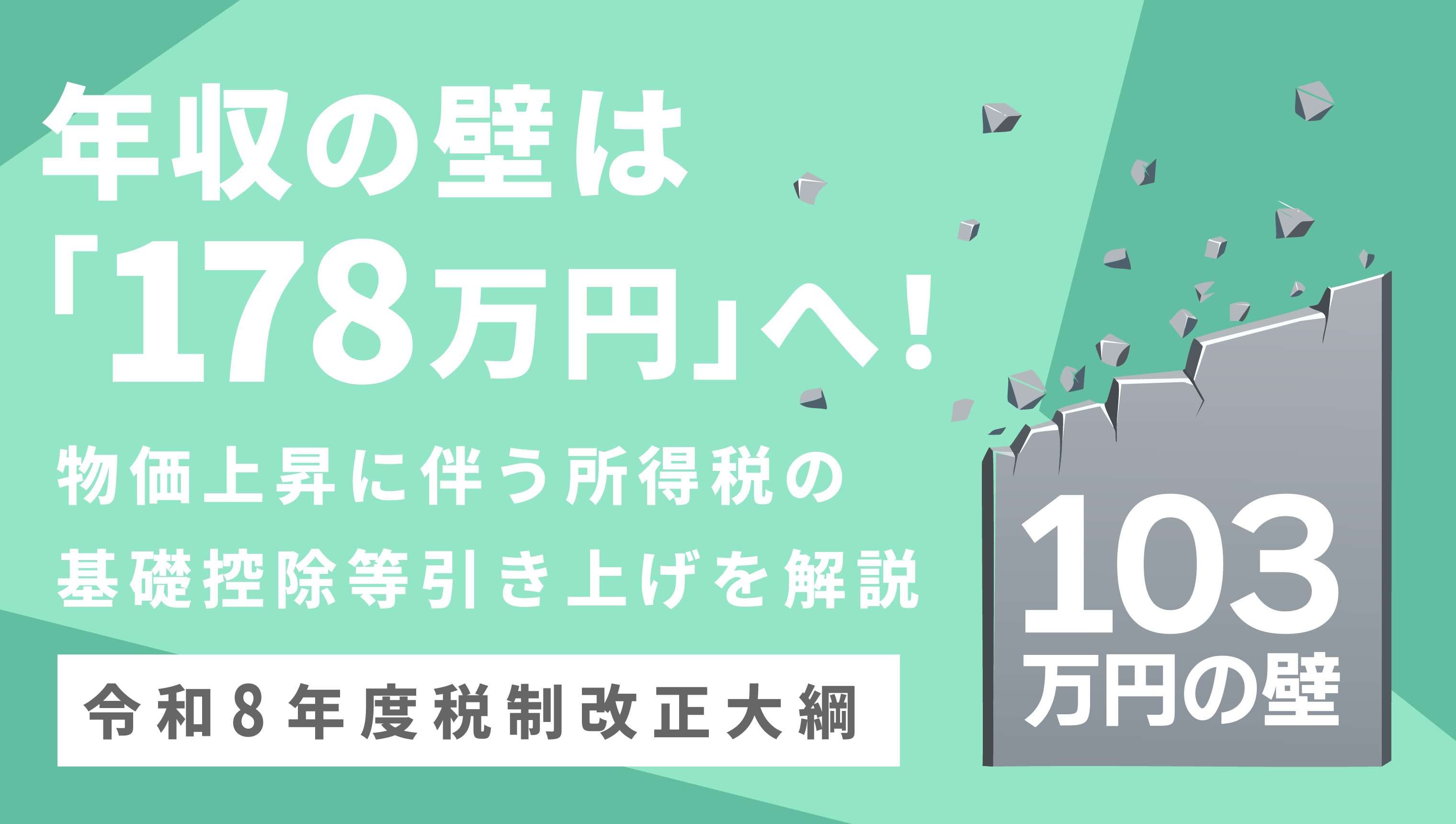
年収の壁は「178万円」へ!物価上昇に伴う所得税の基礎控除等引き上げを解説【令和8年度税制改正大綱】
-

倒産寸前からV字回復!!税理士の事業再生支援【めざせ!TAX MASTER#34】
-
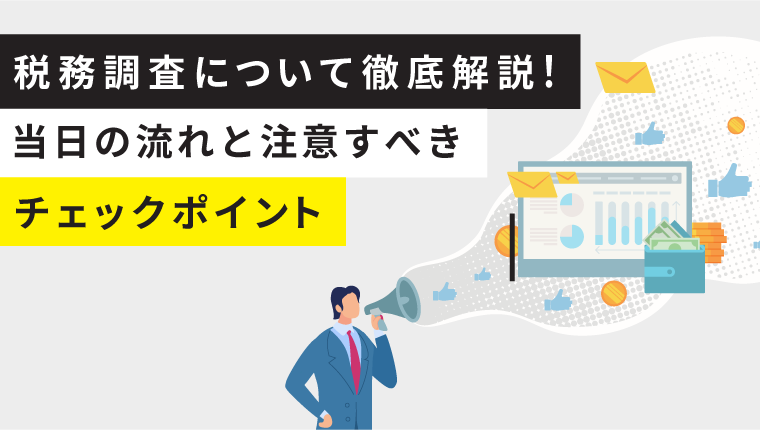
税務調査とは?当日の流れと注意すべきチェックポイントを税理士が徹底解説!
-
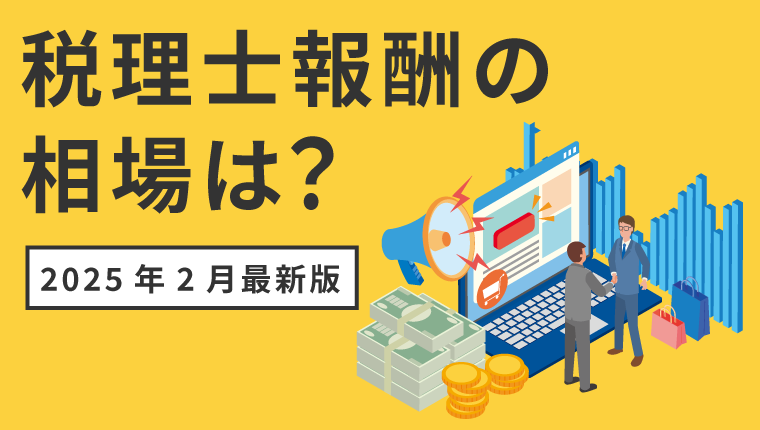
税理士報酬の相場は?2025年最新版
公開日:2025/05/09
最終更新日:2025/09/06
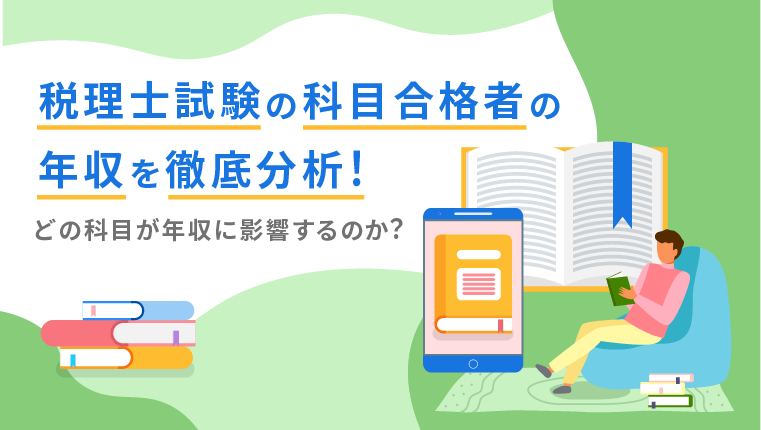
INDEX
「税理士試験に合格していなくても、実務経験を積めばそれなりに稼げるって本当?」
「科目合格者って結局“中途半端”な扱いをされるのでは…」
そんな不安を抱えながら働く受験生や実務者は少なくありません。
しかし、どの科目に合格しているか、どこで働くかによって、年収は大きく変わるのです。
実際、1科目合格するごとに年収が上がるというデータも存在します。
一方で、4科目合格しても年収が頭打ちになってしまうケースもあります。
この記事では、科目合格者のリアルな年収データから、事務所選びのコツ、専門性を活かしたキャリアアップまでを徹底解説します。
「あと一歩」の立場を、“収入アップのチャンス”に変えるヒントがきっと見つかるはずです。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士試験科目合格者の年収とは?
税理士試験の科目合格者(いわゆる「科目合格止まり」の方や、受験継続中の方)の年収については、一般的に「働きながら合格を目指している受験生」や「資格取得前の実務経験者」としての位置づけが強いため、税理士登録者(5科目合格者)と比較すると低い傾向があります。
科目合格が年収に与える影響
税理士試験の科目合格は、年収に明確な影響を与えることが複数の調査から示されています。一般的に、合格科目数が増えるごとに年収が上昇する傾向があります。
合格科目数別の平均年収:
・1科目合格者:平均年収は約420万円
・2科目合格者:平均年収は約446万円
・3科目合格者:平均年収は約480万円
・4科目合格者:平均年収は約495万円
・税理士有資格者(未登録):平均年収は約517万円
・税理士登録済み:平均年収は約683万円
これらのデータから、1科目合格ごとに年収が約15万~30万円増加する傾向が見られます。特に、税理士資格を取得し登録することで、年収が大幅に向上することが示されています。
実際の年収データとその傾向
勤務先の種類によっても年収は異なります。例えば、インハウス(企業内)税理士の平均年収は867万円と、会計事務所勤務の税理士よりも高い傾向があります 。
科目合格者の年収レンジ(目安)
| 勤務形態 | 年収レンジ(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 税理士法人(BIG4除く) | 約300万円~500万円 | 地方や中小事務所は300万台前半が多い |
| BIG4税理士法人 | 約400万円~600万円 | 科目数や業務範囲で変動。残業代含む |
| 一般企業の経理・税務職 | 約350万円~600万円 | 実務経験や企業規模に依存 |
| 派遣・パート勤務 | 時給1,500~2,500円相当 | 扶養内パート・科目勉強と両立しやすい |
科目合格数と年収の関係性
| 科目数 | 年収への影響度 | 備考 |
|---|---|---|
| 1科目合格 | ほぼ影響なし | 実務経験が重要視される |
| 2〜3科目合格 | 微増(+20~50万円程度) | 科目によっては評価が高い(法人税、消費税) |
| 4科目合格 | 高評価の対象 | 「あと一歩」人材として準税理士的に扱われることも |
| 5科目合格 | 一気に年収アップ | 税理士登録可。600万〜1000万円レンジが現実的に |
どの科目が年収に影響を与えるのか?
税理士試験において、どの科目に合格しているかは、年収やキャリアの方向性に大きく影響します。
法人税と所得税の重要性
● 法人税法(税法の中核)
・最も評価が高い税法科目。
・法人クライアントを担当するうえで必要不可欠。
・会計事務所・税理士法人・企業の経理部・コンサルティングファームすべてで重視される。
・法人税法に合格していると、即戦力として見なされやすく、採用・昇給に有利。
年収インパクト:高(400万円台 → 500万円台へ)
● 所得税法(資産税業務や個人富裕層案件で重要)
・不動産オーナーや資産家向けサービスの柱。
・相続税や贈与税と組み合わせて評価される。
・一般企業ではあまり使わないが、資産税系に強い事務所では必須スキルとされる。
年収インパクト:中~高(資産税分野での活躍に直結)
会計科目の評価とその影響
● 簿記論
・実務的な記帳力、決算書作成力のベース。
・若手や未経験者にとっては非常に重要で、採用の入り口。
・ただし、年収インパクトはそこまで大きくはない。
年収インパクト:低~中(400万円前後のラインで足切りを回避)
● 財務諸表論
・会計的な理論面や分析の力が問われる。
・上場企業や経営分析、監査法人出身者には重要視される。
・単独ではインパクトは小さめだが、法人税法とのセットで評価が高くなる。
年収インパクト:中(法人税法と合わせて持つと効果大)
その他の税法
・相続税法:高齢化に伴い需要拡大中。資産税系事務所では重要。地方では特に評価されやすい。
・消費税法:企業向け実務で必須だが、評価は法人税ほど高くない。
・国税徴収法:相続・譲渡・更正の請求対応などに使えるが、評価は控えめ。
年収インパクト:相続税=中、消費税=やや低め、徴収法=低
これらを表にまとめると、価格別の年種の相場観は以下の様になります。
| 合格科目構成 | 想定年収レンジ(目安) |
|---|---|
| 簿記論+財表+法人税法 | 500~550万円 |
| 簿記論+財表+所得税法 | 480~520万円 |
| 簿記論+財表+相続税法 | 470~510万円 |
| 簿記論+財表のみ(税法なし) | 420~450万円 |
| 5科目合格(税理士登録済) | 650~750万円以上 |
税理士事務所での働き方と年収の関係
税理士としてのキャリアを築く上で、どの税理士事務所で働くかは、年収や働き方・成長スピードに大きく影響します。
事務所選びが年収に与える影響
▼ 1. 【小規模事務所】(職員数:~10名程度)
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| クライアント | 地場の中小企業、個人事業主中心 |
| 業務内容 | 記帳代行、申告書作成、年末調整、簡単な税務相談など |
| 働き方 | ルーチン業務が中心。勉強時間の確保がしやすい事務所も多い |
| 年収レンジ | 約300万~400万円(未経験~経験者) |
⚠ デメリット:年収は低めで、昇給幅も小さい。高度税務に触れにくい
▼ 2. 【中堅事務所・税理士法人】(職員数:10〜100名程度)
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| クライアント | 地域の優良中小企業や資産家など |
| 業務内容 | 月次決算、法人税申告、相続、事業承継、MAS業務なども対応 |
| 働き方 | 分業またはチーム制。繁忙期は忙しいが、成長機会も多い |
| 年収レンジ | 約400万〜600万円(経験・科目数により変動) |
⚠ デメリット:事務所によりカルチャーが全く異なり、見極めが重要
▼ 3. 【大手税理士法人(BIG4など)】
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| クライアント | 上場企業・外資系・富裕層など |
| 業務内容 | 国際税務、連結納税、移転価格、組織再編、M&Aなど高度税務 |
| 働き方 | プロジェクト型。残業は多いがリモート制度・福利厚生も充実 |
| 年収レンジ | 約500万~800万円(スタッフ〜シニアスタッフ) |
⚠ デメリット:科目合格者だとプレッシャーが大きく、消耗しやすいことも
表にまとめると以下の様になります。
| 要素 | 影響度 | 内容 |
|---|---|---|
| 事務所の規模 | 高 | 大手ほど給与水準が高く、ボーナス制度も明確 |
| 専門分野の有無 | 中 | 資産税・国際税務などは高単価&高年収につながりやすい |
| クライアント層 | 高 | 上場・富裕層を担当するほど高度税務→高単価→給与反映 |
| 勉強支援制度 | 中 | 科目合格手当・受験休暇の有無で成長スピードに差が出る |
転職時に考慮すべきポイント
税理士業界において転職を考える際は、単に「年収アップ」だけを基準にするのではなく、長期的なキャリア形成と働き方のバランスを踏まえた判断が重要です。以下のような観点を意識することで、自分に合った職場選びがしやすくなります。
① キャリアの方向性が合っているか
まず大切なのは、「自分がどのような税理士を目指すのか」というキャリアの方向性です。たとえば、資産税や相続に特化したいのか、それとも法人税務のプロフェッショナルとして企業経営を支援したいのかによって、選ぶべき事務所は異なります。転職先の事務所が、将来的な専門分野やスキル形成にマッチしているかを確認することが重要です。
② 担当業務の幅と裁量
税理士事務所によっては、補助的な記帳業務にとどまる職場もあれば、顧問先との直接対応やコンサルティング業務にまで関われる職場もあります。成長意欲のある方にとっては、「単純作業の繰り返し」ではなく、「考える税務」に携われるかが非常に大切です。転職前に「担当業務の範囲」や「どこまで任せてもらえるか」をよく確認しておきましょう。
③ 試験勉強との両立環境
まだ科目合格の途中であれば、試験勉強との両立が可能かどうかも重要なポイントです。具体的には、「受験休暇制度があるか」「繁忙期の残業量」「残業代がしっかり支給されるか」などを確認しましょう。特に中小事務所では、制度が整っていないケースも多いため、実際の働き方と試験支援体制の有無は面接で率直に聞くべきポイントです。
④ 評価・昇給の仕組み
長期的に働くことを考えるなら、「評価基準が明確であるか」「成果やスキルに応じた昇給・昇格があるか」も重要です。例えば、「年功序列で役職が決まる」のか、「実績に応じて若手にもチャンスがある」のかで、成長スピードに差が出ます。将来の年収や責任あるポジションを狙うなら、成果主義に近い職場の方が有利です。
⑤ 事務所の文化・人間関係
給与や業務内容がよくても、職場の雰囲気や人間関係が合わなければ長続きしません。特に税理士事務所は少人数組織が多く、上司や同僚との距離が近いため、所長の人柄や社風が自分に合っているかは非常に大切です。可能であれば、内定前に見学をしたり、面談時に現場の雰囲気を感じ取ったりする工夫も有効です。
⑥ 将来性や安定性
最後に、転職先の事務所が中長期的に成長していけるかもチェックしておきましょう。顧問先の業種・規模のバランス、クラウド会計やIT化への対応度、若手の活躍の余地があるかなどを見れば、将来の成長余地や安定性のヒントになります。
| 項目 | 質問例 |
|---|---|
| キャリアの方向性 | 「将来、資産税に特化したいか?企業税務で活躍したいか?」 |
| 業務の幅 | 「補助業務だけでなく、顧問先とのやりとりも担当できるか?」 |
| 勉強支援の有無 | 「試験休暇や受験補助制度はあるか?残業は多いか?」 |
| 評価制度 | 「昇給・昇格は年功序列か?成果主義か?」 |
| 人間関係・風土 | 「所長の価値観と合うか?職場の雰囲気はどうか?」 |
| 将来性 | 「分野特化しているか?顧問先の年商は安定しているか?」 |
科目合格者のキャリアパスと年収の向上
税理士試験の科目合格者は、資格の「途中段階」でありながらも、実務経験と戦略的なキャリア選択によって、着実に年収を上げていくことが可能です。資格取得を目指しながら、どのように自身の専門性を深め、活躍の場を広げていくかが重要なポイントとなります。
専門性を活かした職場でのキャリアアップ
税務業務は非常に幅広く、すべてを満遍なく極めるのは難しいため、得意分野・関心分野を明確にし、専門性を磨くことが年収向上のカギになります。
たとえば、
・法人税法を得意とするなら、企業顧問や中堅〜上場企業を支援する事務所へ
・資産税や相続税に関心があるなら、相続特化型事務所や高齢者向け資産管理業務の多い事務所へ
・国際税務に挑戦したいなら、BIG4や外資系クライアントを抱えるグローバル系法人へ
このように、科目の組み合わせ+実務経験を活かして、「専門領域を軸にした事務所選び・職場移動」を行うことで、自然と単価の高い業務を担当するようになり、年収も上昇していきます。
また、専門性の強い職場では、若いうちから責任あるポジションを任されるケースも多く、スピード感のある昇給・昇格が期待できるのも魅力です。
人脈とネットワークの活用
税理士業界では、「紹介」「共同案件」「独立支援」など、人脈によってチャンスが広がる場面が非常に多いです。とくに科目合格者は、「受験仲間」や「実務家仲間」とのつながりが、その後のキャリアにおいて大きな武器になります。
具体的には、
・勉強会・セミナー・税理士会支部のイベントに参加
・Twitter・note・Xなどで実務の発信を通じて人脈形成
・元職場の上司や先輩との関係維持(転職紹介や共同プロジェクトの可能性)
人とのつながりを丁寧に築くことで、
・年収の高い事務所を紹介してもらえる
・キャリアの節目で相談できる存在がいる
・将来的な独立や法人化時に、仕事や人材を呼び込める
といったメリットがあります。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
この記事では税理士試験科目合格者の年収について解説しました。
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















