INDEX
おすすめ記事
-
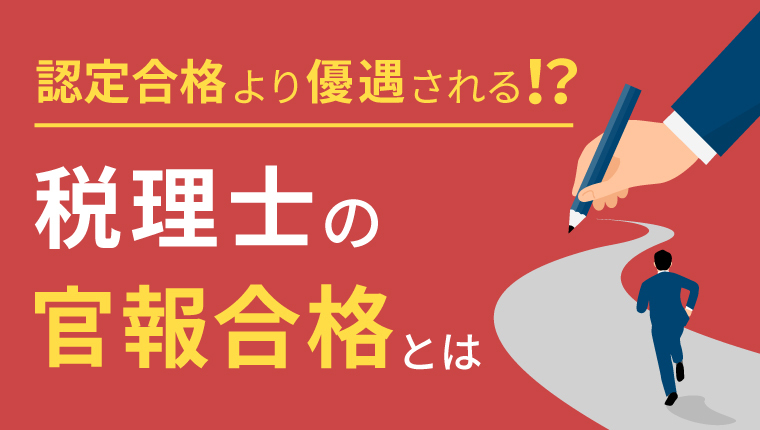
税理士の官報合格とは?認定合格より優遇される?
-

【2025年最新】路線価4年連続上昇の背景と相続税への影響を現役税理士が徹底解説
-
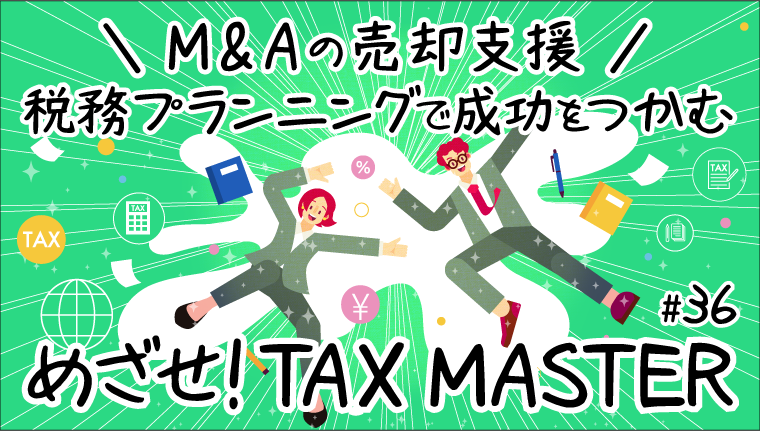
【M&Aの売却支援】税務プランニングで成功をつかむ【めざせ!TAX MASTER#36】
-

国税専門官からの転職|業界別おすすめ職種と必要スキル
-

税理士法人とは?業界の現状と将来性について考える
公開日:2025/05/09
最終更新日:2025/09/06
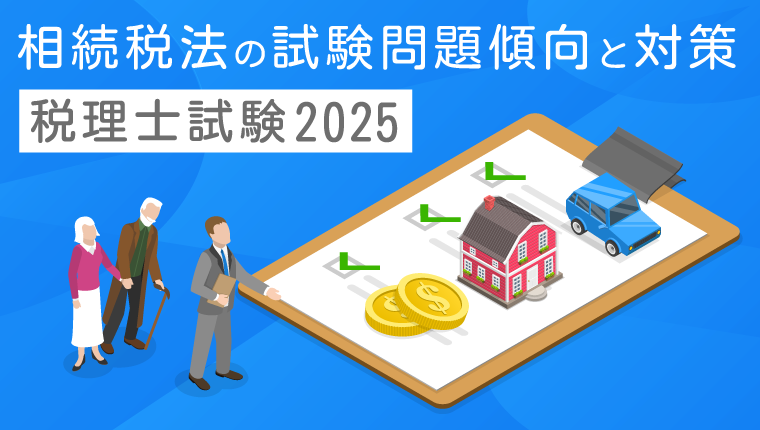
INDEX
税理士試験の中でも“重厚かつ実務直結”といわれる相続税法。
その難易度と重要性ゆえに、多くの受験生が敬遠しがちなこの科目。
しかし、合格すれば資産税分野での大きな武器になること間違いなし。
相続・贈与に関する知識は、高齢化社会においてますますニーズが拡大中。
相続税法は「理論」と「計算」のバランスが難しく、時間配分もカギ。
近年の出題傾向を押さえた対策が、合否を分ける重要なポイントです。
この記事では、相続税法の試験全体像から実践的な対策法までを徹底解説。
相続税法の壁を乗り越え、合格を掴むためのヒントが詰まっています。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
相続税法の試験概要と重要性
相続税法は、税理士試験の税法科目の一つで、主に相続、贈与、財産移転に関する税務を扱います。相続税や贈与税の仕組み、評価、課税方法など、個人財産の承継に関わる重要な理論・計算知識が問われる科目です。
実務でも頻出する分野であるため、試験の難易度は高めですが、税理士として不可欠な知識を身につけられる科目でもあります。
| 項目 | 内容 |
| 試験区分 | 税理士試験の任意選択科目の1つ(税法科目) |
| 試験形式 | 記述式(理論と計算の2部構成) |
| 試験時間 | 2時間 |
| 合格基準 | 満点の60%以上(年により相対的な調整あり) |
| 出題範囲 | 相続税法・贈与税法・財産評価基本通達など |
試験の目的と役割
試験の目的と役割は以下の通りです。
| 観点 | 内容 |
| 試験の目的 | 相続・贈与に関する税務の理解と計算・理論の実践力を測る |
| 税理士試験における位置づけ | 国税三法(所得税法・法人税法・相続税法)の一角で、応用的な税法として位置づけられる |
| 実務における役割 | 相続対策、財産評価、申告書作成、税務調査対応などに必須の知識を身につける |
相続税法の基本的な考え方
基本的な考え方は以下の通りです。
| 考え方 | 内容 |
| 課税の基本単位 | 被相続人の財産に対して、法定相続人ごとに課税する「個人単位課税」 |
| 基礎控除 | 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」により、一定額までは非課税 |
| 累進課税 | 課税価格に応じて10%〜55%の税率が適用される |
| 財産評価 | 「相続税評価額」に基づく(時価ではなく、定められた評価方式を使用) |
| 贈与との関係 | 相続開始前3年以内の贈与財産は加算対象となるため、贈与税との比較・使い分けが重要 |
試験問題の傾向と対策
過去問題の分析と傾向
相続税法では、単なる暗記ではなく、法律と通達を踏まえた論理的思考力が求められます。特に理論問題では、条文の趣旨を正確に理解し、自分の言葉でまとめて説明できる力が重要です。計算問題では、財産の評価や債務控除の適用など、細かいルールに注意しながら正確に計算を行う能力が問われます。
また、相続や贈与の場面は多様なケースが想定されるため、柔軟な対応力も重視されます。
・理論暗記だけでなく「なぜそうなるか」まで理解する
・財産評価基本通達を正確に押さえる
・過去問を徹底的に分析し、出題パターンに慣れる
・計算問題では、基礎パターンを確実にマスターする
・時間配分を意識し、理論・計算両方にバランス良く取り組む
| 区分 | 特徴 | 対策 |
| 理論問題 | ・毎年2~3問構成 ・1題はボリュームが多く「総合問題」 ・条文を踏まえた記述力が問われる |
・頻出論点(財産の評価・課税価格の計算・納税義務者の範囲)を暗記+自分の言葉で書けるように練習 ・条文のキーワードは正確に押さえる |
| 計算問題 | ・大問1問+小問1問 ※小問は出る年と出ない年がある ・相続税+贈与税を含むことが多い ・土地・株式などの財産評価が複雑 |
・財産評価通達の理解がカギ ・基礎→応用→総合のステップで演習を積む ・計算順序や手順のミスを減らすためのフォーマット化 |
重要な理論と計算問題の対策
| 年度 | 理論問題の傾向 | 計算問題のポイント |
| 令和5年 | 1問目:納税義務者の範囲 2問目:相続時精算課税制度の適用除外 |
土地の評価、小規模宅地等の特例、贈与加算の計算が複合出題 |
| 令和4年 | 財産評価の原則・例外、配偶者控除 | 非上場株式評価+相続税+贈与税の総合問題 |
| 令和3年 | 相続税の課税価格の意義と課税の仕組み | 借地権評価、小規模宅地等の要件チェック |
| 令和2年 | 負担付贈与・包括遺贈の取扱い | 特定同族会社の株式+土地評価の難問 |
| 令和元年 | 物納制度・延納制度の違い | 評価明細・基礎控除後の各人負担税額計算 |
傾向からの示唆:
・理論は制度趣旨と規定の根拠を問うものが多く、丸暗記では不十分
・計算は財産評価×税額計算の複合問題が定番。特に土地評価は頻出
合格率と難易度の分析
相続税法は、税理士試験の選択科目の中でも特に実務での需要が高く、人気のある科目です。その一方で、理論と計算の両面で高度な理解と応用力が求められるため、難易度は高めとされています。
過去の合格率の推移
相続税法の合格率は年度によって変動がありますが、概ね10%台で推移しています。特に2024年度(令和6年)は、近年では最も高い合格率となりました。
・2024年(令和6年):18.7%(過去最高水準)
・2023年(令和5年):11.6%
・2022年(令和4年):14.2%
・2021年(令和3年):12.8%
・2020年(令和2年):10.6%
試験の難易度
・理論問題:条文や通達の正確な理解と記述力が必要。
・計算問題:財産評価や課税価格の計算など、複雑な事例に対応する力が求められる。
・学習時間の目安:約400時間(個人差あり) 。
・競争試験の性格:実質的には受験者の上位10~15%が合格する相対評価の試験 。
| 項目 | 難易度 | 理由・背景 |
| 理論問題 | 高 | 暗記+論理的記述力が求められる。毎年“ひねり”や応用があるため、丸暗記では対応困難。 |
| 計算問題 | 非常に高 | 財産評価が複雑。土地・非上場株式の評価+特例適用がセットで出題されることが多く、実務水準の処理が要求される。 |
| 出題傾向の変化 | 中~高 | 特例・通達など“細かい制度の適用要件”を丁寧に押さえていないと解けない設問が増えている。 |
時間配分
| セクション | 推奨時間 | 理由 |
| 計算問題(1問) | 60〜70分 | 問題ボリュームが大きく、土地評価などで時間がかかる。 |
| 理論問題(2問) | 40〜50分 | 1問あたり20〜25分が目安。書きながら思考を整理できるように練習必須。 |
| 見直し・予備 | 5〜10分 | 計算のケアレスミスチェック、理論の言い回し調整のための時間 |
効果的な学習法と時間管理
税理士試験・相続税法において合格を目指すには、理論と計算のバランスを保ちながら、時間を効率的に使った学習法がカギとなります。以下に、効果的な学習法と時間管理のポイントを整理します。
1. 学習戦略の全体像
| 項目 | 内容 |
| 学習期間 | 最低1年間(900〜1200時間程度) |
| 学習配分 | 理論:計算=6:4(初期) → 5:5(直前期) |
| 使用教材 | TACや大原の答練・理論マスター、過去問集、白書的まとめノート |
2. 理論と計算のバランスの取り方
| 時期 | 理論中心 or 計算中心 | ポイント |
| 4月〜8月(基礎期) | 理論重視(6:4) | 理論暗記の土台を固める。毎週の理論暗記+定期的なアウトプット。 |
| 9月〜12月(応用期) | バランス(5:5) | 応用答練に対応できるよう計算力強化+理論の理解深化 |
| 1月〜3月(完成期) | 若干計算寄り(4:6) | 過去問や模試で実戦力をつける。理論は「書けるか」重視。 |
| 4月〜7月(直前期) | 完全実戦型(5:5) | 模試中心。理論一問一答→論述、計算スピードUPを意識。 |
3. 時間を効率的に使う学習法
✅ 学習のフレームワーク
| フェーズ | 学習内容 | 時間管理のコツ |
| インプット | 理論読み込み、計算問題の型を覚える | 朝の時間を活用(頭が冴えているときに理論) |
| アウトプット | 理論の書き・口述練習、計算演習 | 夜に演習(再現練習で記憶定着) |
| 復習 | ミスノート、理論チェック、答練復習 | 週末に1週間の学習をまとめて振り返る |
✅ 学習ルーティン例
| 時間帯 | 内容 |
| 朝(6:00〜7:30) | 理論暗記(1単元+口述練習) |
| 昼休み(12:30〜13:00) | 理論一問一答 or 理論見直し |
| 夜(20:00〜22:00) | 計算演習+間違え直し |
| 土日(計8時間) | 模試や答練、苦手論点の潰し込み、理論暗記の再確認 |
4. 学習効率を高めるTips
・ 「理論は覚えてからがスタート」
→ 書いても出ない理論は意味がない。書ける・話せるようにアウトプット中心に。
・ 「計算はパターンの暗記と処理スピード」
→ 計算ミスは理解不足より反復不足。解き直しノート必須。
・ 「優先順位をつける」
→ 出題頻度の高い理論から潰す(民法、財産評価、贈与関連など)
・ 「模試・答練を“本番”として活用」
→ 毎回本試験のつもりで受けることで時間配分と集中力が鍛えられる。
理論の暗記のためのコツ
相続税法の理論問題は、単なる丸暗記では対応できません。
条文の意味や背景を理解したうえで、「自分の言葉で再現できる」状態に仕上げることが必要です。
覚え方を工夫すれば、量が多くても効率的にマスターすることができます。
理論暗記の基本方針
まずは「丸覚え」しようとする前に、理論の構造や流れを把握しましょう。
条文ごとの「目的」「対象」「効果(結論)」を意識すると、記憶の引っかかりができて、思い出しやすくなります。
また、短期間に何度も繰り返して触れることで、記憶を脳に定着させることができます。
忘れて当たり前、を前提に、復習サイクルを組み込むのが合格への近道です。
理論暗記のコツ(箇条書き)
① まずは「意味」を理解する
◦何を言いたい条文なのか、ざっくり理解してから覚える。
② 重要ワードに注目する
◦「財産の所在」「取得者」「課税価格」などキーワードを意識して記憶。
③ フレームで整理する
◦「定義→課税対象→課税方法→特例」のように理論の型をつかむ。
④ 音読して覚える
◦声に出すことで、視覚・聴覚両方を使って記憶に残す。
⑤ 短時間で繰り返す
◦1回1回の暗記に完璧を求めず、回数重視。翌日・3日後・1週間後に復習する。
⑥ 自分の言葉でまとめ直す
◦一度、自分の表現で書き直すと理解が深まる。
⑦ 模範解答を丸写しする練習をする
◦手を動かしながら覚えると、細かい表現や語尾まで正確に入る。
⑧ 理論マスター表を作る
◦覚えた・忘れたを一覧表にして、進捗管理する。
⑨ 寝る前の「1分間復習」
◦理論タイトルだけでもいいので、毎晩ざっと頭に浮かべる。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
この記事では相続税法の勉強法について書かせていただきました。
この記事がお役に立てば幸いです。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















