INDEX
おすすめ記事
-
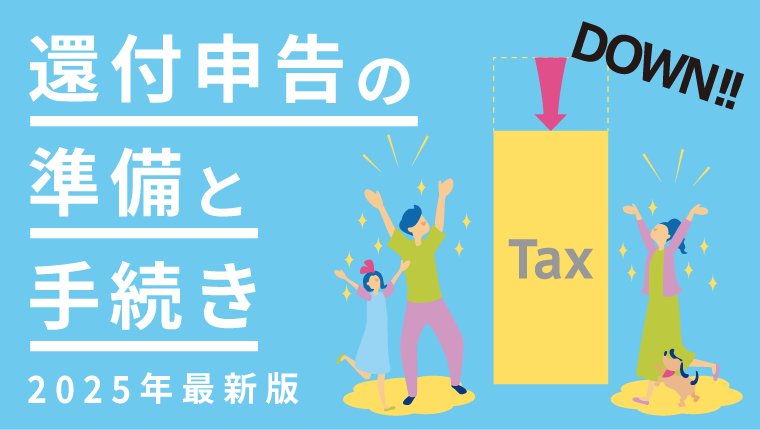
還付申告の準備と手続き【2025年最新版】
-

税理士への不満ランキングTOP5|気を付けるべきポイントと改善策
-

税理士試験の国税徴収法:合格への最短ルート【令和7年(2025年)最新版】
-
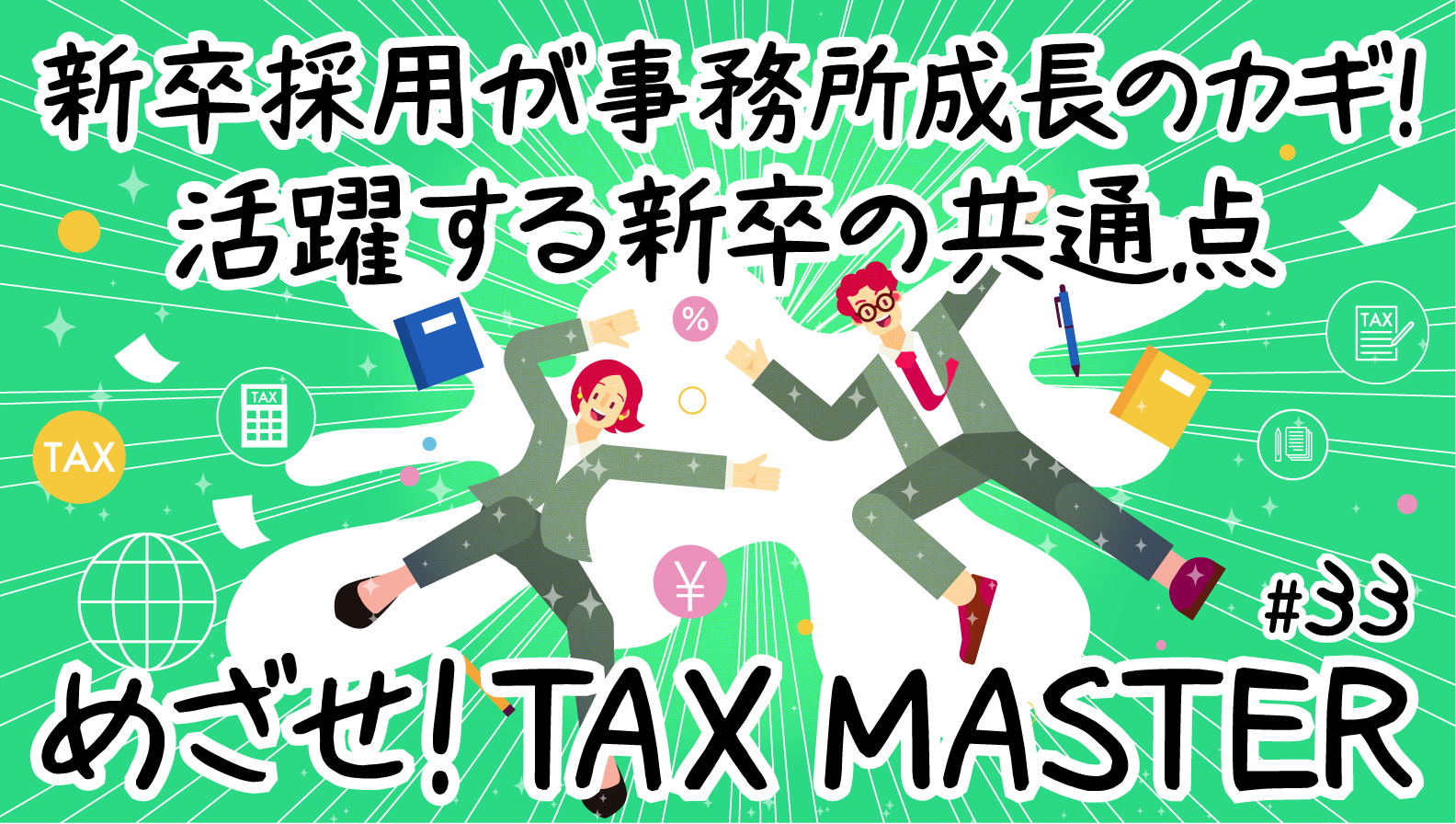
新卒採用が事務所成長のカギ!活躍する新卒の共通点【めざせ!TAX MASTER#33】
-
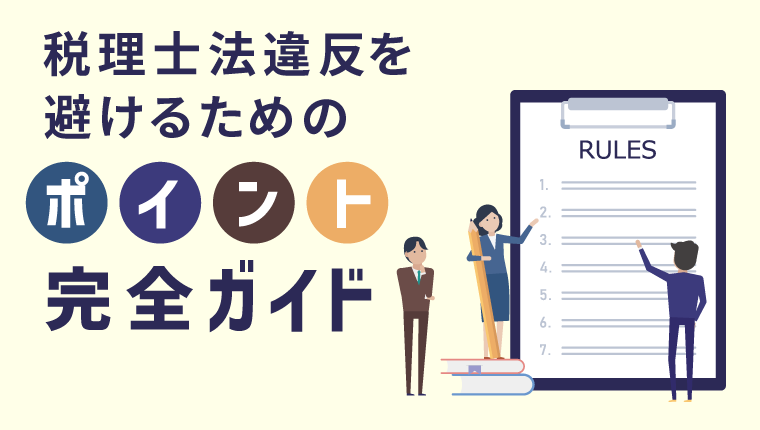
税理士法違反を避けるためのポイント|完全ガイド
公開日:2025/09/28
最終更新日:2025/09/28
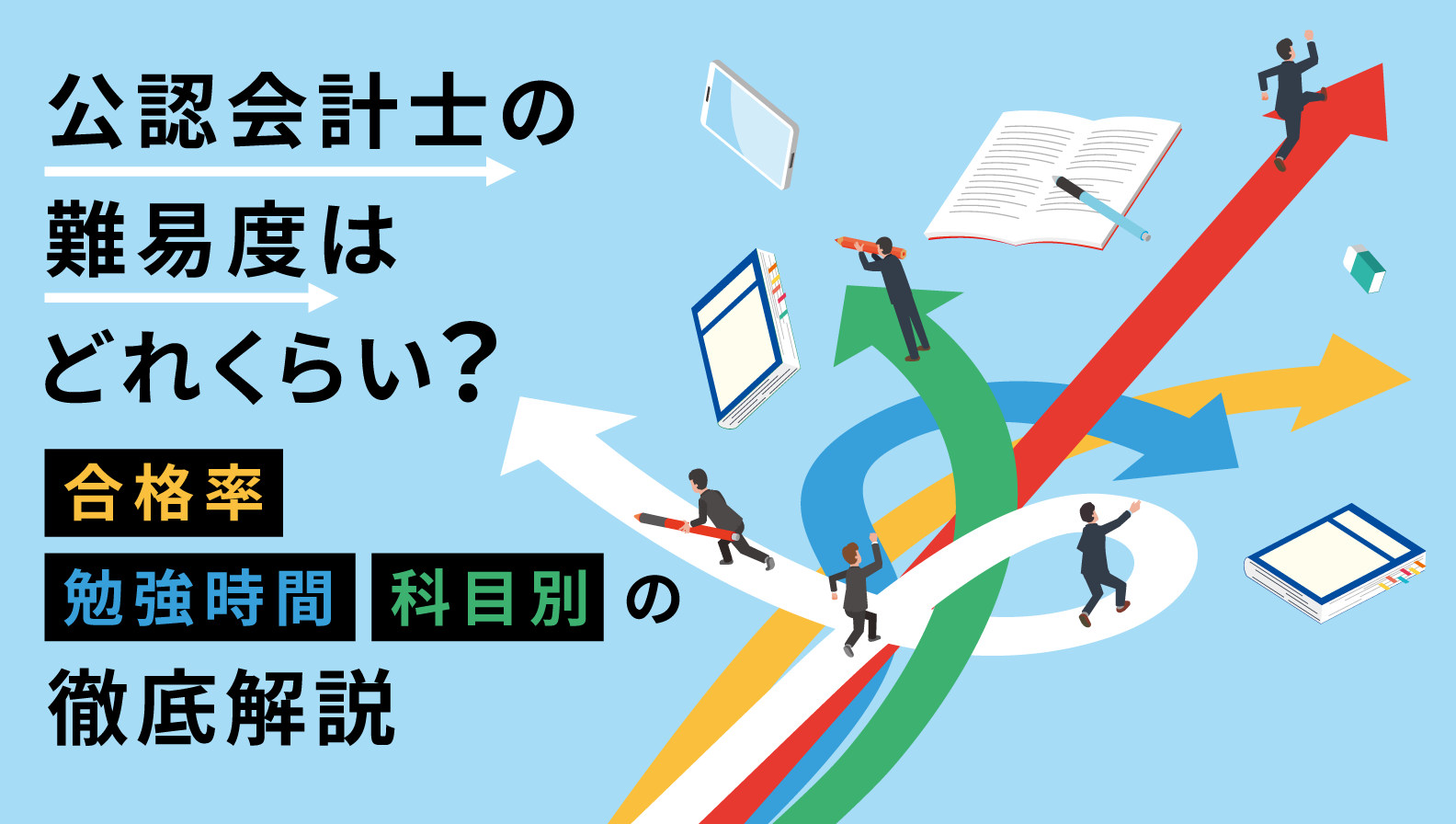
INDEX
「公認会計士って難しい資格って聞くけど、実際どのくらい大変なの?」──会計や金融に関心を持つ方なら、一度は気になったことがあるのではないでしょうか。
本記事では、公認会計士試験の合格率・必要な勉強時間・科目ごとの難易度をデータと経験談を交えて徹底解説します。税理士や司法試験など他資格との比較も紹介し、「本当に自分が目指せるのか」を判断する材料になるはずです。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
公認会計士とは?難易度を語る前に知っておくべき基礎
公認会計士は、企業の財務書類の監査や経営コンサルティングを担う、会計分野の最高峰資格です。日本三大国家資格(弁護士・医師・公認会計士)の一つとされ、社会的信用度は極めて高いもの。
その分、試験のハードルも高く、「誰でも取れる資格ではない」と言われます。ただし、正しい戦略と努力を積み重ねれば合格は十分可能です。
公認会計士試験の合格率
全体の合格率
近年の公認会計士試験のトータル合格率は以下の通りです。
| 年度 | 出願者数 | 合格者数 | 合格率 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年(令和3年) | 14,192人 | 1,360人 | 9.6% | 比較的高い合格率 |
| 2022年(令和4年) | 18,789人 | 1,456人 | 7.7% | 合格率低下開始 |
| 2023年(令和5年) | 20,317人 | 1,544人 | 7.6% | 受験者数増加 |
| 2024年(令和6年) | 21,573人 | 1,603人 | 7.4% | 過去10年最低 |
2024年の合格率7.4%は過去10年間で最低水準となっており、試験の競争激化が見て取れます。この数値は偏差値74に相当し、東京大学合格レベルの学力が求められることを示しています。
段階別合格率の詳細
| 項目 | 短答式試験 | 論文式試験 |
|---|---|---|
| 実施回数 | 年2回(12月・5月) | 年1回(8月) |
| 出題形式 | マークシート方式 | 記述式 |
| 試験科目数 | 4科目 | 5科目 |
| 合格率(2024年) | 12.0% | 36.8% |
| 受験者数(2024年) | 19,564人 | 4,354人 |
| 合格者数(2024年) | 2,345人 | 1,603人 |
論文式試験の合格率は短答式より高いものの、短答式を突破した精鋭のみが受験するため、実質的な難易度は極めて高いといえます。
税理士・司法試験との比較
・税理士試験:1科目ごとの合格率は10〜15%程度。ただし全5科目を揃えるのに平均7〜8年かかる。
・司法試験:合格率は30〜40%だが、受験資格(法科大学院修了など)のハードルが高い。
・公認会計士試験:合格率は低いが、一発合格も可能。20代前半で資格を得られるケースも珍しくない。
| 資格名 | 合格率 | 勉強時間目安 | 偏差値目安 | 位置づけ |
|---|---|---|---|---|
| 公認会計士 | 7.4% | 3,000時間 | 74 | 国家三大資格 |
| 司法試験 | 45%※ | 3,000-8,000時間 | 77 | 国家三大資格 |
| 税理士 | 15-20% | 2,500時間 | 65 | 隣接資格 |
| 不動産鑑定士 | 15% | 2,000時間 | 65 | 国家三大資格 |
| 中小企業診断士 | 4-7% | 1,000時間 | 62 | 経営系資格 |
※司法試験の合格率は予備試験合格者が対象のため高く表示
勉強時間の目安は5,000時間!?
公認会計士試験の最大の難関は「膨大な勉強量」です。
公認会計士試験合格に必要な勉強時間は、2,500~3,500時間が一般的な目安とされています。最短合格を目指す場合でも最低2,500時間、独学の場合は4,000~5,000時間必要になることもあります。
1日5時間勉強した場合、約500日(1年4ヶ月)の学習期間が必要になり、多くの受験生が1.5~2年間の受験期間を設定しています。
科目別勉強時間の詳細
短答式試験(合計:約1,500時間)
・財務会計論: 600時間
・管理会計論: 300時間
・監査論: 200時間
・企業法: 400時間
論文式試験(合計:約1,700時間)
・会計学(財務会計論): 700時間
・会計学(管理会計論): 500時間
・監査論: 300時間
・企業法: 400時間
・租税法: 500時間
・選択科目: 200~300時間
科目別の難易度
公認会計士試験は「短答式(マークシート)」と「論文式(記述)」で構成され、主要科目は以下の通りです。
短答式試験
| 科目 | 勉強時間 | 配点 | 難易度 | 特徴 |
| 財務会計論 | 600時間 | 200点 | ★★★★★ | 最重要・計算+理論 |
| 管理会計論 | 300時間 | 100点 | ★★★★☆ | 数学的要素強い |
| 監査論 | 200時間 | 100点 | ★★★☆☆ | 暗記中心 |
| 企業法 | 400時間 | 100点 | ★★★★☆ | 条文理解重要 |
| 合計 | 1,500時間 | 500点 | - | - |
論文式試験
| 科目 | 勉強時間 | 難易度 | 攻略ポイント |
| 会計学(財務会計) | 700時間 | ★★★★★ | 計算スピードと正確性 |
| 会計学(管理会計) | 500時間 | ★★★★☆ | 理論背景の理解 |
| 監査論 | 300時間 | ★★★☆☆ | 実務的思考力 |
| 企業法 | 400時間 | ★★★★☆ | 判例と条文の適用 |
| 租税法 | 500時間 | ★★★★☆ | 計算問題中心 |
| 選択科目 | 200-300時間 | ★★★☆☆ | 科目選択が重要 |
| 合計 | 2,600-2,700時間 | - | - |
各科目の詳細については以下の通りです。
財務会計論(最重要科目)
難易度: ★★★★★(最高レベル)
配点比重: 短答式200点/500点、論文式で最も配点が高い
財務会計論は公認会計士試験の根幹をなす科目で、簿記2級レベルから上級レベルまでの幅広い知識が求められます。計算問題と理論問題の両方に対応する必要があり、最も時間をかけて学習すべき科目です。
攻略ポイント:
・簿記の基礎から着実に積み上げる
・理論と計算のバランスを重視
・過去問演習を重点的に行う
管理会計論
難易度: ★★★★☆
特徴: 数学的要素が強い科目
原価計算、予算管理、業績評価など、企業の経営管理に関する会計知識を問われます。理系出身者が比較的得意とする科目ですが、文系出身者も適切な学習により十分対応可能です。
攻略ポイント:
・基本的な計算パターンの習得
・理論背景の理解
・問題演習による応用力向上
監査論
難易度: ★★★☆☆
特徴: 暗記中心だが論理的思考も必要
監査の基本概念、監査手続き、監査報告書等について学習します。比較的勉強時間が短くて済む科目ですが、実務経験がない受験生には理解が困難な部分もあります。
攻略ポイント:
・監査の流れを体系的に理解
・重要論点の暗記
・事例問題への慣れ
企業法
難易度: ★★★★☆
特徴: 条文理解と判例知識が重要
会社法を中心とした法律科目で、条文の正確な理解と適用能力が求められます。暗記要素が多いものの、論理的思考力も必要な科目です。
攻略ポイント:
・条文の正確な暗記
・判例の理解
・事例への適用練習
租税法(論文式のみ)
難易度: ★★★★☆
特徴: 計算問題が中心
法人税法と消費税法を中心とした税法の知識が問われます。計算問題の比重が高く、正確性とスピードが要求されます。
選択科目
経営学: 最も選択者が多く、勉強時間が比較的短い(200~300時間)
経済学: 理論的で数学的要素が強い
民法: 法学部出身者に有利
統計学: 理系出身者に適している
難易度を左右する要因
単に合格率が低いだけではなく、以下の要因が「難易度」を引き上げています。
1. 試験範囲の広さ
公認会計士試験は会計、監査、法律、税務と多岐にわたる分野を網羅する必要があり、その範囲の広さが難易度を押し上げています。
2. 競争の激化
受験者数の増加に対し合格者数は一定に抑制されているため、年々競争が激化しています。特に2024年は過去最低の合格率となりました。
3. 実務との乖離
多くの受験生が学生であり、実務経験がないため監査論や企業法などの理解に苦労します。
4. 継続的な学習の必要性
膨大な学習範囲を維持するため、継続的な復習が不可欠です。約60~70%の受験生がリタイアするという統計もあります。
難易度を乗り越えるための勉強戦略
1. 専門学校の活用
独学での合格は極めて困難なため、TACやCPA会計学院などの専門学校を利用することを強く推奨します。
2. 科目の優先順位設定
財務会計論を最重要科目として位置づけ、他科目とのバランスを考慮した学習計画を立てましょう。
3. アウトプット重視の学習
知識のインプットだけでなく、問題演習を通じたアウトプット練習を重視しましょう。
4. 短答式と論文式の違いを理解
マークシート形式の短答式と記述式の論文式では求められる能力が異なるため、それぞれに適した対策が必要です。
公認会計士のキャリア別年収推移
公認会計士の年収は就職先によって大きく異なります。主要なキャリアパス別の年収推移と特徴をご紹介します。
Big4監査法人
入社時500万円から5年後700万円、10年後1,000万円へと順調に上昇します。スタッフ→シニア→マネージャー→パートナーという明確な昇進体系が特徴で、実力に応じて着実にキャリアアップできます。国際的なプロジェクトに参画する機会も豊富です。
中堅監査法人
年収は入社時450万円、5年後650万円、10年後900万円とBig4よりやや控えめですが、ワークライフバランスが良好です。激務が少なく、若手から幅広い業務に携われるため、効率的にスキルアップを図れます。
事業会社(経理)
入社時400万円、5年後600万円、10年後800万円と年収は最も控えめですが、安定性が高いのが魅力です。長期的なキャリア形成が可能で、将来的にCFOを目指すこともできます。有給取得のしやすさや充実した福利厚生も大きなメリットです。
独立開業
最もリスクが高い選択肢で、開業初期は300~500万円程度からスタートします。しかし軌道に乗れば5年後500~1,500万円、10年後1,000~3,000万円と実力次第で大幅な収入アップが期待できます。成功には会計スキルに加えて営業力や経営センスが必要です。
コンサル転職
入社時から600万円の高水準でスタートし、5年後1,000万円、10年後1,500万円に到達します。高収入が魅力ですが、長時間労働を伴う激務であることも特徴です。M&Aアドバイザリーや財務コンサルなど、専門性を活かした高度な業務に従事できます。
| 勤務先 | 入社時年収 | 5年後年収 | 10年後年収 | 特徴 |
| Big4監査法人 | 500万円 | 700万円 | 1,000万円 | 昇進明確 |
| 中堅監査法人 | 450万円 | 650万円 | 900万円 | ワークライフバランス良好 |
| 事業会社(経理) | 400万円 | 600万円 | 800万円 | 安定性高い |
| 独立開業 | 300-500万円 | 500-1,500万円 | 1,000-3,000万円 | 実力次第 |
| コンサル転職 | 600万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 高収入・激務 |
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ:公認会計士の難易度は高いが「努力次第で突破可能」
公認会計士試験は確かに難関ですが、合格者は毎年1000人以上誕生しています。
・合格率は約10%
・勉強時間は3000〜4000時間
・科目は幅広いが戦略次第で得点可能
「自分には無理かも…」と思う人も、正しい方法で努力を積み重ねれば必ず突破できます。難易度が高いからこそ、合格したときの価値も計り知れません。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















