INDEX
おすすめ記事
-

税理士の登録料はいくら?その他の手数料も解説
-
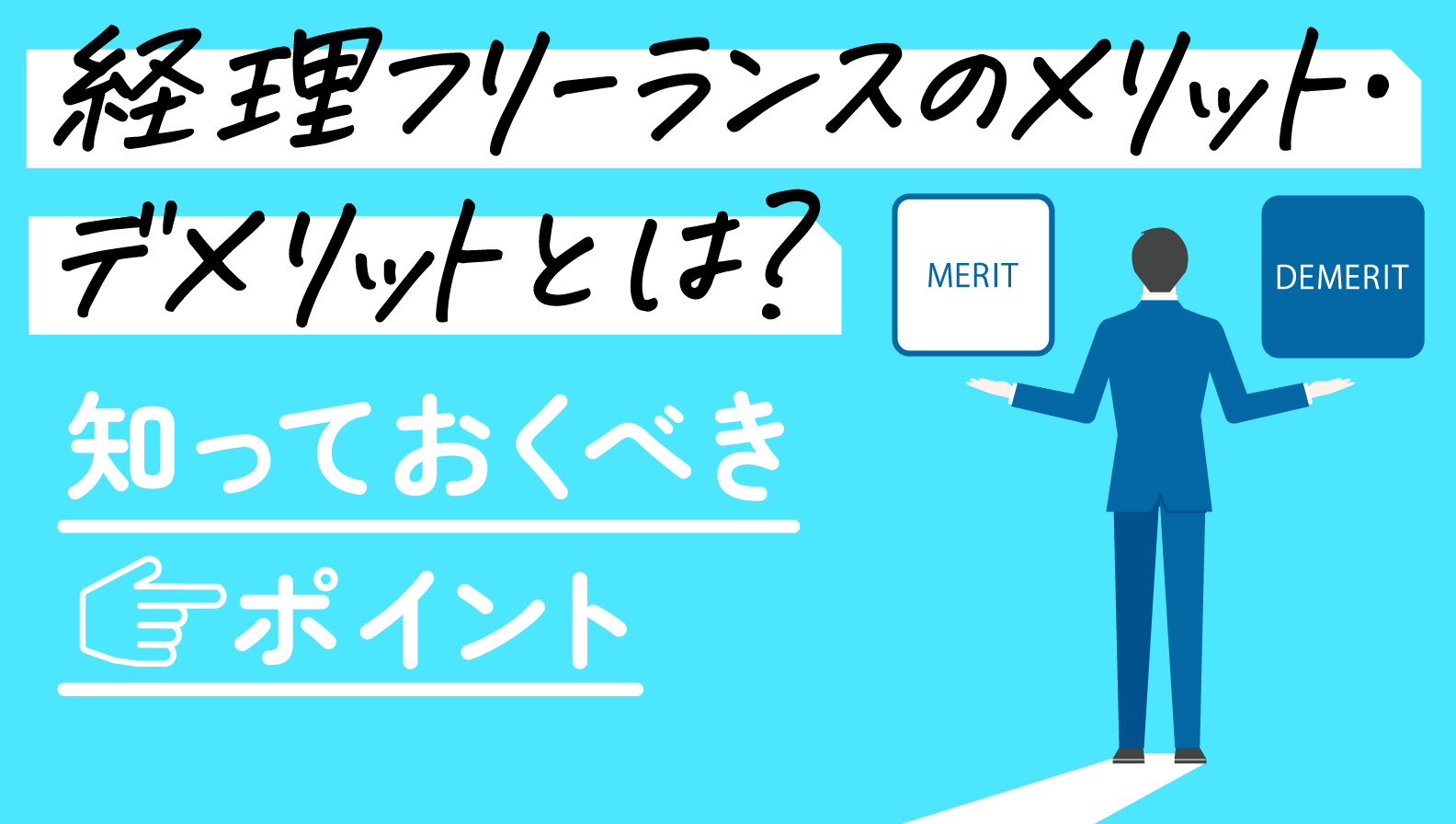
経理フリーランスのメリット・デメリットとは?知っておくべきポイント
-

高卒から経理職へ!未経験からのキャリアアップガイド
-
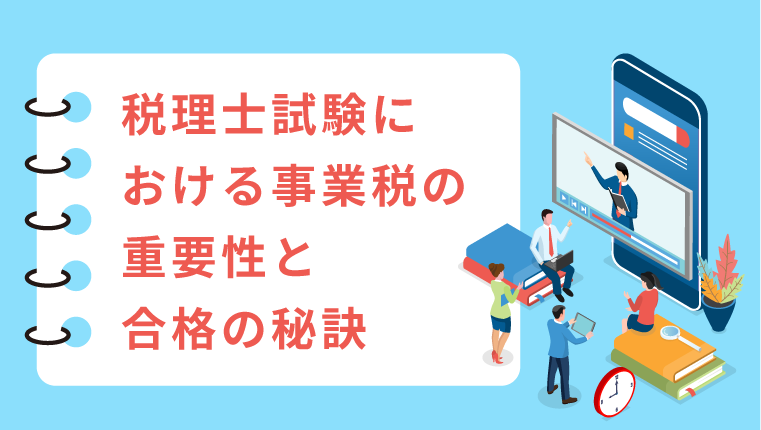
税理士試験における事業税の重要性と合格の秘訣
-
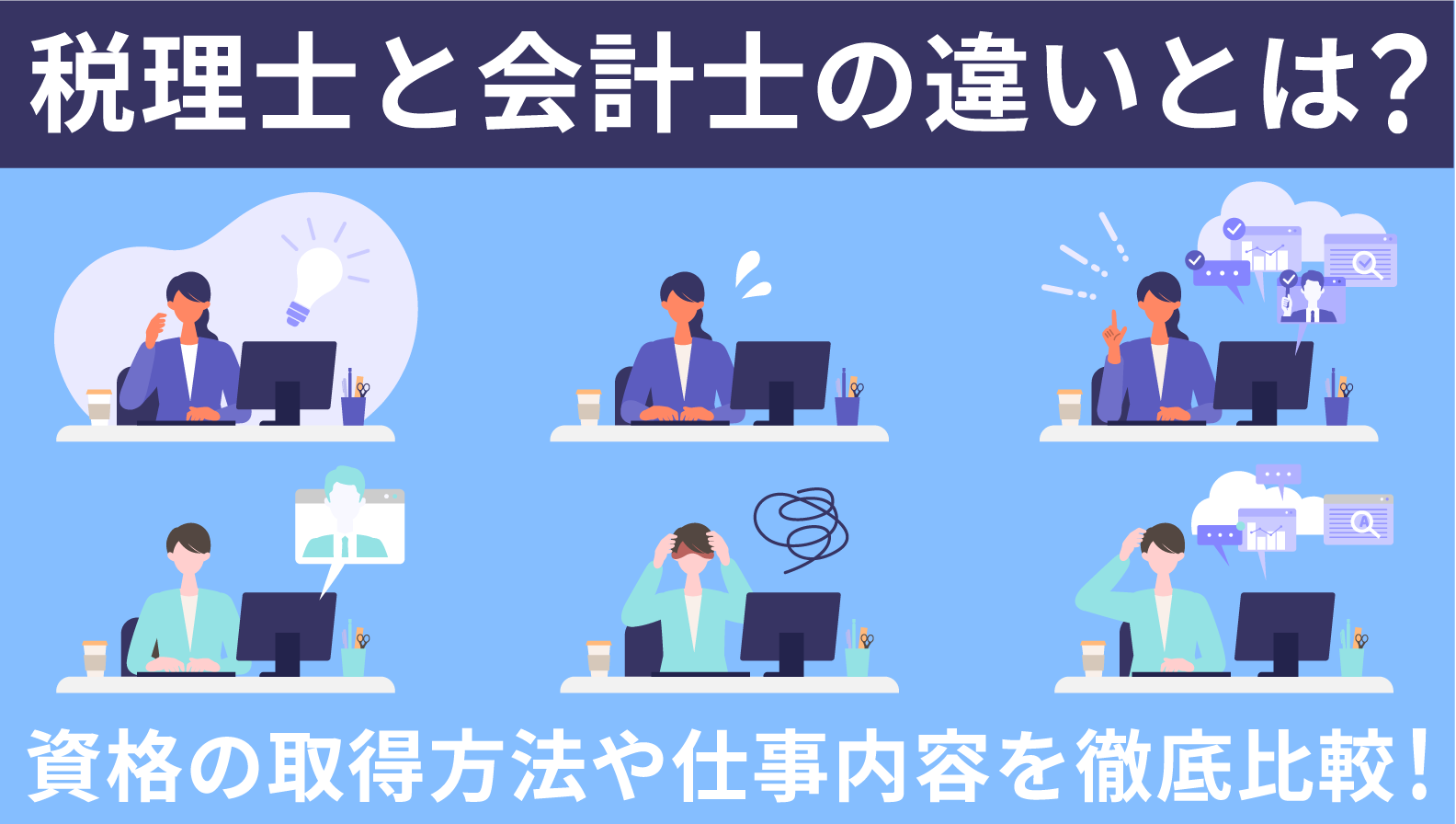
税理士と会計士の違いとは?資格の取得方法や仕事内容を徹底比較!
公開日:2025/10/31
最終更新日:2025/12/04
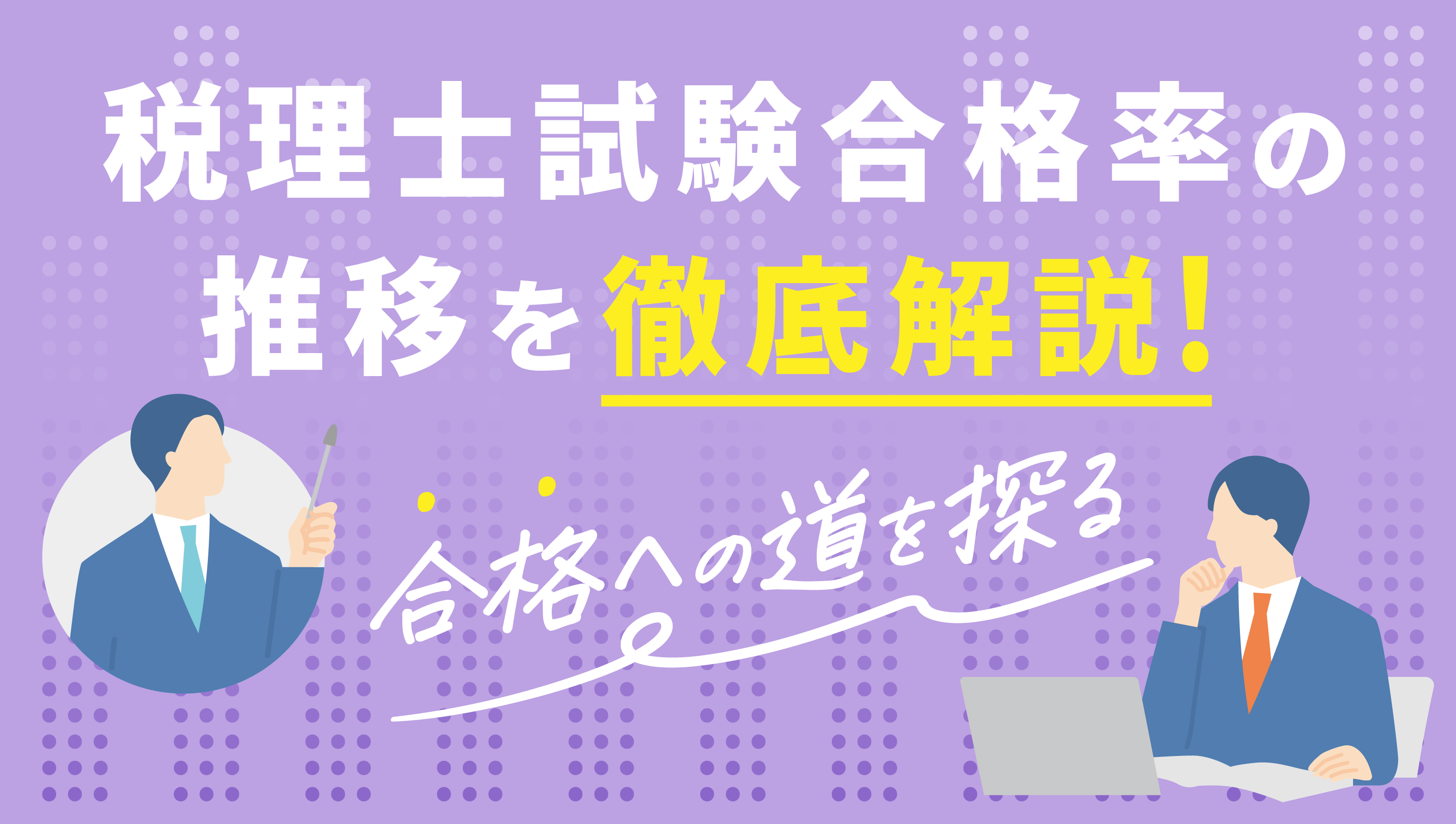
INDEX
1. はじめに:なぜ「合格率の推移」を知ることが税理士試験合格につながるのか?
「税理士試験の合格率は10%〜20%台」
この数字だけを見て、「やっぱり難関すぎる…」「自分には無理かもしれない」と、挑戦する前から不安を感じていませんか?
確かに税理士試験は簡単な試験ではありません。しかし、表面的な合格率の数字だけで判断し、挑戦を諦めたり、非効率な勉強法を選んだりするのは早計です。
本当に大切なのは、合格率が「なぜそうなっているのか」「過去からどう変わってきたのか(推移)」を知ること。そこにこそ、税理士試験を攻略するヒントが隠されています。
この記事は、単に「令和6年度の合格率は〇%でした」とお伝えするだけではなく、なぜ数字が変動するのか、科目ごとにどんな「クセ」があるのかを深掘りし、データを「不安材料」から「戦略的な武器」へ変えることが目的です。
税理士試験の本質をデータから理解し、あなただけの「合格への道」を一緒に探していきましょう。
あなたの「適正年収」を調べてみませんか?
簡単な質問に答えるだけで、一般的な会計事務所ならいくら提示されるのかを即座に算出。「今の適正額」はもちろん、「資格を取得したら年収はどう変わるのか?」など、あなたの現在地と未来の可能性を診断します。
2. 【速報】最新(令和7年度)の税理士試験「合格率」とデータ分析
まずは、国税庁から発表された「令和7年度(第75回)税理士試験」の最新結果を見ていきましょう。あわせて、大きな変化があった前年度(令和6年度)のデータも比較対象として掲載します。
令和7年度・令和6年度 税理士試験 結果比較
| 項目 | 令和7年度(第75回) | 令和6年度(第74回) |
|---|---|---|
| 受験者数(実人数) | 36,320人 | 34,757人 |
| 合格者合計数 | 7,847人 | 5,762人 |
| 全体合格率 | 21.6% | 16.6% |
| 5科目合格者数(官報合格) | 527人 | 578人 |
| 一部科目合格者数 | 7,320人 | 5,184人 |
この最新データから、税理士試験の「今」が明確に見えてきます。
ポイント①:「全体合格率(21.6%)」の急上昇
令和7年度の全体合格率は21.6%となり、前回の16.6%から5.0ポイントも上昇しました。
これは試験全体が簡単になったわけではありません。科目別の合格率を見ると、受験者数の多い「財務諸表論」が31.9%という異例の高い合格率を出したことが、全体の数字を大きく押し上げています。一方で「簿記論」などは難化しており、科目ごとの明暗がはっきりと分かれた年となりました。
ポイント②:最終ゴール「官報合格」は減少(527人)
全体の合格者数が大幅に増えた(+2,085人)一方で、5科目を制覇した「官報合格者数」は527人と、前年の578人から減少しました。
これは、今回の合格者増の多くが「財務諸表論」などの科目合格者(一部科目合格者)であることを示しています。「科目合格までは手が届きやすくなったが、最終的な税理士への到達(官報合格)は依然として狭き門である」という厳しい現実が浮き彫りになりました。
ポイント③:受験者数は3万6千人を突破
受験資格の緩和以降、受験者数は増加の一途をたどっています。令和7年度は36,320人と、前年からさらに約1,500人増加しました。
実受験者が増え、競争が活性化している中で、いかに「取りやすい科目」で確実に合格を拾えるかが、トータルの合格戦略において重要になっています。
3. 【表で徹底解説】税理士試験「合格率」の長期「推移」(過去10年)
最新のデータだけでは、その年が「たまたま難しかった」のか、それとも「ずっと難しい」のか判断できません。そこで、過去10年(平成28年度〜令和7年度)の「受験者数」と「全体合格率」の推移を一覧表で見ていきましょう。
過去10年間(H28~R7)の受験者数と全体合格率の推移
| 試験年度 | 受験者数(実人員) | 合格者合計数(実人員) | 全体合格率 |
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 35,589人 | 5,638人 | 15.8% |
| 平成29年度 | 32,974人 | 6,634人 | 20.1% |
| 平成30年度 | 30,850人 | 4,716人 | 15.3% |
| 令和元年度 | 29,779人 | 5,388人 | 18.1% |
| 令和2年度 | 26,673人 | 5,402人 | 20.3% |
| 令和3年度 | 27,299人 | 5,139人 | 18.8% |
| 令和4年度 | 28,853人 | 5,626人 | 19.5% |
| 令和5年度 | 32,893人 | 7,125人 | 21.7% |
| 令和6年度 | 34,757人 | 5,762人 | 16.6% |
| 令和7年度 | 36,320人 | 7,847人 | 21.6% |
この一覧表から、税理士試験の「合格への道」を探る上で非常に重要な2つの傾向が読み取れます。
傾向①:受験者数は「V字回復」、人気が再燃
まず「受験者数」の推移に注目してください。 平成28年度の約3.5万人から令和2年度の約2.6万人まで、一時は減少傾向にありました。これが「税理士試験離れ」と言われていた時期です。
しかし、令和3年度以降は増加に転じ、直近5年間で力強いV字回復を遂げています。令和7年度には受験者数が3.6万人を超え、減少が始まる前の水準まで回復しました。受験資格の緩和等を背景に、若年層や他分野の社会人の「挑戦の場」として、税理士試験の人気が再燃していることが明確です。
傾向②:「合格率」は15%~20%で安定(=相対評価の示唆)
次に「全体合格率」の推移です。 単年度で見ると上下の変動はあるものの、10年という長期スパンで見れば、概ね「15%〜20%」前後の範囲で安定して推移していることがわかります。
これは、税理士試験が「合格基準点(60点)」という絶対評価を建前としつつも、実質的には合格者数を一定の割合に調整する「相対評価」の側面を強く持つことを示唆しています。
受験者数が増減しても、合格率が極端に乖離することなく一定のレンジに収束していることから、競争試験としての性質を理解し、周囲の受験生に差をつける確実な実力を養うことが重要と言えます。
【受験生が知るべきこと】
この推移からわかるのは、「受験者が減ったからラッキー」「増えたからアンラッキー」という単純な話ではない、ということです。
税理士試験は、常に受験者の中の「上位15%〜20%」に入る実力を身につけることが求められる競争試験であると理解する必要があります。
次の章では、この「全体合格率」をさらに分解し、「合格への道」に直結する「科目別」の合格率と推移を徹底的に分析します。
4. 【合格への最重要ポイント】科目別の「合格率」の「推移」を深掘り
第3章までで、税理士試験全体の合格率が「15%~20%」で推移しており、相対評価的な側面が強いことを解説しました。しかし、税理士試験の最大の特徴は「科目合格制」にあります。
5科目合格への「道」を探るには、科目ごとの合格率と推移を分析することが不可欠です。ここでは主要科目をピックアップし、その傾向と戦略を探ります。
① 必須科目(会計):「簿記論」「財務諸表論」
会計科目は、令和5年度から受験資格が撤廃され、最も受験者層が変化した科目です。特に直近では科目ごとの難易度調整(揺り戻し)が激しくなっています。
【簿記論・財務諸表論】 合格率の推移(過去5年)
| 科目名 | R7年度 | R6年度 | R5年度 | R4年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簿記論 | 11.1% | 17.4% | 17.4% | 23.0% | 16.5% |
| 財務諸表論 | 31.9% | 8.0% | 28.1% | 14.8% | 23.9% |
・簿記論:R7年度は「11.1%」へ急激な難化
過去数年、17%前後で安定していた簿記論ですが、令和7年度は11.1%と大幅に下落しました。これは近年でも稀に見る難易度の高さ(計算量の多さ)を示しており、「安定しているから大丈夫」という油断が禁物であることを証明しました。どんな難問が出ても対応できるよう、基礎計算力の徹底と、取れる問題を落とさない選球眼がこれまで以上に求められます。
・財務諸表論:「ジェットコースター」のような変動
最も注目すべきは財務諸表論の異常なまでの変動幅です。
令和6年度に「8.0%」という歴史的低合格率を記録した反動(揺り戻し)で、令和7年度は一気に「31.9%」まで跳ね上がりました。
この「8.0%(激難)」から「31.9%(易化)」への振れ幅は、試験委員による意図的な調整が働いている証拠です。「財表は受かりやすい」等の予断を持たず、その年が「締め付けの年」になっても合格ラインに残れるよう、理論・計算ともに高水準な対策が必要です。
② 選択必須科目(税法):「法人税法」「所得税法」
多くの受験生が最初に選択する主要税法です。令和7年度の結果を見ても、この2科目は「鉄板の安定感」を見せています。
【法人税法・所得税法】 合格率の推移(過去5年)
| 科目名 | R7年度 | R6年度 | R5年度 | R4年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法人税法 | 13.5% | 16.4% | 14.0% | 12.3% | 12.8% |
| 所得税法 | 13.0% | 12.6% | 13.8% | 14.1% | 12.6% |
・合格率は「12%~14%」へ収束
令和6年度に16.4%とやや高めだった「法人税法」ですが、令和7年度は13.5%へと引き締まりました。一方、「所得税法」は13.0%と前年並みを維持しています。
このように、どちらの科目も長期的に見れば「13%前後」という非常に狭いレンジで安定しています。これは学習量が膨大で、受験生の実力が拮抗しているため、試験委員側が合格率をコントロールしやすいことを示しています。
・戦略:合格率の推移で選ぶな
データが示す通り、両科目の合格率に有利不利の差はほとんどありません。「合格への道」としては、一時の合格率(数%の差)で選ぶのではなく、「実務での需要(法人が圧倒的に多い)」「学習適性(所得税は規定が細かい)」といった観点で選択するのが賢明です。
③ 人気選択科目:「消費税法」「相続税法」
実務での重要性が高い2科目ですが、今年のデータは対照的な動きを見せました。
【消費税法・相続税法】 合格率の推移(過去5年)
| 科目名 | R7年度 | R6年度 | R5年度 | R4年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費税法 | 10.1% | 10.3% | 11.9% | 11.4% | 11.9% |
| 相続税法 | 13.8% | 18.7% | 11.6% | 14.2% | 12.8% |
・消費税法:「10%の壁」が続く最難関
最も警戒すべきは「消費税法」です。令和6年度の10.3%に続き、令和7年度も10.1%と、全科目の中で最も低い合格率となりました。かつては「ミニ税法」と呼ばれましたが、現在は受験者数が多く激戦区となっており、わずかなケアレスミスも許されない「10人に1人しか受からない狭き門」として定着しています。
・相続税法:平常運転への「揺り戻し」
「相続税法」は、令和6年度に18.7%と突出して高かった反動で、令和7年度は13.8%へと正常化(難化)しました。
これは前年が例外的に受かりやすかっただけであり、本来の難易度に戻ったと言えます。学習ボリュームの多さは税法科目屈指であるため、「昨年が高かったから」という安易な選択は禁物です。
科目別分析のまとめ
この科目別推移からわかるのは、「ラクに受かる科目はない」という事実です。
特に受験資格が緩和された会計科目は、合格率の推移が激しく変動しており、今や税法科目以上に「ふるい落とされる」厳しい試験になっています。「合格への道」を探るには、どの科目も「上位15%前後」に入るための徹底した学習が不可欠であると、データが示しています。
あなたの「適正年収」を調べてみませんか?
簡単な質問に答えるだけで、一般的な会計事務所ならいくら提示されるのかを即座に算出。「今の適正額」はもちろん、「資格を取得したら年収はどう変わるのか?」など、あなたの現在地と未来の可能性を診断します。
5. 「合格率」の数字の裏側と「合格への道」を探る戦略
ここまで税理士試験の最新合格率と、過去からの推移を徹底的に分析してきました。
・全体の合格率は「15%~20%」で安定推移(=相対評価の側面が強い)
・科目別の合格率は、安定している科目(税法)と、近年激動している科目(特に財務諸表論)がある
では、これらの事実から、私たちはどのような「合格への道」を描けばよいのでしょうか。合格率の数字の裏側に隠された本質を踏まえ、3つの戦略を提言します。
戦略①:「合格基準60点」の罠。目指すは「上位15%」
税理士試験の要項には「合格基準点は60点」と明記されています。これは「絶対評価」です。しかし、第3章の推移で見た通り、受験者数が変動しても合格率は一定のレンジに収まっています。
さらに第4章で見た「財務諸表論」の推移(R6: 8.0% → R7: 31.9%)は、どう考えても「60点」という絶対的な基準だけで運用されているとは思えません。
これが意味することは一つです。 税理士試験の実態は、「上位15%~20%(科によっては10%)を選抜する相対評価試験」であるということ。
「60点でいいや」という学習は、合格率が低い(=問題が難しい)年に対応できません。「合格への道」は、常に受験生の中の上位15%に入る実力を目指すこと。模試や答練で上位安定を目指す学習こそが、合格率の推移に左右されない唯一の戦略です。
戦略②:「会計科目の早期突破」が最重要課題に
かつては「簿記論・財務諸表論は受かりやすい」と言われた時代もありました。しかし、令和5年度からの受験資格緩和で状況は一変しました。
・受験者が急増し、競争が激化。
・R6年度の財務諸表論(合格率8.0%)に見るように、試験側が明確に「ふるい落とし」にかかっている。
会計科目は、もはや「入口」ではありません。税理士試験の「最初の関門」へと難易度が上がったと認識すべきです。
「合格への道」は、まずこの会計科目を1〜2年で確実に突破する計画を立てること
。ここで足踏みすると、膨大な時間がかかる税法科目の学習に進めず、長期化(いわゆる「沼」)の原因となります。
戦略③:「合格率の推移」に一喜一憂せず、淡々と積み上げる
・「R7の財務諸表論は合格率31.9%でラッキーだった」
・「R6の財務諸表論は合格率8%でアンラッキーだった」
・「R6の相続税法は合格率18.7%だったから、来年は狙い目だ」
合格率の推移を見て、このように一喜一憂するのは最も危険です。
データが示すのは、「どの科目も、いつ難化・易化するかわからない」という事実だけです。狙い目だと思った科目が翌年、超難化することは税理士試験では日常茶飯事です。
税理士試験の本当の難しさは、1回の合格率の低さではなく、この不確実な試験を5回クリアしなければならない長期戦であること。
「合格への道」とは、合格率の推移という「運」の要素に期待するのではなく、どの科目・どの難易度で出題されても「上位15%」に入れる実力を、1科目ずつ淡々と積み上げていく覚悟を持つことに他なりません。




















