INDEX
おすすめ記事
-

簿財の最新情報【2025年最新版】:試験の難易度やキャリアパスを徹底分析
-

税理士法人設立のメリットと成功の秘訣
-

倒産寸前からV字回復!!税理士の事業再生支援【めざせ!TAX MASTER#34】
-
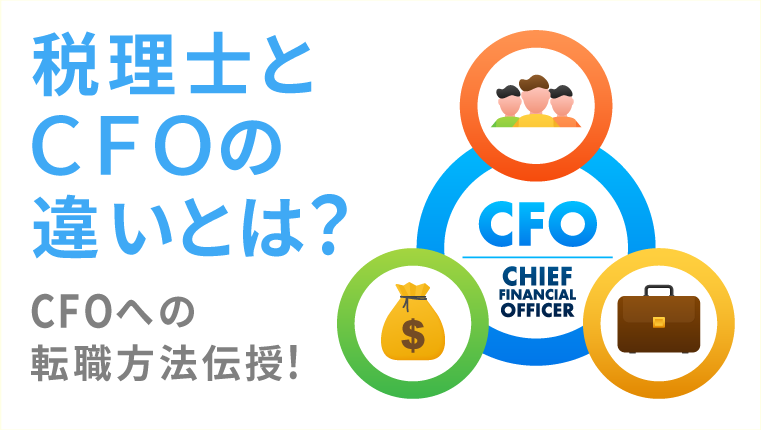
税理士とCFOの違いとは?CFOへの転職方法伝授!
-
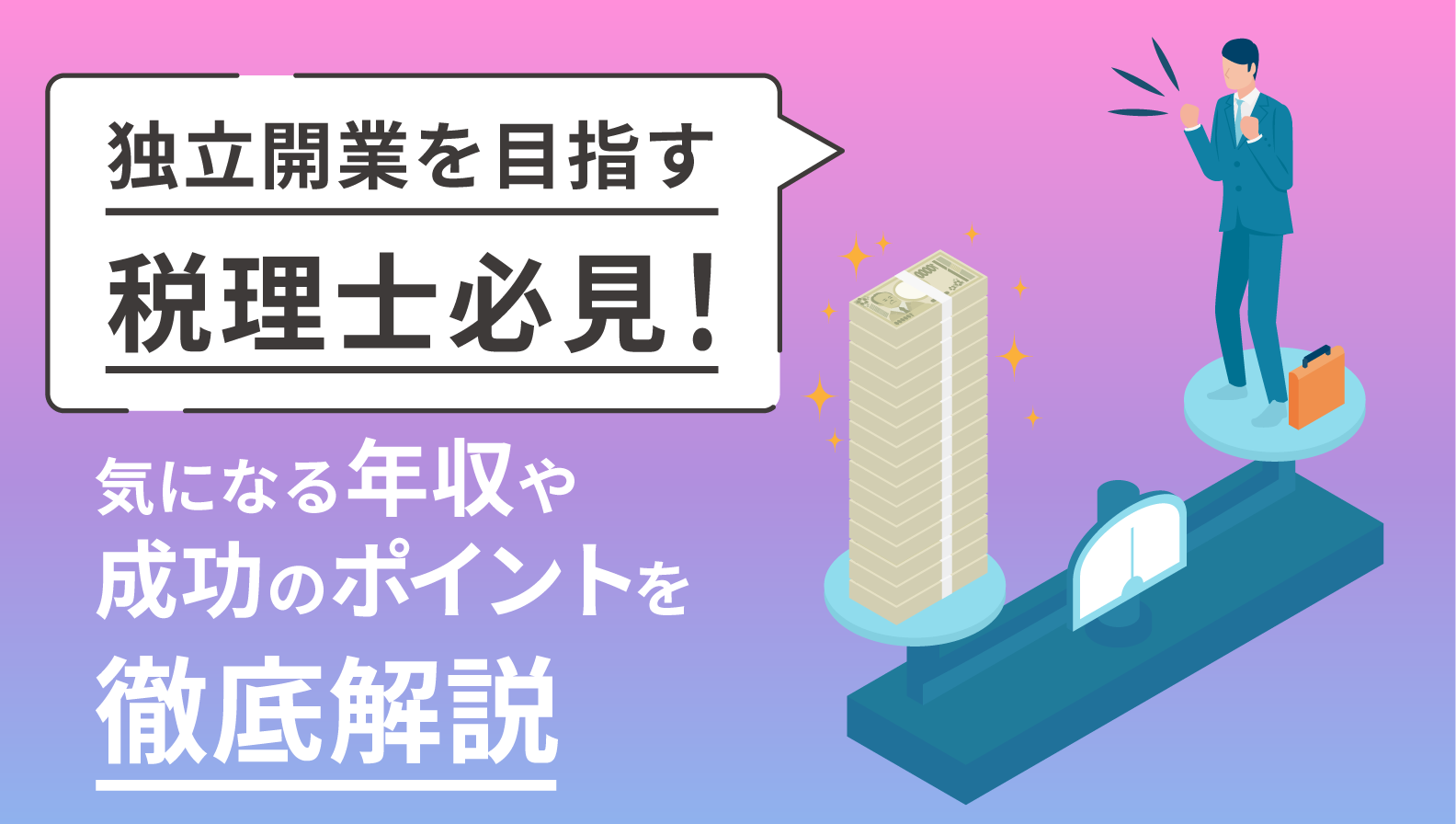
税理士が独立開業したら年収はいくらになる?独立開業後の年収事情を徹底解説
公開日:2025/11/24
最終更新日:2025/11/25
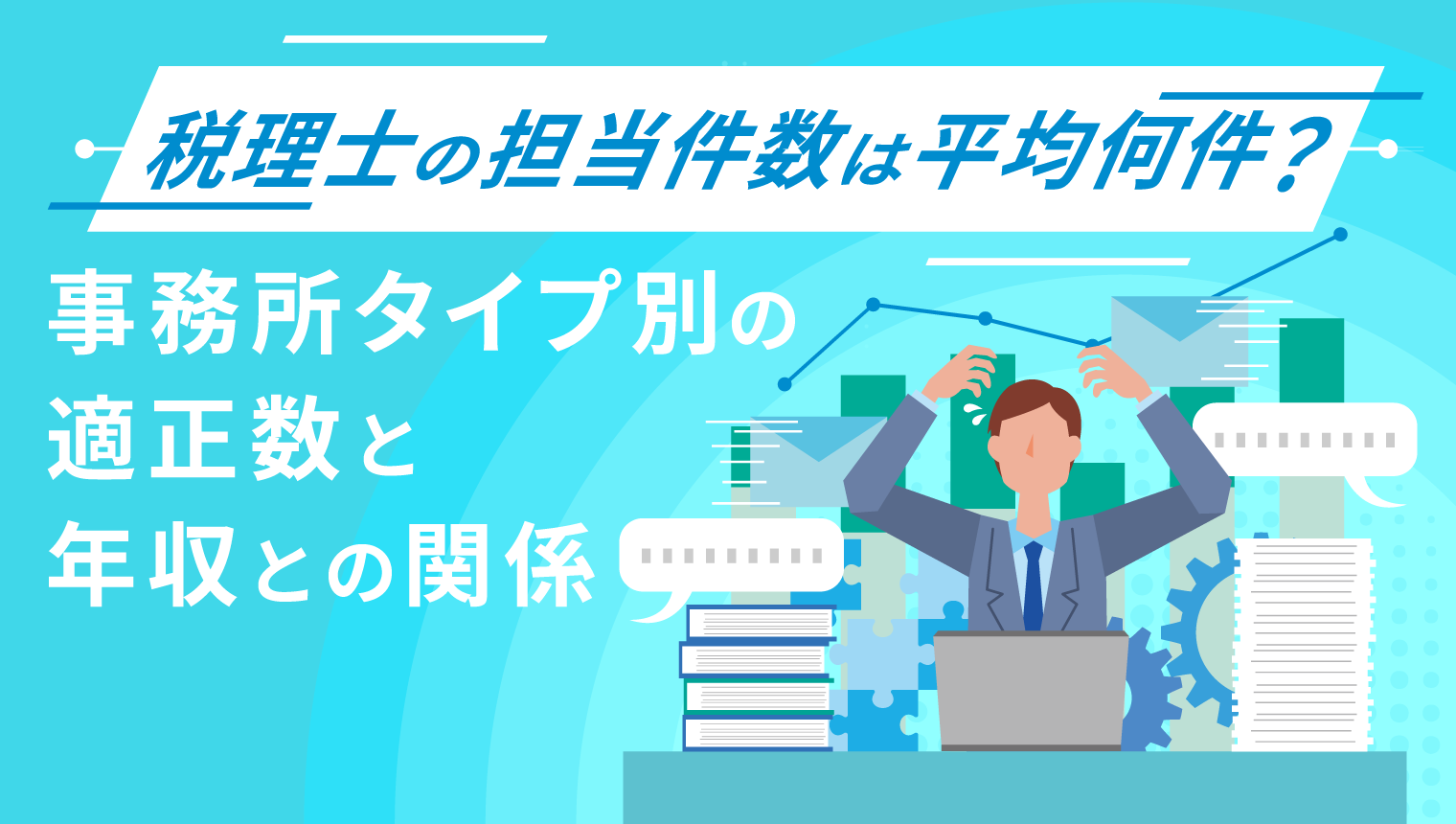
INDEX
「今の税理士事務所で担当件数が30件を超えているけれど、これは税理士として普通なのだろうか?」
「業務量が増えるばかりで給料が上がらない。1人あたりの負担が限界に近い気がする」
税理士事務所で働く税理士や税理士補助(スタッフ)にとって、担当件数は労働環境と年収を決定づける重要な指標です。しかし、この数字には税理士業界共通の明確なルールがなく、税理士事務所の方針や補助スタッフのサポート体制によって「天国」にも「地獄」にもなり得ます。
この記事では、税理士業界における担当件数の平均値や適正ライン、件数が年収にどう反映されるのか、そして税理士事務所の特徴ごとの違いを徹底解説します。
あなたの「適正年収」を調べてみませんか?
簡単な質問に答えるだけで、一般的な会計事務所ならいくら提示されるのかを即座に算出。「今の適正額」はもちろん、「資格を取得したら年収はどう変わるのか?」など、あなたの現在地と未来の可能性を診断します。
税理士の担当件数、税理士事務所の平均は「20件前後」
まず、結論から言います。一般的な税理士事務所において、税理士や担当スタッフ1人あたりが持つ担当件数の平均は、法人クライアントで「15件〜25件」程度と言われています。
ただし、この数字はあくまで目安に過ぎません。税理士事務所の規模や、税理士をサポートする補助者の有無によって、その実質的な負担は大きく異なります。
1. 担当件数の内訳(法人 vs 個人)
同じ「担当件数30件」でもその内訳が重要です。
法人をメインとする場合と個人事業主をメインとする場合で、一般的に担当できる件数は異なります。
・法人がメインの場合:
毎月の巡回監査、月次決算、節税提案などの会計業務が必要なため、税理士1人で20件を超えると多忙になり始めます。
・個人事業主(自計化済み)がメインの場合:
年一回の確定申告が主な業務であれば、税理士1人で50件以上担当することも物理的に可能です。
2. 税理士補助(アシスタント)の有無
最も時間を奪うのが「記帳代行(入力作業)」などの補助的な業務です。
補助業務を担ってくれる税理士補助がいるかどうかで、担当できる件数は大きく変わります。
・補助なし(全て1人):
領収書の整理から入力まで全て税理士自身が行う場合、15件でも限界を感じることがあります。
・補助あり(分業制):
税理士事務所内に有力な補助スタッフ(パート・アルバイト)がいて入力業務を任せられる場合、税理士は30件〜40件でも余裕を持って回せるケースがあります。
3. 税理士事務所の訪問頻度の方針
昔ながらの「毎月訪問」を厳守している税理士事務所か、Zoomなどを活用して「必要に応じて面談」とする税理士事務所かによっても、適正な担当件数は倍近く変わります。移動時間が削減されれば、その分多くのクライアントを1人で担当できるからです。
【税理士事務所のタイプ別】担当件数の目安と特徴
自分の現在の状況が適正なのか判断するために、税理士事務所のタイプごとの担当件数と業務負荷の目安を表にまとめました。
所属している税理士事務所のタイプや担当業務により、担当件数の目安は変わるため注意が必要です。
| 税理士事務所のタイプ | 主な会計業務スタイル | 平均担当件数 | 繁忙度・特徴 |
|---|---|---|---|
| 資産税特化型 | 相続税申告、事業承継 | 年間数件〜10件 | 担当件数は少ないが、税理士としての専門性が求められる。1件あたりの単価が高い。 |
| 中小・零細特化型 | 記帳代行〜決算まで丸投げ | 15件〜20件 | 全て1人でこなす「製版一体型」。補助スタッフがいないと20件超で残業が常態化。 |
| 中堅・大手税理士事務所 | 巡回監査、コンサルティング | 20件〜30件 | 補助部門(製本・入力担当)が付くことが多い。税理士は付加価値業務に集中できる。 |
| 格安・薄利多売型 | 年一決算、訪問なし | 40件〜60件 | クオリティよりスピード重視の税理士事務所。常に何かに追われる状態になりがち。 |
もしあなたの担当件数が30件を超えていて、かつ「記帳などの補助業務を全て自分でやっている」「税理士事務所内にアシスタントがいない」という場合、それは税理士業界の水準から見てオーバーワーク(持ちすぎ)である可能性が高いです。
税理士の担当件数と年収の関係
「担当件数が増えて売上も上がったのに、給料が変わらない」 このような不満を持つ税理士は少なくありません。
しかし、年収は単純に「担当件数」だけで決まるものではありません。税理士事務所の経営視点で見ると、重要なのは「担当売上(単価)」と、その売上を作るために「何人の手が関わっているか(人件費コスト)」という生産性のバランスです。
順を追って、給与決定の裏側にある仕組みを解説します。
1. 基本の目安:「年収=担当売上の30%〜40%」
税理士業界には、古くからベースとされている給与決定の目安があります。 それは、税理士1人が稼ぎ出した売上高(担当顧問料の合計)の約3分の1が年収になる
というものです。
例えば、税理士として年収600万円を目指すなら、逆算して年間1,800万円〜2,000万円程度の売上を担当する必要があります。ここで重要になるのが「単価」です。
・パターンA:安価な顧問先を大量に担当
◦顧問料月3万円 × 50件 = 月商150万円(年1,800万円)
◦→ 担当件数50件でやっと年収600万円が見える
・パターンB:高単価な顧問先を少数精鋭で担当
◦顧問料月5万円 × 30件 = 月商150万円(年1,800万円)
◦→ 担当件数30件で年収600万円が可能
このように、単価の低いクライアントばかりを大量に抱える税理士事務所にいる場合、担当件数の割に年収が上がらない「薄利多売」の状態に陥ります。
2. 注意点:年収は「チーム全体の人件費」で決まる
しかし、上記の「売上の30〜40%」という法則は、あくまで「1人で業務を完結している場合」の話です。
ここに補助スタッフ(パートや入力担当)が関わっている場合、計算式は変わります。税理士事務所としては、あなたの業務を支えるためにかかっている「補助スタッフの人件費」もコストとして計算しなければならないからです。
同じ「年間売上2,000万円」を担当する場合でも、以下の2つのケースでは評価(年収)が異なります。
・ケースA:全て1人で担当(補助なし)
◦売上:2,000万円
◦コスト:本人のみ
◦評価:売上がダイレクトに本人の成果となるため、高年収(600〜700万円など)が狙える。
・ケースB:入力スタッフを使って担当(補助あり)
◦売上:2,000万円
◦コスト:本人 + 補助スタッフ(人件費300万円相当)
◦評価:売上から補助スタッフのコストを差し引いて考えられるため、本人の適正年収は下がる(400〜500万円など)、あるいは担当件数をもっと増やして売上を上げることが求められる。
つまり、税理士事務所があなたに補助スタッフをつけている場合、あなたは「自分と補助スタッフの2人分のコスト」を賄えるだけの高い売上(件数)を達成しなければ、給料は上がらない仕組みになっているのです。
3. 税理士事務所のインセンティブと利益意識
多くの税理士事務所では、基本となるノルマを超えた分にインセンティブを支給しますが、この際も「チームの総コスト」が基準になります。
税理士会の会費負担や、資格手当などの福利厚生コストも含め、トータルで「自分は税理士事務所にいくら利益を残せているか」という視点を持つことが、適正な年収交渉への第一歩です。
また、税理士事務所にいくら利益を残せているかという視点は年収を上げるために必要なだけでなく、将来独立して自分の事務所を持つ場合にも重要な考え方になります。
1人で50件も可能?テクノロジーと「仕組み化」で変わる担当件数の常識
近年、クラウド会計ソフト(マネーフォワード、freeeなど)の進化と、税理士事務所の組織的な「仕組み化」により、1人あたりの適正担当件数の基準は劇的に変わりつつあります。
先進的な取り組みを行う一部の税理士事務所では、税理士や担当者1人が「50件〜60件」ものクライアントを担当しながら、残業ゼロや高収益を実現している事例が出てきています。 なぜ、従来の倍以上の件数をこなすことができるのでしょうか。その特徴は、単なるツールの導入だけでなく、徹底した業務フローの改革にあります。
1. クラウド活用による「入力」の消滅
クラウド活用をして、生産性が高い税理士事務所の最大の特徴は、手入力を極限まで排除している点です。
銀行口座やクレジットカード、POSレジのデータをAPI連携させ、会計ソフトへ自動で取り込みます。紙の領収書もAI-OCR(自動読み取り)を活用します。 これにより、手入力の時間がゼロになり、税理士は「上がってきたデータを確認・修正するだけ」という状態になります。
2. 「製販分離」の徹底と補助スタッフの活躍
担当件数を多く持てる事務所では、「製販分離(製造と販売の分離)」という分業体制が確立されています。
・製造(入力・集計): 補助スタッフやパートチームが担当
・販売(監査・報告): 税理士や担当者が担当
このように役割を明確に分けることで、税理士は付加価値の高い「チェック業務」や「顧客対応」に100%の時間を割くことができます。優秀な補助チームという土台があるからこそ、フロントに立つ担当者は1人で数十件の案件を回すことが可能になるのです。
3. 業務フローの標準化と訪問の廃止
「顧客ごとにやり方が違う」という属人化を排除しているのも特徴です。 資料の回収方法やフォルダ構成、連絡ツール(ChatworkやSlackなど)を全クライアントで統一(標準化)することで、脳の切り替えコストを減らしています。 また、毎月の訪問を廃止し、Zoomなどのオンライン面談に切り替えることで、移動時間を削減。浮いた時間を別のクライアント対応に充てることで、生産性の向上を実現しています。
担当件数に不満がある時の対処法
これまで解説してきたとおり、担当件数は事務所のタイプや業務フローによって、大きく変わります。では、現状の税理士事務所での担当件数や負担感に納得がいかない場合、税理士としてどのようなアクションを取るべきでしょうか。
1. 税理士事務所側に補助を要請する
まずは所長に相談し、入力業務を行う補助スタッフ(パート)の採用や、製版分離(入力と担当を分ける体制)を提案してみましょう。税理士が付加価値業務に集中できれば、税理士事務所全体の売上アップにも貢献できます。
2. 顧問料の適正化を提案する
手間がかかる割に顧問料が安いクライアントがいる場合、値上げ交渉を提案するのも一つの手です。担当件数を減らしつつ売上を維持できれば、税理士事務所の生産性は向上します。
3. 別の税理士事務所への転職を検討する
「人手が足りず、補助もいない」「税理士事務所全体が疲弊している」
そのような環境なら、より生産性の高い税理士事務所への転職を検討すべきです。
「担当件数は20件前後で、補助体制が充実している」「会計ソフトの活用が進んでいる」といった税理士事務所は確実に存在します。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士の担当件数は平均何件? -まとめ
この記事では税理士の担当件数について解説してきました。
・担当件数の平均は?: 法人メインの税理士事務所なら20件前後が目安。
・1人が持つ担当件数の限界は?: 補助なしで15件は限界。補助ありなら30件以上も可能。
・担当件数と年収の関係は?: 件数よりも「担当売上高」とかかっている「人件費」が重要。
・テクノロジーによる担当件数の常識変化:クラウド会計を導入し、うまく仕組み化できている事務所では1人当たり50件以上の担当を持っている事例もある
以上から、「担当件数が多い税理士事務所=ブラック」と一概には言えません。
重要なのは、「その件数を処理するための補助体制や会計システムが整っているか」です。
もし現在の税理士事務所が、ただ闇雲に件数を押し付けられるだけで、税理士としてのスキルアップも望めないのであれば、新しい環境を探すタイミングかもしれません。自分のキャパシティと税理士事務所の環境を今一度、見直してみてはいかがでしょうか。

高梨 茉奈(たかなし まな)
めざせ!TAX MASTER パーソナリティ



















