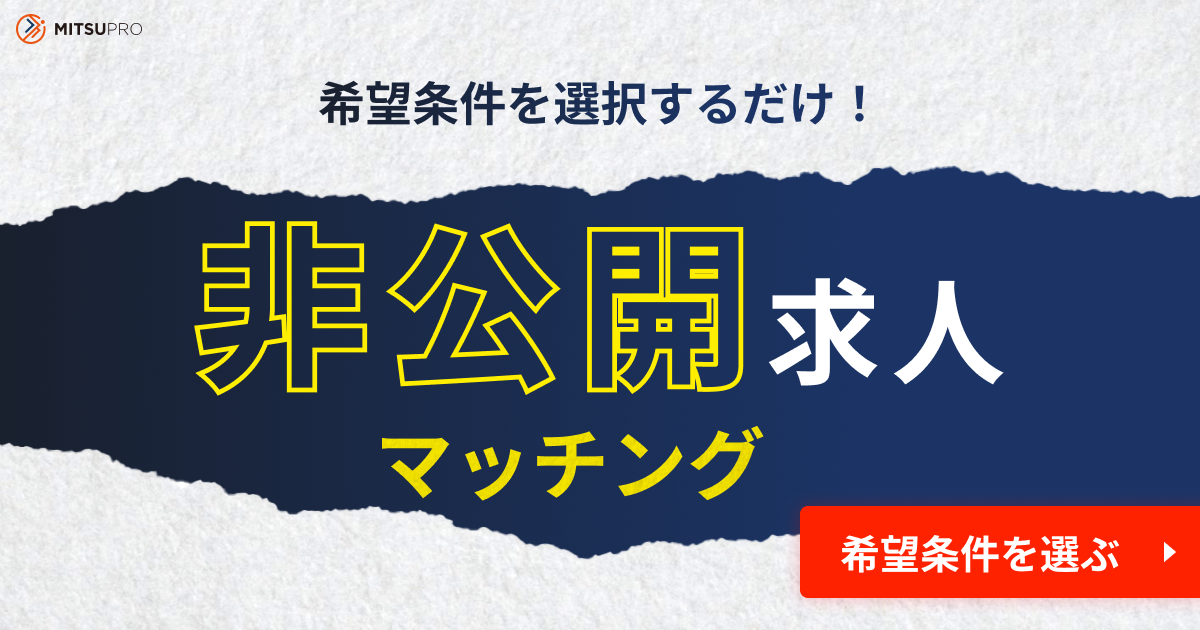INDEX
おすすめ記事
-

外形標準課税とは?対象法人や計算方法、2024年(令和6年)税制改正内容を徹底解説
-
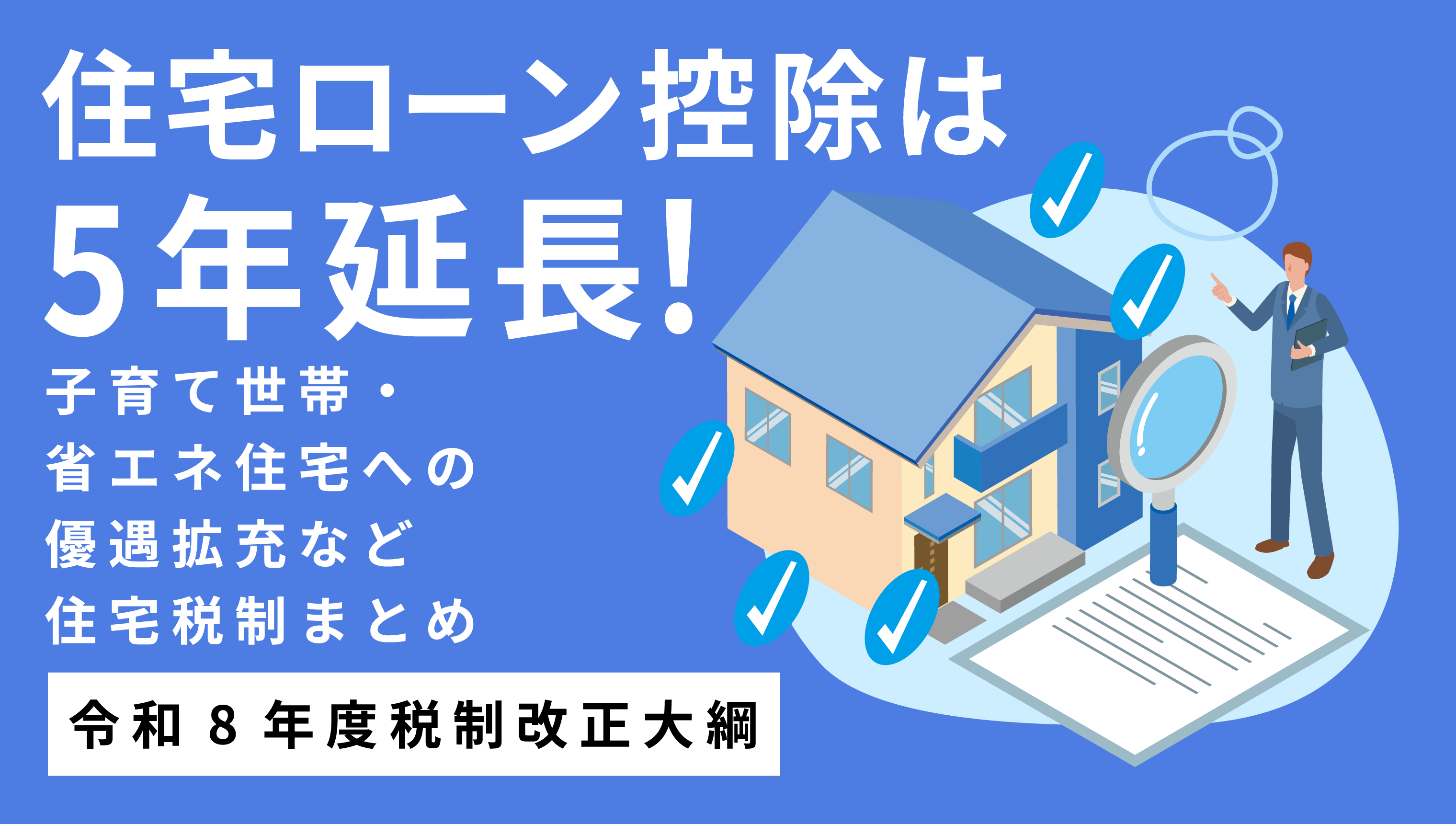
住宅ローン控除は5年延長!子育て世帯・省エネ住宅への優遇拡充など住宅税制まとめ【令和8年度税制改正大綱】
-

女性にとって税理士という職業は魅力的?働き方から年収まで女性が税理士になるメリットを解説
-
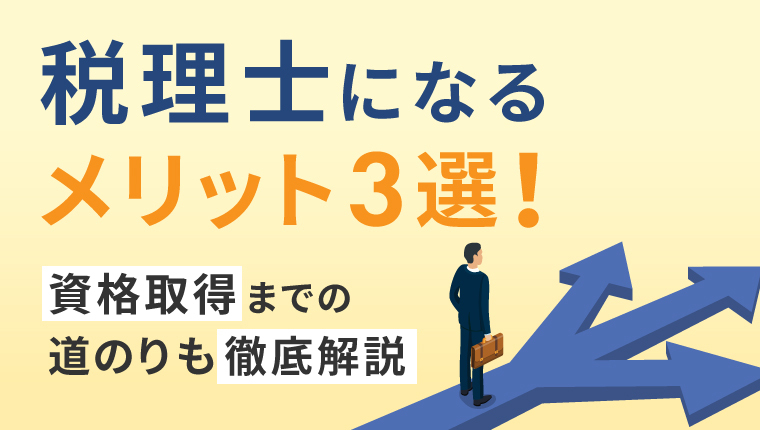
税理士資格を取得するメリット3選!資格取得までの道のりも徹底解説
-
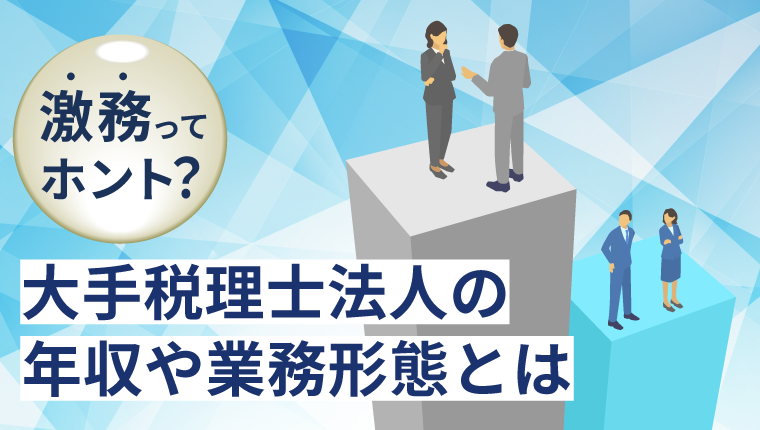
大手税理士法人は激務ってホント?大手税理士法人の年収や業務形態とは
公開日:2024/10/17
最終更新日:2025/09/08
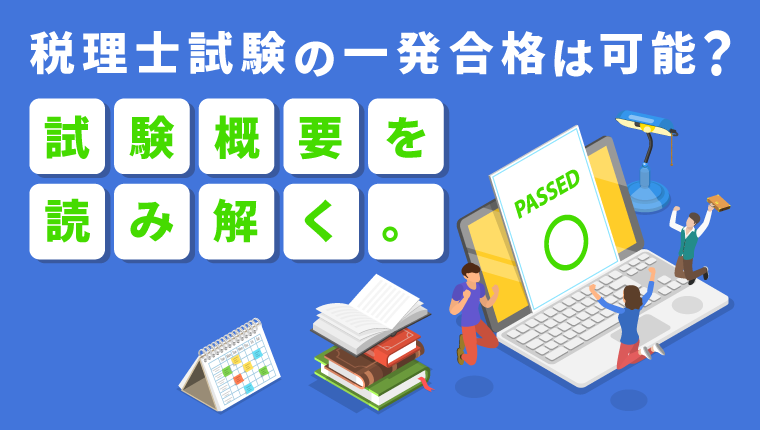
INDEX
税理士試験に合格するためには5科目の合格が必要となります。 では、5科目を1発合格することはできるのでしょうか? この記事では、税理士試験の概要から合格率、更には合格するための攻略法について解説していきます。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士の仕事内容
まずは、税理士の仕事内容について改めて知識を深めていきましょう。 税理士の主な仕事として挙げられるのは、「税務相談」「税務書類の作成」「税務代理」の3つの独占業務です。これらの業務は、税理士資格を持つ者だけが行うことが許されています。
「税務相談」とは、個人や法人が税金に関する疑問や問題を解決するための助言を行う業務です。これには、節税対策、税務リスクの管理、税務調査対応などが含まれます。次に、「税務書類の作成」は、各種税務申告書や決算書などの書類を作成する業務です。これには、確定申告書、法人税申告書、消費税申告書などが含まれます。税理士は、法令に基づいて正確な書類を作成することが求められます。
そして、「税務代理」は、税務署や地方自治体との交渉や、税務調査時の立会いなどを行う業務です。クライアントの代理人として、税務当局とのコミュニケーションを円滑に進める役割を果たします。また、独占業務以外にも、税理士は確定申告や法人決算、記帳代行や年末調整などの業務も行っています。 これらの業務を行うためには、高難易度である税理士試験に合格し、専門的な税務・会計知識を身につけてプロフェッショナルになることが求められます。
税理士試験の一発合格は可能?
税理士の独占業務を行うためには、税理士試験に合格することが求められます。 国家資格の中でも高難易度と言われる税理士試験に一発合格することは可能なのでしょうか?
税理士試験の一発合格は可能
一発合格が可能か不可能か、でいうと可能です。 しかし、税理士試験の5科目を一発で合格するのはごく稀な話であり、令和4年に一発合格者が出た際には11年ぶりの一発合格者として記事になるほど珍しいことです。
税理士試験の各科目の合格率は約10%から20%程度と言われており、1つの科目に一発で合格することすら難しい試験ですなのです。もちろん、目標として設定する分には良いかと思いますが、現実的に考えるとかなり難しいでしょう。 次の章では、税理士試験の概要について詳しく説明いたします。
税理士試験の概要
税理士試験は、毎年8月の年1回行われています。この試験は、税務知識や会計知識を問う試験であり、税理士試験に合格するためには合計で5科目に合格する必要があります。一般的に、5科目合格者を税理士試験合格者と呼び、1科目から4科目合格者は科目合格者と呼ばれています。
税理士試験科目には11科目があり、必修科目である簿記論、財務諸表論を除いた3科目については選択科目となります。 科目については以下の通りです。
| 科目 | 条件 |
|---|---|
| 簿記論 | 必修 |
| 財務諸表論 | 必修 |
| 所得税法 | 所得税法または法人税法のいずれかを選択 |
| 法人税法 | |
| 消費税法 | 消費税法または酒税法のいずれか一方のみ選択可能 |
| 酒税法 | |
| 住民税 | 住民税または事業税のいずれか一方のみ選択可能 |
| 事業税 | |
| 相続税法 | 任意 |
| 国税徴収法 | |
| 固定資産税 |
税理士試験の科目別合格率
ここでは、各科目に対する合格率について見ていきましょう。 科目別の合格率については、税理士試験結果表として国税庁が公表している数値を表記しています。
| 科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 簿記論 | 16,093名 | 2,794名 | 17.4%(6人に1人程度) |
| 財務諸表論 | 13,260名 | 3,726名 | 28.1%(4人に1人程度) |
| 所得税法 | 1,202名 | 166名 | 13.8%(7人に1人程度) |
| 法人税法 | 3,550名 | 497名 | 14.0%(7人に1人程度) |
| 相続税法 | 2,428名 | 282名 | 11.6%(8人に1人程度) |
| 消費税法 | 6,756名 | 802名 | 11.9%(8人に1人程度) |
| 酒税法 | 463名 | 59名 | 12.7%(8人に1人程度) |
| 国税徴収法 | 1,646名 | 228名 | 13.9%(7人に1人程度) |
| 住民税 | 462名 | 68名 | 14.7%(7人に1人程度) |
| 事業税 | 250名 | 41名 | 16.4%(6人に1人程度) |
| 固定資産税 | 846名 | 146名 | 17.3%(6人に1人程度) |
| 合計 | 46,956名 | 8,809名 | 18.80% |
上記の表を見ると、どの科目も難易度が高く決して容易に取れる資格ではないことが分かります。 そのため税理士試験は、一般的には1年に1科目合格を目指して勉強を進める方が多いです。
5科目合格に係る年数は早くて3年から5年、平均では10年ほどと言われています。 そのため、税理士試験に挑むには長い年数を見越してスケジュール設定を行う必要があるのです。
税理士試験に合格するには?
国家資格の中でも難関な資格と言われている税理士試験ですが、合格するにはどのような勉強が必要なのでしょうか? この章では、税理士試験に合格するための勉強方法について解説します。
大学・専門学校・予備校に通う
大学、専門学校、そして予備校は、税理士試験に必要な知識を体系的に学ぶことができます。大学では、経済学や法学などの基礎知識をしっかりと身につけることができ、税理士試験の基盤を築くのに適しています。
専門学校や予備校は、税理士試験に特化したカリキュラムを提供しており、短期間で効率的に学習を進めることができます。また、専門学校や予備校では、過去問や模擬試験を通じて実践的な対策ができます。専門学校では、全ての科目について時間が決められており、苦手分野や得意分野の授業選択を自身で行うことはできませんが、幅広い知識を身につけることが可能です。
一方で、予備校では自身の得意分野のみを勉強するなど、科目別にコースが分かれています。しかし、知識に偏りがでてしまうため、自分自身がどの科目について興味があるのか、自身のキャリアプランを考えたうえでどの科目が必要になるのか、取捨選択が求められます。
さらに、これらの教育機関には同じ目標を持つ仲間が多く集まるため、互いに切磋琢磨しながら学ぶことができます。同じ目標を持った仲間との情報交換やコミュニケーションは、モチベーションの維持にも大いに役立ちます。加えて、大学や専門学校、予備校では、税理士試験に関する最新の情報や資料も豊富に提供されるため、独自に情報収集を行う手間を省くことができます。試験の傾向や変更点についても迅速に対応できるため、常に最新の対策を講じることがでるでしょう。
税理士事務所で働きながら合格を目指す
税理士事務所で働きながら税理士試験に合格することは、時間に追われ大変ではありますが、同時に実践的な経験を積む絶好の機会でもあります。 まず、税理士事務所での実務経験は、試験で問われる知識を現場で体感し、理解を深めることができます。例えば、税務申告書の作成や税務相談の対応といった具体的な業務を通じて、理論と実務の橋渡しが可能になります。
しかし、働きながらの勉強は時間管理が重要です。通常の業務時間外に勉強時間を確保するためには、効率的なスケジュール管理が求められます。例えば、朝早く起きて勉強する、昼休みを活用する、夜間や週末に集中して学習するなど、日々の時間を有効に使う工夫が必要です。 また、オンライン講座や通信教育を活用することで、自宅でも学習が進められます。
税理士事務所の繁忙期には、なかなか勉強時間が取れない場合もありますが、税理士試験取得支援をしている事務所もあるため、就職する際に担当者へ確認する事をおすすめします。最後に、税理士事務所での実務経験は、試験合格後のキャリアにも直結します。試験に合格して税理士登録を行った後に、即戦力として活躍できるため、転職市場でも有利に働くでしょう。
また、実務経験を積むことで、クライアントとの信頼関係を築きやすくなり、プロフェッショナルとしての評価も高まります。総じて、税理士事務所で働きながら試験合格を目指すことは、時間と労力を要しますが、実務経験が試験勉強に直結し、将来のキャリアに大きなメリットをもたらすため、非常に有意義な選択と言えます。
独学で合格を目指す
独学で税理士試験に合格することはかなり難しいですが、不可能ではありません。 独学の最大のメリットは、自分のペースで勉強を進められることです。特に仕事や家庭の関係で時間が限られている方にとって、自分のスケジュールに合わせて勉強できるのは大きな利点です。
しかし、独学にはいくつかの注意点もあります。まず、独学で成功するためには、しっかりとした計画が必要です。試験範囲が広いため、計画的に学習を進めることが重要となります。具体的には、各科目ごとに学習目標を設定し、日々の勉強時間を確保することが求められます。学習スケジュールを作成し、それに従って進めることで、効率的に勉強を進めることができます。
次に、教材の選定も重要です。独学の場合、教材の質が合格の鍵となります。市販の参考書や問題集を利用することが一般的ですが、口コミやレビューを参考にして、信頼性の高い教材を選びましょう。また、最新の税法や会計基準に対応しているかを確認することも忘れずに行いましょう。
独学で税理士試験の合格を目指す場合には、自己管理とモチベーションの維持が非常に重要です。独学では、誰も指導してくれないため、自分で学習の進捗を管理し、モチベーションを維持する必要があります。目標を明確に持ち、達成感を感じられるような小さな目標を設定することで、継続的に学習を進めることができます。
税理士試験合格後の流れ
晴れて税理士試験に合格したからと言って税理士としてすぐに働くことはできません。 税理士として働くためには、日本税理士会連合会へ登録を行う必要があるのです。 税理士試験合格後の流れは以下の通りです。
1.日本税理士会連合会への登録を行う
※2年以上の会計・税務業務に関する実務経験が必要
2.申請書類の作成および提出
3.税理士会による面接
4.税理士登録完了
このように、税理士試験に合格してから税理士としてはたらくまでにもかなりの時間と工数がかかります。 試験前や試験中に2年以上の実務経験が無い場合には、試験合格後に2年の実務経験を積む必要があります。 上記の流れを踏まえて、自身のキャリアプランを明確にしてスケジュールをたてることが必要となります。
税理士事務所で働くために資格は必要?
結論から言うと、税理士事務所で働くために必ずしも税理士資格が必要というわけではありません。むしろ、税理士事務所には多岐にわたる業務が存在し、さまざまな役割が求められるため、資格がなくても働けるポジションが多く存在します。
まず、税理士資格を持たないスタッフとして働く場合でも、税理士事務所での業務経験は将来のキャリアに大いに役立ちます。
例えば、記帳代行や経理補助、税務書類の作成補助、顧客対応などの業務を担当することができます。これらの業務を通じて、実務経験を積みながら税務の知識を深めることができます。また、税理士試験の受験を目指している方にとっては、実務経験が試験対策においても大いに役立つでしょう。
また、税理士事務所では専門的な知識を持つスタッフも求められています。例えば、簿記や会計の資格を持っていると、税務業務に関連する書類の作成やチェック業務をスムーズに行うことができます。ですが、税理士資格がなくとも、ファイナンシャルプランナーや社会保険労務士の資格を持つことで、顧客に対して幅広いアドバイスを提供することが可能になります。これにより、事務所内での役割が広がり、キャリアの選択肢も増えるでしょう。
税理士資格を持たないスタッフとして働く場合でも、将来的に税理士資格の取得を目指すことは十分に可能です。多くの税理士事務所では、スタッフの成長をサポートするための研修制度や学習支援制度を設けています。これらの制度を活用することで、働きながら資格取得を目指すことができます。
総じて、税理士事務所で働くために資格が必須というわけではなく、むしろ多様なスキルや経験を持つ人材が求められています。資格を持たずとも、自身のスキルや経験を活かして充実したキャリアを築くことができるでしょう。
税理士試験の一発合格は可能?-まとめ
この記事では、税理士試験の実態や税理士として働くまでの流れを解説いたしました。 税理士試験の難易度は高く、5科目一発合格はかなり難しくはなりますが、過去に合格者がいるわけですから不可能ではありません。
5科目の一発合格を目指す場合には、綿密なスケジュール設定や一発で税理士試験に合格するという強い気持ちが必要になります。この記事が、自分自身のライフプランを考え直すきっかけとなれば幸いです。

城之内 楊
株式会社ミツカル代表取締役社長