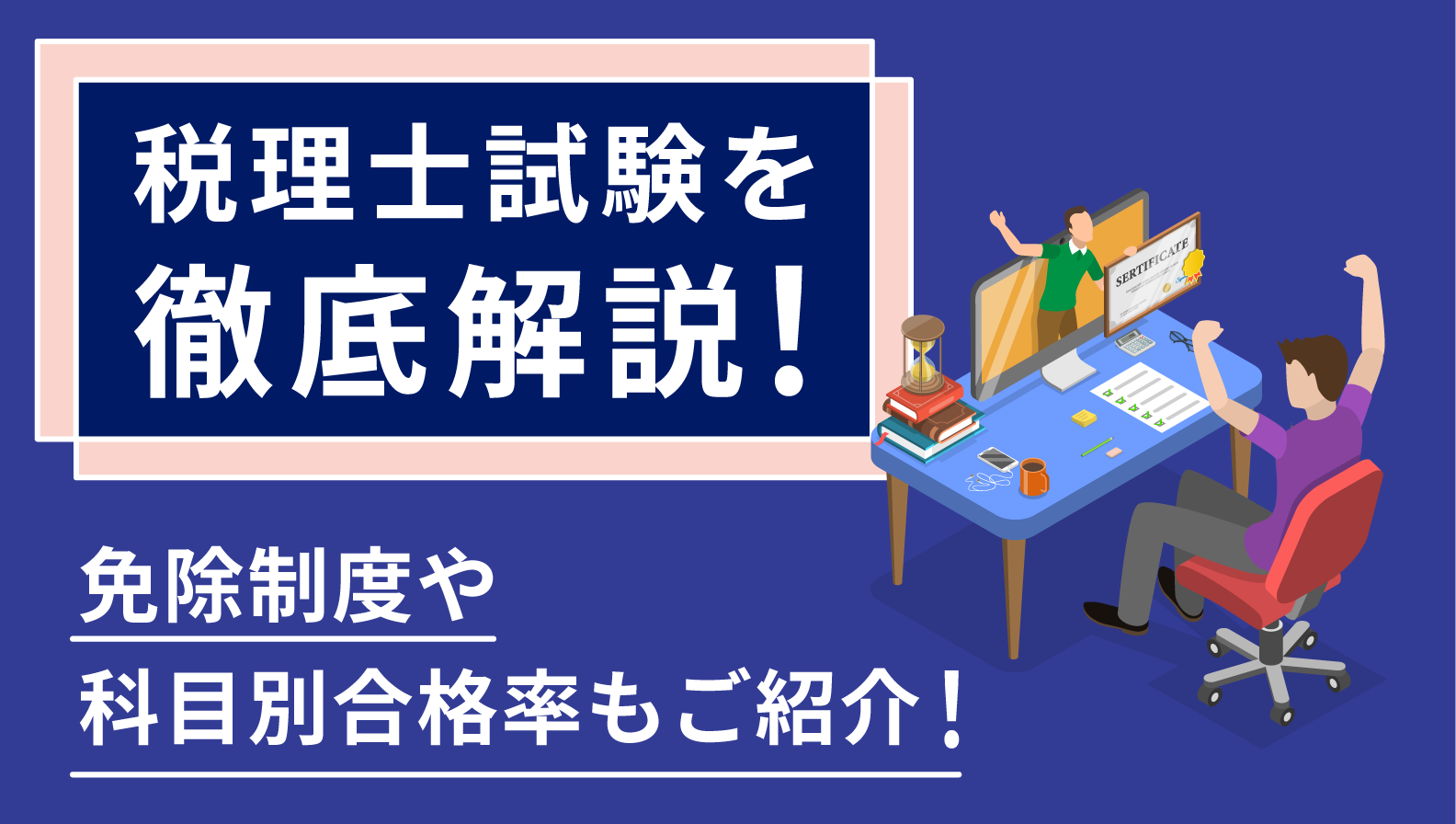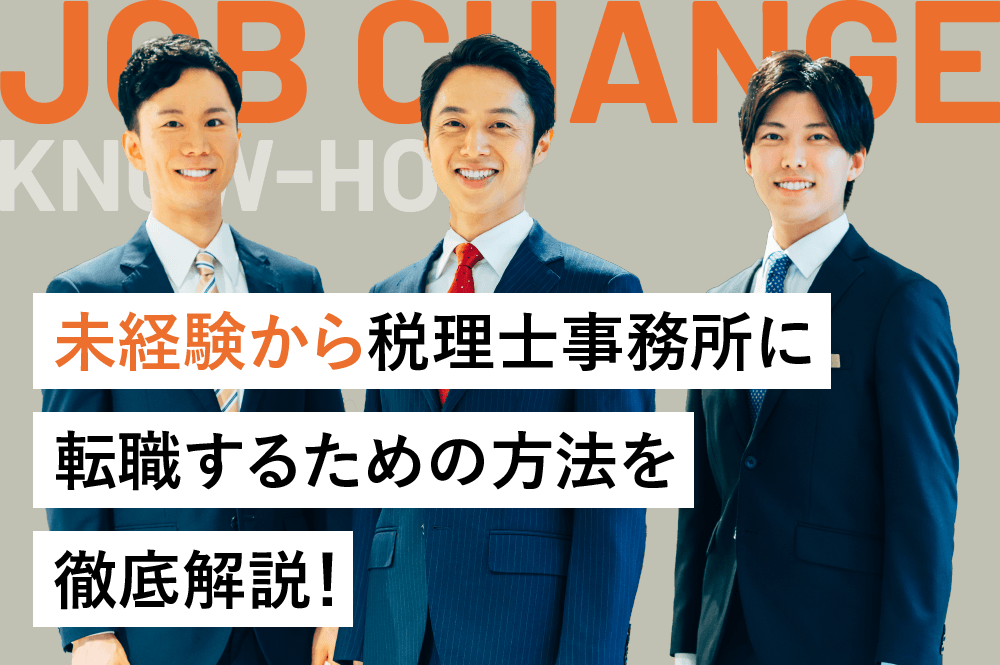INDEX
おすすめ記事
-
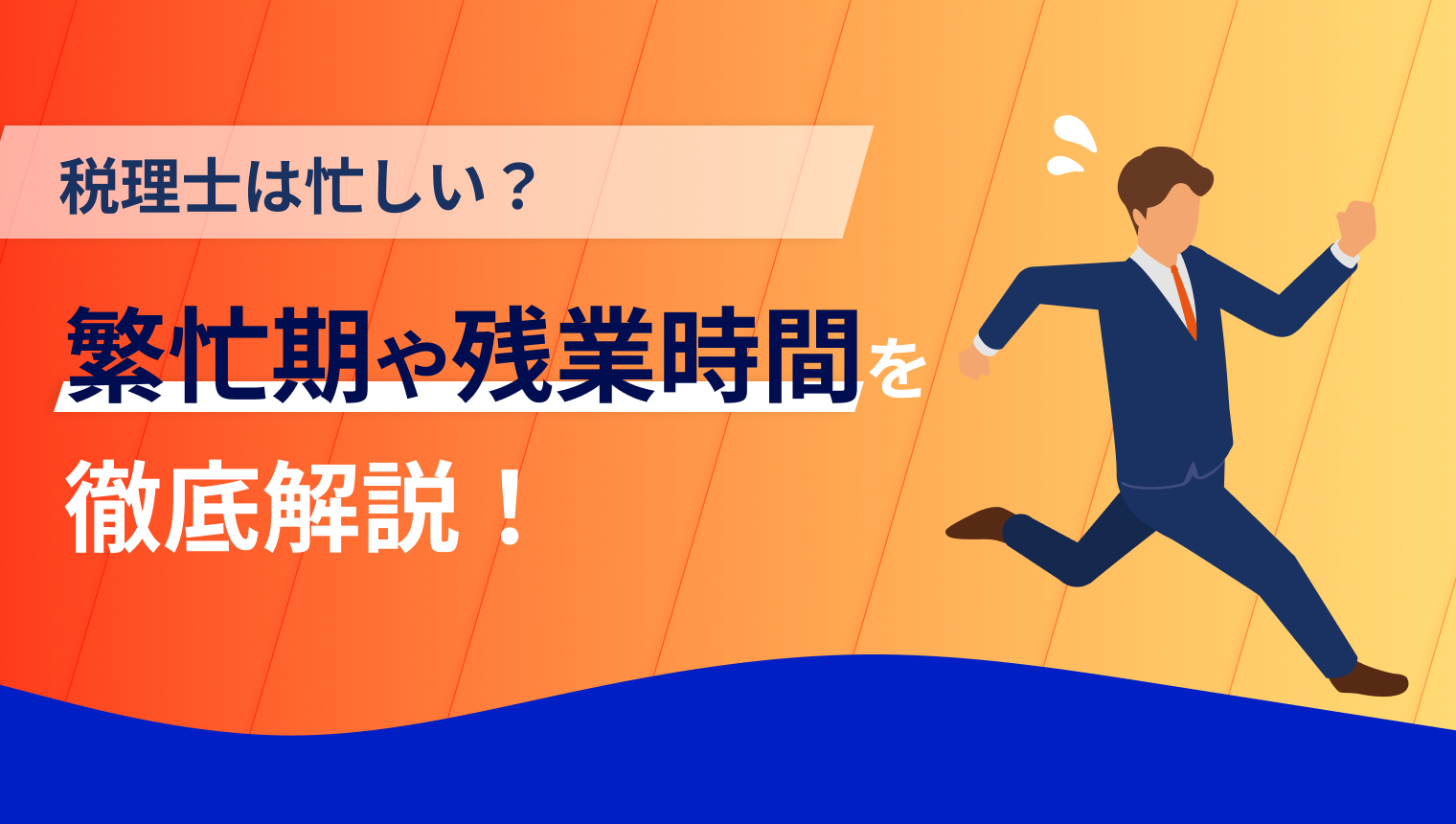
税理士の繁忙期はいつ?忙しい時期や残業時間を徹底解説!
-
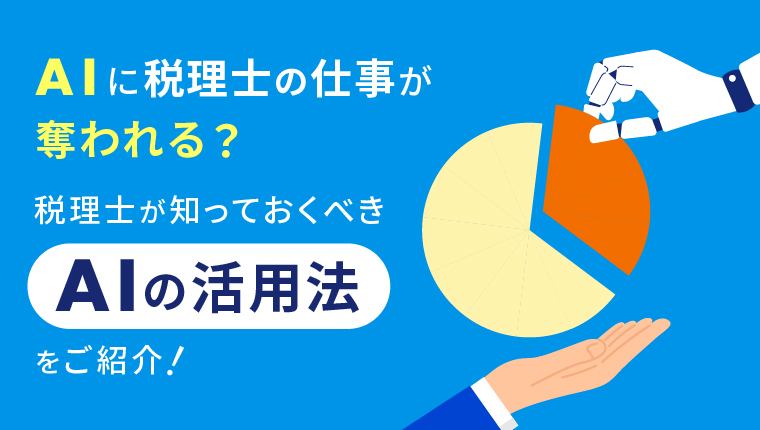
AIに税理士の仕事が奪われる?税理士が知っておくべきAIの活用法をご紹介
-

法人税申告書とは?申告書の作成方法と変更点まとめ【2025年最新版】
-
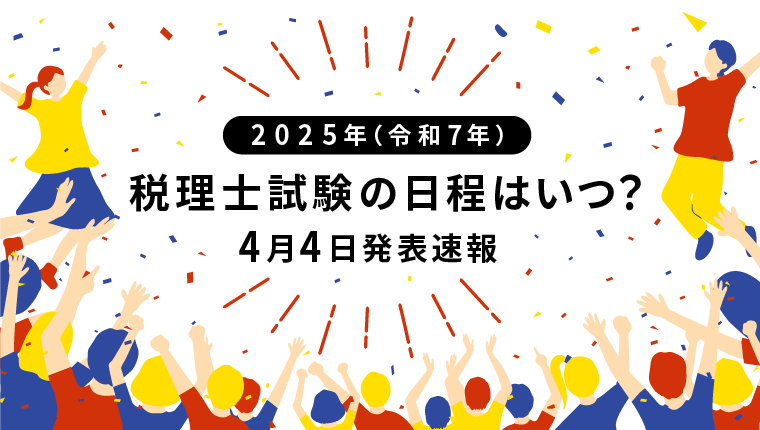
2025年(令和7年)税理士試験の日程はいつ?【4月4日発表速報】
-

税理士は何歳からなれる?上限年齢も解説
公開日:2025/03/21
最終更新日:2025/09/06
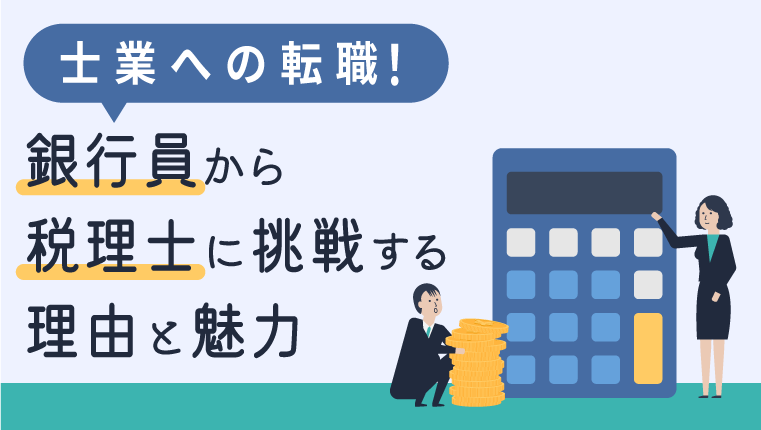
INDEX
税理士には定年退職がなく、専門性を深められるため、銀行員にとって魅力的な転職先の一つといえます。また、銀行員としての経験は、税理士になってからも活かせる部分が多くあります。
たとえば、「融資業務の知識」は企業の資金調達アドバイスに、「法人営業の経験」は税理士としての営業活動に役立ちます。このように、銀行員として培ったスキルは、税理士になった後も強みになります。
銀行員から税理士へ転職する魅力としては、「独立・開業して自由な働き方ができる」ことや、「収入アップのチャンスがある」ことが挙げられます。ただし、税理士になるには税理士試験に合格するなどの課題もあります。
そこで、本記事では、銀行員から税理士になる理由や魅力、税理士と銀行員の違い、税理士になるためのステップ、転職後のキャリア選択まで詳しく解説していきます。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
銀行員と税理士の違い
「銀行員」と「税理士」は、どちらも金融や税務に関連した職業ですが、それぞれの役割や仕事の内容は異なります。
銀行員
・顧客への金融サービスの提供
◦預金や貸付
◦融資業務
◦口座管理
◦財務アドバイス
・個人や企業のお金の管理をサポート
・投資商品やローンなどの金融商品を提供
税理士
・税金に関するアドバイスを提供
・税務申告を代行
・企業や個人に対して、税金の最適化や節税対策を提案
・税務署に提出する書類を作成
・税務調査に対応
・税金に関する相談
これらの職業は異なる分野ですが、銀行員と税理士の両方が、顧客の財務状況を改善するために重要な役割を果たしています。銀行員は主に金融商品を提供し、税理士は税金に関する専門知識でアドバイスを行います。
銀行員から税理士への転職を考える理由
銀行員が税理士へ転職を考える理由はいくつかあります。
主な理由を挙げると以下のようになります。
1.専門性を深め、税務のプロになれる
2.独立・開業して自由な働き方が可能
3.収入アップのチャンスがある
4.顧客と長期的な関係を築ける
5.銀行業界の将来不安から脱却できる
6.ワークライフバランスを改善できる
7.銀行員の知識・経験を活かせる
それではこれらを詳しく見ていきましょう。
1. 専門性の向上
銀行員は、融資・投資・資産運用など幅広い金融知識を持っていますが、税務・会計に関しては基本的な知識しか求められないことが多いです。一方、税理士は「税務・会計のプロフェッショナル」として、法人や個人の税務申告・節税対策・財務アドバイスを行うのが税理士の特徴です。
銀行員として働く中で、「財務や税務の知識を深めたい」「経営者の資金繰りだけでなく、税務面からもサポートしたい」と考えるようになり、税理士を目指すケースが多いです。
特に、法人融資業務を経験した銀行員は、企業の財務状況を分析する機会が多いため、税理士業務との親和性が高く、スムーズにキャリアチェンジしやすいです。
2. 独立・開業の可能性
銀行員は基本的に会社員として働くため、給与やキャリアの上限がある程度決まっています。一方で、税理士は資格を取得すれば独立開業が可能となり、自分のペースで仕事をすることができます。
独立のメリット
・収入の上限がなくなる
◦仕事を取れば取るほど収入が増える
・働く時間やスタイルを自由に決められる
◦会社のルールに縛られず、自由にスケジュールを組める
・クライアントと直接長期的な関係を築ける
◦自分の専門性で顧客をサポートできる
特に、金融機関出身の税理士は資金調達のアドバイスができる強みがあるため、企業経営者からの信頼を得やすく、独立しても顧問契約を取りやすいという点が、銀行員から税理士になる大きなメリットです。
3. 年収アップの可能性
銀行員の収入は安定しているものの、給与テーブルが決まっており、昇給ペースも限られます。特にメガバンクや地方銀行では40代以降の昇給が頭打ちになることも多いです。
一方、税理士として独立すれば、自分の努力次第で高収入を得ることができます。
収入の比較
| 職業 | 年収目安 |
|---|---|
| 銀行員(30代) | 600万~800万円 |
| 銀行員(40代) | 800万~1,000万円 |
| 税理士(勤務) | 500万~800万円 |
| 独立税理士(成功例) | 1,000万~3,000万円以上 |
特に、法人向けの税務顧問を中心に業務を展開すれば、月額顧問料+決算報酬で安定した収入を得ることができます。
4. 顧客との関係の違い
銀行員は顧客と接する機会が多いものの、どうしても営業ノルマや短期的な関係になりがちです。しかし、税理士は顧問契約を結び、長期的に企業や個人と関わることができます。下記に銀行員と税理士での顧客との関係性の違いをまとめました。
| 銀行員と顧客の関係性 | 税理士の顧客との関係 |
|---|---|
|
・融資の提案 ◦一度実行すれば終了 ・投資商品の販売 ◦目標達成が最優先 |
・毎月の会計処理・決算業務をサポート ・税務調査時の対応を支援 ・節税・財務改善のアドバイス |
このように、銀行員は短期間の関与が多い印象がある一方で、税理士は長期間にわたって企業経営をサポートするため、信頼関係を築きやすいです。この関係性の違いにより、税理士としてのやりがいを感じる人が多くなっています。
5. 銀行業界の将来性への不安
近年、銀行業界は低金利政策やデジタル化、競争の激化により、厳しい環境に直面しています。特に、以下の3つが主な厳しい環境として挙げられます。
・低金利政策の影響
◦貸出金利が低下し、銀行の収益が減少
・リストラ・早期退職の増加
◦メガバンク・地方銀行ともに人員削減が進行
・フィンテックの台頭
◦ネット銀行・決済アプリの普及で従来型の銀行業務が縮小
このような状況の中で、銀行員としての将来に不安を感じ、より専門性の高い職業である税理士を目指す銀行員が近年増えている傾向があります。
6. ワークライフバランスの改善
銀行員は長時間労働・土日出勤・ノルマが多く、プレッシャーが大きい職業です。特に、営業職では目標達成のために休日出勤や残業が当たり前になることもあります。
一方、税理士は繁忙期(確定申告・決算期)を除けば、比較的自由にスケジュールを調整できます。独立すれば、働く時間や場所を自分で決められるため、ワークライフバランスを改善したい人にとって魅力的な選択肢です。
7. 既存の知識や経験が活かせる
銀行員の業務経験は、税理士としての仕事に大いに役立ちます。特に、法人営業・融資業務・資産運用の知識は、税理士業務と相性が良いです。実際に、銀行での経験を評価する税理士事務所も多く、税理士事務所の募集要件において、銀行出身者を募集していることも多いです。
このため、銀行員から税理士に挑戦しやすいのも一つの理由です。銀行員の経験が生かされる部分は以下の通りです。
・融資アドバイス
◦銀行との交渉や借入のアドバイスができる
・財務コンサルティング
◦企業の資金繰り改善を支援できる
・経営アドバイス
◦金融知識を活かして企業の経営戦略をサポートできる
銀行員出身の税理士は「金融×税務」の視点を持っているため、経営者にとって心強いパートナーとなります。
銀行員から税理士への転職を考える理由としては、「専門性を深めて税務のプロを目指すこと」や「収入アップ」などが挙げられます。また、銀行員としての経験が税理士事務所で高く評価されているため、挑戦しやすい点も大きな要因と言えます。
このように、銀行員から税理士への転職には多くのメリットがあり、非常に魅力的だと言えるでしょう。
次に、銀行員としての経験がどのように税理士業務に活かされるのかを見ていきましょう。
銀行員としての経験が税理士業務に活かせる
銀行員としての経験は、税理士業務において非常に役立つ場面が多いです。
特に法人営業、融資、財務分析の経験を持つ銀行員は、税理士として独自の強みを発揮できるでしょう。銀行員の経験が税理士業務に活かせる場面として、主に以下の4つが挙げられます。
1.融資業務の知識:企業の資金調達アドバイスに活かせる
2.財務分析のスキル:経営アドバイスに活かせる
3.法人営業の経験:税理士の営業活動に活かせる
4.資産運用の知識:相続・事業承継コンサルティングに活かせる
それでは、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
1. 融資業務の知識:企業の資金調達アドバイスに活かせる
銀行員として企業融資に携わった経験は、税理士としての財務コンサルティングに非常に役立ちます。以下に細かく分けて説明しています。
・金融機関の審査基準を理解しているため、企業の資金調達をサポートできる
◦銀行が融資を判断する際のポイント(財務状況、事業計画、担保の有無など)を把握しているため、クライアントに的確なアドバイスができる。
◦「どうすれば銀行から融資を受けやすくなるか」を具体的に指導可能。
・銀行との交渉を支援できる
◦「この企業なら、どの銀行でどのような融資が受けやすいか?」といったアドバイスが可能。
◦金利交渉や返済計画の提案もできるため、経営者からの信頼を得やすい。
・資金繰りや財務改善のアドバイスができる
◦銀行員時代に培ったキャッシュフロー管理の知識を活かし、クライアントの財務状況を分析して適切な資金繰り対策を提案できる。
・税理士の中でも「資金調達支援ができる専門家」は希少価値が高く、独自の強みになる。
2. 財務分析のスキル:経営アドバイスに活かせる
銀行員は、融資審査の際に財務諸表(貸借対照表・損益計算書)を分析し、企業の経営状況を評価するスキルを持っています。このスキルは、税理士としてクライアントの経営支援をする際に大きな武器になります。財務分析スキルは、以下の3つの方法で活かすことができます。
・決算書を見て、経営課題を指摘できる
◦例えば、「売上は増えているが、営業利益率が低下しているので経費削減が必要」など、企業の課題を正確に把握できる。
◦単なる税務申告だけでなく、「このままだと銀行の評価が悪くなる」といった視点からアドバイスができる。
・銀行評価を意識した財務改善を提案できる
◦銀行が企業のどの指標を重視しているかを理解しているため、「銀行からの信用を高める決算書の作り方」をクライアントにアドバイスできる。
◦例えば、自己資本比率の改善や利益剰余金の積み増しなど、財務体質の強化策を提案可能。
・銀行借入を見越した経営計画の作成ができる
◦クライアントが将来の融資を受けやすくなるように、銀行が評価しやすい形の事業計画を作成できる。
・銀行目線での財務アドバイスができる税理士は経営者にとって貴重な存在になれる。
3. 法人営業の経験:税理士の営業活動に活かせる
銀行員の法人営業経験は、税理士の営業活動にも大いに役立ちます。具体的にどのように役立つかというと、次の3つが挙げられます。
・経営者とのコミュニケーションに活かせる
◦銀行員時代に培った「経営者との会話スキル」が、税理士としての営業やコンサルティングに直結する。
◦特に「財務」や「資金繰り」の話が得意な税理士は、経営者から相談を受けやすい。
・法人ネットワークを活用できる
◦銀行時代に築いた人脈(経営者・取引先・金融機関)を活かして、顧客を獲得に繋がる。
◦銀行を辞めた後も、「元銀行員の税理士」として銀行から紹介を受けることも可能。
・提案営業のスキルを活かして顧問契約を獲得できる
◦銀行員は営業のプロフェッショナルであり、提案力に長けている。
◦そのスキルを活かして、クライアントのニーズに合わせた税務コンサルティングを提案し、契約につなげることができる
・「銀行員+税理士」の経歴を活かせば、他の税理士との差別化がしやすく、顧客を獲得しやすい。
4. 資産運用の知識 : 相続・事業承継コンサルティングに活かせる
銀行員は富裕層向けの資産運用や相続対策の業務にも携わることが多く、これが税理士の相続・事業承継業務に直結します。どのようにつながるかは次の3つのようなアドバイスに活かされます。
・相続税対策のコンサルティングができる
◦銀行員時代に学んだ生命保険・信託・不動産投資の知識を活かし、相続税の節税対策を提案できる。
・事業承継のアドバイスができる
◦銀行では企業の後継者問題に関わることも多いため、「スムーズな事業承継のための財務改善」「株式移転のアドバイス」など、より実践的な提案が可能。
・金融資産の運用アドバイスができる
◦銀行出身の税理士は、株式・投資信託・不動産の知識を活かして、富裕層向けの資産管理業務にも対応しやすい。
・税理士業界では相続・事業承継分野が成長市場のため、「銀行×税理士」のスキルを活かせば高単価案件を獲得できる。
上記の4つの点からも、銀行員の経験は税理士業務で大いに活かせることがわかります。そのため、銀行員から税理士に転職する方も少なくありません。先ほども申し上げましたが、このように銀行員での経験は税理士業務にも共通点があり、税理士事務所でも高く評価されています。
そのため、銀行員は税理士に転職しやすい状況にあり、実際に銀行員からのキャリアチェンジをする人が多いと言えます。では、実際に銀行員から税理士になるためには、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか?
次に、銀行員が税理士になる方法についてご説明します。
税理士になるには?4つのステップ
銀行員から税理士になるには4段階あります。
・Step 1: 受験資格の確認
・Step 2: 税理士試験合格
・Step 3: 実務経験を積む
・Step 4: 登録
それではひとつづつ見ていきましょう。
Step 1: 受験資格の確認
税理士試験は誰でも受験できるわけではなく、一定の受験資格が必要です。銀行員の方は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
学歴による受験資格
・大学・短大で「法律学または経済学の1科目以上」を履修して卒業
◦経済学部・商学部・法学部出身なら、基本的に受験資格あり。
・大学院で法律学または会計学を専攻して修了
◦例えば、法学系や会計系の大学院を修了すれば受験資格を得られる。
職歴による受験資格(実務経験2年以上)
・銀行・信用金庫などの金融機関で会計業務に2年以上従事
◦例えば、融資業務・財務管理・経理関連業務に関わっていた場合、受験資格を満たす可能性あり
・一般企業で経理・会計業務に2年以上従事
◦税理士法人や会計事務所に転職し、2年以上の実務経験を積むのも一つの方法。
銀行員としての業務内容が「会計業務」に該当するか不安な場合は、税理士試験センターに確認するのがおすすめ。
もっと詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。税理士試験の受験資格と注意点をより詳しく解説しています。
Step 2: 税理士試験を受験する
税理士試験は全11科目のうち5科目に合格する必要がある国家試験です。
試験科目: 選択条件
・必須科目(2科目)
1.簿記論
◦仕訳や財務諸表の作成などの知識
2.財務諸表論
◦会計基準や財務分析の知識
・選択必須(1科目)
1.法人税法 or 所得税法
◦ どちらか1科目は必須
◦法人税法を選ぶのが一般的
・銀行員なら特におすすめ
・選択科目(2科目)
1.相続税法 / 消費税法 / 酒税法 / 国税徴収法 など
2.経営学 / 会計学 / 住民税 / 事業税 など
銀行員経験を活かすなら、法人税法・相続税法・消費税法の選択がおすすめ!
科目合格制のため、一度合格した科目は生涯有効(毎年1~2科目ずつ合格を目指せる)。
税理士試験は合格までに長い時間がかかる難関試験です。
以下に、試験にかかる時間や合格率をまとめました。
試験の難易度
・合格率:1科目あたり10~15%
・平均5~10年かかる人も多い(働きながらなら5~7年が目安)
・大学院を活用すれば「税法2科目が免除」される
税理士試験についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をぜひ読んでみてください。科目の特徴や科目別合格率なども細かく説明しているので、今後税理士試験に挑戦しようと思っている方は参考にしていただければと思います。
Step 3: 実務経験を積む(2年以上)
税理士登録には、2年以上の実務経験(会計事務所・税理士法人などでの業務経験)が必要です。
経験を積む方法
・銀行の経理・財務部門の業務が認められる場合もある
◦税理士事務所での実務経験が一般的
・税理士試験に合格する前に実務経験を積んでもOK
◦試験合格後に実務経験を証明できれば登録可能
・税理士法人や会計事務所に転職
◦働きながら試験勉強をする
Step 4: 税理士登録をする
税理士登録の条件は以下の二つです
・5科目合格
・2年以上の実務経験
税理士になるには、上記の4つのステップを踏む必要があります。難関試験に合格するまでの間に実務経験を積むことが、税理士への最短ルートと言えます。
しかし、銀行員から税理士に転職する際には、いくつかのハードルが存在します。それらについても一緒にご紹介したいと思います。それでは、銀行員から税理士への転職における課題を詳しく見ていきましょう。
銀行員から税理士への転職における課題
銀行員から税理士へ転職する際には、4つの課題やハードルがあります。
1. 税理士試験の合格が難しい
課題
・合格までの年数が長い(平均5〜10年)
・働きながらの勉強は大変
・1科目の合格率が10〜15%と低い
・計算問題だけでなく、理論暗記も必要
対策
・大学院ルートの活用
◦税法2科目(法人税法・所得税法)が免除されるため、試験勉強の負担を減らせる。
・科目合格制度を活かして少しずつ合格を目指す
◦1年に1~2科目ずつクリアする。
◦特に銀行員時代に簿記を学んでいれば「簿記論・財務諸表論」は比較的取り組みやすい。
・試験勉強に専念する期間を確保
◦ 銀行を退職または時短勤務に変更し、試験に集中する期間を作る。
・オンライン講座・通信講座を活用
◦大手資格予備校(TAC・大原・クレアールなど)を活用し、効率よく学習。
2. 実務経験の確保(税理士登録のための2年以上の経験)
課題
・銀行での業務が「会計業務」と認められない場合がある
・税理士法人や会計事務所での経験が必要
・未経験からの転職は年収ダウンのリスクがある
◦しかし、銀行員での経験はこう評価のため転職はしやすいのがメリット
対策
・税理士法人・会計事務所への転職を検討
◦税理士試験の受験生を積極採用する事務所も多いので、未経験でも応募可能。
・企業の経理・財務部門に転職
◦実務経験を積みながら、銀行員としての経験も活かせる(企業内税理士を目指すのもアリ)。
・銀行在職中に経理・会計業務に関わる部署へ異動
◦2年以上の経験を積めば、受験資格と登録要件を満たせる可能性がある。
・クラウド会計を活用した副業をする
◦フリーランス向けの確定申告サポートなどで実務経験を積む。
以下記事では、未経験から税理士事務所に転職するための対策方法やポイントをまとめています。
実務経験に悩んでいる方や、これから税理士資格取得を目指している方におすすめできる記事です。
3. 年収ダウンのリスク
課題
・銀行員は平均年収600万~800万円だが、税理士業界は未経験だと400万円前後になる可能性がある
・税理士試験合格までは低収入でも耐える必要がある
・独立開業までの収入の不安定さ
対策
・貯蓄を増やし、転職後の生活費を確保
◦生活費の半年~1年分を貯めてから転職すると安心。
・副業を活用
◦税務関連の仕事や会計ソフト導入支援など
◦クラウド会計や経営コンサル業務で副収入を得る。
・税理士法人ではなく、年収の高い企業の経理部門に転職
◦企業内税理士を目指せば、銀行員時代のスキルを活かしながらキャリアアップ。
・長期的な視点で考える
◦ 独立開業すれば、銀行員時代より高収入になる可能性もあるため、将来性を重視する。
・独立後は年収1,000万円以上も可能
4. 税理士業界の文化や働き方の違い
課題
・銀行は組織体制がしっかりしているが、税理士業界は個人プレーが多い
・銀行のような研修制度がないため、自己学習が求められる
・クライアントとの関係構築が銀行とは異なる
対策
・税理士業界のリアルを知るために、勉強会やセミナーに参加
◦事前に税理士の働き方を知っておくと、ギャップが少なくなる。
・会計事務所のインターンやアルバイトを経験
◦ 実際の業務を体験しながら、職場環境に慣れる。
・クラウド会計や税務ソフトの操作に慣れておく
◦税理士事務所では、弥生会計・freee・マネーフォワードなどの会計ソフトを使うため、事前に学習しておくと転職後スムーズに対応できる。
・銀行時代のスキルを活かせる「資金調達支援」などの分野に特化する
◦他の税理士と差別化しやすく、経営者の信頼を得やすい。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ:
銀行員から税理士への転職は、専門性を深められることや定年退職がないことなど、多くの魅力があります。また、銀行員として培った融資業務の知識や法人営業の経験は、税理士としての業務にも活かせるため、スムーズにキャリアチェンジしやすい点も特徴です。
一方で、税理士になるには税理士試験の合格などの課題もあり、計画的に学習しながら実務経験を積むことが重要です。
本記事では、銀行員から税理士になる魅力や理由、税理士と銀行員の違い、税理士になるためのステップ、転職後のキャリア選択について詳しく解説しました。銀行員から税理士を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

城之内 楊
株式会社ミツカル代表取締役社長