INDEX
おすすめ記事
-
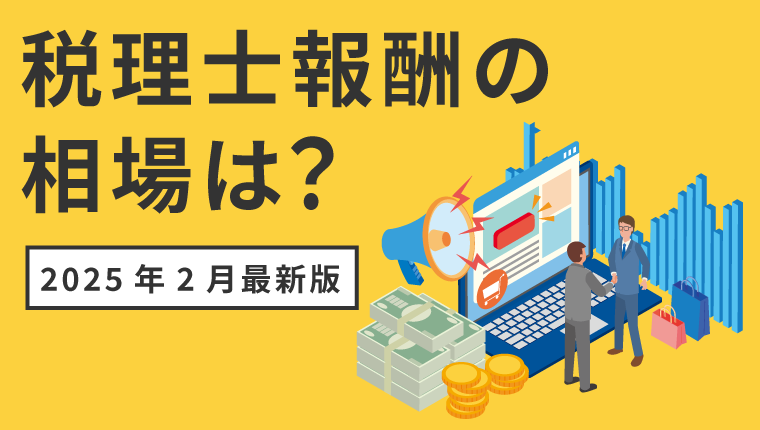
税理士報酬の相場は?2025年最新版
-
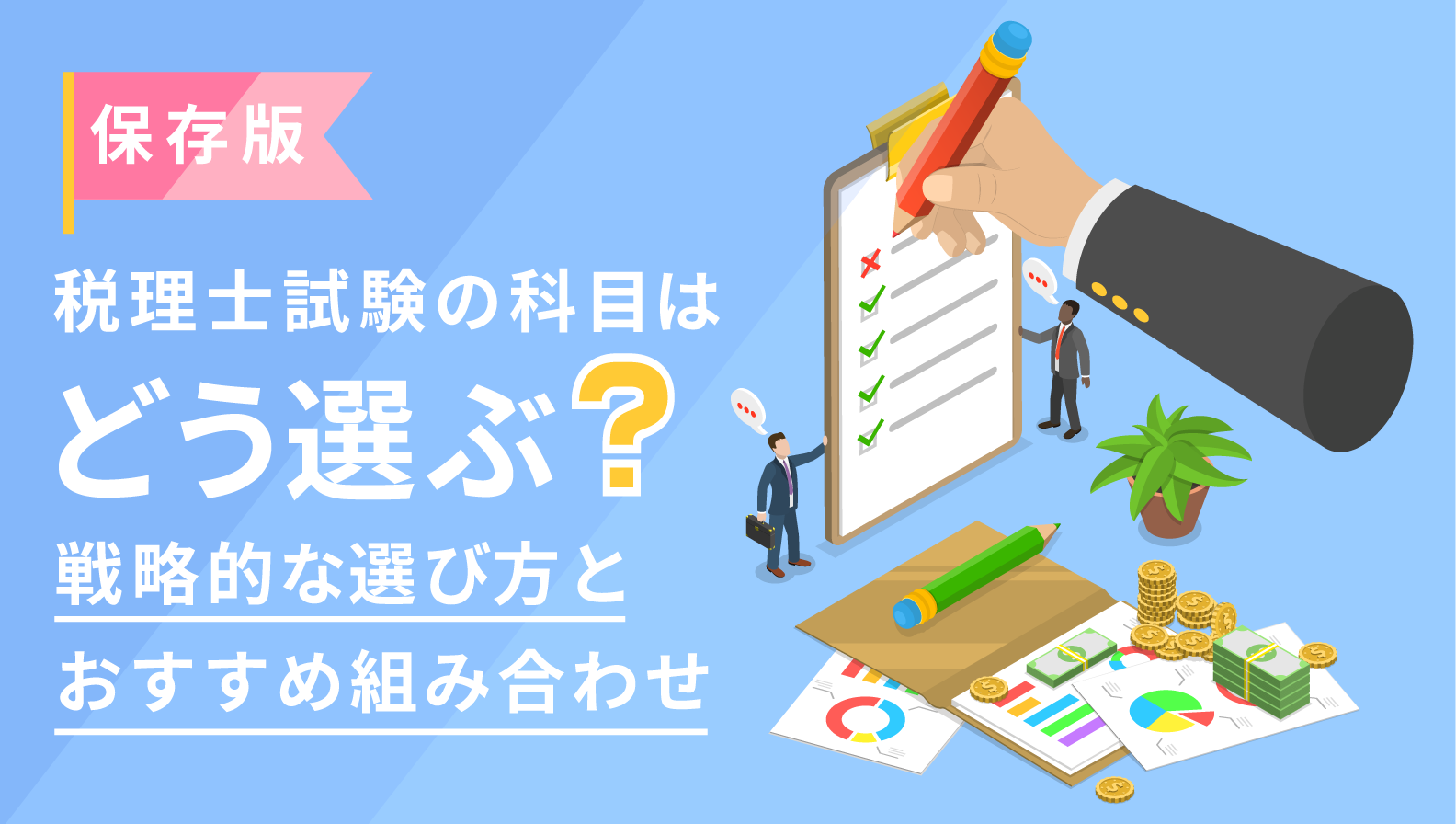
【保存版】税理士試験の科目はどう選ぶ?戦略的な選び方とおすすめ組み合わせ
-
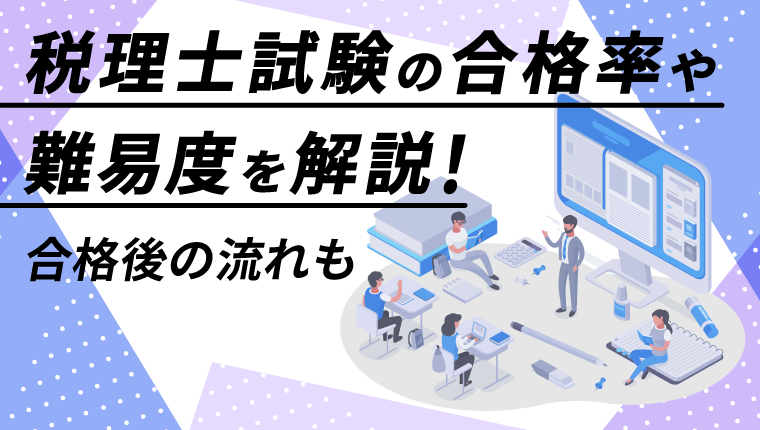
税理士試験の合格率や難易度は!合格するためのポイント~合格後の流れも解説します
-
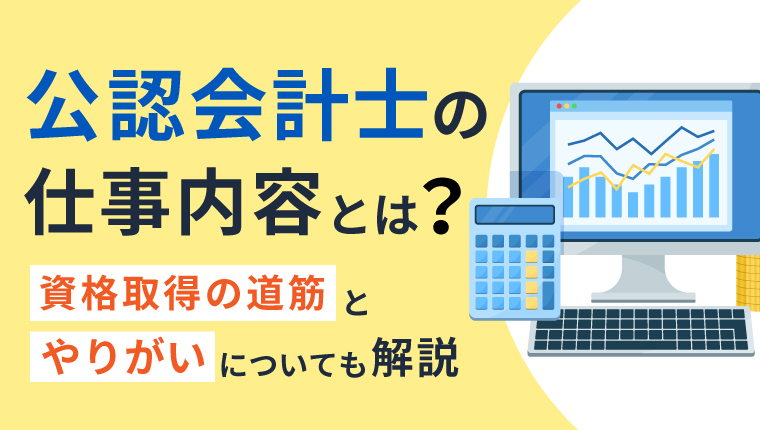
公認会計士の仕事内容とは?資格取得の道筋とやりがいについても解説
-

国税専門官からの転職|業界別おすすめ職種と必要スキル
公開日:2025/10/17
最終更新日:2025/10/17
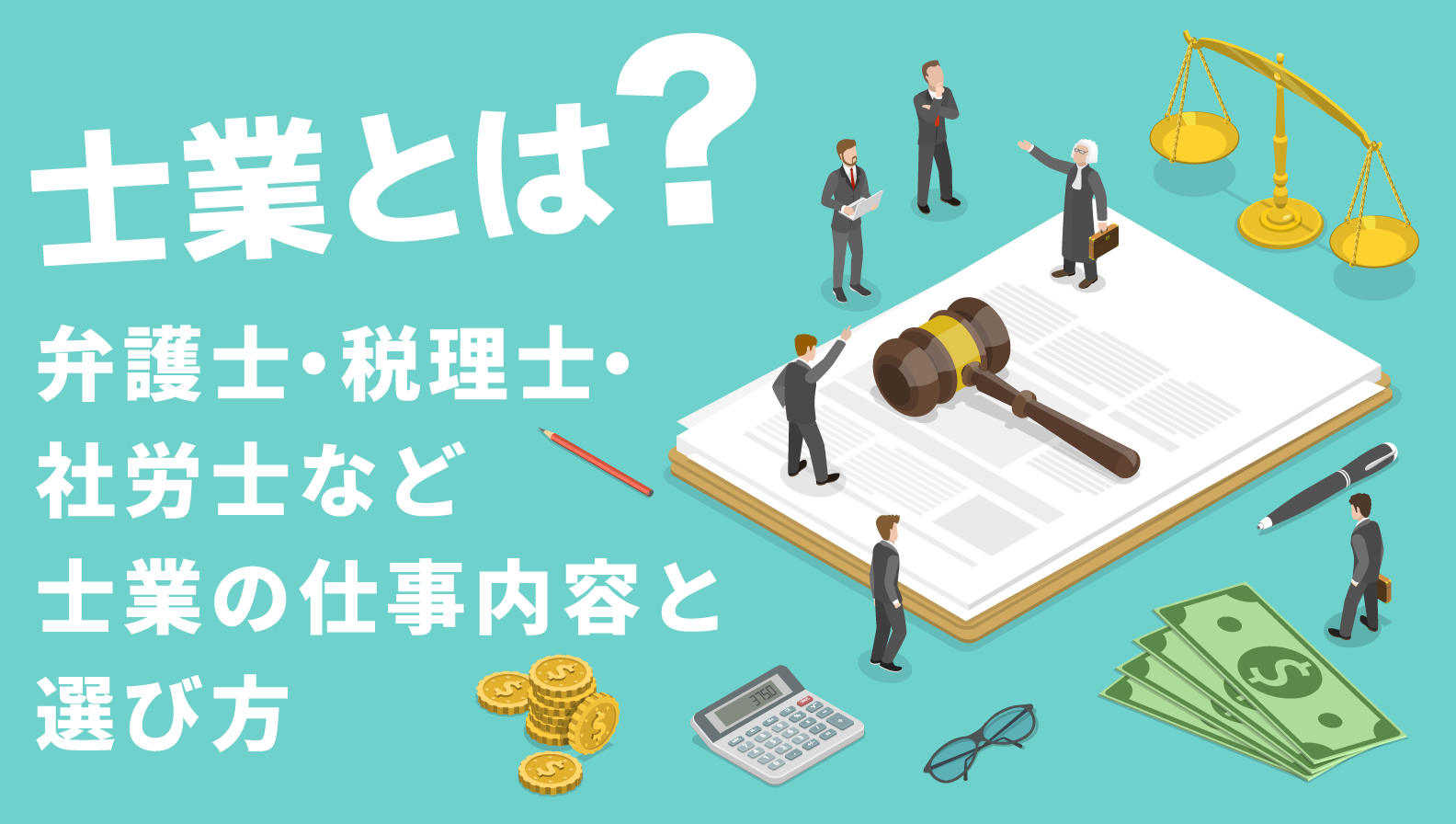
INDEX
「士業(しぎょう)」という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどんな仕事をするのか分からない方は多いのではないでしょうか。
弁護士・税理士・社労士など、国家資格を持つ専門家の総称である「士業」は、私たちの生活やビジネスを幅広く支えています。本記事では、代表的な8士業の仕事内容や依頼すべき場面、さらに士業を選ぶときのポイントをわかりやすく解説します。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
士業とは?
士業の定義
士業とは、特定の法律や専門知識に基づき、国家資格を取得した人が独占的に行える業務を担う職業の総称です。多くの場合、名称の末尾に「士」が付くため「士業」と呼ばれています。
士業が必要とされる理由
・法律・税務・労務など高度な専門知識が必要
・国家資格による独占業務が法律で定められている
・個人や企業が抱える複雑な問題を解決できる
代表的な士業の仕事内容
1. 弁護士(法律問題の総合専門家)
・業務:法律相談、訴訟代理、契約書チェック、紛争解決、刑事弁護
・独占:裁判代理、法律相談、刑事弁護
・依頼例:離婚・相続、企業法務、債権回収、労働紛争、刑事事件
・年収:500万〜2,000万以上
2. 司法書士(登記と法務手続きの専門家)
・業務:不動産・商業登記、相続、成年後見、簡裁訴訟代理
・独占:登記代理、供託手続き
・依頼例:不動産売買、会社設立、相続登記、債務整理(140万以下)
・年収:400万〜1,200万
3. 行政書士(許認可申請の専門家)
・業務:官公庁書類、許認可申請、契約書、遺言・協議書、在留資格
・独占:官公庁提出書類の作成代理
・依頼例:建設業許可、飲食店許可、相続書類、ビザ申請、会社設立
・年収:300万〜800万
4. 税理士(税務の専門家)
・業務:税務申告、記帳代行、節税、税務調査、経営相談
・独占:税務代理、税務書類作成、税務相談
・依頼例:確定申告、相続税、税務調査対応、資金繰り、事業承継
・年収:500万〜1,500万
5. 社労士(労務管理の専門家)
・業務:労務・社会保険手続き、就業規則、給与計算、労務相談、助成金
・独占:労働・社会保険手続き代理
・依頼例:入退社手続き、労務トラブル、助成金申請、働き方改革対応
・年収:400万〜1,000万
6. 弁理士(知的財産権の専門家)
・業務:特許・商標・意匠出願、知財戦略、侵害訴訟、ライセンス契約
・独占:特許庁出願代理、知財審判・異議申立
・依頼例:特許申請、商標登録、意匠登録、知財訴訟、知財戦略
・年収:600万〜1,500万
7. 公認会計士(監査・会計の専門家)
・業務:会計監査、内部統制、M&A、IPO支援、コンサル
・独占:上場企業等の法定監査
・依頼例:監査、IPO準備、M&A財務調査、事業計画支援
・年収:600万〜2,000万以上
8. 中小企業診断士(経営コンサルの専門家)
・業務:経営診断、事業計画、補助金申請、事業再生、研修講師
・独占:なし(名称独占のみ)
・依頼例:経営改善、新規事業、補助金活用、事業承継、組織改革
・年収:400万〜1,200万
表にまとめると以下の通りです。
| 士業 | 主な業務 | 依頼シーン | 年収相場 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 法律相談、訴訟代理、契約書チェック | 離婚・相続トラブル、企業法務、刑事事件 | 500万〜2,000万以上 |
| 司法書士 | 不動産・商業登記、相続手続き、成年後見 | 不動産売買、会社設立、相続登記 | 400万〜1,200万 |
| 行政書士 | 許認可申請、契約書作成、遺言書作成 | 建設業許可、ビザ申請、相続書類 | 300万〜800万 |
| 税理士 | 税務申告、会計業務、節税アドバイス | 確定申告、相続税申告、資金繰り相談 | 500万〜1,500万 |
| 社労士 | 社会保険手続き、就業規則、給与計算 | 従業員入退社手続き、労務トラブル、助成金申請 | 400万〜1,000万 |
| 弁理士 | 特許・商標出願、知財戦略、訴訟対応 | 特許申請、商標登録、知財侵害対応 | 600万〜1,500万 |
| 公認会計士 | 会計監査、M&A支援、IPO準備 | 上場企業監査、財務DD、経営コンサル | 600万〜2,000万以上 |
| 中小企業診断士 | 経営診断、事業計画、補助金申請 | 経営改善、新規事業、事業承継 | 400万〜1,200万 |
士業の業務範囲とすみわけ
業務重複と棲み分け
相続業務での役割分担
相続に関する手続きは複雑で、士業ごとに担当する役割が異なります。
まず、弁護士は相続争いの解決を担当します。遺産分割調停や訴訟、相続放棄や遺留分請求といった紛争解決業務を担い、法律的なトラブル対応を一手に引き受けます。
司法書士は主に相続登記や法的な手続きを担当します。不動産の名義変更や相続放棄の申立、遺産分割協議書の作成など、登記関連の実務が中心です。
税理士は相続税申告や節税対策を専門とし、財産評価や税務署への申告手続きを代行します。相続税の負担を軽減するためのアドバイスも重要な役割です。
一方、行政書士は遺言書や協議書の作成を支援します。自筆証書遺言や遺産分割協議書の作成、車両名義の変更など、官公庁に提出する書類の整備を担います。
| 士業 | 担当業務 | 具体的内容 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 相続争い・調停・訴訟 | 遺産分割調停、相続放棄、遺留分請求 |
| 司法書士 | 相続登記・手続き | 不動産名義変更、相続放棄申立、遺産分割協議書作成 |
| 税理士 | 相続税申告・対策 | 相続税申告、節税対策、財産評価 |
| 行政書士 | 遺言書作成・協議書 | 自筆証書遺言、遺産分割協議書、車両名義変更 |
会社設立での役割分担
会社を設立する際も、複数の士業が関わり、それぞれが専門分野で支援します。
行政書士は設立前の手続きを担当し、定款の作成や認証手続きを行います。会社設立のスタートに欠かせない役割です。
司法書士は設立登記を担い、商業登記申請や登記事項証明書の取得を行います。会社の法的な存在を確立する重要なステップです。
税理士は税務手続きをサポートします。税務署への届出や青色申告承認申請など、設立後の税務体制を整える業務を担います。
社会保険労務士(社労士)は労務関連の手続きを担当し、社会保険や労働保険の加入を代行します。従業員を雇う際の労務環境を整備する役割を担っています。
| 士業 | 担当業務 | 具体的内容 |
|---|---|---|
| 行政書士 | 設立前手続き | 定款作成、認証手続き |
| 司法書士 | 設立登記 | 商業登記申請、登記事項証明書取得 |
| 税理士 | 税務手続き | 税務署届出、青色申告承認申請 |
| 社労士 | 労務手続き | 社会保険加入、労働保険加入 |
業務範囲の制限と注意点
以下の2つの業務については制限があるため注意が必要です。
弁護士法72条(非弁行為の禁止)
他の士業が報酬を得て法律事務を行うことは原則禁止。ただし、各士業法で認められた範囲は例外。
税理士法52条(税理士業務の制限)
税理士でない者が業として税務代理、税務書類作成、税務相談を行うことは禁止。
士業を選ぶときのポイント
1. 専門分野を明確にする
相談内容によって依頼すべき士業は異なります。例えば、労務なら社労士、税務なら税理士、法的トラブルなら弁護士です。
2. 費用体系を確認する
士業は「報酬規程」に基づき料金が決まる場合もありますが、自由化されている分野も多く、事前見積もりが重要です。
3. 実績と相性を見る
同じ士業でも得意分野や経験値は異なります。相談のしやすさや説明の分かりやすさも依頼先を選ぶ大切な基準です。
主要士業の料金体系
弁護士
相談料: 30分5,000円〜10,000円
着手金: 事件の経済的利益の8%〜16%
報酬金: 事件の経済的利益の16%〜32%
顧問料: 月額3万円〜30万円
税理士
顧問料(法人):
・年商1,000万円未満:月額2万円〜3万円
・年商3,000万円未満:月額3万円〜5万円
・年商1億円未満:月額5万円〜10万円
決算申告:
月額顧問料の4〜6ヶ月分
社労士
顧問料:
・従業員10名未満:月額3万円〜5万円
・従業員50名未満:月額5万円〜8万円
・従業員100名未満:月額8万円〜15万円
手続き代行:
1件3,000円〜10,000円
司法書士
不動産登記: 5万円〜15万円
商業登記: 5万円〜20万円
相続登記: 8万円〜20万円
債務整理: 1社3万円〜5万円
行政書士
許可申請: 10万円〜50万円
車庫証明: 1万円〜2万円
遺言書作成: 5万円〜15万円
会社設立: 10万円〜20万円
資格難易度と取得方法
難易度ランキング(合格に要する学習時間)
| 順位 | 資格 | 学習時間 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 司法試験 | 8,000〜10,000時間 | 30〜40% |
| 2 | 公認会計士 | 4,000〜5,000時間 | 10〜11% |
| 3 | 税理士 | 3,000〜4,000時間 | 10〜15% |
| 4 | 司法書士 | 3,000時間 | 4〜5% |
| 5 | 弁理士 | 2,000〜3,000時間 | 6〜8% |
| 6 | 社労士 | 1,000〜1,500時間 | 6〜7% |
| 7 | 行政書士 | 500〜1,000時間 | 9〜10% |
| 8 | 宅建士 | 300〜500時間 | 15〜17% |
受験資格の有無
受験資格は以下の通りです。
受験資格なし
・司法書士、行政書士、社労士、弁理士、宅建士、マンション管理士
受験資格あり
・司法試験:法科大学院修了または予備試験合格
・税理士:学識・資格・職歴・認定のいずれかを満たす
・公認会計士:なし(実質的に大学レベルの学力が必要)
士業の今後とDX化
近年、クラウド会計ソフトやAIの普及により、士業の働き方や提供するサービスは大きく変化しています。従来は「専門知識をもとに手続きを代行すること」が中心でしたが、デジタルツールを活用することで、より戦略的で付加価値の高い業務へとシフトしています。
税理士:クラウド会計導入支援
税理士は、クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生会計オンラインなど)の導入支援を積極的に行っています。従来のように紙の領収書や通帳コピーを基に記帳するのではなく、銀行口座やクレジットカードと自動連携させることで、取引データをリアルタイムに取得可能になりました。
これにより、記帳代行の時間を削減でき、税理士は「日常の会計入力」よりも「経営者への財務アドバイス」に時間を割けるようになっています。具体的には、月次試算表をもとに資金繰りや利益計画を助言し、経営判断をサポートするスタイルが広がっています。
社会保険労務士:クラウド労務管理システムとの連携
社労士もデジタル化の波を受けています。勤怠管理システムや給与計算クラウド(SmartHR、ジョブカン、KING OF TIME など)と連携し、労務データを一元管理する仕組みを整えるサポートが増えています。
従業員の労働時間や残業状況がリアルタイムで可視化されることで、法令違反のリスクを防ぎ、働き方改革にも対応可能です。社労士は単に社会保険手続きを行うだけでなく、「労務リスクの予防策を提案するコンサルタント」としての役割を担うようになっています。
弁護士:AIによる契約書レビュー
弁護士の業務領域でもAIが活用されています。AI契約書レビューサービス(LegalForce、GVA Assist など)を導入することで、契約書のリスクや不備を自動的に検出し、弁護士が最終チェックを行う形が一般化しつつあります。
これにより、契約書チェックのスピードと精度が向上し、依頼者は従来より低コスト・短期間で法的リスクの把握が可能となりました。弁護士はAIを補助的に活用することで、依頼者へのアドバイスや交渉戦略といった「人間ならではの判断」が求められる業務に集中できます。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
士業とは -まとめ
士業とは、国家資格を持つ専門家によって構成される職業群であり、私たちの生活やビジネスの安心を支えています。弁護士・税理士・社労士など、それぞれの専門分野を理解し、状況に応じて最適な士業に相談することが重要です。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















