INDEX
おすすめ記事
-

「戦略分野国内生産促進税制」とは?制度概要と申請の留意点を徹底解説
-
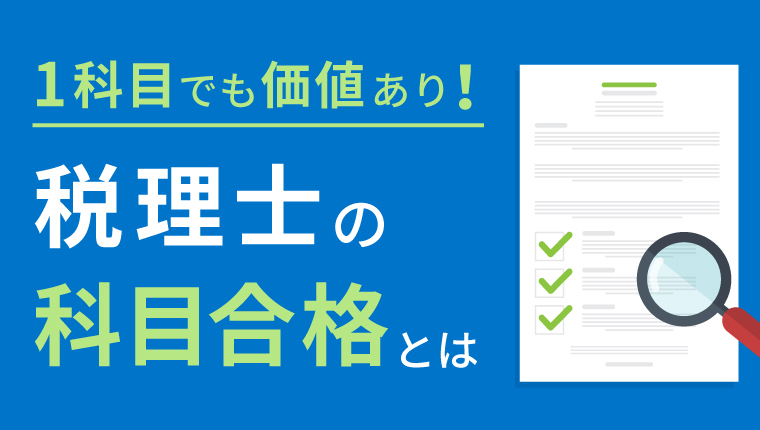
1科目でも価値あり!税理士試験の科目合格とは
-

税理士の仕事内容とは?とある1日のリアルスケジュールを大公開!
-

税理士法人とは?業界の現状と将来性について考える
-
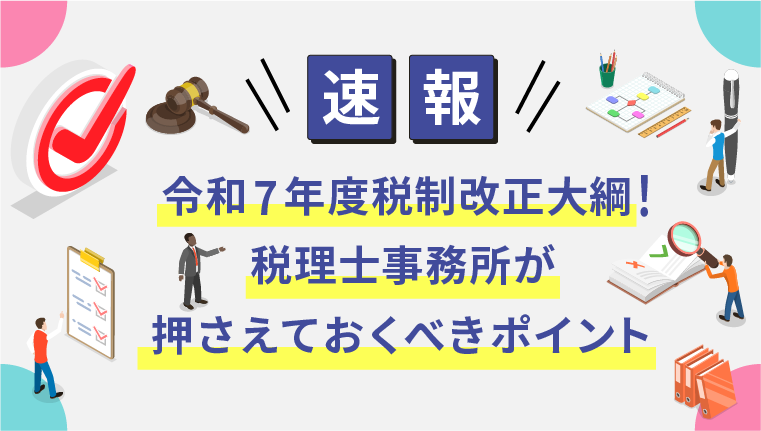
2025年度(令和7年度)税制改正大綱!税理士事務所が押さえておくべきポイント
公開日:2025/10/17
最終更新日:2025/10/17
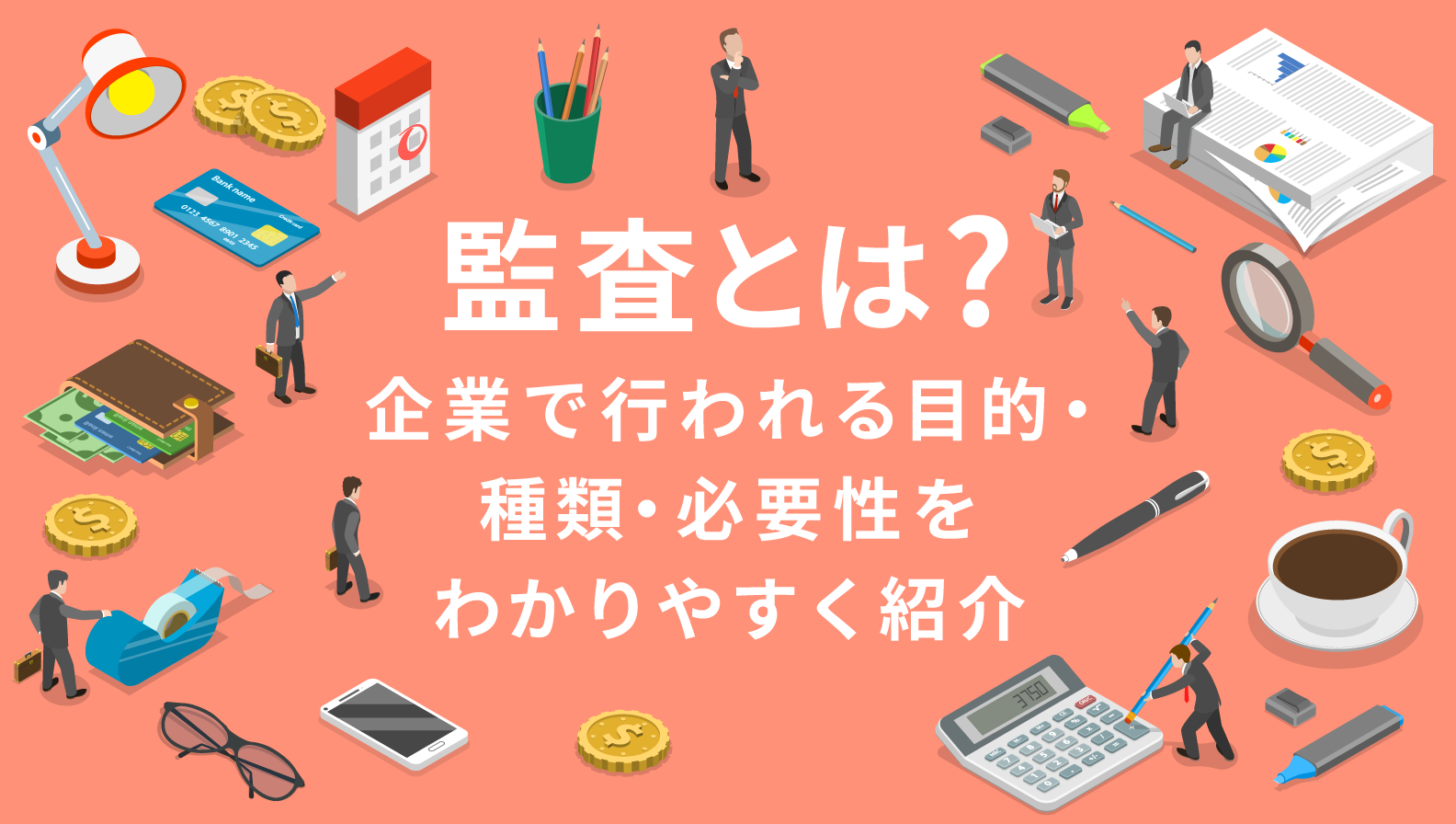
INDEX
「監査」と聞くと、多くの方は会計監査や監査法人をイメージするかもしれません。しかし、実際には会計だけでなく、業務や内部統制、ITシステムに至るまで幅広い分野で監査が行われています。
本記事では、監査の基本的な意味から、企業で行われる目的・種類・必要性までをわかりやすく解説します。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
監査とは?
監査とは、組織や活動の内容を独立的・客観的な立場から検証し、正確性や適正性を評価するプロセスのことを指します。
一般的に「監査」というと、財務諸表の正しさを確認する会計監査を思い浮かべますが、近年では企業統治や内部統制強化の観点から、幅広い分野で監査が行われています。
監査の特徴は以下の3点です。
・独立性:監査人は経営者から独立した立場で判断する。
・客観性:事実に基づき、主観を排して評価する。
・証拠性:裏付けとなる証拠(帳簿、書類、システムログなど)をもとに結論を導く。
監査が企業で行われる目的
監査が企業で重要とされる理由は主に以下の通りです。
1. 信頼性の確保
株主や投資家、金融機関といった外部ステークホルダーに対して、財務情報や経営状況の信頼性を保証することが目的です。監査済みの決算書は、投資判断や融資判断の根拠となります。
2. 不正や誤謬の防止
監査を通じて、粉飾決算や不正経理、業務上の不備を早期に発見・是正できます。監査があることで「見られている」という抑止効果も働きます。
3. 法令遵守(コンプライアンス)
金融商品取引法や会社法など、企業には数多くの法律遵守義務があります。監査は法令遵守状況を点検し、違反を防ぐ役割を担います。
4. 経営改善
監査の指摘事項は単なる批判ではなく、業務プロセスの改善点として活用できます。内部監査などは、経営効率化のヒントを与える存在でもあります。
監査の種類
監査にはさまざまな種類があり、対象や目的によって分類されます。代表的なものを整理すると以下の通りです。
1. 会計監査
・目的:財務諸表が正しく作成され、企業の財政状態や経営成績を正確に反映しているかを確認。
・実施者:監査法人または公認会計士。独立した立場で監査を行い、客観的な「監査意見」を表明。
・根拠法:会社法(大会社には会計監査人設置義務)、金融商品取引法(上場企業に四半期・年次監査義務)。
・対象企業:上場企業、大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)。
・特徴:投資家や金融機関にとっての信頼性確保に不可欠。適正意見・限定付適正・不適正・意見不表明の4区分で報告。
2. 内部監査
・目的:会社内部の業務や統制環境をチェックし、効率化・リスク低減・統制強化を図る。
・実施者:企業内部の監査部門(内部監査室など)。経営者の直轄組織であることが多い。
・特徴:外部への報告義務はなく、経営者や取締役会への助言や改善提言がメイン。監査役や監査委員会と連携するケースもある。
・具体例:経費精算の妥当性チェック、購買プロセスの承認フロー確認、情報セキュリティ運用ルールの遵守点検。
3. 税務監査
・目的:企業が行った税務申告が適正であるかを確認し、脱税や過少申告を防止。
・実施者:国税庁、税務署、国税局の調査官。
・特徴:任意調査(通常)と強制調査(マルサ)の2種類がある。調査結果に基づき追徴課税や修正申告を求められることもある。
・具体例:売上の計上漏れ、架空経費の計上、役員報酬の不適切処理などを確認。中小企業にとっても身近な監査。
4. 業務監査
・目的:会社の業務やプロジェクトが効率的・適切に運営されているかを点検。
・実施者:監査役、内部監査部門、場合によっては外部コンサルタント。
・特徴:財務に限らず、オペレーションや組織運営など幅広い対象をカバー。ガバナンス強化の一環。
・具体例:
◦製造業:製造工程の品質管理体制が国際規格(ISO9001等)に沿っているか。
◦商社・小売:取引先のコンプライアンス監査(反社会的勢力との取引排除など)。
◦サービス業:顧客対応プロセスやクレーム処理体制のチェック。
5. IT監査
・目的:情報システムやIT統制が適切に構築・運用され、セキュリティや信頼性が確保されているかを確認。
・対象:基幹システム、クラウドサービス、セキュリティ対策、個人情報保護。
・実施者:IT監査人、システム監査技術者(情報処理安全確保支援士)、外部ITコンサルタント。
・特徴:DX(デジタルトランスフォーメーション)やサイバー攻撃のリスク増大に伴い、重要性が急上昇。
・具体例:
◦システム開発プロジェクトの進行管理・品質チェック。
◦アクセス権限管理やパスワードポリシーの遵守確認。
◦個人情報保護法やGDPRへの適合性。
まとめると以下の通りです。
| 種類 | 目的 | 実施者 | 主な対象 | 特徴・具体例 |
|---|---|---|---|---|
| 会計監査 | 財務諸表の適正性検証 | 公認会計士、監査法人 | 財務諸表、会計記録 | 上場企業に必須。投資家・金融機関への信頼確保 |
| 内部監査 | 業務効率性・リスク管理 | 内部監査部門 | 業務プロセス、内部統制 | 経営者の補佐役。改善提言に直結 |
| 税務監査 | 税務申告の適正確認 | 税務署、国税局 | 申告書、会計帳簿 | 調査結果に応じ追徴課税も |
| 業務監査 | 業務運営の適正性 | 監査役、内部監査部門 | 製造工程、取引先、組織運営 | ISO監査、コンプライアンス監査など |
| IT監査 | システムの安全性・信頼性 | IT監査人、外部コンサル | ITシステム、データ管理 | DXやセキュリティリスク対策に不可欠 |
監査の流れ
監査は以下のプロセスで進められます。
1. 計画立案(Planning)
監査の最初のステップは、監査計画の策定です。
・監査目的の明確化:何を確認するのか(例:財務諸表の正確性、内部統制の有効性)。
・範囲の決定:対象部門や期間、重点分野を絞る。
・リスク評価:不正や誤謬が起きやすい箇所を事前に洗い出す。
・監査手続きの設計:抽出検査、インタビュー、観察、データ分析などの方法を選定。
2. 実施(Fieldwork)
実際の監査作業を行う段階です。
・証憑確認:請求書、契約書、帳簿、システムログなどをチェック。
・観察・インタビュー:業務現場を観察し、担当者へヒアリング。
・テスト:内部統制が実際に機能しているか検証。
・データ分析:売上や経費の異常値、トレンドを確認。
3. 評価・分析(Evaluation)
収集した情報をもとにリスクや問題を特定します。
・適正性の判断:財務諸表が会計基準に沿っているかを検証。
・不備の特定:内部統制や業務プロセスの弱点を明確化。
・重要性の評価:発見事項が経営判断や投資家に与える影響を分析。
4. 報告(Reporting)
監査結果をまとめ、経営層や株主へ伝えます。
・監査報告書の作成:監査意見(適正意見・限定付適正・不適正・意見不表明)を明記。
・改善提言:問題点の是正案を提示。
・経営陣への説明:口頭やプレゼン形式で詳細に説明することも多い。
5. フォローアップ(Follow-up)
監査の最終段階として、改善策が実行されているか確認します。
・改善状況の確認:期限内に是正措置が取られたかチェック。
・再監査の実施:必要に応じて追加調査を行う。
・継続的改善:次回監査のリスク評価にフィードバック。
表でまとめると以下の通りです。
| ステップ | 内容 | 主な活動 | 成果物 |
|---|---|---|---|
| 計画立案 | 監査の準備 | 目的・範囲設定、リスク評価、手続き設計 | 監査計画書 |
| 実施 | 監査の実行 | 証憑確認、インタビュー、観察、データ分析 | 作業記録、監査証拠 |
| 評価・分析 | 問題点の特定 | 適正性の判断、不備の特定、重要性評価 | 発見事項リスト |
| 報告 | 結果の提示 | 報告書作成、改善提言、経営層への説明 | 監査報告書 |
| フォローアップ | 改善確認 | 是正措置の確認、必要に応じ再監査 | 改善状況報告書 |
監査が必要とされる背景
近年、監査の重要性が高まっている背景には以下の要因があります。
・不祥事防止:粉飾決算(例:東芝、オリンパス事件)を防ぐため。
・グローバル化:国際会計基準(IFRS)の普及により、透明性が求められている。
・ガバナンス強化:コーポレートガバナンス・コードで、監査役や内部監査部門の機能強化が求められている。
・情報セキュリティ:サイバー攻撃や個人情報漏洩のリスクに対応するため、IT監査が注目。
監査を受けるメリット
監査を受ける企業には以下のメリットがあります。
1. 信頼性が高まり、資金調達や取引先との関係構築がスムーズになる
監査済みの財務諸表は、第三者が保証した信頼できる情報として評価されます。
・金融機関の融資審査:監査を受けている企業は財務データの信頼性が高く、融資がスムーズに進む。
・投資家からの信頼:ベンチャー企業やスタートアップでも、監査済み決算があると資金調達時の交渉力が向上。
・取引先との信用構築:大手企業との取引では「監査を受けていること」が前提条件になる場合もあり、商談が有利に進む。
2. 不正やミスの早期発見につながる
監査は抑止力と発見力の両方を持ちます。
・不正会計の抑止:経理担当者や役員も「監査で見られる」という意識を持つことで不正が起きにくくなる。
・誤謬の発見:経理処理や税務申告の単純ミスも監査で見つかり、損失や罰金を未然に防止。
・リスク対応の迅速化:内部統制の不備が発見されると、すぐに改善に着手できる。
3. 業務効率化や内部統制の改善につながる
監査は「欠点探し」ではなく、業務改善のヒントを与える存在でもあります。
・業務プロセスの見直し:無駄な手続きや二重入力など、非効率な業務が浮き彫りになる。
・内部統制の強化:承認フローやアクセス権限の設定など、組織の仕組みそのものを改善できる。
・効率的な経営判断:透明性のある情報を基盤に、経営陣が迅速かつ適切な意思決定を行える。
4. 法令違反リスクを低減し、社会的信用を守れる
企業にとって法令違反は、罰則や信頼失墜につながる重大リスクです。監査はこれを未然に防ぎます。
・法令遵守(コンプライアンス):税務、労務、会計基準など、複雑な規制の順守状況を確認できる。
・罰則・課徴金の回避:監査で不備を事前に修正することで、行政処分や追徴課税を防止。
・社会的信用の維持:不正会計や情報漏洩などの不祥事が発覚するとブランド価値は大きく毀損するが、監査はその防波堤となる。
まとめると以下の通りです。
| メリット | 具体的な効果 | 期待される成果 |
|---|---|---|
| 信頼性向上 | 監査済み財務諸表の活用、投資家・金融機関からの評価 | 資金調達や取引先との交渉が有利に進む |
| 不正・ミス防止 | 不正の抑止、会計・税務上の誤謬発見 | 損失回避、迅速なリスク対応 |
| 業務効率化 | 業務プロセスの改善、内部統制の強化 | 無駄の削減、意思決定の迅速化 |
| 法令遵守・信用維持 | 法規制の順守確認、罰則回避 | 社会的信用の確保、不祥事リスクの低減 |
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
監査とは? -まとめ
監査とは、企業活動の適正性や信頼性を確保するための検証プロセスです。
会計監査、内部監査、税務調査、業務監査、IT監査など、多様な形で行われており、その目的は「信頼性の確保」「不正防止」「法令遵守」「経営改善」にあります。
企業にとって監査は「義務」であると同時に「成長のチャンス」でもあります。監査を単なるチェックではなく、改善と発展のためのパートナーとして活用することが、今後ますます重要になるでしょう。

税理士 平川 文菜(ねこころ)


















